土曜日の晩に体を冷やしたのか、風邪気味です。
日曜日には早寝を。
大汗をかきつつ、眠るのがいちばんの治療法のように思います。
そんなわけで。
「編成表」からネタを。
TOMIXの50系客車が再生産になったようですから、むかしの編成記録をめくってみました。
全国津々浦々を走っていた形式ですから、牽引機も様々ですね。
まず、山陰本線から見ていきましょう。
ほぼ全線にわたって、DD51形牽引で走っていました。
そのうち、国鉄時代の京都口の例。

読みづらいのはご寛恕のほどを。
朝の上り列車の記録です。
こんな列車が、保津峡付近の川沿いを走っていました。
いまもトロッコ列車でたどることができる、あそこです。
おとなりの播但線。
ここもDD51形が主力。

DE10形もあったのですね。
四国です。
線路等級ゆえにDE10形ばっかり。

国鉄時代の記録で、高松行き226列車には汐留(南トメ)配置のマニ50形も併結されています。
宇高連絡船を経由して、山陽・東海道本線を東上するのでしょう。
また、オハ50 2030は2000番台ですから電気暖房併設車。
四国では電気暖房は必要としていませんでしたから、他地区からの転属車だろうと見当がつきます。
九州地方の例はこれだけですが。

筑豊本線はDD51形。
日豊本線のED76形牽引というのは、見たことがありません。
このころすでに冷房改造車(1000番台)が登場していますが、この編成にはありませんでした。
東北地方も、各地で50系客車が活躍していました。
あいにく東北本線の記録が見当たらないのですが、おもにED75形牽引だったはず。
奥羽本線は、福島~山形間がEF71形やED78形、山形以北はED75形700番台の独壇場です。

新庄を出ると、たったの2輌編成です。
左沢線のローカルに、北海道向けのキハ22形が入っていることにもご注目。
いまでもき客車列車に乗れる磐越西線。

郡山~会津若松間はED77形、会津若松~新潟間はDD51形です。
ED77形は亜幹線用として期待されたそうですが、結果的に磐越西線専用の形式となってしまいました。
田沢湖線の電化当時、貨物列車用にこの形式の投入が検討されたと聞きます。
さいごに、羽越本線の例をご紹介。

村上駅北方で交直流のデッドセクションがありますから、EF81形が牽引しています。
夏休みの一日、窓を全開にして日本海沿いを北上していったときの記録です。
もういちど、乗りたいなぁ。

日曜日には早寝を。
大汗をかきつつ、眠るのがいちばんの治療法のように思います。
そんなわけで。
「編成表」からネタを。
TOMIXの50系客車が再生産になったようですから、むかしの編成記録をめくってみました。
全国津々浦々を走っていた形式ですから、牽引機も様々ですね。
まず、山陰本線から見ていきましょう。
ほぼ全線にわたって、DD51形牽引で走っていました。
そのうち、国鉄時代の京都口の例。

読みづらいのはご寛恕のほどを。
朝の上り列車の記録です。
こんな列車が、保津峡付近の川沿いを走っていました。
いまもトロッコ列車でたどることができる、あそこです。
おとなりの播但線。
ここもDD51形が主力。

DE10形もあったのですね。
四国です。
線路等級ゆえにDE10形ばっかり。

国鉄時代の記録で、高松行き226列車には汐留(南トメ)配置のマニ50形も併結されています。
宇高連絡船を経由して、山陽・東海道本線を東上するのでしょう。
また、オハ50 2030は2000番台ですから電気暖房併設車。
四国では電気暖房は必要としていませんでしたから、他地区からの転属車だろうと見当がつきます。
九州地方の例はこれだけですが。

筑豊本線はDD51形。
日豊本線のED76形牽引というのは、見たことがありません。
このころすでに冷房改造車(1000番台)が登場していますが、この編成にはありませんでした。
東北地方も、各地で50系客車が活躍していました。
あいにく東北本線の記録が見当たらないのですが、おもにED75形牽引だったはず。
奥羽本線は、福島~山形間がEF71形やED78形、山形以北はED75形700番台の独壇場です。

新庄を出ると、たったの2輌編成です。
左沢線のローカルに、北海道向けのキハ22形が入っていることにもご注目。
いまでもき客車列車に乗れる磐越西線。

郡山~会津若松間はED77形、会津若松~新潟間はDD51形です。
ED77形は亜幹線用として期待されたそうですが、結果的に磐越西線専用の形式となってしまいました。
田沢湖線の電化当時、貨物列車用にこの形式の投入が検討されたと聞きます。
さいごに、羽越本線の例をご紹介。

村上駅北方で交直流のデッドセクションがありますから、EF81形が牽引しています。
夏休みの一日、窓を全開にして日本海沿いを北上していったときの記録です。
もういちど、乗りたいなぁ。










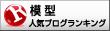
















この資料を見て、DD51やDE10に牽かせて、京都-福知山の方向幕を自作して作ろうかなと思っています。
マメにキレイに記録されていますねえ。感心しました。
客車列車は、模型でも愉しいものです。機関車が引いているという“感覚”がスバラシイ。電車だとモハのT車などというモノがあって、どこか落ち着かない気がします。
なお、50系客車のばあい準備工事だった電照式方向幕が活用された例はなく、すべていわゆるサボでしたから、老婆心ながら申し添えます。
で。
おまけ。
スユニつきの例です。
1986.1.6.出雲市→浜田433列車
DD51 1112(米子)
スユニ50 2011(米ハマ)
オハフ50 2394(米ハマ)
オハ50 262(米ハマ)
オハフ50 5(米ハマ)
いつも参考になります
15年くらい前に東北地方で50系に乗った覚えがあるのですが、機関車と編成は記録がないのでわかりません。やはり記録は大事ですね。
50系オハオハフ各2両手に入れたので、この編成表を元に増備しようか考えています。
キハ58形も良いですよね
オハ50系もキハ58系も、デッキが仕切られているので長旅には向いていましたね。地方都市でも朝ラッシュはそれなりに大変なようで、JR各社ともデッキを仕切った形体の新車はほとんど作っていません。もういちど、あのような列車で旅がしたいのですが。
おまけ。
たぶん「北斗星」の間合い運用です。
1993.10.2.青森→盛岡530列車
EF81 86(田端)
オハフ50 2194(盛モカ)
オハ50 2235(盛モカ)
オハフ50 2195(盛モカ)
3輌とも、座席モケットが赤色に更新されていました。
参考にさせていただきます。って、いつ遊べるのかなぁ?(^^;
たいがい、オハフのほうが多いのです。
車掌室と便所の関係でしょうか?
探していたら、こんな例が。
1992.10.28.東能代→秋田1622列車
ED75 758(秋田)
オハフ50 2487(秋アキ)
オ ハ50 2219(秋アキ)
オ ハ50 2333(秋アキ)
オ ハ50 2156(秋アキ)
オハフ50 2449(秋アキ)
オハフ50 2440(秋アキ)
オハフ50 2443(秋アキ)
オ ハ50 2323(秋アキ)
オハフ50 2445(秋アキ)
オハフ50 2439(秋アキ)
知らないよ~~~っ!