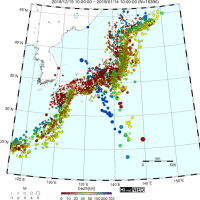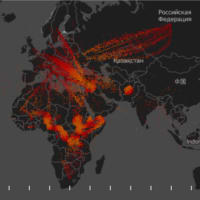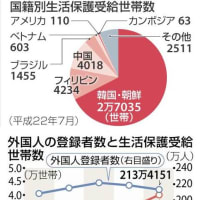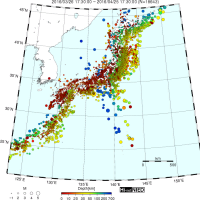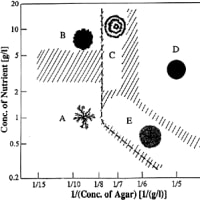1.クリントン夫妻と中国との疑惑:読者のお一人から、私の書いた以下の記事について、
悪魔の帝国・中国の世界戦略2(中):ヒラリーが作る魔の「反日」三角形
ヒラリーが中国に付くことはないのではというご指摘を受けた。補足資料として、クリントン夫妻と中国とのクリントン大統領任期中の特徴的な出来事について、ご存じのかたにはすでに周知のことではあるが、いくつか紹介しておきたい。
なお、こうした話は、床屋談議と思っていただいたほうがよく、間接的な状況証拠ばかりである。しかし、個人が自分の将来(たとえばヒラリーを支持すべきか)を考えるには、参考になる。
2.アメリカでの評価
日本へもよく投稿なさっていたヴァンダービルト大学公共政策研究所日米研究協力センターのジェームス・アワー教授(ホームページからは日米関係について真剣に努力していらっしゃる様子がよく分かる)は、クリントンとブッシュ大統領を比べて、以下のように述べている。
=====
【正論】ジェームス・アワー 二人の大統領はなぜかくも違うのか [2002年03月07日 東京朝刊]
◆時の政権と指導者の大切さ
国民が政治家を選ぶ民主主義社会でも、こと政治については、しばしば皮肉な見方をしがちだ。しかし、時の政権と指導者は、国家や国民を左右する大切な存在だということを忘れてはならない。その意味で、先日のブッシュ大統領の日本、韓国、中国訪問は、一九九八年のクリントン前米大統領の中国訪問とは対照的だった。政権と指導者がいかに大切であるかをよく示している。
九八年、クリントン大統領は中国訪問を予定より六カ月早めた。理由は公にされていない。しかし、当時の共和党議員は、大統領の訪問繰り上げが、後にキャンセルとなったポーラ・ジョーンズ嬢裁判と同時期であることに気づいていた。クリントン氏が訪問を急いでいることをかぎ取った中国側が、次に述べる三点を要求し、クリントン側が全(すべ)て受け入れた、と推測するに十分な理由がある。
第一に、クリントン氏の中国滞在を九日間にする。第二に、中国以外の国を訪問しない。これは、事実上「日本へ行くな」という意味だ。第三に、台湾について、中国政府の立場に立って有利な声明を発表する。どれも、米国の国益にならない。米大統領がこれらの要求を全て受け入れることは、中国側に弱みをさらけだすようなものだった。これらの要求は、まさに中国の国益にかなった。
◆「悪の枢軸」発言は後悔せず
八一年に、ソ連を「悪の帝国」と呼んだレーガン大統領は、前任のカーター大統領が任命したマイク・マンスフィールド駐日大使を再び起用した。大使は、大統領が在任中に日米関係をどうしたいのか、日本政府に明確に伝えるべきだ、と助言した。日本側は、大統領のメッセージに同意できるかどうかよりも、まず大統領のヴィジョンを知りたいのだ、と大使は言った。
一月二十九日の年頭教書演説で、ブッシュ大統領はイラン、イラク、北朝鮮を「悪の枢軸」と位置づけた。これに対し、日本、韓国、欧州、さらには米国国内にも「挑発的な言葉だ」という批判が一部にある。ただ、この三国の行動が、地域のみならず世界の安定をも脅かす可能性があるのは事実だ。東アジア各国訪問の結果を見る限り、大統領は三国の現状を踏まえて「悪の枢軸」と言ったことを、後悔するとは思えない。
ブッシュ大統領が各国で説明したとおり、この三国に米国から戦争をしかけるつもりはない。この三国に中国を加えるべきだった、という人もいるが、大統領は加えなかった。それよりも、日本の国会演説でブッシュ大統領が言ったことは特に注目に値する。
クリントン氏は九八年に上海で、日米の防衛協力をほめたたえ、強化の必要性を言いながら、そのすぐあとに微妙な台湾問題で、中国に受けが良いことを言った。それとは対照的に、ブッシュ大統領は、日本の国会での受けの良さなど気にせず、「米国は台湾の人々への約束を決して忘れない」と言い、結果的には、若い参議院議員を中心に猛烈な喝采(かっさい)を受けた。
◆日米共通の国家戦略を反映
ブッシュ大統領の声明と日本の国会の反応は、日米共通の国際戦略を反映したものだ。つまり、公には独立主権国と認めないものの、台湾が事実上独立していることが、日米両国の国益にかなうのだ。米国をアジアの外に置き、台湾と日本を影響下に置きたいと考える中国の現政権の性格からして、台湾の事実上の独立を保つという日米両国の戦略は変わらないであろう。
台湾の今の繁栄、経済的自由、政治的発展を考えると、台湾にいま必要なのは、自治権を保証する安全保障だけなのだ。クリントン大統領は、米国が台湾を人民解放軍の侵略から守るかどうかについて、一時、疑問を投げかけた。これに対し、ブッシュ大統領は、トルーマン大統領が一九五〇年に出した「米国第七艦隊は中国本土の武力による威嚇から台湾を守る」という誓約を再確認した。これは一九九八年までの過去のすべての大統領に守られてきたものだ。
ブッシュ大統領は米国が優先する国の順に訪問した。中国は、特に台湾についての大統領の日本でのコメントは気に入らなかったと思うが、四年前のクリントン大統領のコメントよりも、今回のブッシュ大統領の言葉には、もっと敬意を払うであろう。共産主義の独裁政権は、軍事大国には尊敬の念を抱くものだ。セオドラ・ルーズベルト大統領やレーガン大統領のように、ブッシュ大統領は、「穏やかに話す」一方で、「手にはこん棒を持っていた」のだ。かくも政権とは重要なものなのだ。そして強力な指導者も同じく重要なのだ。
=====
ここからは、政治の動向はやはり指導的人物の個性に大きく左右されるという点と、アメリカの政界にはっきり親中派と親日派という二つの指導者と官僚の流れが存在するという点とが読み取れる。
さらに、外交評論家の岡崎久彦氏は日米関係での人的要素の重大さについて、以下のように述べている。
米政権とこれからの日米関係この中からクリントン時代を抜き出すと、以下のようになる。
=====
日米経済関係が最悪だったのは、クリントン政権の初めのころだった。あのときの交渉というのは無茶苦茶で、いまから思っても、日本を完全に潰す気だった。数値目標などできないことは向こうも知っている。知っていて無理やりに約束させようとする。それは何を意味するかというと、「約束して一年してもどうせ守れないから、そこで制裁する」という話だ。
日本潰しを救ったのが、一つはペンタゴンだ。政府は民主党ばかりだったが、ペンタゴンは昔からの親日派がたくさんいた。一番関係がひどいときに、例の「ナイ報告」というのを出させて、その中に「経済摩擦によって同盟の基礎をゆるがしてはならない」ということを書いた。これはペンタゴンの公式文書、すなわち公式見解だった。当時それを聞いたホワイトハウスが怒って、「そんなことを言ったら日本を脅すテコがなくなる」と言った。「安保条約を廃棄する、数値目標を呑め」いうくらいの勢いだった。思い出しても怖い。
実はバブルの崩壊が日本潰しを救ってくれた。アメリカ側に言わせると、「交渉を始めたとき、日本は八フィートの巨人だと思って立ち向かっていた。ところが交渉したら六フィートの男だった。交渉が終わる頃になったら五フィートしかなかった。こんなものは怖くない」。
アメリカはバブル潰しにもかなり噛んでいるが、それもあって、もう日本は怖くなくなったということで解決したという面はある。しかし裏で助けてくれたのはペンタゴンの軍事専門家たちだ。
第一次ブッシュ政権でどういうことがあったか。国務副長官はアーミテージで、国防省ではポール・ウォルフォビッツが副長官を務めた。ウォルフォビッツはレーガン時代にアジア局長をやっていて、日本との関係が非常に深い人だ。国務省には、ケリー次官補(東アジア・太平洋担当=アジア局長)もいる。ブッシュ政権では、最終的に日本関係の文書を作ったり、何か言ったりするところは、ホワイトハウスのアジア部長、それから国務省のアジア局長である。つまりホワイトハウスのアジア部長と国務省のアジア局長が日本関係をやっている。
これをクリントン政権と比べるとどうか。クリントンの八年間は、両方とも一貫して中国スクールで、しかも親中派だった。日本に好意的な人はいなかった。ブッシュ政権第一期は、アジア部長もアジア局長も完全な日本派だ。
=====
岡崎氏は、はっきりと国防総省関係での親日派人材がクリントン時代の日米安保破棄を含む親中派対日強硬論を抑えてくれたと言っている。
私はお二人の意見には共通点を認める。つまり、利害打算の冷徹な世界である政治の世界でもなお、そこに一定の規則性があるとすれば、それは、その計算に携わる人物の人柄によるという、政治的人間主義である。
一般的な政治評論では、政策や思想などの抽象面を重視し、こうした政策を出したからこういう行動を取るだろうという見方をしている。いわば、ことばを重視し発言の意味を行動の原因と考えるのが思想主義・動機主義である。そして、そうした思想主義からいけば、人物の行動を基準にするこうした人物主義は唾棄すべき古い考え方のように思われている。しかし、私には台湾での二人の選挙で選ばれた総統の対照からみても、同じ改革を唱えたHと小泉首相の鮮やかな対比からも、思想主義・動機主義は人物の行動を基準にする、両氏のようなこうした人物主義という裏付けがなければ、成り立たないと思われた。
ドイツ・メルケル首相の中国での行動も同じである。複雑で見通しがたい未来を一人の指導者に任せるのは大きな賭になるが、当てずっぽうというわけではない。思想主義・動機主義も人物主義も、それぞれ一定の基準によってある程度、信頼できる未来予想を立てようとしている。しかし、最近の政治の謀略化あるいは情報戦化という傾向から行けば、政治でのことば・思想を信用することはできない。何をしているかをまず見なくては、その国やその人物は分からない。
その点で、クリントンは最悪の人物の一人と思われるし、ヒラリーもそれと大きく変わらない。
3.クリントンの対中従属
クリントンに対して私が”信用おけない人物”と思わざるを得なかったのは、二期目の大統領選挙の頃、中国と台湾から巨額の資金工作を受けているというニュースを台湾のテレビで見たときからである。まだ、ジャーナリストらしかった時代の田中宇氏が書いている。
=====
●中国からクリントン政権に献金の疑惑 1997年2月
米国のクリントン大統領が選挙戦を始めようとしていた1996年に、ワシントンの中国大使館筋が、クリントン大統領の支持基盤である米民主党全国委員会(DNC)に対して、不正な献金を行っていた可能性が強くなった。ワシントンポストが2月14日に特ダネとして報じたもので、米国の司法省がこの件の担当者を大幅増強したという。
米国では、外国人や、外国で調達した資金を政治献金として受け取ることは、国家安全保障上の見地から違法になっており、疑惑の不正性はそこにある。この事件はもともと、元DNCの資金集めの担当者だった中国系米国人のジョン・ホァン氏が台湾系やインドネシア系の米国人の有力者たちから選挙資金集めを行ったが、その資金が米国内ではなく、台湾やインドネシアから来ているのではないか、との疑惑から発生している。ホァン氏は以前、インドネシアの華僑系財閥、リッポーグループで働いており、リッポーは中国とのつながりが深かった。(ここまで引用)
ホァン氏がからむ事件に関しては、英文メディアでは昨年秋からいろいろ報じられていた。事件は複雑なので作者にも分かりにくいのだが、台湾と中国が、米国の対中国政策の先行きをめぐって、献金合戦をしているようにもみえる。第二次大戦のころから、台湾(中国国民党)は米国の政界に多額の献金を続け、それにより共産党の台湾侵攻を米艦隊の力で食い止めてきた。これに対して最近資金が貯まり出した中国は、台湾と米国のカネのつながりに横入りすることで、米国の態度を変えさせようとしている可能性もある。
政界だけでなく金融界でも、今では米国債の半分近くを、台湾や中国などのアジア諸国の政府や金融機関が買っており、特に中国の米国債保有の増加が目立っている。米国の外交政策が、こうした動きから全く自由であるはずはない。世界支配の決定打は、もはやミサイルではなくカネになっているのである。
=====
私には、世界を破滅させる力量をもった国の指導者が軍事衝突するかもしれない相手(台湾海峡危機はこニュースの前)から資金援助を受ける感覚が分からなかった。しかも、女性にルーズなうえに、金にもルーズだとしたら・・・。こんなに動かし易い相手はない。
結局、今から思えば、今の国連事務総長アナンが資金疑惑で中国に尻尾をつかまれピノキオのような木偶の坊にされているのと同じように、クリントンも政権後期は同じ状態にされていたと考えるのが妥当である。
クリントンの1998年の中国訪問の大きな問題点は国際政治評論家・浜田和幸氏の「ザ・レイプ・オブ・南京」中国の陰謀を見た()」で、以下のように指摘されている。
=====
今回のクリントン大統領の訪中に関しても、アメリカ政府は盛んに「中国を国際社会に関与」させるために、アメリカが音頭を取っているような宣伝をしているが、クリントンの側にどうしても訪中し、中国の面子を立てねばならない理由がいくつもたまっていたからであった。
そのことを十分かった上で、中国政府はクリントンを迎え入れているのである。
言い換えれば、クリントンが訪中せざるを得ないような環境を作ってきたのである。
であるからこそ、中国のスタンスは人権問題でも核戦略でも、これまでと全く変わっていないのである。
変わったのはあくまでアメリカの方である。
そのような対米戦略を考案したのは、江沢民国家主席自らが1995(平成7)年に誕生させた「アメリカ議会対策中央作業グループ」で、中国共産党の最高指導機関である中央政治局の有力メンバー7名に対してだけ報告する極秘の組織である。
彼らはアメリカの議会、政府のトップを個別に籠絡するために必要な情報収集や働きかけの作戦を日夜練り上げ、ワシントンの大使館へ指示を出している。
国家主席から特命を受けた対米議会工作班は近年その陣容を大幅に強化しており、日本大使館の動きと対照的である。
いずれにせよ、クリントンにとっての訪中の理由は次の三点に要約できる。
第一に、欧州企業に押され気味であった中国市場におけるアメリカ企業のビジネス開拓戦略を支援すること。
中国は国内のインフラ整備のために道路、港湾、飛行場、鉄道、発電所など総額一兆ドル規模の公共投資を今後3年間で行うと発表し、世界のビジネス界から熱い注目を集めている。
このような中国の潜在的市場性に引きつけられ、アメリカの大手企業上位五百社の半数がすでに中国に拠点を構え、ビジネスチャンスを狙っている。
中国の凄まじい点は、自国の外貨には極力手をつけず、アメリカの輸出入銀行や政府の開発資金をうまく引き出すことを考えたり、アメリカの投資銀行を通じて必要な資金調達に成功していることである。
クリントン政権に政治献金をしてきたアメリカ企業は、訪中の機会に大型商談がまとまるように、ここぞとばかりホワイトハウスに強力な圧力をかけてきた。
クリントン大統領としては、何としてもアメリカ企業のために一肌脱がねばならなかったのである。
ボーイング、ゼネラル・エレクトリック、カーギルなど対中進出企業の集まりである「中国との関係正常化行動委員会」の加盟企業が、今回二十億ドルを越える契約調印にこぎつけたことで、クリントンもほっと一息ついたことだろう。
第二は、インド、パキスタンの核実験を受けて、核拡散や核戦争の危険を回避するためにはどうしても中国を取り込んでおく必要があったこと。
特に、1996年の台湾海峡での中国によるM-9弾道ミサイル発射は、アメリカにとって「米中核戦争」という悪夢のシナリオを想起させた。
昨年秋の江沢民訪米が実現し、今回のクリントン訪中につながったのも、中国は核戦争も辞さない危険を秘めた国であるとの思いが、軍関係者の間で強くなっていたからである。
実はペンタゴンでは1994年、台湾海峡で武力衝突が起こり、米中対立に発展したと仮定した戦争シュミレーションを実施していた。
その時のシナリオでは緊急事態発生は2010年。
8人の海軍大将と40人の海軍大佐に、政策立案スタッフが加わり、状況を変えて5回のシュミレーションを行ったが、どうやってもアメリカ軍は中国軍に勝てなかった。
その悪夢が1996年に早くも実現しそうになったわけで、太平洋司令官のプルハー海軍大将は「あの時は最悪だった。二度とあんなのは御免だ」と語っているほどだ。
今回の米中合意の第一項目に戦略核ミサイルの相互の照準外しが上げられているのも、こうしたアメリカ側の深刻な危機意識を反映した結果である。
たとえ、照準の再設定には15分しかかからないとしても、危機的状況においては1分の時間的余裕さえあれば危機が回避できることもあるので、これはクリントン大統領にとって重大な成果といえよう。
第三に、クリントン政権にまつわる中国からの献金疑惑を打ち消す必要があったためでもある。
もし、議会共和党の反対に押し切られ訪中を延期ないし中止するようなことになれば、献金疑惑を認めたとも受け取られる可能性があったのである。
この献金疑惑とは、中国の人民解放軍の女性中佐が民主党の選挙資金調達担当のジョニー・チュン氏に1996年のクリントン再選キャンペーン中に、10万ドルの違法献金をしたという容疑。
中国政府は否定をしているが、中国の女性軍人が自分のポケットマネーから献金できる金額でないことは誰の目にも明らかである。
しかし、中国のクリントン大統領に対する懐柔作戦はアーカンソー州知事時代に遡るのが実態のようだ。
意外に思われようが、中国共産党は国内の経済社会基盤を整備するために、海外で資産を築いた有力華僑との関係を大切に維持発展させてきている。
特に華僑の百五十財閥との関係には神経を注いでいる。
具体的には、中国政府はこれら華僑財閥が政情不安な海外市場で築いた資産の避難場所を常に提供してきたのである。
そのような華僑財閥のひとつが1977年にアーカンソー州に進出したリアディーズ財閥だった。
この財閥はクリントン知事時代の1984年に、州最大のウォーセン銀行を買収した。
その過程で、同財閥は2つの法律事務所と密接な関係を築いた。
ひとつは地元のローズ法律事務所。
いわずと知れたヒラリー夫人の所属する事務所。
後に大統領の法律顧問を務めながら不可解な死を迎えたビンス・フォスター弁護士もこの事務所の出身である。
もうひとつはロサンゼルスに本拠を構えるマナット・フェルブス法律事務所。
マナットといえば民主党全国委員長を務めた実力者。
日本でもお馴染みの通商代表を務めることになったミッキー・カンターの所属する事務所でもある。
米議会調査局がまとめた中国政府の非合法ビジネスや対米情報工作の実態調査報告書などを分析すると、リアディーズ財閥がこれらクリントン知事に近い法律事務所のチャンネルを使って、莫大な政治献金を行うようになった経緯がよくわかる。
そして1992年にクリントン大統領が誕生すると、中国政府はこのリアディーズ財閥のクリントン・コネクションを通じて、ホワイトハウスにおける情報ルートを確保する。
その結果、クリントン政権の外交政策に関する極秘情報を入手したり、時には中国に有利な方向で影響力を行使するようになっていった。
これは中国政府が在外華僑や人民解放軍のダミー会社を使って行っている対米情報活動の氷山の一角にすぎない。
=====
以上の内容が本当ならば、クリントンがいかに中国の工作にはまりこんでいたかよく分かる。その結果、クリントンが中国で公に発言した台湾に関する「三つのノー」が現在まで糸を引いている。
日本にとっても、クリントンのこうした中国の操り人形化は、大きな禍根を残した。そして、その後の江沢民政権から現在の胡政権へ続く、露骨な「反日」政策につながっている。
クリントンにした中国のやり方は、今年明らかになった上海での日本領事館員自殺事件でよく分かるように、”相手の弱みを作って置いて、それを利用して操作する ”もので、クリントンの場合も、女性問題での裁判、選挙資金疑惑、個人的な金銭感覚の麻痺など個人的弱みを中国側に利用されて、自己保身のためにいいように操作されていったと見るのが妥当であろう。多くの論者が苦労して考えようとしているクリントン政権二期目の思想や政策の変化などは、実は、見せかけであり付けたりに過ぎない。思想の変化からクリントン政権の動きをみるのは本末転倒である。
もともと親中派の官僚が自分の利益のために中国に有利な動きを作っていたところへ、大統領個人が弱みを中国に握られた以上、もう、自立した政策など出せるわけがなかった。
4.現在も続くアメリカ親中派官僚の日本攻撃
日本人は、今、共和党政権という非常に恵まれた相手と関係を話し合っていることを忘れてはならないだろう。
相手が、親中派だったら、たちまち以下のような、「反日」攻撃がアメリカ内部からもすぐにわき起こる。
ドイツ在住のマイネザッヘさんの反日米人の肖像には、アメリカ親中派官僚の代表的人物エドワード・リンカーンによって立案された、1990年代の「日本潰し」が指摘されている。先に挙げた岡崎氏の論にもあったように、1990年代のクリントン一派は、日本を文字通り滅ぼすつもりだったかもしれない。
悪魔の帝国・中国の世界戦略2(中):ヒラリーが作る魔の「反日」三角形
ヒラリーが中国に付くことはないのではというご指摘を受けた。補足資料として、クリントン夫妻と中国とのクリントン大統領任期中の特徴的な出来事について、ご存じのかたにはすでに周知のことではあるが、いくつか紹介しておきたい。
なお、こうした話は、床屋談議と思っていただいたほうがよく、間接的な状況証拠ばかりである。しかし、個人が自分の将来(たとえばヒラリーを支持すべきか)を考えるには、参考になる。
2.アメリカでの評価
日本へもよく投稿なさっていたヴァンダービルト大学公共政策研究所日米研究協力センターのジェームス・アワー教授(ホームページからは日米関係について真剣に努力していらっしゃる様子がよく分かる)は、クリントンとブッシュ大統領を比べて、以下のように述べている。
=====
【正論】ジェームス・アワー 二人の大統領はなぜかくも違うのか [2002年03月07日 東京朝刊]
◆時の政権と指導者の大切さ
国民が政治家を選ぶ民主主義社会でも、こと政治については、しばしば皮肉な見方をしがちだ。しかし、時の政権と指導者は、国家や国民を左右する大切な存在だということを忘れてはならない。その意味で、先日のブッシュ大統領の日本、韓国、中国訪問は、一九九八年のクリントン前米大統領の中国訪問とは対照的だった。政権と指導者がいかに大切であるかをよく示している。
九八年、クリントン大統領は中国訪問を予定より六カ月早めた。理由は公にされていない。しかし、当時の共和党議員は、大統領の訪問繰り上げが、後にキャンセルとなったポーラ・ジョーンズ嬢裁判と同時期であることに気づいていた。クリントン氏が訪問を急いでいることをかぎ取った中国側が、次に述べる三点を要求し、クリントン側が全(すべ)て受け入れた、と推測するに十分な理由がある。
第一に、クリントン氏の中国滞在を九日間にする。第二に、中国以外の国を訪問しない。これは、事実上「日本へ行くな」という意味だ。第三に、台湾について、中国政府の立場に立って有利な声明を発表する。どれも、米国の国益にならない。米大統領がこれらの要求を全て受け入れることは、中国側に弱みをさらけだすようなものだった。これらの要求は、まさに中国の国益にかなった。
◆「悪の枢軸」発言は後悔せず
八一年に、ソ連を「悪の帝国」と呼んだレーガン大統領は、前任のカーター大統領が任命したマイク・マンスフィールド駐日大使を再び起用した。大使は、大統領が在任中に日米関係をどうしたいのか、日本政府に明確に伝えるべきだ、と助言した。日本側は、大統領のメッセージに同意できるかどうかよりも、まず大統領のヴィジョンを知りたいのだ、と大使は言った。
一月二十九日の年頭教書演説で、ブッシュ大統領はイラン、イラク、北朝鮮を「悪の枢軸」と位置づけた。これに対し、日本、韓国、欧州、さらには米国国内にも「挑発的な言葉だ」という批判が一部にある。ただ、この三国の行動が、地域のみならず世界の安定をも脅かす可能性があるのは事実だ。東アジア各国訪問の結果を見る限り、大統領は三国の現状を踏まえて「悪の枢軸」と言ったことを、後悔するとは思えない。
ブッシュ大統領が各国で説明したとおり、この三国に米国から戦争をしかけるつもりはない。この三国に中国を加えるべきだった、という人もいるが、大統領は加えなかった。それよりも、日本の国会演説でブッシュ大統領が言ったことは特に注目に値する。
クリントン氏は九八年に上海で、日米の防衛協力をほめたたえ、強化の必要性を言いながら、そのすぐあとに微妙な台湾問題で、中国に受けが良いことを言った。それとは対照的に、ブッシュ大統領は、日本の国会での受けの良さなど気にせず、「米国は台湾の人々への約束を決して忘れない」と言い、結果的には、若い参議院議員を中心に猛烈な喝采(かっさい)を受けた。
◆日米共通の国家戦略を反映
ブッシュ大統領の声明と日本の国会の反応は、日米共通の国際戦略を反映したものだ。つまり、公には独立主権国と認めないものの、台湾が事実上独立していることが、日米両国の国益にかなうのだ。米国をアジアの外に置き、台湾と日本を影響下に置きたいと考える中国の現政権の性格からして、台湾の事実上の独立を保つという日米両国の戦略は変わらないであろう。
台湾の今の繁栄、経済的自由、政治的発展を考えると、台湾にいま必要なのは、自治権を保証する安全保障だけなのだ。クリントン大統領は、米国が台湾を人民解放軍の侵略から守るかどうかについて、一時、疑問を投げかけた。これに対し、ブッシュ大統領は、トルーマン大統領が一九五〇年に出した「米国第七艦隊は中国本土の武力による威嚇から台湾を守る」という誓約を再確認した。これは一九九八年までの過去のすべての大統領に守られてきたものだ。
ブッシュ大統領は米国が優先する国の順に訪問した。中国は、特に台湾についての大統領の日本でのコメントは気に入らなかったと思うが、四年前のクリントン大統領のコメントよりも、今回のブッシュ大統領の言葉には、もっと敬意を払うであろう。共産主義の独裁政権は、軍事大国には尊敬の念を抱くものだ。セオドラ・ルーズベルト大統領やレーガン大統領のように、ブッシュ大統領は、「穏やかに話す」一方で、「手にはこん棒を持っていた」のだ。かくも政権とは重要なものなのだ。そして強力な指導者も同じく重要なのだ。
=====
ここからは、政治の動向はやはり指導的人物の個性に大きく左右されるという点と、アメリカの政界にはっきり親中派と親日派という二つの指導者と官僚の流れが存在するという点とが読み取れる。
さらに、外交評論家の岡崎久彦氏は日米関係での人的要素の重大さについて、以下のように述べている。
米政権とこれからの日米関係この中からクリントン時代を抜き出すと、以下のようになる。
=====
日米経済関係が最悪だったのは、クリントン政権の初めのころだった。あのときの交渉というのは無茶苦茶で、いまから思っても、日本を完全に潰す気だった。数値目標などできないことは向こうも知っている。知っていて無理やりに約束させようとする。それは何を意味するかというと、「約束して一年してもどうせ守れないから、そこで制裁する」という話だ。
日本潰しを救ったのが、一つはペンタゴンだ。政府は民主党ばかりだったが、ペンタゴンは昔からの親日派がたくさんいた。一番関係がひどいときに、例の「ナイ報告」というのを出させて、その中に「経済摩擦によって同盟の基礎をゆるがしてはならない」ということを書いた。これはペンタゴンの公式文書、すなわち公式見解だった。当時それを聞いたホワイトハウスが怒って、「そんなことを言ったら日本を脅すテコがなくなる」と言った。「安保条約を廃棄する、数値目標を呑め」いうくらいの勢いだった。思い出しても怖い。
実はバブルの崩壊が日本潰しを救ってくれた。アメリカ側に言わせると、「交渉を始めたとき、日本は八フィートの巨人だと思って立ち向かっていた。ところが交渉したら六フィートの男だった。交渉が終わる頃になったら五フィートしかなかった。こんなものは怖くない」。
アメリカはバブル潰しにもかなり噛んでいるが、それもあって、もう日本は怖くなくなったということで解決したという面はある。しかし裏で助けてくれたのはペンタゴンの軍事専門家たちだ。
第一次ブッシュ政権でどういうことがあったか。国務副長官はアーミテージで、国防省ではポール・ウォルフォビッツが副長官を務めた。ウォルフォビッツはレーガン時代にアジア局長をやっていて、日本との関係が非常に深い人だ。国務省には、ケリー次官補(東アジア・太平洋担当=アジア局長)もいる。ブッシュ政権では、最終的に日本関係の文書を作ったり、何か言ったりするところは、ホワイトハウスのアジア部長、それから国務省のアジア局長である。つまりホワイトハウスのアジア部長と国務省のアジア局長が日本関係をやっている。
これをクリントン政権と比べるとどうか。クリントンの八年間は、両方とも一貫して中国スクールで、しかも親中派だった。日本に好意的な人はいなかった。ブッシュ政権第一期は、アジア部長もアジア局長も完全な日本派だ。
=====
岡崎氏は、はっきりと国防総省関係での親日派人材がクリントン時代の日米安保破棄を含む親中派対日強硬論を抑えてくれたと言っている。
私はお二人の意見には共通点を認める。つまり、利害打算の冷徹な世界である政治の世界でもなお、そこに一定の規則性があるとすれば、それは、その計算に携わる人物の人柄によるという、政治的人間主義である。
一般的な政治評論では、政策や思想などの抽象面を重視し、こうした政策を出したからこういう行動を取るだろうという見方をしている。いわば、ことばを重視し発言の意味を行動の原因と考えるのが思想主義・動機主義である。そして、そうした思想主義からいけば、人物の行動を基準にするこうした人物主義は唾棄すべき古い考え方のように思われている。しかし、私には台湾での二人の選挙で選ばれた総統の対照からみても、同じ改革を唱えたHと小泉首相の鮮やかな対比からも、思想主義・動機主義は人物の行動を基準にする、両氏のようなこうした人物主義という裏付けがなければ、成り立たないと思われた。
ドイツ・メルケル首相の中国での行動も同じである。複雑で見通しがたい未来を一人の指導者に任せるのは大きな賭になるが、当てずっぽうというわけではない。思想主義・動機主義も人物主義も、それぞれ一定の基準によってある程度、信頼できる未来予想を立てようとしている。しかし、最近の政治の謀略化あるいは情報戦化という傾向から行けば、政治でのことば・思想を信用することはできない。何をしているかをまず見なくては、その国やその人物は分からない。
その点で、クリントンは最悪の人物の一人と思われるし、ヒラリーもそれと大きく変わらない。
3.クリントンの対中従属
クリントンに対して私が”信用おけない人物”と思わざるを得なかったのは、二期目の大統領選挙の頃、中国と台湾から巨額の資金工作を受けているというニュースを台湾のテレビで見たときからである。まだ、ジャーナリストらしかった時代の田中宇氏が書いている。
=====
●中国からクリントン政権に献金の疑惑 1997年2月
米国のクリントン大統領が選挙戦を始めようとしていた1996年に、ワシントンの中国大使館筋が、クリントン大統領の支持基盤である米民主党全国委員会(DNC)に対して、不正な献金を行っていた可能性が強くなった。ワシントンポストが2月14日に特ダネとして報じたもので、米国の司法省がこの件の担当者を大幅増強したという。
米国では、外国人や、外国で調達した資金を政治献金として受け取ることは、国家安全保障上の見地から違法になっており、疑惑の不正性はそこにある。この事件はもともと、元DNCの資金集めの担当者だった中国系米国人のジョン・ホァン氏が台湾系やインドネシア系の米国人の有力者たちから選挙資金集めを行ったが、その資金が米国内ではなく、台湾やインドネシアから来ているのではないか、との疑惑から発生している。ホァン氏は以前、インドネシアの華僑系財閥、リッポーグループで働いており、リッポーは中国とのつながりが深かった。(ここまで引用)
ホァン氏がからむ事件に関しては、英文メディアでは昨年秋からいろいろ報じられていた。事件は複雑なので作者にも分かりにくいのだが、台湾と中国が、米国の対中国政策の先行きをめぐって、献金合戦をしているようにもみえる。第二次大戦のころから、台湾(中国国民党)は米国の政界に多額の献金を続け、それにより共産党の台湾侵攻を米艦隊の力で食い止めてきた。これに対して最近資金が貯まり出した中国は、台湾と米国のカネのつながりに横入りすることで、米国の態度を変えさせようとしている可能性もある。
政界だけでなく金融界でも、今では米国債の半分近くを、台湾や中国などのアジア諸国の政府や金融機関が買っており、特に中国の米国債保有の増加が目立っている。米国の外交政策が、こうした動きから全く自由であるはずはない。世界支配の決定打は、もはやミサイルではなくカネになっているのである。
=====
私には、世界を破滅させる力量をもった国の指導者が軍事衝突するかもしれない相手(台湾海峡危機はこニュースの前)から資金援助を受ける感覚が分からなかった。しかも、女性にルーズなうえに、金にもルーズだとしたら・・・。こんなに動かし易い相手はない。
結局、今から思えば、今の国連事務総長アナンが資金疑惑で中国に尻尾をつかまれピノキオのような木偶の坊にされているのと同じように、クリントンも政権後期は同じ状態にされていたと考えるのが妥当である。
クリントンの1998年の中国訪問の大きな問題点は国際政治評論家・浜田和幸氏の「ザ・レイプ・オブ・南京」中国の陰謀を見た()」で、以下のように指摘されている。
=====
今回のクリントン大統領の訪中に関しても、アメリカ政府は盛んに「中国を国際社会に関与」させるために、アメリカが音頭を取っているような宣伝をしているが、クリントンの側にどうしても訪中し、中国の面子を立てねばならない理由がいくつもたまっていたからであった。
そのことを十分かった上で、中国政府はクリントンを迎え入れているのである。
言い換えれば、クリントンが訪中せざるを得ないような環境を作ってきたのである。
であるからこそ、中国のスタンスは人権問題でも核戦略でも、これまでと全く変わっていないのである。
変わったのはあくまでアメリカの方である。
そのような対米戦略を考案したのは、江沢民国家主席自らが1995(平成7)年に誕生させた「アメリカ議会対策中央作業グループ」で、中国共産党の最高指導機関である中央政治局の有力メンバー7名に対してだけ報告する極秘の組織である。
彼らはアメリカの議会、政府のトップを個別に籠絡するために必要な情報収集や働きかけの作戦を日夜練り上げ、ワシントンの大使館へ指示を出している。
国家主席から特命を受けた対米議会工作班は近年その陣容を大幅に強化しており、日本大使館の動きと対照的である。
いずれにせよ、クリントンにとっての訪中の理由は次の三点に要約できる。
第一に、欧州企業に押され気味であった中国市場におけるアメリカ企業のビジネス開拓戦略を支援すること。
中国は国内のインフラ整備のために道路、港湾、飛行場、鉄道、発電所など総額一兆ドル規模の公共投資を今後3年間で行うと発表し、世界のビジネス界から熱い注目を集めている。
このような中国の潜在的市場性に引きつけられ、アメリカの大手企業上位五百社の半数がすでに中国に拠点を構え、ビジネスチャンスを狙っている。
中国の凄まじい点は、自国の外貨には極力手をつけず、アメリカの輸出入銀行や政府の開発資金をうまく引き出すことを考えたり、アメリカの投資銀行を通じて必要な資金調達に成功していることである。
クリントン政権に政治献金をしてきたアメリカ企業は、訪中の機会に大型商談がまとまるように、ここぞとばかりホワイトハウスに強力な圧力をかけてきた。
クリントン大統領としては、何としてもアメリカ企業のために一肌脱がねばならなかったのである。
ボーイング、ゼネラル・エレクトリック、カーギルなど対中進出企業の集まりである「中国との関係正常化行動委員会」の加盟企業が、今回二十億ドルを越える契約調印にこぎつけたことで、クリントンもほっと一息ついたことだろう。
第二は、インド、パキスタンの核実験を受けて、核拡散や核戦争の危険を回避するためにはどうしても中国を取り込んでおく必要があったこと。
特に、1996年の台湾海峡での中国によるM-9弾道ミサイル発射は、アメリカにとって「米中核戦争」という悪夢のシナリオを想起させた。
昨年秋の江沢民訪米が実現し、今回のクリントン訪中につながったのも、中国は核戦争も辞さない危険を秘めた国であるとの思いが、軍関係者の間で強くなっていたからである。
実はペンタゴンでは1994年、台湾海峡で武力衝突が起こり、米中対立に発展したと仮定した戦争シュミレーションを実施していた。
その時のシナリオでは緊急事態発生は2010年。
8人の海軍大将と40人の海軍大佐に、政策立案スタッフが加わり、状況を変えて5回のシュミレーションを行ったが、どうやってもアメリカ軍は中国軍に勝てなかった。
その悪夢が1996年に早くも実現しそうになったわけで、太平洋司令官のプルハー海軍大将は「あの時は最悪だった。二度とあんなのは御免だ」と語っているほどだ。
今回の米中合意の第一項目に戦略核ミサイルの相互の照準外しが上げられているのも、こうしたアメリカ側の深刻な危機意識を反映した結果である。
たとえ、照準の再設定には15分しかかからないとしても、危機的状況においては1分の時間的余裕さえあれば危機が回避できることもあるので、これはクリントン大統領にとって重大な成果といえよう。
第三に、クリントン政権にまつわる中国からの献金疑惑を打ち消す必要があったためでもある。
もし、議会共和党の反対に押し切られ訪中を延期ないし中止するようなことになれば、献金疑惑を認めたとも受け取られる可能性があったのである。
この献金疑惑とは、中国の人民解放軍の女性中佐が民主党の選挙資金調達担当のジョニー・チュン氏に1996年のクリントン再選キャンペーン中に、10万ドルの違法献金をしたという容疑。
中国政府は否定をしているが、中国の女性軍人が自分のポケットマネーから献金できる金額でないことは誰の目にも明らかである。
しかし、中国のクリントン大統領に対する懐柔作戦はアーカンソー州知事時代に遡るのが実態のようだ。
意外に思われようが、中国共産党は国内の経済社会基盤を整備するために、海外で資産を築いた有力華僑との関係を大切に維持発展させてきている。
特に華僑の百五十財閥との関係には神経を注いでいる。
具体的には、中国政府はこれら華僑財閥が政情不安な海外市場で築いた資産の避難場所を常に提供してきたのである。
そのような華僑財閥のひとつが1977年にアーカンソー州に進出したリアディーズ財閥だった。
この財閥はクリントン知事時代の1984年に、州最大のウォーセン銀行を買収した。
その過程で、同財閥は2つの法律事務所と密接な関係を築いた。
ひとつは地元のローズ法律事務所。
いわずと知れたヒラリー夫人の所属する事務所。
後に大統領の法律顧問を務めながら不可解な死を迎えたビンス・フォスター弁護士もこの事務所の出身である。
もうひとつはロサンゼルスに本拠を構えるマナット・フェルブス法律事務所。
マナットといえば民主党全国委員長を務めた実力者。
日本でもお馴染みの通商代表を務めることになったミッキー・カンターの所属する事務所でもある。
米議会調査局がまとめた中国政府の非合法ビジネスや対米情報工作の実態調査報告書などを分析すると、リアディーズ財閥がこれらクリントン知事に近い法律事務所のチャンネルを使って、莫大な政治献金を行うようになった経緯がよくわかる。
そして1992年にクリントン大統領が誕生すると、中国政府はこのリアディーズ財閥のクリントン・コネクションを通じて、ホワイトハウスにおける情報ルートを確保する。
その結果、クリントン政権の外交政策に関する極秘情報を入手したり、時には中国に有利な方向で影響力を行使するようになっていった。
これは中国政府が在外華僑や人民解放軍のダミー会社を使って行っている対米情報活動の氷山の一角にすぎない。
=====
以上の内容が本当ならば、クリントンがいかに中国の工作にはまりこんでいたかよく分かる。その結果、クリントンが中国で公に発言した台湾に関する「三つのノー」が現在まで糸を引いている。
日本にとっても、クリントンのこうした中国の操り人形化は、大きな禍根を残した。そして、その後の江沢民政権から現在の胡政権へ続く、露骨な「反日」政策につながっている。
クリントンにした中国のやり方は、今年明らかになった上海での日本領事館員自殺事件でよく分かるように、”相手の弱みを作って置いて、それを利用して操作する ”もので、クリントンの場合も、女性問題での裁判、選挙資金疑惑、個人的な金銭感覚の麻痺など個人的弱みを中国側に利用されて、自己保身のためにいいように操作されていったと見るのが妥当であろう。多くの論者が苦労して考えようとしているクリントン政権二期目の思想や政策の変化などは、実は、見せかけであり付けたりに過ぎない。思想の変化からクリントン政権の動きをみるのは本末転倒である。
もともと親中派の官僚が自分の利益のために中国に有利な動きを作っていたところへ、大統領個人が弱みを中国に握られた以上、もう、自立した政策など出せるわけがなかった。
4.現在も続くアメリカ親中派官僚の日本攻撃
日本人は、今、共和党政権という非常に恵まれた相手と関係を話し合っていることを忘れてはならないだろう。
相手が、親中派だったら、たちまち以下のような、「反日」攻撃がアメリカ内部からもすぐにわき起こる。
ドイツ在住のマイネザッヘさんの反日米人の肖像には、アメリカ親中派官僚の代表的人物エドワード・リンカーンによって立案された、1990年代の「日本潰し」が指摘されている。先に挙げた岡崎氏の論にもあったように、1990年代のクリントン一派は、日本を文字通り滅ぼすつもりだったかもしれない。