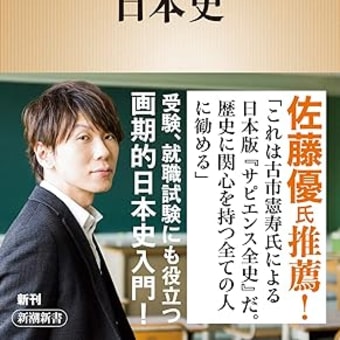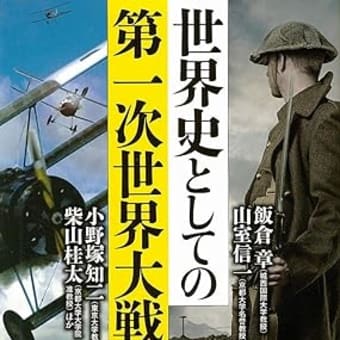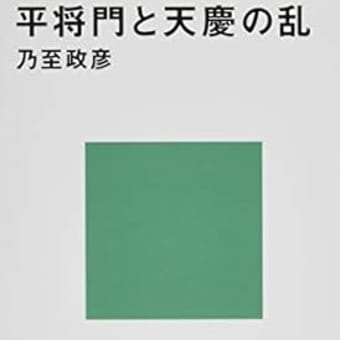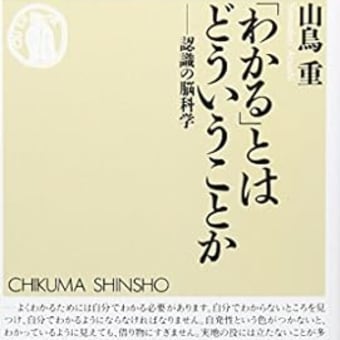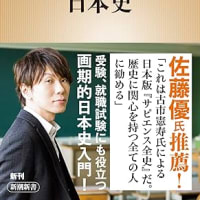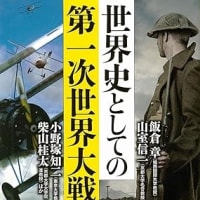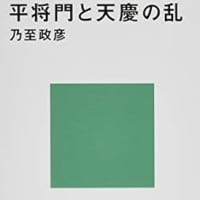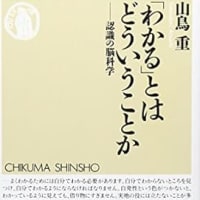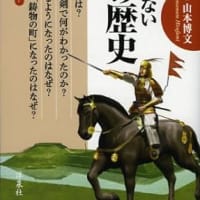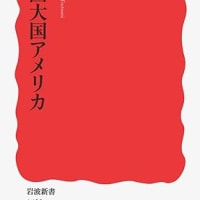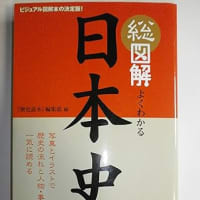原作はアメリカで2008年に発刊された。2006年北半球の25%のハチが消えた、2010年時点でアメリカ国内の34%のハチのコロニーが壊滅しているという。ハチが大量に死んでいるらしい、というニュースは聞いていたが深くは考えていなかった。それがこんなに問題を孕んでいるとは。ハチの大量死、CCD(Colony Collapse Disorder)と呼ばれているこの現象、アメリカ、ヨーロッパだけではなく全世界で起きている現象だという。原因として考えられる事柄を、ミステリーのように一つずつ検証していくので、難しい話があってもノンフィクションであるのにミステリー小説のように読み飽きることがない。
果実がなる樹木には受粉が必要、それをせっせと実行しているのはミツバチ、このことは知っているが、それではミツバチがいなくなるとどうなるのか。そう、受粉されない花には実がならない、つまり果樹の農家は大変なことになる。カリフォルニアではアーモンド農家がミツバチの存在を前提として木の密度を上げていった結果、100年前に比べると数倍の生産性を上げるまでになっていたのが、ミツバチ不足で手作業での受粉になって、アーモンドが値上がりしているという。そもそもミツバチといえば蜂蜜、これが取れなくなってしまう。
果樹やアーモンドだけではない。牛乳を作り出す乳牛の食べるクローバーやアルファルファの花が種を作るにはミツバチの受粉が不可欠。ミツバチの受粉のお世話になる作物は100種類以上、梨、プラム、キーウィー、マカデミアナッツ、アボカド、ブロッコリーなど、そして乳牛もお世話になっているとすれば、我々が毎朝食べている食事の多くが食卓から消えてしまうことになる。
養蜂の技術が確立されたのは1851年、それまでは蜂の巣ごととってしまっていたので、巣を取られたハチはゼロから巣を作り直す必要があった。ラングストロス牧師はハチに木箱の中に巣を作らせる方法を編み出して、巣作りの効率化と蜂蜜採りの効率化を図って成功したというのである。効率は上がったが、ハチは効率化により、自然の中での蜂の巣ではできていた女王蜂を守る、卵から幼虫へいたるプロセスでの育児、そして巣の外から餌をとってくるという役割分担と季節ごとに巣の中で移動しながら季節に合わせた生活をするすべを失っていたという。そしてさらに天敵のミツバチヘギイタダニに対する対抗手段も失っていた。
養蜂家はダニ対策のために抗生剤を使ったり、女王蜂を半年に一度入れ替えるなどをして蜂蜜生産効率の維持を図ってきた。そしてミツバチの疫病である”ノゼマ病”、追い討ちをかけたのはネオニコチノイド系の農薬、自然の中ではいろいろな対抗手段でダニにも対応し、巣の形状を工夫して季節変動を乗り切ってきたミツバチは養蜂家の生産効率のために抵抗力を削がれていたところに疫病、そして農薬にやられてしまった。CCDは人には突然やってきたように見えたが、じつはそれらは長時間をかけて着実にミツバチのコロニーを弱らせていたのであり、あるとき一線を超えたのである。「複合汚染」という有吉佐和子の小説があったが、まさにこれはミツバチにとっての複合汚染であった。
1億4千万年前、爬虫類や哺乳類はいたが花は地球上には咲いていなかった。植物は陸上にあったがそれはシダ類、針葉樹、ソテツ類であり、風に頼る受粉であった。それが昆虫、とくにハチの出現で、植物の戦略が変わった。昆虫による受粉は植物にとっては思っても見ない受粉効率をもたらした。瞬くうちに昆虫の目にとまりやすい花が植物の繁栄をもたらした。白亜紀の初期には3000種類だった植物の種類は白亜紀末期には25-40万種類に増えていた。
そしていま、ミツバチがいなくなるという現象が一気に地球全体に起きている。これはなにかとんでもない事が起きる前兆なのだろうか。筆者によれば日本を訪れた時にニホンみつばちの特性を知って希望を見出したという。それはニホンミツバチがダニに強く、アメリカのような養蜂の効率化の洗礼を受けていいないからだと。我々日本人にも出来ることはあるのではないかと。
素人でも数坪のハチにとって心地よい場所と、2万円ほどを出せば、養蜂の真似事ができるという。ちょっと考えてみようかと思うほど、危機感をもったのだが、筆者はあくまで冷静である。本書は小さな現象から大きな問題を考えさせる貴重な情報源、老若男女、万人に薦めたい一冊である。