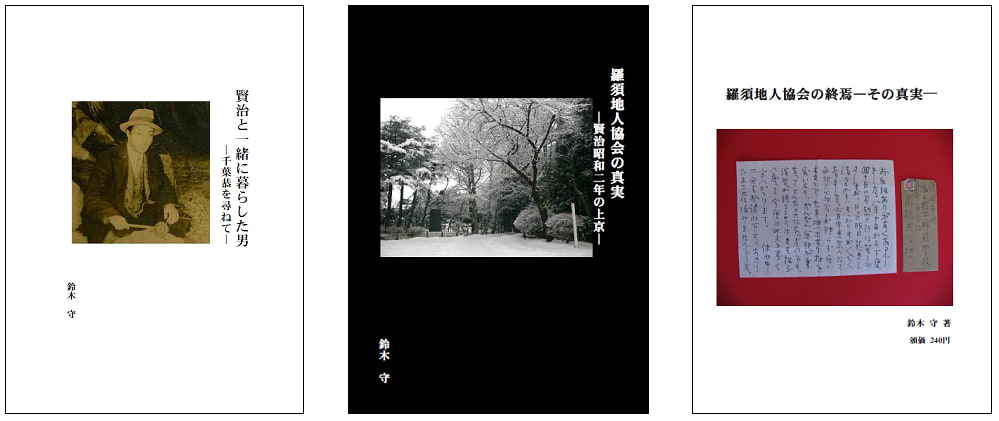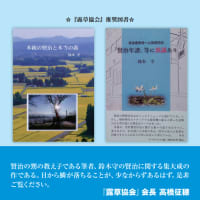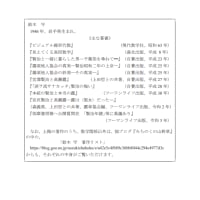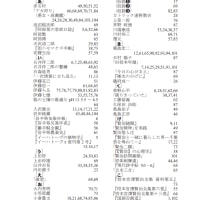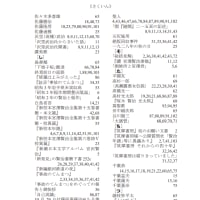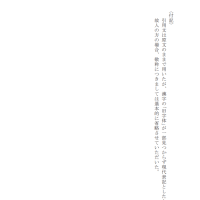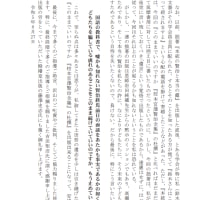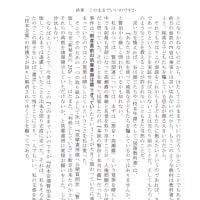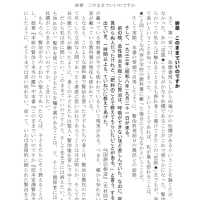続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ
“『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ ”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。
”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。*****************************なお、以下はテキスト形式版である。****************************
賢治・家の光・犬田卯・佐伯郁郎
では今度は、賢治は何故訪問応諾をドタキャンをしたのかということを論じてみたい。
そのために、まずは当時の農村のおかれた状況等に関して少し眺めてみる。
まずは、井上寿一氏は『戦前昭和の社会』において、
農村は疲弊していた。欧州大戦後の戦争景気の反動不況が都市よりも農村に深刻な打撃を与えたからである。農村雑誌の『家の光』が創刊されたのは、このような状況のなかだった。創刊号(一九二五(大正一四)年)のカラーの表紙はのどかな田園風景である。農婦が菖蒲の花を活けている。遠くには鯉のぼりが泳いでいる。
このような明るい表紙とは異なって、誌面には危機感が溢れていた。「本紙記者」は言う。「去る大正十年頃から急に農村問題が社会問題の中心となって……猫も杓子も口にし、筆にしなければならぬ大きな問題となった」。「今日迄の農村振興は何も空鉄砲である、不渡手形である。そこで何とか局面を転回して農民の実生活方面から根本の改造」をしなければならない。
<『戦前昭和の社会』(井上寿一著、講談社現代新書)、117p~>
というように農村雑誌『家の光』の創刊について論じている。
そしてまた、板垣邦子氏も『昭和戦前・戦中期の農村生活』において、大正14年~昭和3年頃の『家の光』に関して、
農村文化建設の提唱
創刊号以降昭和三年頃までの『家の光』は、芸術・娯楽を主な内容とした農村文化問題に力を入れている。この時期、この問題の占める比重は大きく、農民文学・農民美術・農民劇に関する記事は、農民芸術運動を盛り上げようとする意欲を感じさせる。家庭雑誌といいながら、農村青年層を対象とした文芸雑誌的傾向さえある。
農村の経済的不振、青年男女の都会集中、小作争議の頻発にみられる農村良風俗の荒廃を憂うという立場から、『家の光』は農村文化の建設を提唱する。その趣旨は、農村が独自の立場を堅持し、なおかつ現代文明を摂取して農村にふさわしい文化を建設し、生活の豊かさをとりもどさねばならないというものである。退廃に堕した都会文化への憧憬を捨て、健全な農村文化を築くべきであるという。
<『昭和戦前・戦中期の農村生活』(板垣邦子著、
三嶺書房)、18p~>
と同様なことを論じている。
そこで実際に当時の雑誌『家の光』を幾つか開いて見てみれば、二人の言う通りであり、
雑誌『家の光』は当時すこぶる疲弊していた農村を憂い、農民芸術運動を盛り上げようという意図で農民劇等に関する記事を載せたりしながら、農村文化の建設を提唱していた。
…………①
と言えることを知った。
するとここで思い出されるのが、大正15年4月1日付『岩手日報』のあの記事であり、賢治は記者の取材に対して、
(1) 現代の農村は経済的にも種々行きつまつてゐるやうに考へらる。
(2) そこで東京と仙台の大學あたりで自分の不足であった『農村経済』について少し研究したい。
(3) 半年ぐらゐは花巻で耕作にも従事し生活即ち藝術の生がいを送りたい。
(4) ために、幻燈會はまい週のやうに開さいする。
(5) レコードコンサートも月一囘位もよほしたい。
(6) 同志二十名ばかりいる。
(7) 自分がひたいにあせした努力でつくりあげた農作ぶつの物々交換をおこないたい。
というようなことをその際に答えていたわけだが、改めてこれら〝(1)~(7)〟と前頁の〝①〟とを見比べてみれば、当時の『家の光』と賢治とはかなり通底していたことに気付く。
そして板垣氏は続けて同書で、
農民芸術の振興
芸術については農民文学・農民劇・農民美術に関する記事が多く、寄稿者や座談会出席者として犬田卯、佐伯郁郎、白鳥省吾、中村星湖、渋谷栄一ら当時活発な運動を展開していた農民文芸会のメンバーがしばしば登場し、なかでも犬田卯の活躍がめだっている。
<前掲書、20p~>
とも述べており、農民芸術に関する『家の光』における寄稿者等には犬田卯、佐伯郁郎、白鳥省吾等がいて、中でも犬田卯の活躍が目立っていることはこれまた当時の雑誌『家の光』を見てみれば直ぐにわかる(巻末資料『犬田卯等の作品リスト』参照)。
一方で、時代が大正に入るとおびただしい数の雑誌が多くの大衆芸術を生み、「民衆芸術論」をより一層発展せしめたというし、農民文学運動はそのような時代背景の下に発生していた(『犬田卯の思想と文学』(安藤義道著、筑波書林)、49p~)という。つまり、この時代は「民衆芸術」が勃興し、それに伴って「農民文学運動」や「農民芸術運動」も盛り上がっていったと言える。そして前掲書で板垣氏が言う通り、第一次世界大戦後の不況により農村は経済的な打撃を受けた上に、青年男女の都会集中で農村は荒廃する一方だったから、それらの運動は、「退廃に堕した都会文化への憧憬を捨てて健全な農村文化を築くべく盛り上がった運動だった」と言えそうだ。
実際、例えば、白鳥省吾を始めとする「民衆詩派」(ただし世間は白鳥省吾を農民詩人と見て(〈註一〉)いた節もある)の詩人等が活躍し、犬田等が取り組んだ「農民文芸運動」では犬田のみならず、その一環として佐伯郁郎が先頭に立って「農民詩」の啓蒙をし、あるいは、『野良に叫ぶ』を出版した渋谷定輔の農民詩集が反響を巻き起こしていた時代でもあった。他にも、「黒耀会」の下で民衆美術運動を始めた望月桂、同様旺盛な「農民美術運動」を行った山本鼎、そして土田杏村等がおり、機構や組織としてはこの土田の『信濃自由大学』、賢治の『羅須地人協会』、松田甚次郎の『最上共働村塾』、はたまた、あの千葉恭の『研郷会』等があったということになろう。
そこで逆からこの時代を眺めてみると、『農民芸術概論』は賢治の全くのオリジナルであったというわけではなくて、当時澎湃として起こっていた「民衆芸術」のうねりの中で、「農民文学運動」や「農民芸術運動」を体系化・理論化しようとした一つが「農民文芸会」の『農民文芸十六講』であり、そして賢治の『農民芸術概論綱要』もその一つであると見ることができるのではなかろうか。つまり『農民芸術概論綱要』も「同時代(〈註二〉)性」から生まれた一つの産物であり、延いては賢治、犬田卯、佐伯郁郎、「農民文芸会」そして『家の光』等は皆強い相似性があると言える。
一方、川原仁左エ門は、
(賢治は)岩手県農会には盛岡に来れば殆ど寄り、当時、全国の各道府県農会報が毎月刊行して、賢治は之を二時間位借覧してゐた。
又、岩手県農会は農業関係の蔵書が相当数あつたものだ。この蔵書を賢治は読んでゐた。この記事につき大森技師とよく論戦してゐた。
<『宮沢賢治とその周辺』(川原仁左エ門編著)、280pより>
と述べているから、このような機会等を通じて賢治は少なくとも『家の光』にも目を通していたであろう。
さてそれではこれでだいたい準備ができたので、「旧校本年譜」の「大正十五年七月二十五日」の話に戻ろう。先に私は、この項の次のような記述、
盛岡啄木会の招きで講演のためにきた白鳥省吾・犬田卯が賢治訪問の希望を持っており、手紙で連絡があった。賢治も承諾の返事を出していたが、この日断わりの使いを出す。使者は下根子桜の家に寝泊りしていた千葉恭で午後六時ごろ講演会会場の仏教会館で白鳥省吾にその旨を伝える。
を取り上げ、賢治の「訪問応諾ドタキャン」は身勝手なものだったと結論づけたが、ではそもそも何が原因で賢治はドタキャンしたというのだろうか。そのことは一般には明らかにされていないようだ。
そこで常識的に考えれば、予定通りに白鳥省吾と犬田卯が来訪するのであれば、それをドタキャンすることはいくら「不羈奔放」な賢治といえども流石にあり得ないであろう。そのようなことをすれば、あまりにも身勝手であり、おかしいことだろうと言わざるを得ないからだ。よって、普通このような行為に及ぶとすれば、訪問応諾後に何か大きな条件の変化が起こっていたということが考えられる。
そこでそのことを検証してみようとしたところ、そのヒントを教えてくれそうなのが次の大正15年7月31日付『岩手日報』に載っていた「感謝の言葉」であり、次のようなことなどが述べられていた。
わたしたちは、実は花巻でも、講演し、釜石でもするはずであった。前者は、わざわざ花巻到着時間を電知し、せっかくの好摩の盆踊りも見ないで、やって行ったのに対して主催者側の不手際から、どこでどうやればいいかもわからぬ破目になって、阿部、米内、村井、加藤の四氏に御迷惑をかけて花巻遊園地むなしく(実は非常に愉快であったが)一日をくらしてしまうこととなり、釜石へは白鳥氏の急用のために果たさないでしまった。折角の機会、殊にも、犬田氏は多忙中を、わざわざやって来てくれたのに対して、只一ヶ所の講演は実に残念ではあった。
さてこの記事中の「わたしたち」の「わたし」とは誰のことかというと、佐伯郁郎のことである。実は、そもそもこの時の講演会は〝啄木会主催『農民文芸会盛岡講演会』〟というタイトルで開かれたものであり、この「農民文芸会」を当時実質的に取り仕切っていたのが犬田卯であるという。そして白鳥も佐伯も共に同会のメンバーであった。そこでだろう、この時の講演会には佐伯も同行しており、佐伯が代表してお礼を述べた言えるのがこの「感謝の言葉」となろう。
そこでこの記事に従えば、白鳥・犬田・佐伯の三人は25日の講演会の後の、翌日26日に花巻を訪れて講演をするつもりだったのだが、不手際があってそれが叶わなかったということを述べていたわけである。したがって、この三人は羅須地人協会を訪れて賢治に会うつもりだったということがわかる。
ということであれば、当初は白鳥と犬田の二人の訪問については賢治は事前に応諾していたのだが、その後、佐伯も一緒に訪れるということを賢治が知ったとなればこの変化は、その後に起こった「大きな変化」となり得るということを教えてくれる。つまり、ドタキャンの理由の可能性の一つとして、佐伯も実は一緒に羅須地人協会を訪れることを新たに知ったことであった、ということもあり得ると私は直感した。
そこでもう少し当時の新聞を調べてみたならば、大正15年7月22日付『岩手日報』に次のような、
岩手の地と農民の藝術
二十五日佛教會館で講演する佐伯氏談
來る二十五日夜啄木會主催の文藝講演會でフランスの農民藝術について講演すべき東京女子高等學院の教授佐伯郁郎氏は二十日夜行にて來盛したが同氏は次の如き語つた。
私は白鳥犬田の兩氏と同樣な農民藝術協會の會員で主としてフランスの農民藝術についてのお話しをしやうと考へて居ります我々同志の手で近く春陽堂から農民文藝第十二講と云ふ本を出版する事になつてゐるのでわたしは原稿執筆のため友人の好意に誘われて外山牧場でのこの一夏を送る事になつてゐるのです白鳥氏は農民的な詩人としての聲價は今改めて御話をする迄もなく詩壇の第一位を占むるものであると信じます、犬田氏はほんとうに農民自身として三十年の生ガイを土に即して謙ソンにしかも勇敢に生きた來た人で土の藝術家として故長塚節先生に師事し農民大衆の合理的な解放のために戦つて来た人です、氏は多分自分自己の体験から大地の藝術について素ボクにして迫力ある話しをさるゝ事と思ひます
<大正15年7月22日付『岩手日報』>
という「佐伯氏談」が載っていた。
そこで私は次のような別の可能性、
この記事を見た賢治は(そして実際見ていたと判断して構わないだろう)、佐伯等は近々「農民芸術について」体系化して「農民文藝十二講と云ふ本を出版する」予定であり、そのために佐伯は「原稿執筆のため友人の好意に誘われて外山牧場でのこの一夏を送る」ということを賢治は知った。しかも、彼らは「農民芸術」に関する理論を構築し間もなく公にするというではないか、ということも知ったので、賢治は急遽訪問応諾をドタキャンしたという可能性。
もあると直感した。それはまず第一に、賢治は「農民芸術概論」の完成のためにはここは会わない方が賢明だと急遽判断してドタキャンをしたという可能性があったことに私は気付き、第二に、いみじくも断りの使者千葉恭が、賢治は「その場合に彼等に會ふのは私は心をにごすことになるし」と言ったということと見事に符合しているからである。
つまり、賢治は当初は単に白鳥と犬田が来訪するということで訪問の応諾をしていたのだが、7月22日付『岩手日報』の記事等を見て、実は白鳥・犬田以外に佐伯もやって来て、しかもこの面々は近々「農民芸術について」体系化して「農民文藝十二講と云ふ本を出版する」ということを知ったし、そのあげく、佐伯はそのために「原稿執筆のため友人の好意に誘われて外山牧場でのこの一夏を送る事になつてゐる」というではないか。
そのような面々が訪問してくるとなればので、まさに「彼等に會ふのは私は心をにごすことになる」という理屈から、賢治はドタキャンしたという蓋然性が高まってきた。しかも、もしそうではなく、早い時点でこの訪問を謝絶しようと賢治が決意していたというのであれば、応諾していた白鳥等にできるだけ迷惑をかけたりしないためにも、また一緒に生活していた千葉恭に厭な思いをさせぬためにも、もっとましな断り方が賢治にはできたはずだが、実際にははそうしなかったことからもこのことは裏付けられる。
というのは、その断りの使者としては千葉恭よりもはるかにベターな適役宮澤安太郎がいたからだ。この年(大正15年)であれば、安太郎は既に中央大学を卒業して花巻に戻って、上町に「大正十三年十月、酒販店「十字屋」を開業し」ていた(『ワルトラワラ・第三十七号』、91p)ということだから、大正15年7月25日頃は安太郎は花巻に居たことになる。しかも、安太郎は賢治の従弟だし、同時に佐伯とも懇意(〈註三〉)だった。そこで、安太郎を断りの使者に立てれば、その謝絶の場で佐伯が取りなしてくれたでもあろうから、賢治が一旦応諾していた訪問を前もって早い時点で断りたかったのであれば、はるかに千葉恭よりも波風が立たないましなルート、つまり安太郎を通じて断ることだってあり得たのだ。にもかかわらず、賢治が安太郎を使者に立てなかったということは、やはりこの訪問謝絶は賢治の唐突な決断だったということを教えてくれるし、しかも、物事を思い立ったら遮二無二突き進むという賢治の性向もあってなおさらに賢治をしてそうさせた、という蓋然性が高い。
つまるところ、賢治の「農民藝術概論綱要」も「同時代性」を抜きにしては稿が成ることはなかったであろうということと、このドタキャンの大きな理由の一つとして、前掲の7月22日付『岩手日報』の記事があった蓋然性が高いのではなかろうかということを知って、私はひとまず腑に落ちた。さりながら、このことを実証することは容易でないということもまた明らかだから、現時点では、この節については可能性として以上右のようなことがあり得たという段階にとどめておきたい。
〈註一〉大正15年7月24日付『岩手日報』に、
啄木會主催本社後えんの文藝思汐講演會にのぞむべき農民詩人白鳥省吾氏の一行は二十五日午前十一時着の急行にて来盛する事に成つたが氏は着盛に先立ち啄木會に對し左の感想を寄せた。
という記事があり、当時世間は白鳥のことを「農民詩人」と見ていた節もある。
<註二> ただし同時代とは言え、『家の光』は大正14年4月に創刊されているから、賢治が下根子桜に移り住む1年前に既に創刊されていたことになる。また、「農民文芸研究会」は大正13年に結成されて犬田卯が中心となって活動していたし、同会が「農民文芸会」と改称され、同会の『農民文芸十六講』が出版されたのは大正15年10月であるという。
<註三> まずは、『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)補遺・伝記資料篇』(筑摩書房)の335pに次ような〔啄木会成立宣言文〕なるものが載っている。
△啄木会は遂に成立した。在京の純粋故郷出身の青年□五十余名を以て、
△七月十四五日頃盛岡で文学講演会を開く。出来るならば建碑費の幾分を儲けたいのだが結局は只我等の啄木運動プロパガンダに終わるだらう、費用が多くかヽるだらうから。…(筆者略)… 啄木会同志名(順不同)
石川準十郎、石川斌、木村不二男、船越一郎、村井源一、佐伯慎一、宮沢安太郎、高橋大作…(略)…深沢省三…(略)…宮沢賢治…(略)…
〔注〕大正十年六月十八日に結成された「啄木会」関係資料のひとつ。結成時に頒布されたものと思われる。
つまり、佐伯慎一(佐伯郁郎)、宮沢安太郎、宮澤賢治は共に『東京啄木会』のメンバーであったから、少なくともある程度は顔見知りであったであろう。
それから、昭和7年6月24日付『岩手毎日新聞』朝刊で、佐伯は、
◇読んでいく中に随分なつかしい顔にも出逢ひました。啄木はいはずもがな、堀越夏村氏は学校の先輩とも聞いてゐて遂にお目にかゝれないでしまつたし、宮沢賢治氏にはお目にかゝつたことがないのですが御親類の安太郎さんを通じて「修羅と春((ママ))」をいたゞいてゐます。
と述べていて、佐伯は『春と修羅』を安太郎を通じて貰ったと証言している。
したがって共に『東京啄木会の』メンバーであっただけではなく、安太郎は賢治から『春と修羅』を預かって佐伯にそれを渡すような間柄あったから、二人は懇意だったと言えるだろう。
***************************** 以上 ****************************
《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)
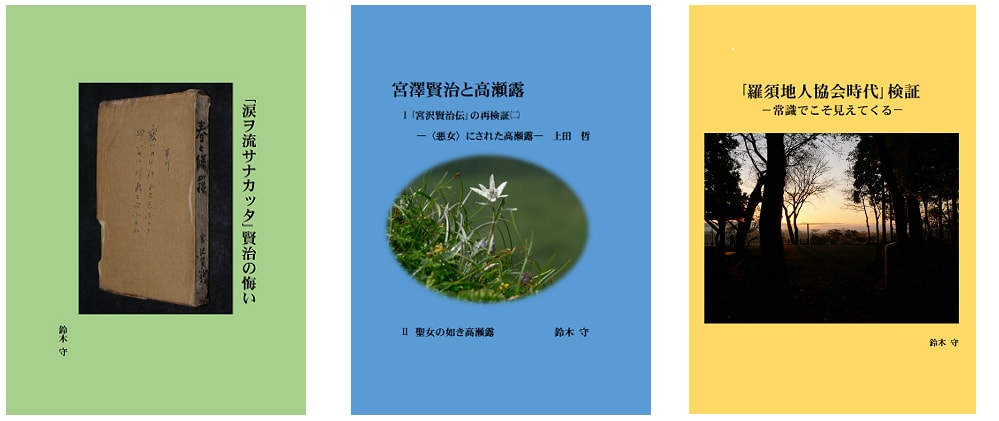
なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』