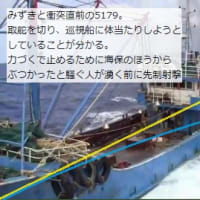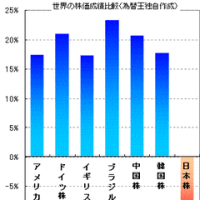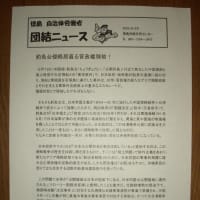聖書は、旧約と新約の複数の文書からなる文集みたいなものだが、旧約はユダヤ教の聖典、旧約・新約はキリスト教の聖典である。イスラム教は、マホメッドによるコーランを真の神の教えを伝える拠り所としているが、新約のキリストも預言者の一人とみなし、旧約や新約も聖典とみなされる。ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒、いずれも旧約聖典を聖典する聖典の民である。
聖書は、ここ2000年の世界の文化と歴史に多大な影響を与えてきたし、現在も与えている。キリスト教圏では、聖書は、単なる一冊の本ではなく、社会に浸透し人々の考えと行動を左右する社会テキストとなっている。聖書をふまえて多くの文学や思想作品が書かれてきた。教会、祭り、毎日の言葉、親の話しや行動、絵本、教師の話しや行動、音楽、演劇、映画、あらゆる社会の意味あるメッセージになかに様々な形で聖書の考えが書き込まれている。「GOD―神の伝記」 には、こう書かれている。「神は欧米の家庭においては日常のありふれた言葉以上のものである。すなわち神は、歓迎されていようといまいとにかかわらず、欧米の家族の実質的な一員なのである。」(GOD、p15.)キリスト教圏では、聖書を全く読まなくとも、社会テキストとしての聖書から、影響を受けざるをえない。
「欧米人の多くはもはや神を信じていない。だが、失った信仰は、失った宝のように、まだその影響を引きずっている。何不自由なく育て上げられた若者がいたとしよう。彼は青年に達すると、自分の財産を手放して貧しい者たちと連帯して生きるかもしれない。だが、その場合でも、彼の性格は何一つ不自由なく育て上げられた男のそれであろう。なぜなら、彼は自己の歴史を手放すことなどできないからである。同じようにして、何世紀にもわたる、厳格で、信心深い性格の形成は、たとえその基が、多くの者から取り除かれたとはいえ、確固として立つ人間の性格の規範を創出してきた。われわれ欧米人が異なる規範を有する文化に出会ったり、「日本人は違っている」と思わず呟くとき、われわれは間接的にだが、われわれ自身の規範、すなわち人間のあるべき姿について継承してきた理解が他の理解と相容れずにつづいてきたことを確認する。.........両者の間には大きな違いが存在する。なぜなら、聖書の神が欧米人の鏡であった幾世紀もの間、日本人はそれとは異なる宗教・文化の鏡の中を覗き込んでいたからである。」(GOD、pp12-13.)
聖書が社会テキストして書き込まれていない日本で育った我々は、聖書を知ろうということになるが、福音書は別として、聖書を読み通すのはなかなか難しい。死の床に聖書を置いたという芥川も「侏儒の言葉」(松本清張はこの本について幼稚だと評している。たしかに高校生向きかもしれない。)で、旧約について、個人の知恵は民族の知恵にしかない、しかしもうすこし簡潔であればなどと書いている。
素人なりにざっと聖書を読んでみて驚くのは、新約のキリストの民族を越えた愛と平和の教えと、旧約における自民族中心主義の血なまぐさい虐殺の物語の共存である。長谷川は、バベルの謎―ヤハウィストの冒険-で、旧約の神には、全能の創造主と部族の神の二系統の物語が、はいりこんだものと指摘している。たしかに、嫉妬深く、疑り深く、残酷で、怒りっぽい部族の神としてのエホバは、どうも全能の創造主とは違うようだ。また、旧約はユダヤ民族を中心とした民族の歴史と預言者、神の話しであるのに対し、新約はあくまでキリストを中心とする教団の教えを説いたもので、両者は分けて考えた方が良さそうだ。
こうした素朴な疑問を抱いて、解説書にあたる。たしかに聖書の解説書は沢山ある。しかし、信者の立場からの解説だったり、歴史の紹介だったり、信者でないにしても、ただひたすら聖書をありがたがるお花畑の本だったりする。聖書学には、膨大な文献学的、歴史的研究の蓄積がある。これらは研究としては貴重だが、一般の知的な読者層に対しては専門的すぎる。
「誰も教えてくれない聖書の読み方」には、聖書に何が書いてあるのか、旧約と新約の断絶、性格の悪い神エホバ、旧約の神が推奨する敵部族のだましと徹底的虐殺(割礼をしたら仲間として友好関係をむすぼうと持ちかけ、それを信じ割礼をしたら、痛がっている間に皆殺し、神様は良くやったと大喜び。あるいは、敵の大人の男達だけを皆殺しにしたら、ぬるいとしかりつけ、男は子供も殺せ、男と交わった経験のある女も殺せ、男と交わった経験のない女は孕ませろときつく命令。等々。)、女性差別、等々、あれこれもったいぶらずに、分かりやすくまとめてある。これを読むと、十字軍による略奪と殺戮、新大陸での侵略と大規模な虐殺など、聖書の精神からの逸脱でなく、旧約の精神にのっとっていただろうことがよく分かる。近年では、ボスニア紛争における民族浄化など、旧約の神が嘉し賜うところだろう。もちろん旧約は、伝道の書のような哲学的考察、ヨブ記などの神義論、雅歌のような文学、などなど、芥川の言う民族の知恵が結集された複数の側面をもったテキストではある。しかし、砂漠の古代文明における部族間の生き残りのための熾烈なだましと虐殺、選民思想を伝えた、強烈な文化ウィルスを、そのテキストの中核に持っていることも事実である。
キリスト教が、一筋縄でいかないのは、こうした旧約に、強引に、キリストによる民族を越えた愛と平和の教えを接合させていることである。マタイ福音書冒頭の系譜についてで書いたように、マタイ福音書の冒頭は、新約を旧約の物語につなぐことを狙ったものだが、旧約の由緒ある父系の系譜を列挙してきて、最後は、処女懐胎、アレー!とくるが、とにかく無理でも旧約と新約を接続してしまっている。
「筆者が以下で示すように、神はひとつの性格の中で諸人格が融合したものである。これらの人格間での緊張が神をわかりにくいものにするが、それはまた神を抗しがたい魅力のあるものにさえする。欧米人は、神の徳を意識的に見習っているものの、無意識のうちに、神の「一」性と「多」性の間で不安を誘発する緊張を自分のものにしている。.....われわれがこの人は本物だとする人物は、その人のアイデンティティがいくつかの相容れないサブ・アイデンティティをひとつに束ねている人なのである。.....さまざまな役割と演じることがうまいだけの者は、この規範に達しないでいる。.....複雑でない単純な人たちもまた、この規範に達しないでいる。」(GOD、pp16-17.)
このようにキリスト教の神を鏡とし、ダイナミックな人格形成が行われる。こうした鏡を持たない文化の人格は素朴である。ここで、人格に、旧約と新約の二重性をとりこむと、筋金入りの恐ろしい偽善者が出来上がることに注意したい。ジミー・カーター前大統領のように、新約の精神が前面に出た善意の人はいる。しかし指導者としては単純でお人好しすぎたのかもしれない。フランクリン・ルーズベルトやクリントンなど、リベラルな装いの新約のうわべに旧約の残酷さや狡猾さをちゃんと備えた、より複雑でダイナミックな人格である。
イスラエル大使館公使を勤めたことのある今西は「聖書の誤り―キリスト教文明の大罪」で、旧約が自民族中心主義によるだましと虐殺の正統化をもたらしてきたことを痛烈に批判している。アメリカ大統領が就任の宣誓で聖書の手を置くが、聖書を使って宣誓するなら新約聖書とキリストの精神に対してのみにすべきだと主張している。もちろん、だましと虐殺のテキストは旧約だけではない。旧約の影響なしにも、梅棹の指摘するユーラシアの破壊勢力の影響をうけた中国を初めとして、だましと虐殺の文化的伝統は様々に存在する。人間の同じ種内における組織的殺戮には、チンパンジー由来の側面、集団力学による部分も否定しがたい。ではあるが、砂漠の古代文明における部族間の生き残りのための熾烈なだましと虐殺の教えを継承して、旧約がそのテキストの中核にしこんだ文化ウィルスが、自民族中心主義によるだましと組織的虐殺を世界に広める上で大きな役割を担ったのも事実だろう。
聖書は、ここ2000年の世界の文化と歴史に多大な影響を与えてきたし、現在も与えている。キリスト教圏では、聖書は、単なる一冊の本ではなく、社会に浸透し人々の考えと行動を左右する社会テキストとなっている。聖書をふまえて多くの文学や思想作品が書かれてきた。教会、祭り、毎日の言葉、親の話しや行動、絵本、教師の話しや行動、音楽、演劇、映画、あらゆる社会の意味あるメッセージになかに様々な形で聖書の考えが書き込まれている。「GOD―神の伝記」 には、こう書かれている。「神は欧米の家庭においては日常のありふれた言葉以上のものである。すなわち神は、歓迎されていようといまいとにかかわらず、欧米の家族の実質的な一員なのである。」(GOD、p15.)キリスト教圏では、聖書を全く読まなくとも、社会テキストとしての聖書から、影響を受けざるをえない。
「欧米人の多くはもはや神を信じていない。だが、失った信仰は、失った宝のように、まだその影響を引きずっている。何不自由なく育て上げられた若者がいたとしよう。彼は青年に達すると、自分の財産を手放して貧しい者たちと連帯して生きるかもしれない。だが、その場合でも、彼の性格は何一つ不自由なく育て上げられた男のそれであろう。なぜなら、彼は自己の歴史を手放すことなどできないからである。同じようにして、何世紀にもわたる、厳格で、信心深い性格の形成は、たとえその基が、多くの者から取り除かれたとはいえ、確固として立つ人間の性格の規範を創出してきた。われわれ欧米人が異なる規範を有する文化に出会ったり、「日本人は違っている」と思わず呟くとき、われわれは間接的にだが、われわれ自身の規範、すなわち人間のあるべき姿について継承してきた理解が他の理解と相容れずにつづいてきたことを確認する。.........両者の間には大きな違いが存在する。なぜなら、聖書の神が欧米人の鏡であった幾世紀もの間、日本人はそれとは異なる宗教・文化の鏡の中を覗き込んでいたからである。」(GOD、pp12-13.)
聖書が社会テキストして書き込まれていない日本で育った我々は、聖書を知ろうということになるが、福音書は別として、聖書を読み通すのはなかなか難しい。死の床に聖書を置いたという芥川も「侏儒の言葉」(松本清張はこの本について幼稚だと評している。たしかに高校生向きかもしれない。)で、旧約について、個人の知恵は民族の知恵にしかない、しかしもうすこし簡潔であればなどと書いている。
素人なりにざっと聖書を読んでみて驚くのは、新約のキリストの民族を越えた愛と平和の教えと、旧約における自民族中心主義の血なまぐさい虐殺の物語の共存である。長谷川は、バベルの謎―ヤハウィストの冒険-で、旧約の神には、全能の創造主と部族の神の二系統の物語が、はいりこんだものと指摘している。たしかに、嫉妬深く、疑り深く、残酷で、怒りっぽい部族の神としてのエホバは、どうも全能の創造主とは違うようだ。また、旧約はユダヤ民族を中心とした民族の歴史と預言者、神の話しであるのに対し、新約はあくまでキリストを中心とする教団の教えを説いたもので、両者は分けて考えた方が良さそうだ。
こうした素朴な疑問を抱いて、解説書にあたる。たしかに聖書の解説書は沢山ある。しかし、信者の立場からの解説だったり、歴史の紹介だったり、信者でないにしても、ただひたすら聖書をありがたがるお花畑の本だったりする。聖書学には、膨大な文献学的、歴史的研究の蓄積がある。これらは研究としては貴重だが、一般の知的な読者層に対しては専門的すぎる。
「誰も教えてくれない聖書の読み方」には、聖書に何が書いてあるのか、旧約と新約の断絶、性格の悪い神エホバ、旧約の神が推奨する敵部族のだましと徹底的虐殺(割礼をしたら仲間として友好関係をむすぼうと持ちかけ、それを信じ割礼をしたら、痛がっている間に皆殺し、神様は良くやったと大喜び。あるいは、敵の大人の男達だけを皆殺しにしたら、ぬるいとしかりつけ、男は子供も殺せ、男と交わった経験のある女も殺せ、男と交わった経験のない女は孕ませろときつく命令。等々。)、女性差別、等々、あれこれもったいぶらずに、分かりやすくまとめてある。これを読むと、十字軍による略奪と殺戮、新大陸での侵略と大規模な虐殺など、聖書の精神からの逸脱でなく、旧約の精神にのっとっていただろうことがよく分かる。近年では、ボスニア紛争における民族浄化など、旧約の神が嘉し賜うところだろう。もちろん旧約は、伝道の書のような哲学的考察、ヨブ記などの神義論、雅歌のような文学、などなど、芥川の言う民族の知恵が結集された複数の側面をもったテキストではある。しかし、砂漠の古代文明における部族間の生き残りのための熾烈なだましと虐殺、選民思想を伝えた、強烈な文化ウィルスを、そのテキストの中核に持っていることも事実である。
キリスト教が、一筋縄でいかないのは、こうした旧約に、強引に、キリストによる民族を越えた愛と平和の教えを接合させていることである。マタイ福音書冒頭の系譜についてで書いたように、マタイ福音書の冒頭は、新約を旧約の物語につなぐことを狙ったものだが、旧約の由緒ある父系の系譜を列挙してきて、最後は、処女懐胎、アレー!とくるが、とにかく無理でも旧約と新約を接続してしまっている。
「筆者が以下で示すように、神はひとつの性格の中で諸人格が融合したものである。これらの人格間での緊張が神をわかりにくいものにするが、それはまた神を抗しがたい魅力のあるものにさえする。欧米人は、神の徳を意識的に見習っているものの、無意識のうちに、神の「一」性と「多」性の間で不安を誘発する緊張を自分のものにしている。.....われわれがこの人は本物だとする人物は、その人のアイデンティティがいくつかの相容れないサブ・アイデンティティをひとつに束ねている人なのである。.....さまざまな役割と演じることがうまいだけの者は、この規範に達しないでいる。.....複雑でない単純な人たちもまた、この規範に達しないでいる。」(GOD、pp16-17.)
このようにキリスト教の神を鏡とし、ダイナミックな人格形成が行われる。こうした鏡を持たない文化の人格は素朴である。ここで、人格に、旧約と新約の二重性をとりこむと、筋金入りの恐ろしい偽善者が出来上がることに注意したい。ジミー・カーター前大統領のように、新約の精神が前面に出た善意の人はいる。しかし指導者としては単純でお人好しすぎたのかもしれない。フランクリン・ルーズベルトやクリントンなど、リベラルな装いの新約のうわべに旧約の残酷さや狡猾さをちゃんと備えた、より複雑でダイナミックな人格である。
イスラエル大使館公使を勤めたことのある今西は「聖書の誤り―キリスト教文明の大罪」で、旧約が自民族中心主義によるだましと虐殺の正統化をもたらしてきたことを痛烈に批判している。アメリカ大統領が就任の宣誓で聖書の手を置くが、聖書を使って宣誓するなら新約聖書とキリストの精神に対してのみにすべきだと主張している。もちろん、だましと虐殺のテキストは旧約だけではない。旧約の影響なしにも、梅棹の指摘するユーラシアの破壊勢力の影響をうけた中国を初めとして、だましと虐殺の文化的伝統は様々に存在する。人間の同じ種内における組織的殺戮には、チンパンジー由来の側面、集団力学による部分も否定しがたい。ではあるが、砂漠の古代文明における部族間の生き残りのための熾烈なだましと虐殺の教えを継承して、旧約がそのテキストの中核にしこんだ文化ウィルスが、自民族中心主義によるだましと組織的虐殺を世界に広める上で大きな役割を担ったのも事実だろう。