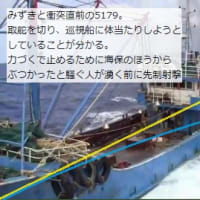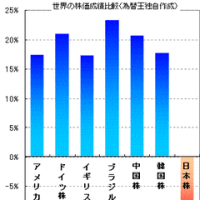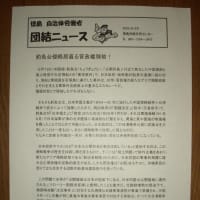ずいぶん前に、緑夢で「ぐりむ」と読ませるという記事を読み、はやりの万葉仮名風の表記をも超えた大胆さというか放恣さに、驚いた記憶がある。トリノオリンピックで、その後の消息に出会う事が出来た。
日本語の人名表記は、でたらめかつ、混乱のきわみの世界である。日本には、約14万の苗字がある。また、珍妙なよみの個人名も日々うまれている。日本語における文字コードの問題は、人名表記の問題である。
よみと漢字の対応のでたらめは、苗字と個人名の両方で大規模にしょうじている。苗字には、なぜそうよむかわからないようなものがおおい。たとえば、五十嵐(いがらし)、乃位(のぞき)など。紫田(しばた)は、「紫」を「柴」とまちがえてつかったのを、そのままよみにしてしまったものである。また、いくとおりものよみががあるものもある。四方(ヨカタ、シホウ、シカタ)など。また、ひとつの音に対応する苗字の漢字はきわめておおい。たとえば、「ソガ」にたいしては、蘇我、曽我、十川、十河、宗丘、宗宜、宗岳、宗我、宗賀、崇賀、我何、曽加、曽宜、曽賀、曾宜、曾我、曾谷、素我、素賀、蘇何、蘇宜、蘇宗、蘇賀など、あとJIS第二水準では表記できない文字をつかった「ソガ」が二種類ある。一方、名前のほうは、名前につかう漢字の制限はあるが、漢字とよみの対応の制約はない。このため、緑夢(ぐりむ)などの外国語の音をあててもよいし、温大(はると)など、よみはどうふっても自由である。最近のはやりは、沙矢香(さやか)などの万葉仮名風の表記とよみである。以上の結果として、人名の名簿では、漢字とよみがなの両方を参照しないと個人を識別してよぶことができなくなる。
苗字には、さらに異字体の問題がある。渡邊・渡辺、藤澤・藤沢、広瀬・廣瀬、程度ではない。手書きにおける字体のすこしの差異も、戸籍の電算化とともに、異字体として登録されてしまう。学校の名簿でも、梯子高などは、JIS第二水準までのパソコンでは、対応するフォントなしとして、ゲタ(〓)で表示されてしまう。「團」という作曲家は、「団」という宛名の郵便物はすべてうけとりを拒否したと自慢している。これは、文字フェティシズム、文字の呪術崇拝をほこっているようなものである。
名前の出鱈目な読みの新感覚の世界を見て、以前、戸籍の電算化とかで、役所で初めてみる字体のフォントを示され、あなたの苗字は電算化するとこうなりますとか言われ、役人と言い合いになり、こんな文字フェチを飼うために税金を払っているのかと憤慨した事を思い出した。一方には、漢字の字体に拘泥し、判子で一杯の、そして奇怪なお役所言葉と整備文の形式主義の世界があり、もう一方には出鱈目な読みのフィーリング世界がある。簡潔明解な日本語など知ったことではないというのだろうか、両方で日本語をもてあそんでいる。
日本を代表する人類学者の一人である梅棹忠夫氏は、日本語における複雑で煩瑣な文字表記に、大文明を担う文字表記システムとしては問題があると、早くから警鐘をならしてきた。日本語の文字表記の混乱を是正するためには、ひらがな表記による名前の音を一義としてもっと大切にし、漢字の字体とよみとの対応は標準的なものに制限する必要がある。オングが名著「声の文化と文字の文化」で説いているように、文字や記号システムが思考や文化のありかたに与える影響は思いのほか大きい。
日本語の人名表記は、でたらめかつ、混乱のきわみの世界である。日本には、約14万の苗字がある。また、珍妙なよみの個人名も日々うまれている。日本語における文字コードの問題は、人名表記の問題である。
よみと漢字の対応のでたらめは、苗字と個人名の両方で大規模にしょうじている。苗字には、なぜそうよむかわからないようなものがおおい。たとえば、五十嵐(いがらし)、乃位(のぞき)など。紫田(しばた)は、「紫」を「柴」とまちがえてつかったのを、そのままよみにしてしまったものである。また、いくとおりものよみががあるものもある。四方(ヨカタ、シホウ、シカタ)など。また、ひとつの音に対応する苗字の漢字はきわめておおい。たとえば、「ソガ」にたいしては、蘇我、曽我、十川、十河、宗丘、宗宜、宗岳、宗我、宗賀、崇賀、我何、曽加、曽宜、曽賀、曾宜、曾我、曾谷、素我、素賀、蘇何、蘇宜、蘇宗、蘇賀など、あとJIS第二水準では表記できない文字をつかった「ソガ」が二種類ある。一方、名前のほうは、名前につかう漢字の制限はあるが、漢字とよみの対応の制約はない。このため、緑夢(ぐりむ)などの外国語の音をあててもよいし、温大(はると)など、よみはどうふっても自由である。最近のはやりは、沙矢香(さやか)などの万葉仮名風の表記とよみである。以上の結果として、人名の名簿では、漢字とよみがなの両方を参照しないと個人を識別してよぶことができなくなる。
苗字には、さらに異字体の問題がある。渡邊・渡辺、藤澤・藤沢、広瀬・廣瀬、程度ではない。手書きにおける字体のすこしの差異も、戸籍の電算化とともに、異字体として登録されてしまう。学校の名簿でも、梯子高などは、JIS第二水準までのパソコンでは、対応するフォントなしとして、ゲタ(〓)で表示されてしまう。「團」という作曲家は、「団」という宛名の郵便物はすべてうけとりを拒否したと自慢している。これは、文字フェティシズム、文字の呪術崇拝をほこっているようなものである。
名前の出鱈目な読みの新感覚の世界を見て、以前、戸籍の電算化とかで、役所で初めてみる字体のフォントを示され、あなたの苗字は電算化するとこうなりますとか言われ、役人と言い合いになり、こんな文字フェチを飼うために税金を払っているのかと憤慨した事を思い出した。一方には、漢字の字体に拘泥し、判子で一杯の、そして奇怪なお役所言葉と整備文の形式主義の世界があり、もう一方には出鱈目な読みのフィーリング世界がある。簡潔明解な日本語など知ったことではないというのだろうか、両方で日本語をもてあそんでいる。
日本を代表する人類学者の一人である梅棹忠夫氏は、日本語における複雑で煩瑣な文字表記に、大文明を担う文字表記システムとしては問題があると、早くから警鐘をならしてきた。日本語の文字表記の混乱を是正するためには、ひらがな表記による名前の音を一義としてもっと大切にし、漢字の字体とよみとの対応は標準的なものに制限する必要がある。オングが名著「声の文化と文字の文化」で説いているように、文字や記号システムが思考や文化のありかたに与える影響は思いのほか大きい。