国書刊行会から発行されていた「ソラリス」が文庫化され本屋の平台に並んでいたのを見かけついつい購入しました。

本作は飯田規和訳で「ソラリスの陽のもとに」としてハヤカワ文庫で刊行されていましたが、従来版がロシア語からの訳で、本書はポーランド語から直訳というのが売りです。
ロシア語版でカットされていた部分を追加している「完全版」とのこと。
原書は1961年刊行です。
'12年ローカス誌オールタイムベストでは東欧圏の作品としては最上位の25位。
日本での人気はとても高く’06年、'14年ともにSFマガジンオールタイムベストで1位になっています。
私が中高生時代(1980年頃)も本作と「幼年期の終わり」「火星年代記」「夏への扉」辺りはベストを決めると上位に来ていた記憶があります。
息の長い作品ですねぇ。
昔から人気ではあったので従来版は高校生くらいの時(30年弱前)に買っていたのですがずっと未読でやっと読んだのが10年位前で結構感動した記憶があります。
そこから私の中で「SFブーム」になりそうにもなったのですが…。
その時はそのまま立ち消えここ2、3年の「マイSFブーム」に至っております。
内容紹介(裏表紙記載)
惑星ソラリス――この静謐なる星は意思を持った海に表面を覆われていた。惑星の謎の解明のため、ステーションに派遣された心理学者ケルヴィンは変わり果てた研究員たちを目にする。彼らにいったい何が? ケルヴィンもまたソラリスの海がもたらす現象に囚われていく……。人間以外の理性との接触は可能か?――知の巨人が世界に問いかけたSF史上に残る名作。レム研究の第一人者によるポーランド語原典からの完全翻訳版。
10年前に読んだきりの作品ですから、読みだすまでほとんど内容を忘れていましたが読み始めると結構思い出しました。
ケルヴィンがソラリス上のステーションに到着直後のなんとも不可解な状況がミステリアスでハラハラした記憶があったのですが、今回筋立てはわかっていたので読み出しから今一つ作品を楽しむ気分になれませんでした。
そんなこんなのためか10年前くらいに読んだ時より全体的にインパクトは薄めでした。
ウリの「未訳分」はほとんどソラリス学のところのようで違いはそれほど感じられませんでした。
(詳細に比べてないのでかなりいい加減です)
「人間の心」の不可知性と決定的に異なる存在との意思疎通の不可能性、ひいては「超越した存在」の不可知性・存在可能性などを象徴的に描いている作で刊行された1961年という時代を考えるとインパクトのあった作品なんでしょうが、今日的に考えて「オールタイムで1位」というのは「ちょっとどうかなぁ?」とも感じました。
(私の読み方が浅いということはあるとは思います。)
全惑星的な生命体という点ではアシモフの「ネメシス」とかなりダブるのですが、アシモフがあくまで通俗的に「少女」と「人情味のある惑星生命体」との心のふれあいというテーマだったかと思うので「真逆だなぁ…」という意味では興味深かったです。
ある意味アシモフの方が「そんなことあるはずないよなぁ…」ということを描いている点ではシュールな気もします。(笑)
かなり「真剣」な作品でしたのでもっと「遊び」がある作品の方が私の好みなんでしょうねぇ。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村

本作は飯田規和訳で「ソラリスの陽のもとに」としてハヤカワ文庫で刊行されていましたが、従来版がロシア語からの訳で、本書はポーランド語から直訳というのが売りです。
ロシア語版でカットされていた部分を追加している「完全版」とのこと。
原書は1961年刊行です。
'12年ローカス誌オールタイムベストでは東欧圏の作品としては最上位の25位。
日本での人気はとても高く’06年、'14年ともにSFマガジンオールタイムベストで1位になっています。
私が中高生時代(1980年頃)も本作と「幼年期の終わり」「火星年代記」「夏への扉」辺りはベストを決めると上位に来ていた記憶があります。
息の長い作品ですねぇ。
昔から人気ではあったので従来版は高校生くらいの時(30年弱前)に買っていたのですがずっと未読でやっと読んだのが10年位前で結構感動した記憶があります。
そこから私の中で「SFブーム」になりそうにもなったのですが…。
その時はそのまま立ち消えここ2、3年の「マイSFブーム」に至っております。
内容紹介(裏表紙記載)
惑星ソラリス――この静謐なる星は意思を持った海に表面を覆われていた。惑星の謎の解明のため、ステーションに派遣された心理学者ケルヴィンは変わり果てた研究員たちを目にする。彼らにいったい何が? ケルヴィンもまたソラリスの海がもたらす現象に囚われていく……。人間以外の理性との接触は可能か?――知の巨人が世界に問いかけたSF史上に残る名作。レム研究の第一人者によるポーランド語原典からの完全翻訳版。
10年前に読んだきりの作品ですから、読みだすまでほとんど内容を忘れていましたが読み始めると結構思い出しました。
ケルヴィンがソラリス上のステーションに到着直後のなんとも不可解な状況がミステリアスでハラハラした記憶があったのですが、今回筋立てはわかっていたので読み出しから今一つ作品を楽しむ気分になれませんでした。
そんなこんなのためか10年前くらいに読んだ時より全体的にインパクトは薄めでした。
ウリの「未訳分」はほとんどソラリス学のところのようで違いはそれほど感じられませんでした。
(詳細に比べてないのでかなりいい加減です)
「人間の心」の不可知性と決定的に異なる存在との意思疎通の不可能性、ひいては「超越した存在」の不可知性・存在可能性などを象徴的に描いている作で刊行された1961年という時代を考えるとインパクトのあった作品なんでしょうが、今日的に考えて「オールタイムで1位」というのは「ちょっとどうかなぁ?」とも感じました。
(私の読み方が浅いということはあるとは思います。)
全惑星的な生命体という点ではアシモフの「ネメシス」とかなりダブるのですが、アシモフがあくまで通俗的に「少女」と「人情味のある惑星生命体」との心のふれあいというテーマだったかと思うので「真逆だなぁ…」という意味では興味深かったです。
ある意味アシモフの方が「そんなことあるはずないよなぁ…」ということを描いている点ではシュールな気もします。(笑)
かなり「真剣」な作品でしたのでもっと「遊び」がある作品の方が私の好みなんでしょうねぇ。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










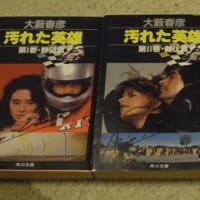
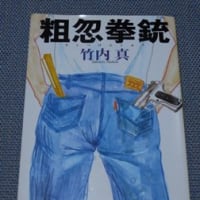
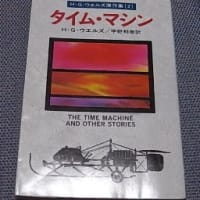
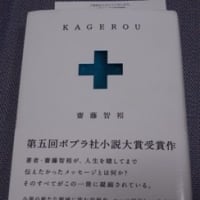
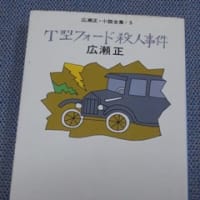
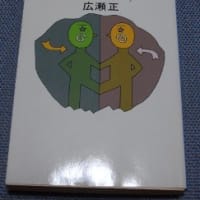


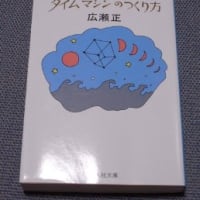
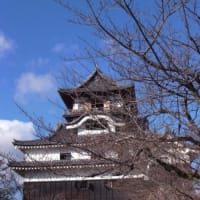
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます