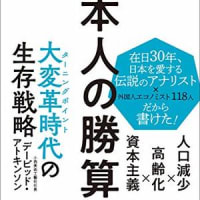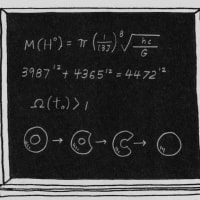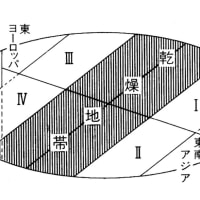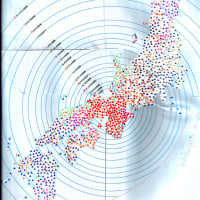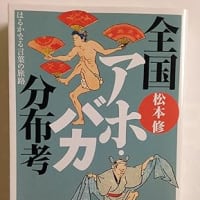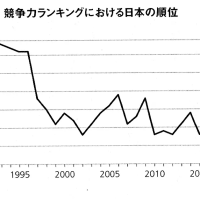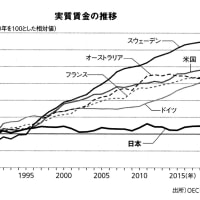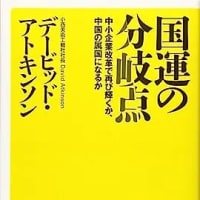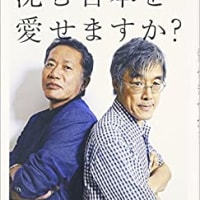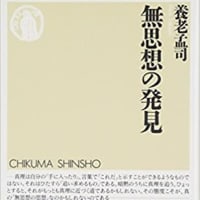セクハラ恐竜の存在
財務省の福田淳一事務次官のテレビ朝日記者へのセクハラ問答(事務次官は「言葉遊び」と強調)は、非常に不快な事件である。
① まず、福田次官の認識。「(女性の応答を含め)録音全体を復元してくれたら、セクハラでないことが分かる」と言っていたが、裏を返せば「女性記者も楽しんでいた」ということだろう。自分が楽しんでいたのだから、相手も楽しんでいたはず…とは、いかにもエリート然とした独善的な考え方である。誰かが「(セクハラに関する)恐竜の生き残り」と称していたが、その通り。
② テレビ朝日の対応。女性記者が上司に相談したにもかかわらず、消極的な態度で結果的にもみ消したこと。セクハラへの意識の低さは、財務省並みではないか。本筋から言えば、女性記者とテレビ朝日が、福田次官を訴えるべきであった。財務省とテレビ会社では、力が違いすぎる…というなら、ベトナム戦争の際の米軍発表の嘘を暴いたニューヨークタイムス、ワシントンポスト紙が連邦国家と裁判で争った故事を思い出してはいかがか。
③ 思い余った女性記者が週刊新潮に録音データを持ち込んで記事にしたこと。テレビ記者として取材で得た情報は、第三者に洩らしてはならない。切羽詰っていたとはいえ、この点で道義的な責任は生ずる。かつては、沖縄の返還に伴う裏の約束を毎日新聞の記者が掴んだのはいいが、その情報を社会党の代議士に流して国会で質問させた事件があった(西山事件)。こういうことがあるから、第三者への提供は厳禁されているのである。これが三つ目の割り切れなさ。
④ 福田次官と何度も夜の店で取材をしていた女性記者の意図が分からない。事務次官といえば、官僚のトップ。そこから特ダネに匹敵するようなニュースを聞きだすことは至難の業である。責任ある地位だからこそ、当たり障りのない意見しか出てこないのが当然である、と思わなければならない。いくら酒の席であろうが、1対1であろうが無理である。その意味で、この記者は取材のイロハを知らないといえる。特種を狙う記者は、その部署でくすぶっている反主流派の人物を狙うものである。福田次官にしてみりゃ、格好の暇つぶし相手だっただろう。要するに、おちょくられているのである。9割は次官が悪いが、1割は無知な女性記者の責任。テレビ朝日の上司が、彼女に張り付かせたのであれば、上司の責任でもある。
⑤ 問題が広がりを見せたころ、野党の女性国会議員を中心に「#Me Too」のプラカードを掲げた一団が、財務省を訪れ、玄関で守衛と押し合いをした。この女性議員たちも福田次官と似たような世代である。今から40年前、50年前の日本はセクハラという言葉もなく、卑猥な言葉や通勤電車の痴漢が跋扈(ばっこ)していた時代であった。同じ時代を生きていた者として、彼女たちの怒りはよく分かる。しかし、それでも私には「#Me Too」のプラカードへの違和感は残っている。この「#Me Too」はもともとハリウッドの発祥である。カードを掲げてあらわれた女優さんたちは、心の葛藤を乗り越え、相当の勇気をふりしぼって登場したに違いないのである。その姿勢が多くの共感を得たのであった。しかし、財務省に押しかけた議員たちには、そうした苦悩が見えなかった。というと、言い過ぎになるかもしれない。女性がどれだけ抑圧されてきたか、と説教をくらうに違いない。しかし、それならもっと効果的に訴えなければならない。政治家は国民に訴える商売だからこそ、そこに工夫が要求されるのである。その点、「#Me Too」のプラカードを掲げた一団は、流行に乗った気楽なおばさんたちという印象が強かった。安易なのである。もう少し知恵を働かせてもらいたかったなあ…というのが、私の要求である。
⑥ 結論として、セクハラは一部の男性には依然として鈍感さと頑固さをもって残り、同時に女性の抗議も上滑りに終わって、日本は大して変わらないと予想できたところが、大変に切ない出来事であった。そうそう。立憲民主党にはセクハラ議員が何人かいたね。随分、処分が甘かった、という記憶がある。他人の不倫には厳しく、自分のことになると質問をシャットアウトする山尾志桜里議員もいる。立憲民主党はこれらの議員のクビを切って模範を示してはどうだろうか。世間の喝さいを浴びると思うよ。
福田次官の「言葉遊び」は度が過ぎる
●たはむれの猥褻(わいせつ)会話のそのあまり軽きを責められ三歩あゆまず
(本歌 たはむれに母を背負いてそのあまり軽きに泣きて三歩あゆまず 石川啄木)
(蛇足)通常の取材の最中に、「胸さわっていい?」とか「キスしていい?」とか、会話としてはおよそ理解しがたい猥褻さである。しかも、反省の色がなく発言が軽い。記者たちに囲まれ「三歩あゆまず」となったのは、歌のとおり。
まだ、セクハラの意味が分からない(次官)
●吹くからにテレビ記者のしをるればむべ「言葉遊び」をセクハラといふらむ
(本歌 吹くからに秋の草木のしをるればむべ山風を嵐といふらむ 文屋康秀)
(蛇足)言葉遊びはホステスさんとなら成立するだろう。それが商売だからである。福田次官の言い分は強引に聞こえる。
次官にしてみれば晴天の霹靂
●店先のつれなく見えし別れより新潮ばかり憂きものはなし
(本歌 有明のつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし 壬生忠岑)
(蛇足)エリート街道を走ってきた次官には、自らの間違いに気づくことは難しかろう。週刊新潮とは対決するつもりだろう。
「#Me Too」には流行に乗った安易さが
●黒服が「#Me Too」かかげて財務省雄叫びあげて肩を並べる
(本歌 白菜が赤帯締めて店先にうっふんうっふん肩を並べる 俵万智)
(蛇足)60-70年前、日本の商品は外国の猿マネだといわれてきた。しかし、今や日本の製品は外国が真似しようと思ってもできないほどの域に達している。政治の世界だけ、「#Me Too」といった無残な猿マネが横行しているのは情けない。行進していたおばさまたちは一騎当千の兵(つわもの)。セクハラなんか、鼻息で飛ばしそうだ。そのパワーで、外国に猿マネさせるくらいの戦術を考えてくれ!