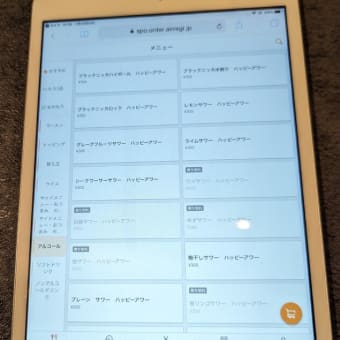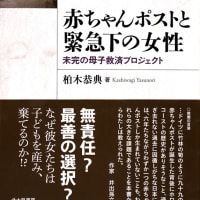赤ちゃんポスト研究のはじまりは、「ドイツ語テレビ講座」だった。たまたまドイツ語講座を見た時、「ドイツに、赤ちゃんを置き去ることのできるボックスがある」という話を聴いた。その時には、あまり運命みたいなものは感じず、「すごいなぁ」と思う程度だった。
その後、この話を当時の学生たちに話したら、みんな、興味をもってくれて、「先生、調べたらどうですか?」と言われ、調べることとなった。そうしたら、なんと、「どうやらドイツの幼稚園の先生たちが作ったらしい」ということを知り、「へー!!」となった。当時の僕は、「教育学と社会福祉のあいだ」を研究していて、赤ちゃんポストはまさにその「真ん中」にあった。どうして幼稚園の先生(教師)が、赤ちゃんポストなるものを作ったのか、とても気になった。
調べていくうちに、赤ちゃんポストを創った団体、シュテルニパルクは、かなりユニークな教育思想をもった、かなり変わった幼稚園団体だということもわかってきた。なにが変わっているかというと、まずは「かなり過激な団体だった」ということである。シュテルニパルクの代表、ユルゲン・モイズィッヒ先生は、67年の学生運動でバリバリ暴れまわっていた人で、その奥さんのハイディさんも学生運動にバリバリ参戦していた人だった。
さらに、モイズィッヒさんは、「新教育」を大事にしていて、更に、「公立幼稚園・保育園」でやるような幼児教育を否定ことから出発した人だった。つまりは、「国嫌い」の人だった。「私が愛しているのは、国家ではなく、私の妻である」というのが、彼の一つの口癖だった。彼は、どこまでも子どもたちの「主体性」を大事にする教育者だった。
と、同時に、彼が大事にしていたのが、「自律性」だった。自律とは、「同調しない力」である。彼は、権威に同調せず、権威に対して逆らえる人間を育てようとしていた。
この「新教育」×「反権威主義」が、彼の教育思想にあった。
他方、児童福祉は、主に(歴史的に)キリスト教→国家が担ってきた。キリスト教も国家も「権威」である。言うことは聞いておいた方がいい(苦笑)。しかし、ゆえに、「上の人間が下の人間を施してやる」という福祉行政が主流となるのである。福祉事務所も児童相談所も、根本的には「役所」であり、そこで働いている人は「公務員」である。赤ちゃんポストは、そうした役所の役人では考え付かないアイデアだった。ゆえに役人は赤ちゃんポストを嫌う。(管理しきれない部分があるから)
モイズィッヒさんは、当事者の目線を大事にし、そして反国家権力・反権威主義の思想をもって、「市民(民間人)の力」をどこまでも信じる人だった。「児童中心主義」と「反権威主義」のミクスチャー系の教育学(教育実践)というのは、聴いたことがなかった。
このことを知った時、今の日本の教育にも保育にも児童福祉にも欠けているものが、彼の思想と実践の中にある!と直感した。それは、僕がずっと学校や施設に抱いていた不満であり、欠点だった。とりわけ「反権威主義的教育学」という言葉に魅了される自分がいた。
…
PS
もし、あの時、ドイツ語テレビ講座を見ていなかったら、きっとこの研究はしていなかったと思う。ほんの一瞬の出来事だった。この一瞬があったからこそ、二冊の本も出せたわけだし、色んな出会いにつながっていった。
人間の一生を決めるのって、その「ほんの一瞬」であることが多い。結果論でしかないけど、人生って、その「一瞬」によって、180度違う方向に向かっていくのだろう、としみじみ思う。
さらにさかのぼること、大学院時代、院に残るか、就職するかで悩んだけど、あの時に院に残っていたら、きっとまた今と全然違う人生を生きていたんだろう、とも思う。今思えば、その頃もまた「一瞬」だった。
人生というのは、ホント、分からないものだなぁ、と思う。
なんてことない「一瞬」によって、その人生が大きく変わるのだから…