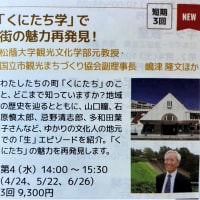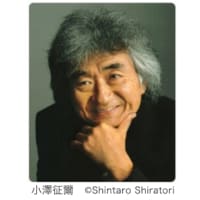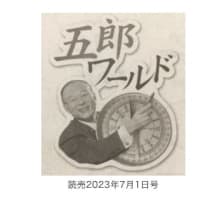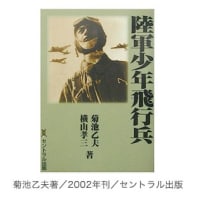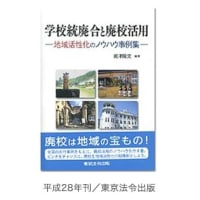写真:「万里の長城」と称された10m防潮堤を津波は越えた(本人撮影)
先週末は盛岡市での「全国都市問題会議」の出席し、その帰路、被災地の宮古、山田町、大槌町、釜石に足をのばしました。
宮古で訪れた一つが田老(たろう)です。「津波太郎(田老)」の言われるほど津波が多く、明治29年には人口の83%に当たる1867人が死亡。昭和8年でも559戸中500戸が流失し、死亡・不明は人口32%の911人という地域です。
その田老が対策として選択したのは防潮堤です。昭和33年に長さ1350m、高さ10mの大堤を完成させます。果たして昭和35年のチリ津波では近隣地域と比べ被害は軽微となり、同地区に伝わる「津波てんでんこ」の紙芝居教育や防災訓練と絡み、「防災の町」と注目されました。
しかし今次の津波でこの防潮堤の500メートルが倒壊しました。津波は堤防の高さの倍あったといわれ、200人近い死者・不明者が出たのです。「立派な防潮堤があるという安心感から返って多くの人が逃げ遅れた」とも言われました。
ところが今回、この地に訪れてきっぱりとした声を耳にしました。「それでも私たちは防潮堤を求めます。防潮堤が波を一時でも食い止めてくれれば、その間に高台に逃げるようにします」。自然の脅威への諦めでなく、そこには自然を受け入れつつ尚立ち向かおうとする人々の強靭な決意がありました。
和辻哲郎は名著『風土論』で、台風や地震に苦しめられる日本人の性格を「しめやかな激情」と「戦闘的な恬淡」と指摘しました。その紛れもない姿勢の一つが、まさに凄惨な被害にあったこの田老地区には彷彿としていたのです。