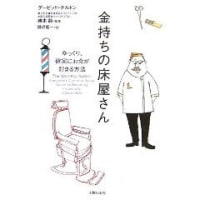りんどうです。
今「ラ講」と言ってどれだけの人が覚えているんでしょう・・・
しかし当時一流と言われていた予備校・大学講師陣がこぞって参加していて、タイマー録音して聞いていたのが日課でした。
英語は御園和夫先生・J.B.ハリス先生、数学では秋山仁先生・長岡亮介先生、国語・現代文は出口汪先生、古文は林省之助先生、漢文は宮下典男先生、日本史にしても菅野祐孝先生等など。とにかく第一線の先生方の授業を早朝に聞いて、それから登校という生活をしていました。
「出口の現代文」についてはラボでもPRしていることもあり、国語コースは出口信奉者が集まっている傾向があります。実際私もセンター現代文満点でした。
今は現代文の先生も色々な先生が出てきています。フィーリングでなく論理で解くということで、解説も進化してきているわけですが、出口先生が草分け的存在であったことは間違いのない話です。
旺文社ラジオ講座は、それこそNHK英語講座を聴くような感覚で、当時地方在住の高校生・宅浪生などが利用していました。スクーリングもあって私は青山学院大学が会場の回に参加したことがありました。
今から考えると「特殊な知識をもっていれば有利」などという発想ではなく、「その問題に限って使える解き方」は決して用いず、マジメに努力を継続すれば、誰でも納得できる解法をコンパクトに示していた内容だったように思います。
医学部専門予備校で教えるようになって、ミラクルな解法がきっとあるに違いないという幻想を持っている人が意外に多いことに気づきます。
しかし「文章の中に答えとなる根拠が必ず存在する」という鉄則は全てにあてはまるのであって、適切な解法で解けるわけです。
少なくとも現在求めている学力を測るテスト形式であれば、基礎を踏まえて演習を継続して、成果が上がるわけです。
ICUの研究会で、現在の日本における国語テストでは、大学文学部で行うような「文学理論」「テクスト論」に基づいた視点でのテストではなく、ひたすらに内容把握や細部の設問が問われているので、もっと中学・高校段階で理論を踏まえた指導を行って「大学での国語」にあたるような内容でテストした方が良いのではないか、という海外からの発表もあったことは事実です。
今後学力に関するモノサシが変わっていく可能性は十分にあるものの、いずれにせよ内容を把握するようなことが大前提としてあった上でのことですので、基礎をおろそかにして良いわけでは決してありません。
問題が正攻法で必ず解ける、そういう指導からブレないこと。・・・
私にとっていつの時代においても心掛けたい指導訓です。
今「ラ講」と言ってどれだけの人が覚えているんでしょう・・・
しかし当時一流と言われていた予備校・大学講師陣がこぞって参加していて、タイマー録音して聞いていたのが日課でした。
英語は御園和夫先生・J.B.ハリス先生、数学では秋山仁先生・長岡亮介先生、国語・現代文は出口汪先生、古文は林省之助先生、漢文は宮下典男先生、日本史にしても菅野祐孝先生等など。とにかく第一線の先生方の授業を早朝に聞いて、それから登校という生活をしていました。
「出口の現代文」についてはラボでもPRしていることもあり、国語コースは出口信奉者が集まっている傾向があります。実際私もセンター現代文満点でした。
今は現代文の先生も色々な先生が出てきています。フィーリングでなく論理で解くということで、解説も進化してきているわけですが、出口先生が草分け的存在であったことは間違いのない話です。
旺文社ラジオ講座は、それこそNHK英語講座を聴くような感覚で、当時地方在住の高校生・宅浪生などが利用していました。スクーリングもあって私は青山学院大学が会場の回に参加したことがありました。
今から考えると「特殊な知識をもっていれば有利」などという発想ではなく、「その問題に限って使える解き方」は決して用いず、マジメに努力を継続すれば、誰でも納得できる解法をコンパクトに示していた内容だったように思います。
医学部専門予備校で教えるようになって、ミラクルな解法がきっとあるに違いないという幻想を持っている人が意外に多いことに気づきます。
しかし「文章の中に答えとなる根拠が必ず存在する」という鉄則は全てにあてはまるのであって、適切な解法で解けるわけです。
少なくとも現在求めている学力を測るテスト形式であれば、基礎を踏まえて演習を継続して、成果が上がるわけです。
ICUの研究会で、現在の日本における国語テストでは、大学文学部で行うような「文学理論」「テクスト論」に基づいた視点でのテストではなく、ひたすらに内容把握や細部の設問が問われているので、もっと中学・高校段階で理論を踏まえた指導を行って「大学での国語」にあたるような内容でテストした方が良いのではないか、という海外からの発表もあったことは事実です。
今後学力に関するモノサシが変わっていく可能性は十分にあるものの、いずれにせよ内容を把握するようなことが大前提としてあった上でのことですので、基礎をおろそかにして良いわけでは決してありません。
問題が正攻法で必ず解ける、そういう指導からブレないこと。・・・
私にとっていつの時代においても心掛けたい指導訓です。