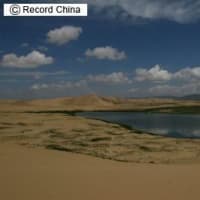其の六の続き
■セラ寺は、「チベット解放」までは、ちょうど平安時代の比叡山みたいに、時には武力さえ使って政治に介入したほどの力と人口を有する巨大な寺です。チベットの寺院は、日本の寺とはぜんぜん違います。墓地など有りませんし、住職さん一家が仲良く暮らすような場所でもありません。そこは仏教の総合大学であり、僧侶達が共同生活する一つの城壁都市でもあります。ですから、巨大寺院ともなれば、数千人の僧侶を抱えるのも珍しくないのです。全盛期のセラ寺は5000人以上の僧侶が居たと思われる規模を持っていますぞ!しかし、解放戦争・文化大革命と続く大規模な弾圧と破壊にあって伽藍は廃墟となり、多くの僧侶が虐殺されたり、「強制還俗」が大流行しました。その時に、無理やり還俗させらたチベット人は何処にでもいますから、仲良くなれば、当時の「思い出」を話してくれるかも知れせんが、「壁に耳有り、障子に目有り、家族の間でも密告有り」という国だという事をお忘れなく。
■中華人民共和国は、大規模な弾圧と破壊の後で、チベット人の抵抗と憎悪に対して恐れをなして、今度は懐柔策を取りました。ところが、社会主義革命の名前で国を作ったので、お寺のお坊さんを「労働者」にしてしまいました!出家した者が「労働者」なら、お釈迦様も観音様も皆、労働者ですなあ。労働者が労働者を拝んでいるのなら、これは喜劇ですぞ!カトリック教会と仲直りし始めている中国共産党には、「イエス・キリストさんも労働者なのか?」と聞いてみたいものです。
■現在のチベット寺院は、一つの例外も無く、政府の命令で「定員」が決まっています。正確には、修行僧の数の上限が厳しく決まっているのです。チベット仏教の絶滅を密かに願っている北京政府は、お坊さんが居なくなって寺が無人の廃墟になる日を楽しみにしています。ある有名な門前町に行ってみると、町の中心地やら目抜き通りに「仏教は迷信だから距離を取りましょう」「科学知識を学んで宗教を捨てましょう」「国家分裂主義者の僧侶を密告しましょう」などと露骨な嫌がらせ看板が並んでいます。そんな街中を仲良くなったお坊さん達と散歩をするのは楽しいものです。
■こういう露骨な言論による洗脳と弾圧をしている場所では、時々、朝起きてみると、あーら、誰がやったか知らないけれど、存在してはならない「チベット国旗」が政治宣伝用の看板にかぶせられている事が有るそうです。勿論、オチョクられて面子を潰された地方政府の公安は、徹底的な調査と密告の奨励をするのですが、なかなか「犯人」は見つからないようですなあ。余りしつこく「探索」と「捜査」を続けていると、誰が首謀者というわけでもないのに、大勢のお坊さんや信者が街路に集まり始めて町中に不穏な空気が満ちるのだそうです。そうならない程度に、「洗脳」と「監視」をするのが公安の腕の見せ所とも聞きました。ご苦労様です。
■御寺の定員制は、実際には守られていません。公式な出版物の中に、チベット寺院案内が有りまして、場所や来歴と一緒に「定員」が書かれていますから、それを持ってお寺を巡って仲良くなったお坊さんに、人数を教えてもらうのは面白い体験です。地元の信者達が欠かさないお布施で運営されているのですから、定員など決めても無駄なのです。徳の無いお坊さんばかりにでもなれば、信仰心が失われてお寺は衰えて廃墟となるでしょうが、そんな心配は今のところは無いそうですよ。
「どうしてお坊さんになったのですか」
■「大きなお世話だ!お前はどうして出家しないでぶらぶらしているんだ?」加藤さんの不躾で失礼で愚かな質問に対してセラ寺のお坊さんは、こんな風には答えませんよ。本心は分かりませんがね…
「良い心を持てるように、心が平和になるためです」
■途中で音声が途切れているので、編集してあるようですが、ラサ語でお坊さんが答えます。ちゃんとラサ語の通訳が加藤さんに同行しているではないですか?始めからそうすれば良いのに、そんなにラサの街中で「北京語」を使ってみたかったのですか?テロップには「6年目の修行僧 サンタンリシさん(23)」と出ています。彼はどうして、この程度のインタヴューなら北京語で答えられるに決まっているのに、ラサ語だけで答えているのでしょう?その意味を加藤さんは知っているのに、知らん振りしているだけでしょうか?北京政府に対する抗議の姿勢を示す嫌がらせだと知った上での事ならば、加藤さんは偉い!と言わなければならないのですが……
■このテロップにあった「6年目」と「23歳」という数字にも注目する必要が有りますぞ!本当は、幼児の段階から仏門に入って修行を始め、その成果が見えて心が決まったら、正式に得度して「沙彌戒」を授かり、更に修行が進んだら「具足戒」も受けるのです。宗教的な決断は個人の尊厳に関わる事ですから、これは人権問題にも関係します。中国では、18歳未満の「出家」を禁止しているのです。まったく大きなお世話ですが、これも仏教勢力を増やさない工夫で、世俗の大学への進学や職業訓練にチベット人を追い込もうというわけです。しかし、この御蔭で大学まで進んでしっかり世俗の教養を身に付けてから出家して、以前よりも短期間で難解な仏教哲学を理解する優秀なお坊さんが増えているようです。北京政府の作戦は失敗です。若い担い手は大丈夫なのですが、度重なる残虐な弾圧で、高位の学僧が次々とインドや米国に亡命してしまったので、仏教教学の上層部には不安が広まっています。
「ダライ・ラマを今でも尊敬していますか」「ええ、とても尊敬しています」
■セラ寺のお坊さんを相手に、こんな質問をする為に番組の制作費やら諸手続き費用、特別許可料金、怪しい賄賂などに大金をつぎ込んで取材旅行をしていたのでしょうか?まったく、アホかいな?どうせ聞くなら「北京政府が嫌いですか?」「毛沢東をどう思いますか?」「独立運動に参加していますか?」「最近のラサ暴動を実際に見ましたか?」などなど、スクープ映像間違いなしの質問は幾らでも有ります。慶応大学に行って、「福沢諭吉を尊敬していますか?」と問えば、「尊敬しない」と言うヘソ曲がりが出て来ることもあるでしょうが、チベット仏教のゲルク派の寺なら、100%返答は決まっているのです。それをわざわざ確認することに何の価値が有るのでしょう?これが「報道」なのでしょうか?
其の八に続く
■セラ寺は、「チベット解放」までは、ちょうど平安時代の比叡山みたいに、時には武力さえ使って政治に介入したほどの力と人口を有する巨大な寺です。チベットの寺院は、日本の寺とはぜんぜん違います。墓地など有りませんし、住職さん一家が仲良く暮らすような場所でもありません。そこは仏教の総合大学であり、僧侶達が共同生活する一つの城壁都市でもあります。ですから、巨大寺院ともなれば、数千人の僧侶を抱えるのも珍しくないのです。全盛期のセラ寺は5000人以上の僧侶が居たと思われる規模を持っていますぞ!しかし、解放戦争・文化大革命と続く大規模な弾圧と破壊にあって伽藍は廃墟となり、多くの僧侶が虐殺されたり、「強制還俗」が大流行しました。その時に、無理やり還俗させらたチベット人は何処にでもいますから、仲良くなれば、当時の「思い出」を話してくれるかも知れせんが、「壁に耳有り、障子に目有り、家族の間でも密告有り」という国だという事をお忘れなく。
■中華人民共和国は、大規模な弾圧と破壊の後で、チベット人の抵抗と憎悪に対して恐れをなして、今度は懐柔策を取りました。ところが、社会主義革命の名前で国を作ったので、お寺のお坊さんを「労働者」にしてしまいました!出家した者が「労働者」なら、お釈迦様も観音様も皆、労働者ですなあ。労働者が労働者を拝んでいるのなら、これは喜劇ですぞ!カトリック教会と仲直りし始めている中国共産党には、「イエス・キリストさんも労働者なのか?」と聞いてみたいものです。
■現在のチベット寺院は、一つの例外も無く、政府の命令で「定員」が決まっています。正確には、修行僧の数の上限が厳しく決まっているのです。チベット仏教の絶滅を密かに願っている北京政府は、お坊さんが居なくなって寺が無人の廃墟になる日を楽しみにしています。ある有名な門前町に行ってみると、町の中心地やら目抜き通りに「仏教は迷信だから距離を取りましょう」「科学知識を学んで宗教を捨てましょう」「国家分裂主義者の僧侶を密告しましょう」などと露骨な嫌がらせ看板が並んでいます。そんな街中を仲良くなったお坊さん達と散歩をするのは楽しいものです。
■こういう露骨な言論による洗脳と弾圧をしている場所では、時々、朝起きてみると、あーら、誰がやったか知らないけれど、存在してはならない「チベット国旗」が政治宣伝用の看板にかぶせられている事が有るそうです。勿論、オチョクられて面子を潰された地方政府の公安は、徹底的な調査と密告の奨励をするのですが、なかなか「犯人」は見つからないようですなあ。余りしつこく「探索」と「捜査」を続けていると、誰が首謀者というわけでもないのに、大勢のお坊さんや信者が街路に集まり始めて町中に不穏な空気が満ちるのだそうです。そうならない程度に、「洗脳」と「監視」をするのが公安の腕の見せ所とも聞きました。ご苦労様です。
■御寺の定員制は、実際には守られていません。公式な出版物の中に、チベット寺院案内が有りまして、場所や来歴と一緒に「定員」が書かれていますから、それを持ってお寺を巡って仲良くなったお坊さんに、人数を教えてもらうのは面白い体験です。地元の信者達が欠かさないお布施で運営されているのですから、定員など決めても無駄なのです。徳の無いお坊さんばかりにでもなれば、信仰心が失われてお寺は衰えて廃墟となるでしょうが、そんな心配は今のところは無いそうですよ。
「どうしてお坊さんになったのですか」
■「大きなお世話だ!お前はどうして出家しないでぶらぶらしているんだ?」加藤さんの不躾で失礼で愚かな質問に対してセラ寺のお坊さんは、こんな風には答えませんよ。本心は分かりませんがね…
「良い心を持てるように、心が平和になるためです」
■途中で音声が途切れているので、編集してあるようですが、ラサ語でお坊さんが答えます。ちゃんとラサ語の通訳が加藤さんに同行しているではないですか?始めからそうすれば良いのに、そんなにラサの街中で「北京語」を使ってみたかったのですか?テロップには「6年目の修行僧 サンタンリシさん(23)」と出ています。彼はどうして、この程度のインタヴューなら北京語で答えられるに決まっているのに、ラサ語だけで答えているのでしょう?その意味を加藤さんは知っているのに、知らん振りしているだけでしょうか?北京政府に対する抗議の姿勢を示す嫌がらせだと知った上での事ならば、加藤さんは偉い!と言わなければならないのですが……
■このテロップにあった「6年目」と「23歳」という数字にも注目する必要が有りますぞ!本当は、幼児の段階から仏門に入って修行を始め、その成果が見えて心が決まったら、正式に得度して「沙彌戒」を授かり、更に修行が進んだら「具足戒」も受けるのです。宗教的な決断は個人の尊厳に関わる事ですから、これは人権問題にも関係します。中国では、18歳未満の「出家」を禁止しているのです。まったく大きなお世話ですが、これも仏教勢力を増やさない工夫で、世俗の大学への進学や職業訓練にチベット人を追い込もうというわけです。しかし、この御蔭で大学まで進んでしっかり世俗の教養を身に付けてから出家して、以前よりも短期間で難解な仏教哲学を理解する優秀なお坊さんが増えているようです。北京政府の作戦は失敗です。若い担い手は大丈夫なのですが、度重なる残虐な弾圧で、高位の学僧が次々とインドや米国に亡命してしまったので、仏教教学の上層部には不安が広まっています。
「ダライ・ラマを今でも尊敬していますか」「ええ、とても尊敬しています」
■セラ寺のお坊さんを相手に、こんな質問をする為に番組の制作費やら諸手続き費用、特別許可料金、怪しい賄賂などに大金をつぎ込んで取材旅行をしていたのでしょうか?まったく、アホかいな?どうせ聞くなら「北京政府が嫌いですか?」「毛沢東をどう思いますか?」「独立運動に参加していますか?」「最近のラサ暴動を実際に見ましたか?」などなど、スクープ映像間違いなしの質問は幾らでも有ります。慶応大学に行って、「福沢諭吉を尊敬していますか?」と問えば、「尊敬しない」と言うヘソ曲がりが出て来ることもあるでしょうが、チベット仏教のゲルク派の寺なら、100%返答は決まっているのです。それをわざわざ確認することに何の価値が有るのでしょう?これが「報道」なのでしょうか?
其の八に続く