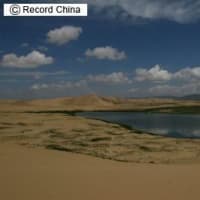其の参の続き
■さて、カメラはラサの中心に聳えるポタラ宮に迫ります。
ラサの中心に聳(そび)え建つポタラ宮、チベット仏教で観音菩薩が降り立ったと言われる丘に建つ、高さ115メートルの宮殿です。かつて
■観音菩薩が降り立つとは、まるで欧州のマリア様が現れた騒動のような話です。誰がこんな可笑しな話を吹き込んだのでしょう?歴史を無視した素朴な信仰話として流布してるとも聞きますが、それをナマの形でテレビ放送に使うのかどうでしょう?観音菩薩が天界のポタラから降りて来たから、あの場所がポタラなのでなく、観音様の化身が住む場所だからポタラと呼ばれるようになったという順番が正しいのです。簡単に歴史をたどりますと、ソンツェン・ガンポ王によって建国された吐蕃王国の時代に、既にこの丘に宮殿が建てられていたと推測されています。当時の吐蕃王国は仏教とは無縁でした。その後、ネパールと唐からお嫁さんを貰ったり、留学生を派遣したりして、徐々に仏教文化を取り入れて行ったのだと、伝説は言いますが、本当のソンツェン王は武力と戦略の権化みたいな猛々しい人物だったようです。彼が死去した後に仏教が導入されて国教となった歴史を、一まとめにして偉大なる初代の大王の輝かしい業績として語り伝えたので、文武両道を兼ね備えた英邁なる君主像が完成しました。チベット人はソンツェン王が大好きです。
■しかし、9世紀の大混乱で吐蕃王国は瓦解します。ラサが再びチベット人にとって特別な場所になったのは、ダライ・ラマ政権が確立した17世紀です。そのダライ・ラマが観音菩薩の化身とされているからこそ、あの建物は「ポタラ」なのですが……。日本ではすっかり女性にされてしまった観音様ですが、テレビ朝日のスタッフはポタラの丘に降臨した観音様はどんな姿だったのか?そして、それは男の姿をしていたのか?女性の姿をしていたのか?ちゃんと聞いたのでしょうか?是非、教えて頂きたいものですなあ。きっと、チベット人も知らない話ですぞ。
■今でも「偉大なる五世」と呼ばれる第五代ダライ・ラマ、ロサン・ギャムツォは巧みな外交と人心を集める学識で、絶大な権力と権威を一身に集めました。モンゴルのグシ汗という実力者を後ろ盾にして、他の仏教勢力を完全に支配下に置きました。その事実を万人に知らせるべく、このポタラ宮の建設が始まったのです。しかも、摂政だったサンギェ・ヤムツォという非常に有能な為政者が、ダライ・ラマ五世の死を14年間も隠し通して、この未曾有の大工事を完成させたのです。何せ、ピラミッドを建造するようなトンデモない人力だけの大工事ですからなあ。ご苦労様でした。ついでながら、『セブン・イヤーズ・イン・チベット』という本には、チベットには一切の「車輪」が存在しない、と著者のハラーは驚きを書いています。この特集の最初に、古舘さんが「チベット部分に初めて鉄道が通った」と言うのは歴史的には正しいのです。車輪が無いのですから、手押し車さえも無いのですから、馬車も牛車も無かったのがチベットです。この点をチベット人に尋ねた事が有ります。答えは簡単でした。「要らないから」単純明快です。
■まあ、急峻な山を越えたり、馬鹿馬鹿しいほど広い草原を横断する時は、とっとと自分の足で歩けば良いし、馬に跨った方が快適で早いのです。自動車文化の元となった欧米の長距離馬車は、実際には不快で不便で危険だったと、モーツァルトなどの多くの旅をした有名人達が口を極めて呪いの言葉を残していますなあ。今のダライ・ラマ14世は、子供の頃から機械が好きで、インドから購入した「走らない自動車」が大のお気に入りだったそうです。ハラーさんはエンジンを利用して発電し、映画を上映して見せてくれたのでした。だから、本当はラサの街を自動車が走り回るのは止めて欲しいのですがなあ。
■後で出て来るジョカン寺などは、占いの結果選ばれた土地が何と湖(沼地)だったので、黒山羊さんと白山羊さんの背中に埋め立て用の石を載せて運んだのだそうで、それを記念して山羊さんの像が建っていたとの話も有りますし、山羊(ラ)の土地(サ)が本当の地名だったとの珍説も有ります。でもRとLの音を明確に区別するチベット語では、ちょっと無理なコジツケのようです。しかし、一切の車輪付きの道具を使わずに埋め立て工事を完了したのは本当の話ですぞ。ですから、チベット語では「車」と言えば、「マニ車」か「法輪」ぐらいしか有りませんでした。
白い壁の「白宮」は政治・生活の場、赤い壁の「紅宮」は歴代のダライ・ラマを祀る墓です。
■ちょっと、ちょっと、「墓です」なんて言ったら、多くの日本人はあの中に立派な墓石が並んでいると思ってしまうじゃないですか!あれは「霊廟(れいびょう)」です。ポタラ宮を建設した第五世からのダライ・ラマの遺体をミイラにして、金箔をべたべた貼り付けて祀っている御堂が4層に重なっているのです。戒名を彫りつけた墓石が並んでいるのではないので、誤解の無いように。因みに、シガツェの歴代パンチェン・ラマ霊廟は、文化大革命中に紅衛兵に襲われて遺体を飾っていた貴金属類は略奪されて「中身」はゴミとして廃棄された事が有りましたなあ。チベット各地から略奪された金銀財宝や膨大な森林資源は、「一体、何処に行ったのだろう?」と今でもチベット人は考え込んでいます。
■でも、ゴミとして捨てられたパンチェン・ラマのミイラは、ちゃんと信者達が密かに拾い集めて隠していたので、パンチェン・ラマ10世が1989年1月に、監禁されていた北京からチベットに帰還して、念願だった歴代パンチェン・ラマの供養を盛大に催した時、パンチェン・ラマ五世から九世までの亡骸(なきがら)を、再建されたばかりの大仏塔に安置することが出来ました。良かったですね。ところが、このちょっと目出度いイベントの6日後に、パンチェン・ラマ十世は信者達の目の前で心臓発作を起こして昏倒してしまいます。病院に運ばれたのですが、残念ながら逝去します。実は、大仏塔の除幕式の翌日に、「チベットは過去三十年間、その発展の為に記録した進歩よりも大きな代償を支払った」と言う有名な共産党批判をしていたので、この急死は毒殺だ!とチベット人達は信じているようですなあ。
其の五に続く
■さて、カメラはラサの中心に聳えるポタラ宮に迫ります。
ラサの中心に聳(そび)え建つポタラ宮、チベット仏教で観音菩薩が降り立ったと言われる丘に建つ、高さ115メートルの宮殿です。かつて
■観音菩薩が降り立つとは、まるで欧州のマリア様が現れた騒動のような話です。誰がこんな可笑しな話を吹き込んだのでしょう?歴史を無視した素朴な信仰話として流布してるとも聞きますが、それをナマの形でテレビ放送に使うのかどうでしょう?観音菩薩が天界のポタラから降りて来たから、あの場所がポタラなのでなく、観音様の化身が住む場所だからポタラと呼ばれるようになったという順番が正しいのです。簡単に歴史をたどりますと、ソンツェン・ガンポ王によって建国された吐蕃王国の時代に、既にこの丘に宮殿が建てられていたと推測されています。当時の吐蕃王国は仏教とは無縁でした。その後、ネパールと唐からお嫁さんを貰ったり、留学生を派遣したりして、徐々に仏教文化を取り入れて行ったのだと、伝説は言いますが、本当のソンツェン王は武力と戦略の権化みたいな猛々しい人物だったようです。彼が死去した後に仏教が導入されて国教となった歴史を、一まとめにして偉大なる初代の大王の輝かしい業績として語り伝えたので、文武両道を兼ね備えた英邁なる君主像が完成しました。チベット人はソンツェン王が大好きです。
■しかし、9世紀の大混乱で吐蕃王国は瓦解します。ラサが再びチベット人にとって特別な場所になったのは、ダライ・ラマ政権が確立した17世紀です。そのダライ・ラマが観音菩薩の化身とされているからこそ、あの建物は「ポタラ」なのですが……。日本ではすっかり女性にされてしまった観音様ですが、テレビ朝日のスタッフはポタラの丘に降臨した観音様はどんな姿だったのか?そして、それは男の姿をしていたのか?女性の姿をしていたのか?ちゃんと聞いたのでしょうか?是非、教えて頂きたいものですなあ。きっと、チベット人も知らない話ですぞ。
■今でも「偉大なる五世」と呼ばれる第五代ダライ・ラマ、ロサン・ギャムツォは巧みな外交と人心を集める学識で、絶大な権力と権威を一身に集めました。モンゴルのグシ汗という実力者を後ろ盾にして、他の仏教勢力を完全に支配下に置きました。その事実を万人に知らせるべく、このポタラ宮の建設が始まったのです。しかも、摂政だったサンギェ・ヤムツォという非常に有能な為政者が、ダライ・ラマ五世の死を14年間も隠し通して、この未曾有の大工事を完成させたのです。何せ、ピラミッドを建造するようなトンデモない人力だけの大工事ですからなあ。ご苦労様でした。ついでながら、『セブン・イヤーズ・イン・チベット』という本には、チベットには一切の「車輪」が存在しない、と著者のハラーは驚きを書いています。この特集の最初に、古舘さんが「チベット部分に初めて鉄道が通った」と言うのは歴史的には正しいのです。車輪が無いのですから、手押し車さえも無いのですから、馬車も牛車も無かったのがチベットです。この点をチベット人に尋ねた事が有ります。答えは簡単でした。「要らないから」単純明快です。
■まあ、急峻な山を越えたり、馬鹿馬鹿しいほど広い草原を横断する時は、とっとと自分の足で歩けば良いし、馬に跨った方が快適で早いのです。自動車文化の元となった欧米の長距離馬車は、実際には不快で不便で危険だったと、モーツァルトなどの多くの旅をした有名人達が口を極めて呪いの言葉を残していますなあ。今のダライ・ラマ14世は、子供の頃から機械が好きで、インドから購入した「走らない自動車」が大のお気に入りだったそうです。ハラーさんはエンジンを利用して発電し、映画を上映して見せてくれたのでした。だから、本当はラサの街を自動車が走り回るのは止めて欲しいのですがなあ。
■後で出て来るジョカン寺などは、占いの結果選ばれた土地が何と湖(沼地)だったので、黒山羊さんと白山羊さんの背中に埋め立て用の石を載せて運んだのだそうで、それを記念して山羊さんの像が建っていたとの話も有りますし、山羊(ラ)の土地(サ)が本当の地名だったとの珍説も有ります。でもRとLの音を明確に区別するチベット語では、ちょっと無理なコジツケのようです。しかし、一切の車輪付きの道具を使わずに埋め立て工事を完了したのは本当の話ですぞ。ですから、チベット語では「車」と言えば、「マニ車」か「法輪」ぐらいしか有りませんでした。
白い壁の「白宮」は政治・生活の場、赤い壁の「紅宮」は歴代のダライ・ラマを祀る墓です。
■ちょっと、ちょっと、「墓です」なんて言ったら、多くの日本人はあの中に立派な墓石が並んでいると思ってしまうじゃないですか!あれは「霊廟(れいびょう)」です。ポタラ宮を建設した第五世からのダライ・ラマの遺体をミイラにして、金箔をべたべた貼り付けて祀っている御堂が4層に重なっているのです。戒名を彫りつけた墓石が並んでいるのではないので、誤解の無いように。因みに、シガツェの歴代パンチェン・ラマ霊廟は、文化大革命中に紅衛兵に襲われて遺体を飾っていた貴金属類は略奪されて「中身」はゴミとして廃棄された事が有りましたなあ。チベット各地から略奪された金銀財宝や膨大な森林資源は、「一体、何処に行ったのだろう?」と今でもチベット人は考え込んでいます。
■でも、ゴミとして捨てられたパンチェン・ラマのミイラは、ちゃんと信者達が密かに拾い集めて隠していたので、パンチェン・ラマ10世が1989年1月に、監禁されていた北京からチベットに帰還して、念願だった歴代パンチェン・ラマの供養を盛大に催した時、パンチェン・ラマ五世から九世までの亡骸(なきがら)を、再建されたばかりの大仏塔に安置することが出来ました。良かったですね。ところが、このちょっと目出度いイベントの6日後に、パンチェン・ラマ十世は信者達の目の前で心臓発作を起こして昏倒してしまいます。病院に運ばれたのですが、残念ながら逝去します。実は、大仏塔の除幕式の翌日に、「チベットは過去三十年間、その発展の為に記録した進歩よりも大きな代償を支払った」と言う有名な共産党批判をしていたので、この急死は毒殺だ!とチベット人達は信じているようですなあ。
其の五に続く