その①、その②の続き
映画『アラビアのロレンス』前半の最大のクライマックスはアカバ攻略となっている。そして砂漠の風景こそはこの映画最大の見ものであり、これほど砂漠の雄大さ、美しさを見事に映し出したのは、後にも先にもこれを超えるものはない。砂漠の風紋や奇岩も大画面でこそ栄え、中には松島の仁王島そっくりの奇岩もあった。映画のロレンスの台詞のように、まさに「砂漠は櫂の入らぬ海」なのだ。
アカバ攻略を映画ではロレンスの発案という描き方になっており、砂漠の中で一晩中考え抜き、夜明けに彼を崇拝する2人のアラブ少年を前に「アカバ!」というシーンはドラマチックで忘れがたい。
しかし、このアカバ攻略がロレンスの発案であるかは様々な異論が出ている。既に英軍の将校が献策していた、フランス将校の案だったと見る人もいるし、アラブ人史家はアウダ・アブ・タイの案をロレンスが奪ったとまで言う。ロレンスによるアカバ攻撃の前年1916年夏ごろ、連合軍側がこの地に目を付けていた事実もあり、2度に亘り海上から攻撃、いったんは上陸に成功しながら結局は敗退している。
実はロレンスは戦前に一度アカバに来ている。考古学者だった彼はシナイ地方での聖書「出エジプト記」の足跡を辿る科学調査団の一員として参加している。実はこの調査団は科学調査に銘打った偵察であり、この時ロレンスは海陸両方面からアカバ湾に達している。あたかも下検分を思わせ、決してアカバ奇襲を偶然思いついたはずはない。当たり前だが、映画では以上のことは触れられていない。
もろろん、ロレンスらアラブ軍がアカバを攻撃、占領したのは史実だし、この時のみならず、それ以降もアラブ人がトルコ兵や捕虜への惨い行為に及んだのも映画通り。トルコの歴史小説『トルコ狂乱』((トゥルグット・オザクマン著、三一書房)の解説にも、「フサイン(映画には登場しないが、ファイサルの父で反乱の精神的指導者)はトルコ人に対して“イギリスやフランスでさえ不適切と見なした”ほどの残虐な振る舞いに及ぶ…」と著者は書く。英仏は不適切と見なしても、特に制止もしなかったようだが。
アカバはローマ時代、ローマ式街道が通っていたことが『ローマ人の物語』(9巻:賢帝の時代)に載っていた。ロレンスは灼熱の砂漠を苦難して越えることになるが、「もしもそれがローマ時代であったならば、灼熱下ということならば同じでも、舗装の行き届いた街道を行くだけで着けたのだ」とか。
アカバ攻略が前半の見せ場なら、ダマスカス進軍が後半の中心となっている。アラブ兵、トルコ軍双方が血みどろの殺戮を行い、英軍よりも一足先にロレンスらアラブ人部隊はダマスカスに無血入城、この古い都での4世紀に及ぶオスマン帝国支配はここに終わりを告げる。
実はアラブ人部隊や英軍のダマスカス無血制圧の背景には、ムスタファ・ケマルの決断が影響していた。当然ながらこの映画にケマルは登場しないし、名も上らない。1918年8月末、ケマルはシリア戦線に送られ、現代のヨルダンにいたトルコ第七軍の司令官として着任している。トルコにとって敗色の濃いこの方面には、優秀な指揮官が必要だったのだ。
だが、ケマルは着任するや、「軍」など書類の上のみで存在していたことを思い知らされた。しかも、この方面におけるケマルの上司でもあり、エンヴェル、タラートと並ぶ三頭政治家の1人ジェマル・パシャは、事態をあまりにも楽観していた。ジェマルはケマルが説いたダマスカスへ総軍退却、戦線を立て直し英仏軍を迎え撃つ作戦を一笑に付す。さらに間が悪く、ケマルの完治していない腎臓病が再発、彼は約一か月間、ダマスカスの病院に横たわることになる。その間、北上を開始した英仏軍は各地でトルコ軍を蹴散らし、アラブ・ゲリラ軍と歩調を合わせ、ダマスカス目前に迫ってきた。
医者の説得を無視、病院を後にしたケマルはかつてゲリボル(英名ガリポリ)の戦いで共に戦ったドイツ人将軍ザンデルスと再会、もはやダマスカスで戦線を統一する機会が失われたと言明、北シリアのアレッポへ総退却、戦線を立て直すよう進言する。ザンデルスはケマルの作戦に全面的に賛成、そして全権をケマルに委ねた。
この時、退却するなら焦土作戦をとれと主張するジェマル・パシャを、ケマルは無用の犠牲だと説得し、焦土作戦は行われなかった。こうしてダマスカスの市街は全く無事にすみ、10月1日、アラブ軍と英軍は抵抗も受けず無事に無血入城となる。もしケマルの病気が再発しなかったならば、中東戦線はどのような展開になっていたのだろうか。軍事に関心のある人ならシュミレーションをするのも一興と思う。
その④に続く
◆関連記事:「学術研究という名のスパイ活動」
よろしかったら、クリックお願いします
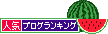

映画『アラビアのロレンス』前半の最大のクライマックスはアカバ攻略となっている。そして砂漠の風景こそはこの映画最大の見ものであり、これほど砂漠の雄大さ、美しさを見事に映し出したのは、後にも先にもこれを超えるものはない。砂漠の風紋や奇岩も大画面でこそ栄え、中には松島の仁王島そっくりの奇岩もあった。映画のロレンスの台詞のように、まさに「砂漠は櫂の入らぬ海」なのだ。
アカバ攻略を映画ではロレンスの発案という描き方になっており、砂漠の中で一晩中考え抜き、夜明けに彼を崇拝する2人のアラブ少年を前に「アカバ!」というシーンはドラマチックで忘れがたい。
しかし、このアカバ攻略がロレンスの発案であるかは様々な異論が出ている。既に英軍の将校が献策していた、フランス将校の案だったと見る人もいるし、アラブ人史家はアウダ・アブ・タイの案をロレンスが奪ったとまで言う。ロレンスによるアカバ攻撃の前年1916年夏ごろ、連合軍側がこの地に目を付けていた事実もあり、2度に亘り海上から攻撃、いったんは上陸に成功しながら結局は敗退している。
実はロレンスは戦前に一度アカバに来ている。考古学者だった彼はシナイ地方での聖書「出エジプト記」の足跡を辿る科学調査団の一員として参加している。実はこの調査団は科学調査に銘打った偵察であり、この時ロレンスは海陸両方面からアカバ湾に達している。あたかも下検分を思わせ、決してアカバ奇襲を偶然思いついたはずはない。当たり前だが、映画では以上のことは触れられていない。
もろろん、ロレンスらアラブ軍がアカバを攻撃、占領したのは史実だし、この時のみならず、それ以降もアラブ人がトルコ兵や捕虜への惨い行為に及んだのも映画通り。トルコの歴史小説『トルコ狂乱』((トゥルグット・オザクマン著、三一書房)の解説にも、「フサイン(映画には登場しないが、ファイサルの父で反乱の精神的指導者)はトルコ人に対して“イギリスやフランスでさえ不適切と見なした”ほどの残虐な振る舞いに及ぶ…」と著者は書く。英仏は不適切と見なしても、特に制止もしなかったようだが。
アカバはローマ時代、ローマ式街道が通っていたことが『ローマ人の物語』(9巻:賢帝の時代)に載っていた。ロレンスは灼熱の砂漠を苦難して越えることになるが、「もしもそれがローマ時代であったならば、灼熱下ということならば同じでも、舗装の行き届いた街道を行くだけで着けたのだ」とか。
アカバ攻略が前半の見せ場なら、ダマスカス進軍が後半の中心となっている。アラブ兵、トルコ軍双方が血みどろの殺戮を行い、英軍よりも一足先にロレンスらアラブ人部隊はダマスカスに無血入城、この古い都での4世紀に及ぶオスマン帝国支配はここに終わりを告げる。
実はアラブ人部隊や英軍のダマスカス無血制圧の背景には、ムスタファ・ケマルの決断が影響していた。当然ながらこの映画にケマルは登場しないし、名も上らない。1918年8月末、ケマルはシリア戦線に送られ、現代のヨルダンにいたトルコ第七軍の司令官として着任している。トルコにとって敗色の濃いこの方面には、優秀な指揮官が必要だったのだ。
だが、ケマルは着任するや、「軍」など書類の上のみで存在していたことを思い知らされた。しかも、この方面におけるケマルの上司でもあり、エンヴェル、タラートと並ぶ三頭政治家の1人ジェマル・パシャは、事態をあまりにも楽観していた。ジェマルはケマルが説いたダマスカスへ総軍退却、戦線を立て直し英仏軍を迎え撃つ作戦を一笑に付す。さらに間が悪く、ケマルの完治していない腎臓病が再発、彼は約一か月間、ダマスカスの病院に横たわることになる。その間、北上を開始した英仏軍は各地でトルコ軍を蹴散らし、アラブ・ゲリラ軍と歩調を合わせ、ダマスカス目前に迫ってきた。
医者の説得を無視、病院を後にしたケマルはかつてゲリボル(英名ガリポリ)の戦いで共に戦ったドイツ人将軍ザンデルスと再会、もはやダマスカスで戦線を統一する機会が失われたと言明、北シリアのアレッポへ総退却、戦線を立て直すよう進言する。ザンデルスはケマルの作戦に全面的に賛成、そして全権をケマルに委ねた。
この時、退却するなら焦土作戦をとれと主張するジェマル・パシャを、ケマルは無用の犠牲だと説得し、焦土作戦は行われなかった。こうしてダマスカスの市街は全く無事にすみ、10月1日、アラブ軍と英軍は抵抗も受けず無事に無血入城となる。もしケマルの病気が再発しなかったならば、中東戦線はどのような展開になっていたのだろうか。軍事に関心のある人ならシュミレーションをするのも一興と思う。
その④に続く
◆関連記事:「学術研究という名のスパイ活動」
よろしかったら、クリックお願いします



















