
この写真は1958年(昭和33年)に撮影されたもので
新潟市古町にあった映画館「新潟日活」である。
石原裕次郎主演の「陽のあたる坂道」の看板が見える。
この年、映画人口、史上最高の12億2745万人を記録している。
国民一人当たり12回~13回、映画館で映画を見ている勘定になる。
まさに日本映画の黄金時代のピークが1958年だったのだ。
以後、映画はテレビに押され衰退していく。
町の中心街にあった映画館はことごとく姿を消してしまい
どこに映画館があったのかさえも、忘れ去られようとしている。
涙あり、笑いあり…。私達に感動を与えてくれた庶民の娯楽の殿堂
「町の映画館」は、巷の文化の発信基地でもあった。
現在、シネマコンップレックスという名のアメリカスタイルの
複合した映画館が、全国的に町の映画館に代わって登場している。
多くは大型ショッピングセンターの中に存在している。
「シネマコンプレックス」と「町の映画館」とは
同じ映画館であっても、経営形態がまったく違うものだ。
町に映画館があった時代は地元商店街も活気があった。
町にわくわくする面白さがあった。日本も元気があった。
昭和時代、あるいは20世紀の文化を考えるとき
町の映画館が果たしてきた役割は非常に大きかったと思う。
消滅した町の映画館は姿を消して、業態を変えてしまっているので
完全に忘れさられようとしているのは、あまりにも寂しい。
私は2000年に「20世紀の館」というホームページを開設した。
巷の文化史という副題をつけている。
21世紀を前にして、20世紀の宝物を見直そう
という思いをこめて開設したものだ。
映画館を経営する家で育ち、映画看板の修行時代をすごした
体験をつづったエッセイ「映画の時代」もある。
写真などの画像を貼り付けることができる「画像掲示板」もあるので
映画館についての対話も可能である。
>>>>■募集!おらが町の映画館の写真■<<<<<
ここで全国の映画ファンにお願いがります。
あなたの町の映画館の写真をもっておられる方は
この「画像掲示板」に貼り付けてください。
撮影した年と映画館名がわかりましたら記入してください。
古い写真、大歓迎です。
できれば、全国の町の映画館の写真を集めて
「20世紀の館」に「全国の町の映画館」として残しておきたいと思います。
なにとぞご協力をお願いします。
追伸
この企画ははっきりいって、かなり無理がある、
ということは承知しています。
若い頃に映画青年だった人も、高齢者の仲間入りをしています。
高齢者はパソコンが苦手なのであります。
さらに、当時カメラを持っていい人が少なかったので、
町の映画館の写真が非常に少ないと考えています。
だからこそ、貴重な町の映画館の写真を集めて残しておく
ことは、巷の文化史としても意味があると考えています。
新潟市古町にあった映画館「新潟日活」である。
石原裕次郎主演の「陽のあたる坂道」の看板が見える。
この年、映画人口、史上最高の12億2745万人を記録している。
国民一人当たり12回~13回、映画館で映画を見ている勘定になる。
まさに日本映画の黄金時代のピークが1958年だったのだ。
以後、映画はテレビに押され衰退していく。
町の中心街にあった映画館はことごとく姿を消してしまい
どこに映画館があったのかさえも、忘れ去られようとしている。
涙あり、笑いあり…。私達に感動を与えてくれた庶民の娯楽の殿堂
「町の映画館」は、巷の文化の発信基地でもあった。
現在、シネマコンップレックスという名のアメリカスタイルの
複合した映画館が、全国的に町の映画館に代わって登場している。
多くは大型ショッピングセンターの中に存在している。
「シネマコンプレックス」と「町の映画館」とは
同じ映画館であっても、経営形態がまったく違うものだ。
町に映画館があった時代は地元商店街も活気があった。
町にわくわくする面白さがあった。日本も元気があった。
昭和時代、あるいは20世紀の文化を考えるとき
町の映画館が果たしてきた役割は非常に大きかったと思う。
消滅した町の映画館は姿を消して、業態を変えてしまっているので
完全に忘れさられようとしているのは、あまりにも寂しい。
私は2000年に「20世紀の館」というホームページを開設した。
巷の文化史という副題をつけている。
21世紀を前にして、20世紀の宝物を見直そう
という思いをこめて開設したものだ。
映画館を経営する家で育ち、映画看板の修行時代をすごした
体験をつづったエッセイ「映画の時代」もある。
写真などの画像を貼り付けることができる「画像掲示板」もあるので
映画館についての対話も可能である。
>>>>■募集!おらが町の映画館の写真■<<<<<
ここで全国の映画ファンにお願いがります。
あなたの町の映画館の写真をもっておられる方は
この「画像掲示板」に貼り付けてください。
撮影した年と映画館名がわかりましたら記入してください。
古い写真、大歓迎です。
できれば、全国の町の映画館の写真を集めて
「20世紀の館」に「全国の町の映画館」として残しておきたいと思います。
なにとぞご協力をお願いします。
追伸
この企画ははっきりいって、かなり無理がある、
ということは承知しています。
若い頃に映画青年だった人も、高齢者の仲間入りをしています。
高齢者はパソコンが苦手なのであります。
さらに、当時カメラを持っていい人が少なかったので、
町の映画館の写真が非常に少ないと考えています。
だからこそ、貴重な町の映画館の写真を集めて残しておく
ことは、巷の文化史としても意味があると考えています。












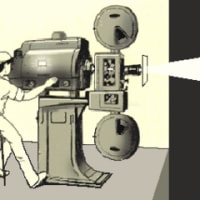




町の映画館の話、大好きだった映画館を思い出しました。
わが町神戸では、震災でほとんどの映画館が全壊、いまだ日劇系列の
一番大きな映画館でさえ仮設で運営しています。
震災後、そういう大きな映画館がこぞってシネコン化し、
おっしゃるとおり小さな映画館が1つ、また1つと姿を消しています。
写真、取っておけばよかったのですが、ごめんなさい、持ってません。
最近愛用していたアサヒシネマは、壊された後でそのかけらを
1ついただきましたが。
でも、日劇系列の映画館も、そのうち仮設を解体し、新たな映画館に生まれ変わると思いますので、
それまでにはフレームに収められたらと思います。
最後になりましたが、TBありがとうございました。
素敵な写真ですね。
新しい映画も古い映画も大好きで
これからもいろいろみていきたいと思ってました。
また遊びに来ます。ではでは。
昭和33年と言えば高度成長期にさしかかる頃でしょうか。
当時はどこの町にも写真のような映画館があったのですね。
人と人とのふれあいが感じられていいなあと思いました。
「新潟日活」の写真、いい感じの写真ですね。
20年くらい前、近所にあった映画館が取り壊されました。今では駐
車場になっています。昨日、その場所を久しぶりに通ってきました。
シネコンはスクリーン数が多くて音響や映像が良くなっていますが、
1スクリーンのみの映画館にも久しぶりに行ってみようかなと思いま
した。
また訪問させて頂きます。失礼致しました。
なかなか多忙にて映画館にも行けませんが、映画は大好きという若輩者です。
またお邪魔させていただきますね。
大変興味深く読ませていただきました。
私の住んでいる町には、昔、映画街呼ばれる場所があり、
いわゆる「町の映画館」がいくつも並んでいました。
しかし、某シネコンが次々と県内に進出してきて
映画街と呼ばれていた場所から映画館が全て
消えてしまいました。
今では、ミニシアター系の映画を上映する
小さな映画館が一つ、残るのみです。
今まではあまり気にしていなかったことですが、
ここの記事を拝読し、なんだか寂しくなりました。
残念ながら、当時の写真はありません。
ごめんなさい。
こちらのブログを更新次第、
TBさせていただきますね。
TBありがとうございました。
銀座のような土地であっても、町の映画館が消えつつある昨今。本当に残念ですね。並木座も確か消えちゃいましたし、有楽町駅の近くに大島渚が時代に逆行しようとして作った映画館も、すぐに消えてしまいました。
田舎町も同様で、よく自転車で通ったのにぃ、というような映画館も、次々に駐車場と化し、校外のシネコンの看板を立てています。
シネコンも便利ですからよく利用しますが、あそこは消費の場ですよね。本当に「いい映画」を大事に味わえる場が、減っていくような寂しさを感じています。
外観がこちらのお写真にある新潟日活に少し似ています。
映画館の中にトイレがあったり、1階席の壁際に背もたれのない
木製のベンチが置いてあったり、何とも味のある素敵な映画館でした。
どこで見ても同じ気になるシネコンより、町の映画館で独特の空気の中、
映画を楽しむという娯楽、もはや既に贅沢になりつつあるのでしょうか。