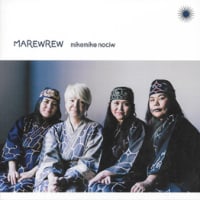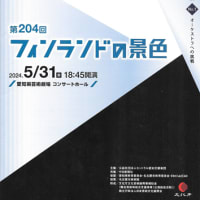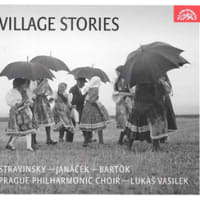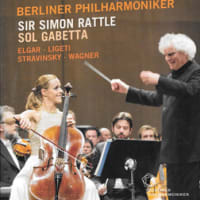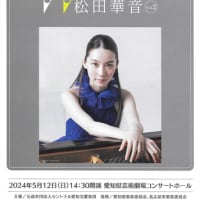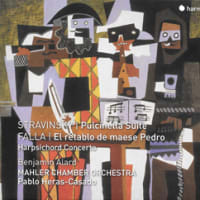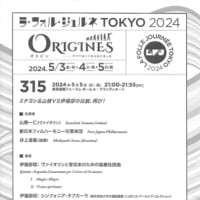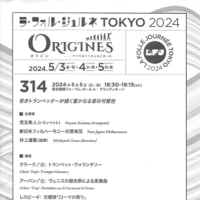現代音楽と呼ばれる音楽のジャンルがある.制作され,世に出てから間もない音楽,要するに新しい音楽を指すが,どれくらい新しければそう呼べるのか,はっきり決まっているわけではない.また,音楽のスタイルとしても,おおむね西洋クラシック音楽の流儀を受け継いだ(その流儀を否定することも,継承の方法の一種だ)アーティスティックな前衛音楽を意味することが多いものの,それに留まらず,商業を目的に次々に生み出されるポピュラー音楽など,あらゆる「新曲」を総称するケースもある.そして,前者のグループに属する音楽は,とかく「デタラメにきこえる」とか,「メロディがなくて音楽らしくない」などと,その内容の難解さから,大多数のリスナーに拒絶されるようだ.たとえば,ノーノやシュトックハウゼンの曲を突然聴かされて,それを音楽だと思う人はほとんどいないだろう.
これには,創作サイドもしくは数少ない愛好家たちから,さまざまの反論があるようで,一つには,現代音楽を聴くにはいくらかのコツと慣れが必要であり,サウンドとしての美しさや驚きを体験すればいいのだという.言いたいことは分かるし,間違いではないと思う.だが,現代音楽は,聴き方が悪いからつまらないのだろうか.そして,彼らが擁護するとおり,そもそもそんなにすばらしい存在なのだろうか.ここで断っておけば,僕自身は現代音楽を聴くのが好きだし,細々と続ける作曲活動は,文字通り新しく音楽を作り出す営みだ.だがいっぽうで,新しい音楽というものは一般に,そのだいたいがつまらないということも,事実だと思うのである.
というのは,生み出されたばかりのものは玉石混交で,多くの人々と時間のなかを通過していくにつれて,その真価が分かってくるだろうからだ.どの時代もきっとそうだったのであり,それが面白ければ長く愛されるだろうし,つまらなければ忘れられていくということが,ずっと続いてきたのに違いないのである.これは,作曲者が手抜きをしているとか,その方法に問題があるというのではなく,音楽は多数の工程を積み重ねて得られる一種の「製品」であり,どんなに念入りに作り,一流のプレイヤーが演奏したとしても,不良品が混ざるのは避けられないことだからだ.統計学に信頼性理論という分野があって,あらゆる工業製品は新しいものほど故障しやすく,故障しなかったものだけが安定期に入り,やがて壊れることを確率的に説明しているのであるが,その文脈になぞらえれば,音楽とは著しく初期不良が多い製品だということになる.もちろん,これはポピュラーにも当てはまるだろうし,もっと話を広げれば,アート全般に言えることだ.
極端な言い方になるが,上述のように,それを聴くのにコツを要するような音楽は,やはりその時点で面白くないのである.幼いころCDで聴いて気に入り,僕がクラシックに入門するきっかけとなったストラヴィンスキーの『春の祭典』は,少し前まで現代音楽の一つとして数えられていた曲であるが,それは聴き手に何か事前の訓練を求める音楽だろうか.そうではなく,もっと単純に,身体に心に響いて楽しい,気持ちいいから好きなのである.それ以来,どうしてホールに出かけてまで,諸々の現代音楽を聴くかといえば,そうした出会いがあるかもしれないからだし,外れたときには,大いに文句を言う資格があるからだ.
現代音楽がつまらないという感想は,その意味では実に当たっているのであり,さらには,「良い現代音楽」に出会っていないだけなのかもしれないと,素朴に信じている.そして,良いものと悪いものが混在するからといって,新しい音楽を作り,聴くことはぜんぜん無意味ではないし,そのスリリングな現場にぜひとも立ち会っていたいというのが,現代音楽ファンとしての僕のモチヴェーションである.
外部リンク:
クラシック症候群(シンドローム)
http://yoshim.music.coocan.jp/~data/BOOKS/Columun/column06.html
これには,創作サイドもしくは数少ない愛好家たちから,さまざまの反論があるようで,一つには,現代音楽を聴くにはいくらかのコツと慣れが必要であり,サウンドとしての美しさや驚きを体験すればいいのだという.言いたいことは分かるし,間違いではないと思う.だが,現代音楽は,聴き方が悪いからつまらないのだろうか.そして,彼らが擁護するとおり,そもそもそんなにすばらしい存在なのだろうか.ここで断っておけば,僕自身は現代音楽を聴くのが好きだし,細々と続ける作曲活動は,文字通り新しく音楽を作り出す営みだ.だがいっぽうで,新しい音楽というものは一般に,そのだいたいがつまらないということも,事実だと思うのである.
というのは,生み出されたばかりのものは玉石混交で,多くの人々と時間のなかを通過していくにつれて,その真価が分かってくるだろうからだ.どの時代もきっとそうだったのであり,それが面白ければ長く愛されるだろうし,つまらなければ忘れられていくということが,ずっと続いてきたのに違いないのである.これは,作曲者が手抜きをしているとか,その方法に問題があるというのではなく,音楽は多数の工程を積み重ねて得られる一種の「製品」であり,どんなに念入りに作り,一流のプレイヤーが演奏したとしても,不良品が混ざるのは避けられないことだからだ.統計学に信頼性理論という分野があって,あらゆる工業製品は新しいものほど故障しやすく,故障しなかったものだけが安定期に入り,やがて壊れることを確率的に説明しているのであるが,その文脈になぞらえれば,音楽とは著しく初期不良が多い製品だということになる.もちろん,これはポピュラーにも当てはまるだろうし,もっと話を広げれば,アート全般に言えることだ.
極端な言い方になるが,上述のように,それを聴くのにコツを要するような音楽は,やはりその時点で面白くないのである.幼いころCDで聴いて気に入り,僕がクラシックに入門するきっかけとなったストラヴィンスキーの『春の祭典』は,少し前まで現代音楽の一つとして数えられていた曲であるが,それは聴き手に何か事前の訓練を求める音楽だろうか.そうではなく,もっと単純に,身体に心に響いて楽しい,気持ちいいから好きなのである.それ以来,どうしてホールに出かけてまで,諸々の現代音楽を聴くかといえば,そうした出会いがあるかもしれないからだし,外れたときには,大いに文句を言う資格があるからだ.
現代音楽がつまらないという感想は,その意味では実に当たっているのであり,さらには,「良い現代音楽」に出会っていないだけなのかもしれないと,素朴に信じている.そして,良いものと悪いものが混在するからといって,新しい音楽を作り,聴くことはぜんぜん無意味ではないし,そのスリリングな現場にぜひとも立ち会っていたいというのが,現代音楽ファンとしての僕のモチヴェーションである.
外部リンク:
クラシック症候群(シンドローム)
http://yoshim.music.coocan.jp/~data/BOOKS/Columun/column06.html