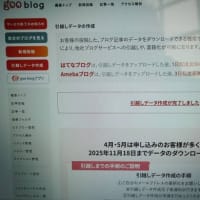次は宍道湖を時計回りに廻って、この地方独特の防風林と屋敷墓を持つ民家をバスから眺めながら出雲大社参拝に向う。
近づくと天気がいい日だけに掲揚するという75畳の国旗(冒頭写真)が翻っているのが見えてきて、これは昔来た時は見なかった、何でもNHKの放送開始終了時に写る日の丸がこれだそうで、見上げる限りではそんなに大きくは見えない。土産物屋から案内人が出てきて引率、独特のクロス型千木がある本殿は60年毎の大修理で桧皮葺替えのために仮設鞘堂にすっぽり覆われていたのは残念、こちらもあと5年かかるそうだ。ここの参拝は二礼四拍一礼と他の神社より拍手が多いのが仕来り。拝殿脇には数年前だったか発掘され話題となった古の3本組柱が、その位置に赤い丸で新たに描かれていた。結婚式場などがある神楽殿のほうには日本一大きいという4.5tの注連縄が下り、これに硬貨を投げて刺さったら良いことがあると聞いてすかさず5円玉で挑戦、3投目で見事スポッと中まで入ってしまった。まだまだ豪直球を投げられるぞと自慢すれば女房は年寄りの冷や水だってさ。最後はここの国造宮司で84代続く千家の屋敷を通り抜けて土産物屋に戻る。4.5tを筆頭に注連縄は各建物正面に計3本あり、いずれも餅米の藁だそうだ。また今年の八百万の神様の集合は12月26日(旧暦10月10日)で、夜に海から来られるのを皆でお迎えするという、出雲は今も神様が現役の土地なのですね。
松江はお土産屋地ビール館の駐車場に入り、ここでのオプションは舟での堀川めぐり、でもそれに乗ると他の観光は出来ないから我々はお城見物もしたしで、小泉八雲旧居や武家屋敷のある塩見縄手を歩いて見物しながら、城の反対側に新たに出来た島根ふるさと館で地場産品のお買物タイムにあてる。日本橋三越前にも島根のアンテナショップがあるけれど、ここは本場だけに鮮魚農産物から和菓子や名産品がズラッとあり、2階は工芸品売場とほぼ何でも揃っている。恐らく日本橋にもあるだろうけれど、高橋張子虎本舗の来年の干支で小さな寅を買っておいた。女房は若草という和菓子と途中で食べようとシジミカレーパンなるものを買込んでいた。戻ってからの地ビールのほうは普通のビアホールなら350円のカップ1杯が550円だと、地ビールはややクセがあって旨いと思ったことはないからと止めておいた。
二日目最後は中海内にある大根島の由志園という牡丹園と日本庭園の施設、オプション見物の庭園は回遊式ということだが室内からもメイン部分が見えるから入る必要も無い。館内の売場ではこの島のもうひとつの名産品である朝鮮人参の加工品も販売していて、その薬用茶が1杯サービスとなっていた。お茶を飲ませながらの効用宣伝がお上手です、人参入り石鹸や乳液など買い求めるオバチャン達、こういう漢方薬は効きがスローで買った分だけでは良くなりませんぞ、それであとは止めてしまうのがオチだから買わんでもと言っていたら女房も石鹸を買込んでおった。信じる者は救われるとはイエス様だったかな。
本土側に渡れば漫画家水木しげるの出身地で漁港としても有名な境港、ここは弓ケ浜沿いに素通りして夕方7時前に着いた皆生温泉も分宿で、1号車の半分だけが岩崎館という鉄骨ALC3階建ての古めかしい旅館、ここは玄関に下足番がいて脱いであがる昔のスタイル。皆生温泉は大きい温泉地だと想像していたのだが、中心部は大型旅館らしい建物が並んで見えるもっと海寄りのようだ。館内はかなり前に改修したらしく廊下は全て畳敷き、昔からの各部屋は大きめで、トイレもウォシュレット完備でこれなら文句はない。老舗だったらしいのだが大型ホテル風旅館になるのに乗り遅れたのでしょう、先代らしきが釣りキチのようで諸外国まで行って釣った魚拓や写真が飾ってあったから金の使い道を間違ったのかな。露天風呂はなくただ一箇所の内風呂はやや小さめで混み合ったら厳しいが、24時間入れる。掲示板に源泉掛け流しで70℃ほどの泉温を加水調整していると書いてあったが成分表示は無し。泉質はナトリウム・カルシウム塩化物泉、かなり成分濃度が濃い湯で添乗員は上がり湯したほうがと言っていたが、舐めてみた限りでは焼津ほどしょっぱくはない。
夕食膳には大好物のメバルの煮付一匹がまず目に入る。刺身も新鮮でさすがは境港が近いから魚介類が美味しい、ただし蟹は冷凍物だろうけれどね。境港のパンフレットにはここの沖はプランクトンが多いから魚が旨いとあった。またここでも蕎麦があったから出雲周辺では定番メニューらしい。僕には質量とも昨日より満足度が高い夕食でした。岩崎館と書かれた冷酒の醸造元を訊くと境港の千代むすび酒造の本醸造だそうだ。これが辛口なのにコクのある旨口でよろしい、焼津の磯自慢といい漁港地域には銘酒ありか、偶然か。