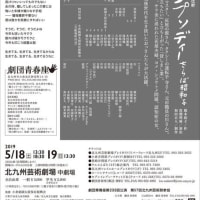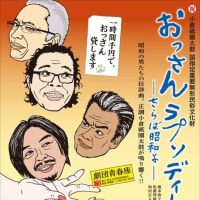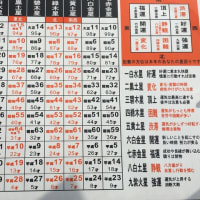「崇徳上皇」2
白河法皇の後ろ盾をなくした待賢門院璋子は髪を下ろし以後の住処としての法金剛院を仁和寺の境内に造ることに熱中します。得子への敗北感を仏教に帰依し、法皇の菩提を祈ることで乗り越えたかったのかもしれません。大規模な工事となるので完成までは数年かかります。お堂が出来た、庭が出来たとその都度に大がかりな法要が行われ鳥羽上皇、崇徳天皇、雅仁親王ら百官らが出席しました。兄弟仲はよく母思いでした。
近衛天皇が十七歳で病死しました。得子は崇徳側の呪詛のせいだと怒り狂い、天皇の位を養子にしていた璋子の四男の雅仁親王にするように鳥羽に迫りました。雅仁親王は崇徳の父違いの弟です。近衛の死によって自分の息子の重仁を皇太子にと思っていた崇徳と璋子には今まで以上に耐えがたいことでした。
体調が優れなくなってきた璋子は完成間近の法金剛院や後白河天皇(雅仁親王)の三条高倉第で静養します。鳥羽も子供達も度々見舞いに訪れますが四十五歳で亡くなり法金剛院の五位山に葬られました。そして、母璋子の最期を一緒に見守った崇徳と後白河の兄弟は保元の乱で相対することになります。
後白河天皇は父の鳥羽から「うつけ」と見放されていた皇子でいずれは僧門に入れられる身だろうからと皇位には何の関心もなく遊びほうけていました。鳥羽と得子は手元で育てている後白河の息子の守仁皇子を天皇にするつもりだったのですが、父親の後白河を差し置いて天皇にするのはまずいから中継ぎとして即位させたのです。
やがて鳥羽上皇が病の床につきました。鳥羽の命令で、見舞いに行った崇徳は追い払われ、亡くなったときも御車から降りられない状態まで門が警護の武士達で固められていました。鳥羽上皇の胸の奥深くに崇徳への怨念がずっと燻っていたのでしょう。
崇徳側と鳥羽方(後白河)の背後の人々の思惑から兄弟の皇位争いの戦いとなりました。保元の乱です。「崇徳上皇に謀反の動きあり」という風評がきっかけでした。すべては鳥羽の遺言だと取り仕切ったのは美福門院得子です。
清盛と源義朝らが後白河側に勝利をもたらせました。平家にすればどちらにつくかが大きな問題だったのでしょうが、この勝利が武士の世への第一歩となりました。
乱暴な言い方かも知れませんが崇徳も八歳年下の後白河もただ御輿に乗せられていただけだったような気がします。関白はじめ多くの貴族達と複雑な婚姻関係、付随する権力と経済力、私利私欲などがないまぜになって起こった皇位争いだったと、言ってしまうにはあまりにも多くのドラマやエピソードが展開されていました。
崇徳は剃髪して仁和寺に逃れ、一番気になる一人息子の重仁も仁和寺の別室に匿われましたが顔を見ることは許されなかったそうです。四〇〇年ぶりという配流(島流し)の沙汰が下されて崇徳は海の向こうの讃岐へと連行されて行きました。
後白河天皇の世となりました。しかし、二年後には息子の守仁親王を天皇として自分は上皇に退きます。そして出家して後白河法皇となるのです。
崇徳が最後まで気にかけていた重仁は仁和寺で出家して仏道に励んでいたのですが二十三歳で病没しました。
崇徳上皇は都では罪人ですが讃岐では尊いお方として地元の人々から警護つきではありますが大切に遇されました。しかし、松風と波の音しか聞こえない毎日はあまりにも寂しく、都恋しさが募るばかりでした。歌を作り写経し都に帰る日を夢見て過ごしましたが八年後に四十六歳で没しました。
遺体は都からの指示を待って、崇徳の遺言通り白峯山で荼毘にふされ納骨されました。
朝廷では崇徳への流罪に後味の悪い思いがあったのでしょう。悪いことが起こる度に崇徳上皇の祟りだと怖れ、霊を鎮めるために院号を贈ったり次々と寺院を造営したりしました。
崇徳の魂が恋しい都に戻ってこられたのはその死の七百年の後、明治維新の頃に京都下京区に白峯宮が建てられてのことでした。
崇徳、後白河の戦いの折に二人の生母の待賢門院璋子が生存されていなかったことに僅かながら救われるような気がします。

白河法皇の後ろ盾をなくした待賢門院璋子は髪を下ろし以後の住処としての法金剛院を仁和寺の境内に造ることに熱中します。得子への敗北感を仏教に帰依し、法皇の菩提を祈ることで乗り越えたかったのかもしれません。大規模な工事となるので完成までは数年かかります。お堂が出来た、庭が出来たとその都度に大がかりな法要が行われ鳥羽上皇、崇徳天皇、雅仁親王ら百官らが出席しました。兄弟仲はよく母思いでした。
近衛天皇が十七歳で病死しました。得子は崇徳側の呪詛のせいだと怒り狂い、天皇の位を養子にしていた璋子の四男の雅仁親王にするように鳥羽に迫りました。雅仁親王は崇徳の父違いの弟です。近衛の死によって自分の息子の重仁を皇太子にと思っていた崇徳と璋子には今まで以上に耐えがたいことでした。
体調が優れなくなってきた璋子は完成間近の法金剛院や後白河天皇(雅仁親王)の三条高倉第で静養します。鳥羽も子供達も度々見舞いに訪れますが四十五歳で亡くなり法金剛院の五位山に葬られました。そして、母璋子の最期を一緒に見守った崇徳と後白河の兄弟は保元の乱で相対することになります。
後白河天皇は父の鳥羽から「うつけ」と見放されていた皇子でいずれは僧門に入れられる身だろうからと皇位には何の関心もなく遊びほうけていました。鳥羽と得子は手元で育てている後白河の息子の守仁皇子を天皇にするつもりだったのですが、父親の後白河を差し置いて天皇にするのはまずいから中継ぎとして即位させたのです。
やがて鳥羽上皇が病の床につきました。鳥羽の命令で、見舞いに行った崇徳は追い払われ、亡くなったときも御車から降りられない状態まで門が警護の武士達で固められていました。鳥羽上皇の胸の奥深くに崇徳への怨念がずっと燻っていたのでしょう。
崇徳側と鳥羽方(後白河)の背後の人々の思惑から兄弟の皇位争いの戦いとなりました。保元の乱です。「崇徳上皇に謀反の動きあり」という風評がきっかけでした。すべては鳥羽の遺言だと取り仕切ったのは美福門院得子です。
清盛と源義朝らが後白河側に勝利をもたらせました。平家にすればどちらにつくかが大きな問題だったのでしょうが、この勝利が武士の世への第一歩となりました。
乱暴な言い方かも知れませんが崇徳も八歳年下の後白河もただ御輿に乗せられていただけだったような気がします。関白はじめ多くの貴族達と複雑な婚姻関係、付随する権力と経済力、私利私欲などがないまぜになって起こった皇位争いだったと、言ってしまうにはあまりにも多くのドラマやエピソードが展開されていました。
崇徳は剃髪して仁和寺に逃れ、一番気になる一人息子の重仁も仁和寺の別室に匿われましたが顔を見ることは許されなかったそうです。四〇〇年ぶりという配流(島流し)の沙汰が下されて崇徳は海の向こうの讃岐へと連行されて行きました。
後白河天皇の世となりました。しかし、二年後には息子の守仁親王を天皇として自分は上皇に退きます。そして出家して後白河法皇となるのです。
崇徳が最後まで気にかけていた重仁は仁和寺で出家して仏道に励んでいたのですが二十三歳で病没しました。
崇徳上皇は都では罪人ですが讃岐では尊いお方として地元の人々から警護つきではありますが大切に遇されました。しかし、松風と波の音しか聞こえない毎日はあまりにも寂しく、都恋しさが募るばかりでした。歌を作り写経し都に帰る日を夢見て過ごしましたが八年後に四十六歳で没しました。
遺体は都からの指示を待って、崇徳の遺言通り白峯山で荼毘にふされ納骨されました。
朝廷では崇徳への流罪に後味の悪い思いがあったのでしょう。悪いことが起こる度に崇徳上皇の祟りだと怖れ、霊を鎮めるために院号を贈ったり次々と寺院を造営したりしました。
崇徳の魂が恋しい都に戻ってこられたのはその死の七百年の後、明治維新の頃に京都下京区に白峯宮が建てられてのことでした。
崇徳、後白河の戦いの折に二人の生母の待賢門院璋子が生存されていなかったことに僅かながら救われるような気がします。