
宇治上神社

(うじがみじんじゃ)
京都府宇治市宇治山田59
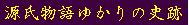


宇治神社から北へ100mほど離れた地に鎮座する宇治上神社。
〔御祭神〕
菟道稚郎子尊
(うじのわきいらつこのみこと)
応神天皇
(おうじんてんのう)
仁徳天皇
(にんとくてんのう)
宇治神社の脇を伸びる「さわらびの道」を進み、その名のもととなった「早蕨の碑」に心を留めつつ100mほど歩みを進めると、朱塗り鮮やかな鳥居のもとへ辿り着きます。木々に囲まれ、あたかも古の貴人が隠棲する草庵の如き境内に一歩踏み入れると、平安の名残りが色濃く残る寝殿造りの拝殿と、前垂注連に結界された中に円錐形に盛られた「清め砂」と呼ばれる盛砂が、否が応でもここが神々を祀る厳かな地であるという事を気付かせてくれます。この神社の名は宇治上神社。南接する宇治神社と一対の社として、明治維新まで「宇治離宮明神」などと称されて人々の崇敬を集めていた古社です。

朱塗りの鳥居をくぐって参道を進むと、豊かな木々に囲まれた境内へと辿り着きます。
宇治上神社は、前述したように宇治神社と一対として建てられた神社で、「宇治離宮明神」、「離宮八幡」などと呼ばれていた古称にちなみ、「離宮下社」と呼ばれていた宇治神社に対し、「離宮上社」と呼ばれていました。
応神天皇の息子である兄皇子・大鷦鶺命(のちの仁徳天皇)との間で「百世の美徳」と賞賛される皇位の譲り合いを繰り広げた末に、自ら宇治川に入水することによって継承問題にピリオドを打った悲運の皇子・菟道稚郎子命の遺徳を偲び御魂を安らかしめるために、その邸宅跡に建立されたというのが宇治上神社、宇治神社の起源とされています。また、神託を受けた醍醐天皇が901(延喜元)年に社殿を設けたのが始まりともいわれていますが、詳細は定かではありません。


宇治上神社の拝殿。
『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルとされる源融卿が、美しい景観を誇る宇治川のほとりに建てた別荘・宇治院。藤原氏の全盛期を築いた藤原道長卿は、宇多天皇から源重信卿の手へと渡っていた宇治院を手に入れ、別荘「宇治殿」を営みました。1052(永承7)年には、その子・藤原頼通卿が宇治殿を寺院に改めて平等院と名付けます。この時、鎮守社と定められたのが宇治離宮明神、今の宇治上神社と宇治神社でした。1067(治暦3)年に後冷泉天皇が平等院に行幸した際、その鎮守社である宇治離宮明神に対して正三位の神位授与を行ったことが文献に残されています。毎年5月に行われた例祭には、藤原氏から神馬が奉納され、散楽等も奉仕されたそうです。
その歴史を裏付けるように、覆屋と呼ばれる建物の中に鎮座する3社の本殿は、年輪測定法に基づく調査によって平安時代末期の1060(康平3)年頃に切り出された木材を使って建立されたものであることが判明しました。その前に建つ拝殿も鎌倉時代初期に切り出された檜を使い、平安時代に貴族の邸宅で数多く用いられた寝殿造りによって建てられた建物です。
拝殿の右手には、室町時代に選定された「宇治七名水」の1つである桐原水(きりはらすい)が、今もなお澄んだ清水を湧出しています。残念ながら、残りの高浄水・泉殿・百月夜・公文水・法華水・阿弥陀水は、宅地造成や工場建設などのために枯渇し、現在も清水を湛えているのは桐原水のみとなっています。

社殿覆屋。この中に平安時代後期に建てられた3つの本殿が並んで鎮座しています。
御祭神・菟道稚郎子命をモデルとして描かれたといわれる『源氏物語』の『宇治十帖』の登場人物・八の宮。光源氏の異母弟である八の宮は、政争に倦んで宇治川のほとりに隠棲しますが、その邸宅とされた場所が、現在宇治上神社と宇治神社が建つエリアにあったといわれる菟道稚郎子命の桐原日桁宮跡といわれています。この2つの神社の間には、『源氏物語』の第四十八帖・「早蕨」を偲ぶ碑が建てられています。


鎌倉時代建立で藤原氏の氏神を祀る春日神社(左)と宇治2社の間に立つ「早蕨の碑」(右)。
アクセス
・京阪電車「宇治駅」より南へ徒歩約5分
・JR「宇治駅」より東へ徒歩約13分
 宇治上神社地図 Copyright (C) 2000-2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.
宇治上神社地図 Copyright (C) 2000-2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料
・無料
拝観時間
・9時~16時30分





















お返事遅くなりすみません
宇治上神社は、「源氏物語」を読んでいて興味を持ったのがきっかけで訪れてみました。
まだまだ掲載したい事がたくさんあるのですが(祭礼の日程など)、訪れる前の予習の手助けになればと思って作成してます。少しでもお役に立てれば嬉しいです。これからもよろしくお願いします!
宇治には2度遊びに行って、あちこちの建物を見てきましたので、有名な建物(神社・仏閣など)はわかりますよ
初夏の青葉の季節、秋の紅葉の季節、一年を通じて楽しめますよ。