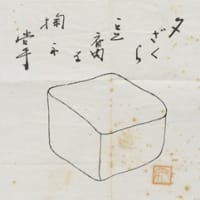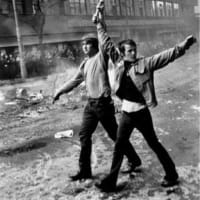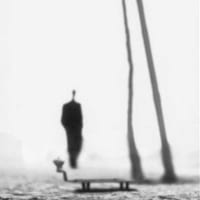姪っ子メグ おじさんが吸ってるのは、最近はマイルドセブン1ロングボックスね。昔は?
姪っ子メグ おじさんが吸ってるのは、最近はマイルドセブン1ロングボックスね。昔は? キミオン叔父 高校の時だからなあ。最初はチェリーかな。真っ赤なデザイン。大学時代は、ピースかな。平和思想にかぶれていたのかもしれない(笑)。それから、峰とかキャスターとかキャビンとかハイライトとか・・いろいろ転々としたな。舶来に行ったこともあるし、中南海なんて怪しげな健康たばこも吸ってたし、紙巻たばこの時代もあったし・・・。ここ10年ぐらいは、マイルドライト系統。まあ、オーソドックスなんじゃないかな。
キミオン叔父 高校の時だからなあ。最初はチェリーかな。真っ赤なデザイン。大学時代は、ピースかな。平和思想にかぶれていたのかもしれない(笑)。それから、峰とかキャスターとかキャビンとかハイライトとか・・いろいろ転々としたな。舶来に行ったこともあるし、中南海なんて怪しげな健康たばこも吸ってたし、紙巻たばこの時代もあったし・・・。ここ10年ぐらいは、マイルドライト系統。まあ、オーソドックスなんじゃないかな。 おばさんは、いまでもエコー一辺倒でしょ。
おばさんは、いまでもエコー一辺倒でしょ。 そうなんだ。労働者たばこね(笑)。
そうなんだ。労働者たばこね(笑)。 でも、この勢いでたばこ廃絶運動がおこると、おじさんたちは絶滅種扱いになるね。
でも、この勢いでたばこ廃絶運動がおこると、おじさんたちは絶滅種扱いになるね。 まあな。最近、テレビのゲストでもたばこ吸いながら話してる奴っていないだろ。昔は、結構、いたんですよ。テレビ局も許容してたんだろうね。「朝まで生テレビ」なんかでもさ、おじさんは呼ばれないけどさ、たばこなしにあんな苛々する議論につきあえないよ(笑)。
まあな。最近、テレビのゲストでもたばこ吸いながら話してる奴っていないだろ。昔は、結構、いたんですよ。テレビ局も許容してたんだろうね。「朝まで生テレビ」なんかでもさ、おじさんは呼ばれないけどさ、たばこなしにあんな苛々する議論につきあえないよ(笑)。 映画で見たけどさ、アメリカの反骨ニュースキャスターが、たばこ吸いながら、報道している。またそれがスタイリッシュで。
映画で見たけどさ、アメリカの反骨ニュースキャスターが、たばこ吸いながら、報道している。またそれがスタイリッシュで。 「日本沈没」の昔のビデオだったかな、小松左京さんが特典映像で解説してるんだけどさ、もうタバコプカプカ吸って、灰皿に吸殻が山盛りになってるの。笑っちゃったよ。
「日本沈没」の昔のビデオだったかな、小松左京さんが特典映像で解説してるんだけどさ、もうタバコプカプカ吸って、灰皿に吸殻が山盛りになってるの。笑っちゃったよ。 いまや、学校の職員室でも駄目なのかしら。むかしは、授業中に吸ってた先生がいて、だーれもそれを咎めなかったけど。
いまや、学校の職員室でも駄目なのかしら。むかしは、授業中に吸ってた先生がいて、だーれもそれを咎めなかったけど。 研究室なんかも禁煙でさ、パイプ燻らしながら思考するなんてこともなくなったのかな。嫌な世の中だねぇ。
研究室なんかも禁煙でさ、パイプ燻らしながら思考するなんてこともなくなったのかな。嫌な世の中だねぇ。







 江戸時代は、刻みタバコだけど、女の人もずいぶん吸ってたのね。
江戸時代は、刻みタバコだけど、女の人もずいぶん吸ってたのね。 うん、町人なんかもおしゃれに煙管とか刻みタバコを印籠に入れたりして、持ち歩いていたものね。お茶屋があちこちにあって、ちょっと一服と。
うん、町人なんかもおしゃれに煙管とか刻みタバコを印籠に入れたりして、持ち歩いていたものね。お茶屋があちこちにあって、ちょっと一服と。 明治からたばこ商が出てくるのね。全国に自由化の嵐があって、だんだん有力ないくつかの会社に統合されていくんだ。煙草専売法が施行されたのが明治37年。それからは、煙草の意匠デザインも公募されるようになるのね。
明治からたばこ商が出てくるのね。全国に自由化の嵐があって、だんだん有力ないくつかの会社に統合されていくんだ。煙草専売法が施行されたのが明治37年。それからは、煙草の意匠デザインも公募されるようになるのね。 当時で言えば、杉浦非水とか、商業デザインの先駆者が出てくるのね。紙巻たばこが刻みたばこの製造を上回るのが1920年代前半。戦時は銘柄の横文字が禁止され、配給制が実地される。で、戦後は、ヤミ煙草が横行する。専売公社が発足したのが昭和24年で、まずは制服を着て、闇煙草の摘発に走り回るんだな。
当時で言えば、杉浦非水とか、商業デザインの先駆者が出てくるのね。紙巻たばこが刻みたばこの製造を上回るのが1920年代前半。戦時は銘柄の横文字が禁止され、配給制が実地される。で、戦後は、ヤミ煙草が横行する。専売公社が発足したのが昭和24年で、まずは制服を着て、闇煙草の摘発に走り回るんだな。 そして、昭和26年に「ピース」のデザインをしたレイモンド・ローウィンが来日するのね。サンフランシスコ講和条約が批准されて、ラジオ・テレボ放送が始まり、マスコマーシャルが始まる。そんな時代に、この「ピース」のデザインというか、そのプレゼンテーションの遣り方自体に圧倒されるわけね。
そして、昭和26年に「ピース」のデザインをしたレイモンド・ローウィンが来日するのね。サンフランシスコ講和条約が批准されて、ラジオ・テレボ放送が始まり、マスコマーシャルが始まる。そんな時代に、この「ピース」のデザインというか、そのプレゼンテーションの遣り方自体に圧倒されるわけね。 そこから、日本の若きクリエーターたちが、タバコの意匠やポスター制作なんかに、応募するようになる。和田誠のピース「広告」シリーズが昭和36年から。
そこから、日本の若きクリエーターたちが、タバコの意匠やポスター制作なんかに、応募するようになる。和田誠のピース「広告」シリーズが昭和36年から。 それにしても、ポスターのデザインやコピーがとてもいいわね。いまなんか、反対論者がキーキーいいそうなコピーなんだけどね、もう自由化されたJTでも、こういうコピーを出すことは無理でしょうねぇ。
それにしても、ポスターのデザインやコピーがとてもいいわね。いまなんか、反対論者がキーキーいいそうなコピーなんだけどね、もう自由化されたJTでも、こういうコピーを出すことは無理でしょうねぇ。 このポスター群ってさ、ちょっとはある意味でいい日本社会かもしれないよ。なんか、大量複製して、喫煙可の食堂や居酒屋さんに展示してみたいね。このよさがわかんない女の子とはつきあいたくない!(笑)
このポスター群ってさ、ちょっとはある意味でいい日本社会かもしれないよ。なんか、大量複製して、喫煙可の食堂や居酒屋さんに展示してみたいね。このよさがわかんない女の子とはつきあいたくない!(笑) おじさんが興奮しても、もう世の中の流れには逆らえないわよ。
おじさんが興奮しても、もう世の中の流れには逆らえないわよ。 いやいや、この前の松沢馬鹿知事の条例に反抗して、どこかの議会で、喫煙自由化条例が出されたら、おじさんは成人になってから一度も投票したことないけど、これはもう選対にボランティアで応募してもいいよ(笑)。
いやいや、この前の松沢馬鹿知事の条例に反抗して、どこかの議会で、喫煙自由化条例が出されたら、おじさんは成人になってから一度も投票したことないけど、これはもう選対にボランティアで応募してもいいよ(笑)。