低く垂れ込めた雲。時折かすかに頬を打つ小さな冷たいもの。足下に重くたまった空気。
こういう日は偏頭痛がひどくてかなわない。朝、目が覚める少し前から、「ああ、天気が悪いんだな」と分かっている。眉間に不機嫌なくぼみが刻まれた状態でのそのそと起き出す。この手の偏頭痛に薬は効かないし。
全身の拒否反応を押しても出かけたのは、Science Agora 2006。「科学と親しむ広場」という意味のイベントが、昨日から明日にかけてお台場で開催されている。主催はJST。興味深いテーマの講演やワークショップが複数の会場で同時進行するスタイルのイベントで、私の関心領域は昨日の開催がほとんどだったのだが、1つだけ、面白そうなワークショップが残っていた。
「海の科学教育プログラムMARE(マーレ)と子供達に伝えるための科学コミュニケーション」。米国カリフォルニア大学バークレー校のLawrence Hall of Scienceで開発された科学教育プログラムを、沖縄を拠点とするNPOが日本語に翻訳して、学校や科学・教育関連施設でのアクティビティ実施に向けて紹介・普及していこうという、その最初の一歩としてのワークショップだという。
日曜日のタイムテーブルの最初の時間帯だったせいか、参加者は全部で12名。こじんまりと説明が始まった。
ワークショップでは、NPOの紹介に続いて、2種類のアクティビティを体験させてもらった。1つは、参加者が小学6年生になったつもりで、実際の授業で行われる内容3コマ分をダイジェストで体験するもの。そしてもう1つは、こうした科学教育プログラムの指導スタイルを同じ題材で複数体験して、手法によって子どもの反応や理解はどのように違うのかを感じてみるというもの。
前者は調査のやり方を考え、実際に模擬調査を体験してデータ集計を行い、調査結果をもとに会議を開いて議論をする、という一連のプロセスを体験するもの。題材は「サメ」だった。後者の題材は「真水と塩水」。密度とはどういうものか、という学習テーマを底流に潜ませた上で、実験方法を自由に研究させるスタイル、文献資料を与えて理論的に研究させるスタイル、具体的な課題を与えて解決法を議論させるスタイルなどをそれぞれ体験した上で、科学教育プログラムに求められる指導方法と効果を考える、というものだった。
体を動かし、同じテーブルの仲間とああでもないこうでもないとおしゃべりしながら考える、というプロセスは、懐かしいようでもあり、新鮮なようでもあり、楽しかった。MARE自体があくまでも「海の」科学教育のためのプログラムなので、主題が理科、中でも海の生き物、という風に偏っていたことは事実だけど、調査データを集計するには、平均を出したり、全体数を推測したりといった数学的センスも必要だし、実験方法の議論では論理的に自分の考えを説明できるだけの言葉の力も必要、はたまた、観察したサメの特徴を絵にする技術や、問題解決のアイディアを思いつく独創力などなど、いわゆる“総合的な学習”のためのプログラム開発がされていた。
国語、算数、理科、社会。大人は区切って考えがちだけど、それはそれで、頭が少しずつ固くなる準備をしているようなものなのかも知れないな、と思った。世の森羅万象に国語とか算数とか理科とか社会だなんて区切りはないのだ、と、そういう目で物事を見ることができるってことが、まず一番大切な学習態度なのかなぁ、と。そんな気がした。
それにしても頭痛が痛い。
最新の画像[もっと見る]
-
 『機動戦士ガンダム THE ORIGIN V』
7年前
『機動戦士ガンダム THE ORIGIN V』
7年前
-
 絵に描いたような夏空
11年前
絵に描いたような夏空
11年前
-
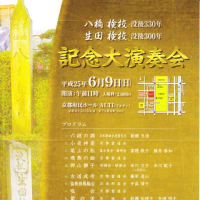 なぜいつもみんな、同じ日
11年前
なぜいつもみんな、同じ日
11年前
-
 DriWater
12年前
DriWater
12年前
-
 鳥ってふしぎ
12年前
鳥ってふしぎ
12年前
-
 稽古復帰(2)
15年前
稽古復帰(2)
15年前
-
 春 遠からじ
15年前
春 遠からじ
15年前
-
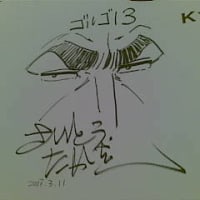 忙中閑 in 京都
15年前
忙中閑 in 京都
15年前
-
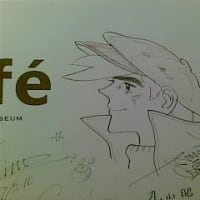 忙中閑 in 京都
15年前
忙中閑 in 京都
15年前
-
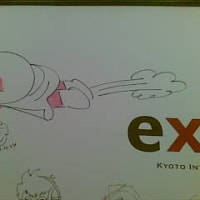 忙中閑 in 京都
15年前
忙中閑 in 京都
15年前















