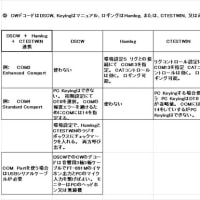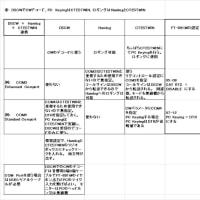いよいよ本命の工作について真面目に考え始めた。 これは長年の夢であったし、今回も夢に終わるかもしれないが・・・
手始めに、Gary Dierking という人の書いた Building Outrigger Sailing Canoes(アウトリガー・セーリング・カヌーの作り方)という本を買った。
なぜアウトリガーで、セイリングで、カヌーなのか、というと・・・細身で軽いだろうから一人でも運べそう、アウトリガー付だから海で釣りするにも安定が良いだろう、セイリングできるから、あわよくば遠くまで簡単に行けるだろう・・・という打算からである。 それに・・・安く作れそうだし・・・手漕ぎもできそうだし・・・
この船で館山湾でアオリイカや鯵、タイやヒラメを釣りたいわけさ。 夏には孫達を乗せて遊ばせることもできるしね。
この本で紹介されているのは、
ハワイアン アウトリガー・セイリング・カヌーのUlua(16Feet、魚Giant Trevally いわゆる GT という意味のハワイ語)、
Wa'apa(24Feetまたは16Feet、Three-boads canoeとも言われる)、
それから、ミクロネシアのマーシャル諸島やキリバチ近辺で見られるT2(16Feet)、というアウトリガー・セイリング・カヌーの3種。
この本の特徴は、アウトリガー・セイリングの2つの方法によってカヌーやリグを大別している。 その方法とは、方向転換の方法で、タッキングとシャンティングの2つである。 それに合わせてリグ(セイルや舵等の仕掛けのこと)もタッキングリグ、シャンティングリグと呼ぶ。
タッキングリグはヨットと同じように船の前方の固定位置にマストをセットし、セイルや舵を左右にコントロールしながら方向を変えて通常のヨットのように帆走する。
ヨットの世界では、風上に向かってに向きを変えるのをタッキング、風下に向かって向きを変えるのをジャイビングという。 ヨットの帆走法と同じだということでタッキングリグと称しているんだろう。
風向きを一本の線だと仮定すると、船のバウ(船首)が線をまたいで方向転換する。 したがって、アウトリガーは風上側になったり風下側になったりする。
一方、シャンティングというのは、船が前後で同じ形をしており、常にアウトリガーを風上側にする。
方向を変えるときにはセイル、舵を船の反対側に移動させて逆方向に進む・・・大変そうだね~。
絶対にバウは風向き線をまたがないで線を斜めに横切るようにスイッチバック(クゥオーターリー)あるいはスイッチフォワード(クローズホールド)するような形で帆走する。
船体が常に一定方向から風を受けるので方向転換が安全にできる。 通常のヨットの本ではこの帆走方法は書いてないのだが、実際の現場(ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアなどの・・・)では、この方法で大海を渡ってきたのである。
アウトリガーが風下側に来る場合が問題になる。 アウトリガーが船体に対して抵抗となりやすいので、強風時にはその抵抗のためにアウトリガーが水に潜ってしまい、前のめりにひっくり返るようなことも起こるらしい。
そのために地域によっていろいろな工夫がなされてきたんだろう。 また、こういうった方法を追跡することで南アジアや南太平洋での民族の移動関係などが分かってくるらしい。
タッキングリグでは、アウトリガーが風下側に来る場合、反対側にハイクアウトするようにハイキングシートが用意されたりする。 アウトリガーの形や位置、浮力の大きさなども地域によって工夫の仕方がすこしづつ違うのは、大変興味をそそられる。
T2という船は、船体の左右のカーブ形状が異なる。 左右いびつなの。 アウトリガー側の船体が大きく湾曲していて、直進させると船体自体はアウトリガーと反対側に曲がろうとする。 一方アウトリガーは船体に対して抵抗舵として働くので、互いの曲がり圧力を相殺して直進しやすくする、という訳だ。
Uluaはタッキングリグのカヌーで、T2はシャンティングリグのカヌー。 Wa'apaはどちら用にもできる。
そのほかにもネットで調べるとタヒチアン スタイルのVa'a Motuというカヌーがあった。 4x8 6㎜厚の合板6枚で作れるみたい・・・
ところで、Wa'aとかVa'aとか、音が似てると思いませんか? ポリネシアとかタヒチとか、文字の無い民族が長い年月をかけて海を渡って、別の島に移り住んでいった過程で、音が少しづつ変化していったものではなかろ~か。
Va'a Motu(G.Dierkingの)は、まるで沖縄のサバニを小型化してアウトリガー・セイリング・カヌーにしたみたいなもの 。 スターンは三角形で水面より上に出るようになっている。(この特徴が同じ) スターンが水面上に出ているので旋回性能が優れていて小回りが利く。 タッキングリグ仕様でセイルは細長いジャンクリグのようなものを使っている。 設計図も公表されている
沖縄とタヒチ・・・ほんとか~? かつて中国人が王の命令で不老不死の薬草をもとめて南米に漂着した、といった話も聞いたことがある。
比べてみて・・・
 G.DierkingのVa'a Motu
G.DierkingのVa'a Motu  サバニ帆船、アウトリガーなし
サバニ帆船、アウトリガーなし
ワシとしては本当はUluaやVa'a Motuを作りたいのだが、16フィート(5.4m)という船の長さが問題になる。 運搬と保管場所だ。 どこで作るかも問題だ。 ワシのRAV4ではルーフキャリアを付けても60~65㎝間隔のバーの上に乗せることになる。 また、乗せられるのは車長の1.1倍、4m40㎝までだからダメということになる。 トレラー買うにしても・・・
ところが、Wa'apaは形は直線的でややダサいが、合板で作ることができ、しかも、船体を3つに分割できる。 各2.4m長で、前後2つを連結すると4.8mのカヌー、3つ連結すると7.2mのカヌーとすることができる。 各連結は直径8mmのボルト4つか5つで連結する。
うむ、これならワシのRAV4でも運べるし、出艇場所まではリアカーで運べる。 うちの狭い庭でも作ることもできる。 保管も・・・それほど・・・場所をとらない。 欠点は、船体が重いことだ。 UluaもT2もストリップ プランキングという、カナディアンカヌーの製作法と同じで、船体が軽く仕上がるのだが・・・まあ、仕方がない。 ちなみにUluaは船体全体で29Kg、Wa'apaは各1/3セクションで26Kgと重い。 まあ、一つづつならワシでももてるだろうけれど・・・つなげると持ちあがらない・・・かな・・・
UluaやVa'a Motuを2分割か3分割してストリップ・プランキングで作れないかな・・・なんて考えることもあるが・・・ストリップ・プランキングで作るには、ストリップを安く自作するためにテーブルソーを買わねばならない。 いろんな道具を買い込みすぎて家に収まらなくなっている反省もあるので・・・今回はジグソーと銅線とエポキシだけで作れるWa'paを作ることにしよう・・・かな・・・まだ迷いがあるな・・・ ・・・
Wa'apaの作り方は、Three-boads Canoeといういうように、合板3枚を貼り合わせて作るので割と簡単ではある。
6㎜厚のマリングレード合板、と指定されているが、日本ではマリングレード合板は製造されていないし、輸入すると高価なので、5.5㎜厚のシナ合板かラワン合板(T1)で作ってみようと思う。 安く、早く、簡単に作りたい。 別に30年も持たせる必要もないのでね・・・ マリングレード合板は重いので、Wa'apaの26Kg/セクションは、ラワン合板ならもっと軽くなるはずだしね・・・
作り方はネイル&グルーというやり方。 合板を形通りにカットし、ガンネル、チャインストリンガー、バルクヘッド、等をネジ釘とエポキシ接着剤、グラステープで糊付けする方法だ。 外側だけグラスクロスをエポキシでFRP処理する。 最終はプライマーとラッカー塗料で防水塗装をする。 Amaの一部だけはステッチ&グルーとなる。
作るとなると気持ちが騒ぐ・・・な。 どれにしようかな・・・ ・・・まだ迷ってるな・・・ ・・・