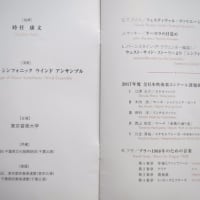このところの残暑のせいもあってか、いささか夏バテ気味。体がだるくて、やる気が沸いてこない。
そこで、気分転換にと久しぶりに映画を見に行く。
見たのは、「ラストゲーム」~最後の早慶戦である。

<野球(ベースボール)、生きてわが家(ホーム)に
還るスポーツ>(写真は、劇場用解説書より)
昭和18年10月16日。(昭和18年は小生が生まれた年でもある。)
時は太平洋戦争の真っ只中。
二度と帰れないかもしれない若者たちに「生きた証」を残してやりたい、と早慶戦の開催に奔走する信念と勇気を持った二人の男がいた。
慶應義塾大学の塾長小泉信三と早稲田大学野球部顧問の飛田穂洲の二人である。
しかし、時は厳しい戦時体制下、単に好きな野球をやらせたいということさえも周囲からさまざまな圧力がかかる。
そうした幾多の困難を乗り越えて、遂に「最後の早慶戦」=「出陣学徒壮行早慶野球戦」が実現し、その試合が早稲田大学戸塚球場で行われる。
この映画は、そんな実際にあった出来事を野球というスポーツを通じて友人、師弟、親子など、人と人とのつながりの大切さ、平和のありがたさを描いたヒューマン・ドラマである。
「一球入魂」。
この飛田穂洲が唱えたモットーは、この映画のさまざまな場面でてくる言葉で、この映画の一つのキーワードとなっているように思える。
先ずは、早慶戦の開催に強硬に反対する早稲田の総長との交渉において、一歩も引かず、学生たちに試合をさせてやるためなら、全ての責任を取り、反対する者とあくまでも戦うと断固意志を貫らぬいた姿勢の中に「一球入魂」の精神の表れを見る思いがする。
そして、最後の早慶戦。
結果こそ10対1と大差のゲームとなったが、一瞬、一瞬を懸命にそして精一杯生きた証としてこの試合にかけた思いの深さにおいて、まさに飛田が提唱した「一球入魂」の真髄を体現した試合であったと思う。
試合終了後両校の学生が一緒になって校歌、応援歌を大合唱する場面は本当に感動的で胸が熱くなった。
それから5日後の10月21日、出陣学徒の壮行会。
折からの降りしきる雨を突いて神宮外苑の競技場を行進する出陣学徒の中に、早慶戦を戦った選手たちの顔があった。
次々と映し出される選手たちの顔の中に、主役を演じた早稲田大学の戸田順治がクローズアップされる。
そして、画面が切り替わりテロップが流れる。
「戸田順治をはじめ、幾多の若者たちが戦場に散り、帰らぬ人となった」と。
次に、米艦に体当たりして行く飛行機の実写フィルムが重なる。
何とも切なく、哀しく、胸をかきむしられるシーンである。
この戸田選手には仲の良い軍人の兄がいたが、出征して戦死したばかりである。
目に入れても痛くない(戸田選手の父親の言葉。実はこの父は、長男の戦死は名誉と心ないうそで自分を偽っていたのだ。)ほど愛していた息子二人を相次いで戦争で失った両親の思いはいかばかりかと、思うと涙がとめどなく頬を伝って落ちた。
そして、平和ボケしていると言われる昨今の日本であるが、一人の親として少なくとも子供たちを戦場に送らないで済む平和な時代に生きていることを心からありがたいと思った。
同時に、「球を打ち、ホームベースに還ってくるのがルールの野球を愛した若者たちが、なぜ、自分自身のベースである家族の待つ家へ帰れない戦場へと送られなければならなかったのか?映画を見終わったとき、そう思わない人は一人もいないはず」と映画評論家の渡辺祥子さんがいみじくも書いているが、小生もこれから先、大切な家族を戦場に送ることは決してあってはならない、許してはならないとこの映画を見て改めてそう思った。
小生が見た映画館は、平日にしては観客の入りはまずまずであったが、高齢者の姿が目についた。
この映画を撮った神山征二郎監督がインタビューの中で、「20歳前後で、命と直接向かい合わなくてはいけなかった若者たちを描くことで、見る人に何かを感じてもらえたらと思いました」と言っているが、「ラストゲーム~最後の早慶戦」が行われたあの時代がどんな時代であったか、若い人たちにも是非この映画を見て知ってもらいたいと思った次第である。
そこで、気分転換にと久しぶりに映画を見に行く。
見たのは、「ラストゲーム」~最後の早慶戦である。

<野球(ベースボール)、生きてわが家(ホーム)に
還るスポーツ>(写真は、劇場用解説書より)
昭和18年10月16日。(昭和18年は小生が生まれた年でもある。)
時は太平洋戦争の真っ只中。
二度と帰れないかもしれない若者たちに「生きた証」を残してやりたい、と早慶戦の開催に奔走する信念と勇気を持った二人の男がいた。
慶應義塾大学の塾長小泉信三と早稲田大学野球部顧問の飛田穂洲の二人である。
しかし、時は厳しい戦時体制下、単に好きな野球をやらせたいということさえも周囲からさまざまな圧力がかかる。
そうした幾多の困難を乗り越えて、遂に「最後の早慶戦」=「出陣学徒壮行早慶野球戦」が実現し、その試合が早稲田大学戸塚球場で行われる。
この映画は、そんな実際にあった出来事を野球というスポーツを通じて友人、師弟、親子など、人と人とのつながりの大切さ、平和のありがたさを描いたヒューマン・ドラマである。
「一球入魂」。
この飛田穂洲が唱えたモットーは、この映画のさまざまな場面でてくる言葉で、この映画の一つのキーワードとなっているように思える。
先ずは、早慶戦の開催に強硬に反対する早稲田の総長との交渉において、一歩も引かず、学生たちに試合をさせてやるためなら、全ての責任を取り、反対する者とあくまでも戦うと断固意志を貫らぬいた姿勢の中に「一球入魂」の精神の表れを見る思いがする。
そして、最後の早慶戦。
結果こそ10対1と大差のゲームとなったが、一瞬、一瞬を懸命にそして精一杯生きた証としてこの試合にかけた思いの深さにおいて、まさに飛田が提唱した「一球入魂」の真髄を体現した試合であったと思う。
試合終了後両校の学生が一緒になって校歌、応援歌を大合唱する場面は本当に感動的で胸が熱くなった。
それから5日後の10月21日、出陣学徒の壮行会。
折からの降りしきる雨を突いて神宮外苑の競技場を行進する出陣学徒の中に、早慶戦を戦った選手たちの顔があった。
次々と映し出される選手たちの顔の中に、主役を演じた早稲田大学の戸田順治がクローズアップされる。
そして、画面が切り替わりテロップが流れる。
「戸田順治をはじめ、幾多の若者たちが戦場に散り、帰らぬ人となった」と。
次に、米艦に体当たりして行く飛行機の実写フィルムが重なる。
何とも切なく、哀しく、胸をかきむしられるシーンである。
この戸田選手には仲の良い軍人の兄がいたが、出征して戦死したばかりである。
目に入れても痛くない(戸田選手の父親の言葉。実はこの父は、長男の戦死は名誉と心ないうそで自分を偽っていたのだ。)ほど愛していた息子二人を相次いで戦争で失った両親の思いはいかばかりかと、思うと涙がとめどなく頬を伝って落ちた。
そして、平和ボケしていると言われる昨今の日本であるが、一人の親として少なくとも子供たちを戦場に送らないで済む平和な時代に生きていることを心からありがたいと思った。
同時に、「球を打ち、ホームベースに還ってくるのがルールの野球を愛した若者たちが、なぜ、自分自身のベースである家族の待つ家へ帰れない戦場へと送られなければならなかったのか?映画を見終わったとき、そう思わない人は一人もいないはず」と映画評論家の渡辺祥子さんがいみじくも書いているが、小生もこれから先、大切な家族を戦場に送ることは決してあってはならない、許してはならないとこの映画を見て改めてそう思った。
小生が見た映画館は、平日にしては観客の入りはまずまずであったが、高齢者の姿が目についた。
この映画を撮った神山征二郎監督がインタビューの中で、「20歳前後で、命と直接向かい合わなくてはいけなかった若者たちを描くことで、見る人に何かを感じてもらえたらと思いました」と言っているが、「ラストゲーム~最後の早慶戦」が行われたあの時代がどんな時代であったか、若い人たちにも是非この映画を見て知ってもらいたいと思った次第である。