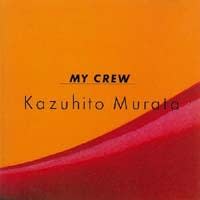David T.Walkerの2度目の来日公演が今月ブルーノート東京で行われる。
チケットはもう買ってあるので今から楽しみだが、この人がバックを務めたアーティストはとにかく枚挙に暇がない。
アメリカはもとより井上陽水やドリカムまでという奥行きと幅広さなので、
とてもすべてを聴き通すことは不可能なわけだけど、せっかくのライブの前に少しは予習しておきたいところ。
Odyssey。僕はクラブなどにはあまり行かないので、このアルバムがいわゆるレア・グルーヴの一枚として
数年前に盛んにクラブで取り上げられていたということは知らない。
特に「Bttened Ships」のような跳ねたリズムのミディアム・チューンは確かにクラブ受けするだろうなあ、という気がする。
白色混合の7人組のOdysseyは72年にMotownのサブレーベルであるMo-westから出たアルバム。
アルバムはこの一枚きりのようだ。雰囲気的には5th Dimensionがちょっと若くなった感じ。
考えてみるとモータウンのアルバムを買うのも久しぶりだなあ・・・。
いわゆるヴォーカル・インストゥルメンタルのグループでDavid T.が参加しているのは「Our Lives Are Shaped By What We Love」の一曲のみ。
この1曲で聴ける彼のギターはまさにDavid T.節。
そう思って聴くと他の彼が参加していない曲に比べて落ちついた雰囲気が感じられる。
どんな人のバックで演奏しようとも必ず自分の存在感をそれとなく発揮する。
David T.Walkerのギターはさりげなく主張するのだ。
チケットはもう買ってあるので今から楽しみだが、この人がバックを務めたアーティストはとにかく枚挙に暇がない。
アメリカはもとより井上陽水やドリカムまでという奥行きと幅広さなので、
とてもすべてを聴き通すことは不可能なわけだけど、せっかくのライブの前に少しは予習しておきたいところ。
Odyssey。僕はクラブなどにはあまり行かないので、このアルバムがいわゆるレア・グルーヴの一枚として
数年前に盛んにクラブで取り上げられていたということは知らない。
特に「Bttened Ships」のような跳ねたリズムのミディアム・チューンは確かにクラブ受けするだろうなあ、という気がする。
白色混合の7人組のOdysseyは72年にMotownのサブレーベルであるMo-westから出たアルバム。
アルバムはこの一枚きりのようだ。雰囲気的には5th Dimensionがちょっと若くなった感じ。
考えてみるとモータウンのアルバムを買うのも久しぶりだなあ・・・。
いわゆるヴォーカル・インストゥルメンタルのグループでDavid T.が参加しているのは「Our Lives Are Shaped By What We Love」の一曲のみ。
この1曲で聴ける彼のギターはまさにDavid T.節。
そう思って聴くと他の彼が参加していない曲に比べて落ちついた雰囲気が感じられる。
どんな人のバックで演奏しようとも必ず自分の存在感をそれとなく発揮する。
David T.Walkerのギターはさりげなく主張するのだ。