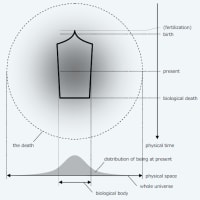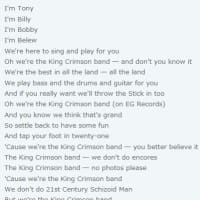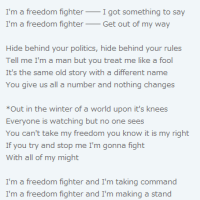7. 人間を科学的像に放り込む(Putting Man into the Scientific Image)
もし仮に、前節で述べた建設的な提言から(前進して)日常的像の感覚・イメージ・感じといったものを科学的像の言葉によって作り直すというようなやり方でもって適切な説明をひとつ練り上げられるほどのものになったとしても、それで科学的像の優位という主張(thesis)が離陸に成功したなどとは、なかなか言えたものではないであろう。
(そんなぬか喜びする前に)自分が(倫理的とか論理的とかその他の)さまざまな基準──しばしば自身の欲求や衝動と競合し、彼はそれに従うことも従わないこともできるというような──に直面していると気づいた汎人物としての人間に関わるカテゴリは、「人間は科学が『オマエハコウイウ奴ダ』という通りの存在だ」という観念と和解させることができる、ということを示す課題が残るであろう。
一見すると科学的像の枠内で、特に人間というものを捉えなおすやりかたは、ただひとつしかないように思えるであろう。生化学の概念は原子以下の物理学(sub-atomic physics)の言葉で(原理上)再構成されるわけである、だからそれと似たようなやりかたで、汎人物のカテゴリは科学的像の基礎概念から漏れなく再構成されるんじゃないだろうか、と。
こうした示唆に対しては、まず第一におなじみの反論がある。すなわち──
この一手(move)を指す人は(しかし)以下に(第1節で展開した区別に従って)応答することを求められうる。すなわち──
で、わたしの考えでは、この「再反論」、汎人物に関するカテゴリの再構成提案に答えるであろうような応答は、この線に沿ってやれば(ムチャムチャ)詳細なものになりうるということになる。
この再構成提案は(だから)上述の「反論」(「自由意志」論法とでも呼ぼうか)には対処できるであろう、しかし、別の理由によって決定的(decisively)に失敗(不成立)となるのである。なぜなら、わたしの信じるところでは、上述のごとき再構成は原理的に不可能であって、件の不可能性は厳密に論理的な不可能性であると決定的(conclusive)に示しうる(証明できる)からである。
(わたしはこの点を明に論じるつもりがないのであるが、しかし以下に述べる内容は本質的な手がかりを含んでいる。)
もしそうだとすれば一巻の終わりであるように思える。我々は以下の3つの選択肢からの選択に(※つまり「ふりだし」に)戻らなくてはならないのではないか?
本論考における論証の流れに沿って言えば、この3つの選択肢はどれも満足のいくものではないわけである。ならば出口は存在するのであろうか?
わたしは「ある」と信じているわけである。それを適切な形で説明し擁護しようとすれば、少なくともぶ厚い本一冊分(※つまり、この論文が収録された本)の分量が必要になるであろうが、かいつまんだ要点ならこの狭い紙幅の中でも述べられる。
ある汎人物が「Aしたいと欲した」「Bを行うことを自己の義務と考えた」「しかしCをせざるを得なかった」等々と言うことは、科学実験の標本か何かを記述するように彼を記述することではないのである。確かに(indeed)これらはその汎人物の記述ではある、が、記述するだけではなく、何かそれ以上のことをやっているのである。そして汎人物の枠組みが還元不能である、その核心とはこの「何かそれ以上のこと」なのである。
「それ以上の」何があるというのだろうか。まずは相対的に表面的なことが道案内となるであろう。(すなわち)羽のない二足動物を汎人物として考えることは、そいつ(it)を権利と義務の網状組織(network)に組み込まれた存在として考えることである。この観点からすると汎人物的なものの還元不能性(irreducibility)とは、「べきである(ought)」を「ある(is)」に還元することの不可能性である。
しかしもうひとつ、もっと基本的なことがある(とはいえ究極的には両者は一致する。あとでわかる)。(すなわち)羽のない二足動物を汎人物と考えるということは、その成員の各々が自らをその集団の一員として考えているような包括的な集団(embracing group)において(そいつが)実際に(actual)(あるいは潜在的potentialに)その成員であるということによって(in terms of)そいつの行動を解釈するということである、という事実である。
そのような集団を「共同体(community)」と呼ぼう。かつてそれは原始的な部族であった。今のそれは(ほとんど)「人類皆兄弟」、潜在的には(カントの「目的の王国」にいう)理性的な存在の「共和国」のことである。個人は多数の共同体に所属することができる。いくつかは重なり合い、いくつかは入れ子細工の箱(Chinese boxes)のように配列されている。彼が所属するうちで最も包括的な共同体とは、彼が意味のある会話(discourse)に加わることができる人々からなる共同体である。
包括的な共同体の範囲(scope)は、最も包括的かつ比喩的でない用法における「我々(we)」の範囲である。この根本的な──フランス語の'on'ないし英語の'one'と等価な──意味における「我々」は、動詞が結びつく他の「人称」に劣らず基本的なものである。したがって、羽のない二足動物かイルカか火星人か、とにかくそいつを一個の汎人物として認識することは、自分自身とそいつがある共同体に所属するものとして考えることなのである。
さて、ある共同体の根本原理、つまり何が「正しい」か「間違い」か、何が「正当」か「不正」か、何が「行われた」か「行われていない」のかを定義する共同体の根本原理は、その集団の成員の行動に関してその共同体がもつ最も一般的な共通の意図である。
したがって、羽のない二足動物かイルカか火星人か、とにかくそいつを一個の汎人物として認識することは、各々が「ワレワレハ(人間タルモノハ)状況Cニ於テ行為Aヲスベキデアル(差シ控エルベキデアル)」という形の考えを考えることを要求するということである。この種の考えを考えることは、分類したり説明したりすることではなく、ある意図を試演(rehearse)することである*。
したがって、汎人物の概念的な枠組みとは、そのもとで我々がお互いのことを共同体の意図を共有するものと考えるような枠組みのことである。共同体の意図がもたらすものは、我々が自らの個人としての生をその中で生きる(わけても意味のあるハナシ(discourse)と合理性それ自体を可能にする)、その原則と基準の環境(ambience)である。
汎人物とは意図をもつ存在である、と、ほとんどそう定義できそうなくらいである。だから汎人物の概念的な枠組みは、科学的像と和解することを要する何かではなく、科学的像に結合されるべき何かなのである。
かくして、科学的な像を完結させるためには、それはどういうことなのか(what is the case)の説明のしかたを増やすのではなしに、共同体や個人の「意図の言語」によって科学的な像の内容を豊富にする必要があるのである。そのためには、我々がしようと意図している行為、それらをなそうとする状況を科学的な言葉で解釈することによって、科学理論によってそう考えられた世界を我々の「目的」に直接的に関係づけ、(「目的」に関係づけられた)それを我々の世界とすること、そして(その「目的」を)我々がまさにその中で生きている世界の疎遠な付属物にはもはやしないことが求められるのである。
むろん現状においてはそのような、科学的な像の我々の生き方への直接的な統合(incorporation)などというのは、想像の中でしか実現できないことである。けれども想像の中だけであれそうした統合をやる(do)ということは、人間の日常的な像と科学的な像の二元論を超越(transcend)するということなのである。
(第7節おわり──むろん、PSIMについての作業はまだまだこれからである)
もし仮に、前節で述べた建設的な提言から(前進して)日常的像の感覚・イメージ・感じといったものを科学的像の言葉によって作り直すというようなやり方でもって適切な説明をひとつ練り上げられるほどのものになったとしても、それで科学的像の優位という主張(thesis)が離陸に成功したなどとは、なかなか言えたものではないであろう。
(そんなぬか喜びする前に)自分が(倫理的とか論理的とかその他の)さまざまな基準──しばしば自身の欲求や衝動と競合し、彼はそれに従うことも従わないこともできるというような──に直面していると気づいた汎人物としての人間に関わるカテゴリは、「人間は科学が『オマエハコウイウ奴ダ』という通りの存在だ」という観念と和解させることができる、ということを示す課題が残るであろう。
一見すると科学的像の枠内で、特に人間というものを捉えなおすやりかたは、ただひとつしかないように思えるであろう。生化学の概念は原子以下の物理学(sub-atomic physics)の言葉で(原理上)再構成されるわけである、だからそれと似たようなやりかたで、汎人物のカテゴリは科学的像の基礎概念から漏れなく再構成されるんじゃないだろうか、と。
こうした示唆に対しては、まず第一におなじみの反論がある。すなわち──
| [反論] 人間は正真正銘の(genuine)選択肢の中から正真正銘の選択を行う、その選択の責任を負わされうる、(多くの場合)実際にはやらなかったことを「やろうと思えばできた」と言いうる動作主(agent)である。だから人間を(統計的あるいは非統計的な)自然の法則に沿って時間発展する物理系(感覚や感情を含めて広く解釈されたものとしよう)として解釈することは、端的にできないのである。 |
この一手(move)を指す人は(しかし)以下に(第1節で展開した区別に従って)応答することを求められうる。すなわち──
| [再反論] 我々がある汎人物の「性格」について考えることに関する概念(concept)、すなわち「彼は別様にやろうと思えばできたはずである」とか「彼の行為は予測可能である」とかの事実は、ムチャムチャ複雑に定義される概念として再構成されたもののうちに現れるはずのものである。それは我々が塩化ナトリウム(NaCl)の「本性」について考えることに関する概念、すなわち「与えられた同一の初期条件のもとで系Xは状態Sをとることはできないであろう」とか「これらの初期条件を所与(given)として、系Xは状態Sをとるであろうことは予測可能である」とかの事実と混同されてはならないものである。 |
で、わたしの考えでは、この「再反論」、汎人物に関するカテゴリの再構成提案に答えるであろうような応答は、この線に沿ってやれば(ムチャムチャ)詳細なものになりうるということになる。
| ※ | このへんはあんまり真面目に読んでもしょうがないところである。要はすべては物理として再構成されるはずで、ゆえに「反論」のような主張はムチャムチャ複雑(extraordinary complex)な再構成のどっかでいつの間にか概念規定がズレてしまっただけの、つまり錯覚なのだ、錯覚でないなら(それは自明ではないから)それを示せ、示せないだろう、というのがこの再反論の趣旨である。・・・それはそうと、邦訳書ではなぜかNaClが「塩化カルシウム」と訳されている。思えばサールの「MiND」の邦訳書も(初版では)水素と酸素を間違えていた。真っ青になって原書を買いに走ったものであった。わが国の専門の哲学者というのは翻訳に際して元素の名前を間違えなくてはならない規則でもあるのだろうか? |
この再構成提案は(だから)上述の「反論」(「自由意志」論法とでも呼ぼうか)には対処できるであろう、しかし、別の理由によって決定的(decisively)に失敗(不成立)となるのである。なぜなら、わたしの信じるところでは、上述のごとき再構成は原理的に不可能であって、件の不可能性は厳密に論理的な不可能性であると決定的(conclusive)に示しうる(証明できる)からである。
| ※ | セラーズは手抜きをしているわけであるが(笑)、「錯覚でしかありえない」かと言えばそんなことはない、ムチャムチャ複雑な再構成の詳細を示さなくても、その再構成が「原理的に不可能」であることを示せば「再反論」は退けられると言っているわけである。いいかえれば「すべてが物理であるということはすべてが物理として再構成可能であることを意味するわけではない」ということである。 |
(わたしはこの点を明に論じるつもりがないのであるが、しかし以下に述べる内容は本質的な手がかりを含んでいる。)
もしそうだとすれば一巻の終わりであるように思える。我々は以下の3つの選択肢からの選択に(※つまり「ふりだし」に)戻らなくてはならないのではないか?
| (a) | 二元論。すなわち、科学的な対象物としての人間は、それらの汎人物としての存在の源泉および原理としての「心(精神)」とは違うものである(対照される)とする。 |
| (b) | 消去主義。日常的な意味での「物理的な対象物」ということも、汎人物の実在性ということも廃棄する。そして科学的な対象物の排他的な実在性を(つまり科学的な対象物だけが実在であって、他は実在ではないオバケだという主張を)支持する。 |
| (c) | 現象主義。理論的な枠組みの地位は単に「計算上のもの(calculational)」ないし「補助的なもの(auxiliary)」であるという主張(thesis)へ、そして日常的像の優位性の承認(affirmation)へと回帰し、それっきりとする。 |
本論考における論証の流れに沿って言えば、この3つの選択肢はどれも満足のいくものではないわけである。ならば出口は存在するのであろうか?
わたしは「ある」と信じているわけである。それを適切な形で説明し擁護しようとすれば、少なくともぶ厚い本一冊分(※つまり、この論文が収録された本)の分量が必要になるであろうが、かいつまんだ要点ならこの狭い紙幅の中でも述べられる。
ある汎人物が「Aしたいと欲した」「Bを行うことを自己の義務と考えた」「しかしCをせざるを得なかった」等々と言うことは、科学実験の標本か何かを記述するように彼を記述することではないのである。確かに(indeed)これらはその汎人物の記述ではある、が、記述するだけではなく、何かそれ以上のことをやっているのである。そして汎人物の枠組みが還元不能である、その核心とはこの「何かそれ以上のこと」なのである。
「それ以上の」何があるというのだろうか。まずは相対的に表面的なことが道案内となるであろう。(すなわち)羽のない二足動物を汎人物として考えることは、そいつ(it)を権利と義務の網状組織(network)に組み込まれた存在として考えることである。この観点からすると汎人物的なものの還元不能性(irreducibility)とは、「べきである(ought)」を「ある(is)」に還元することの不可能性である。
しかしもうひとつ、もっと基本的なことがある(とはいえ究極的には両者は一致する。あとでわかる)。(すなわち)羽のない二足動物を汎人物と考えるということは、その成員の各々が自らをその集団の一員として考えているような包括的な集団(embracing group)において(そいつが)実際に(actual)(あるいは潜在的potentialに)その成員であるということによって(in terms of)そいつの行動を解釈するということである、という事実である。
そのような集団を「共同体(community)」と呼ぼう。かつてそれは原始的な部族であった。今のそれは(ほとんど)「人類皆兄弟」、潜在的には(カントの「目的の王国」にいう)理性的な存在の「共和国」のことである。個人は多数の共同体に所属することができる。いくつかは重なり合い、いくつかは入れ子細工の箱(Chinese boxes)のように配列されている。彼が所属するうちで最も包括的な共同体とは、彼が意味のある会話(discourse)に加わることができる人々からなる共同体である。
包括的な共同体の範囲(scope)は、最も包括的かつ比喩的でない用法における「我々(we)」の範囲である。この根本的な──フランス語の'on'ないし英語の'one'と等価な──意味における「我々」は、動詞が結びつく他の「人称」に劣らず基本的なものである。したがって、羽のない二足動物かイルカか火星人か、とにかくそいつを一個の汎人物として認識することは、自分自身とそいつがある共同体に所属するものとして考えることなのである。
さて、ある共同体の根本原理、つまり何が「正しい」か「間違い」か、何が「正当」か「不正」か、何が「行われた」か「行われていない」のかを定義する共同体の根本原理は、その集団の成員の行動に関してその共同体がもつ最も一般的な共通の意図である。
したがって、羽のない二足動物かイルカか火星人か、とにかくそいつを一個の汎人物として認識することは、各々が「ワレワレハ(人間タルモノハ)状況Cニ於テ行為Aヲスベキデアル(差シ控エルベキデアル)」という形の考えを考えることを要求するということである。この種の考えを考えることは、分類したり説明したりすることではなく、ある意図を試演(rehearse)することである*。
| * | 共同体の意図(「人は・・・すべきである」)は個々人がもつ私的な意図(「わたしは・・・すべきである」)とは違う(これは上述の「我々」の還元不能性ということの言い換えである)。とはいえ、共同体の意図と私的な意図との間には論理的なつながりが存在する。なぜなら、ある人が共同体の意図をどんだけ試演していようとも、相当する私的な意図の適切なところにそれが反映されない限り、かれは本当にそれ(共同体の意図)を共有していることにはならないからである。 |
したがって、汎人物の概念的な枠組みとは、そのもとで我々がお互いのことを共同体の意図を共有するものと考えるような枠組みのことである。共同体の意図がもたらすものは、我々が自らの個人としての生をその中で生きる(わけても意味のあるハナシ(discourse)と合理性それ自体を可能にする)、その原則と基準の環境(ambience)である。
汎人物とは意図をもつ存在である、と、ほとんどそう定義できそうなくらいである。だから汎人物の概念的な枠組みは、科学的像と和解することを要する何かではなく、科学的像に結合されるべき何かなのである。
かくして、科学的な像を完結させるためには、それはどういうことなのか(what is the case)の説明のしかたを増やすのではなしに、共同体や個人の「意図の言語」によって科学的な像の内容を豊富にする必要があるのである。そのためには、我々がしようと意図している行為、それらをなそうとする状況を科学的な言葉で解釈することによって、科学理論によってそう考えられた世界を我々の「目的」に直接的に関係づけ、(「目的」に関係づけられた)それを我々の世界とすること、そして(その「目的」を)我々がまさにその中で生きている世界の疎遠な付属物にはもはやしないことが求められるのである。
むろん現状においてはそのような、科学的な像の我々の生き方への直接的な統合(incorporation)などというのは、想像の中でしか実現できないことである。けれども想像の中だけであれそうした統合をやる(do)ということは、人間の日常的な像と科学的な像の二元論を超越(transcend)するということなのである。
(第7節おわり──むろん、PSIMについての作業はまだまだこれからである)