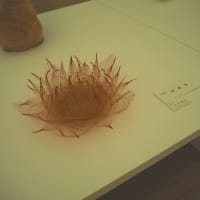【カイロ時事】13日に起きたパリ同時テロをめぐるニュースが連日、世界で大々的に報じられている。一方、アラブ世界では、今回のテロをはるかに上回る犠牲者がシリア内戦などで毎日出ているが、パリほど注目されない。人々の間では「なぜフランスの事件ばかり関心が集まるのか」と違和感が広がっているようだ。
アラブ世界のイスラム教徒の間でも、129人が犠牲になったパリ同時テロへの関心は高い。市民からは、犯行声明を出した過激派組織「イスラム国」を非難し、突然の凶行で命を落とした人々やその遺族らへの同情の声が聞かれる。 ただ、その1日前の12日にレバノンの首都ベイルートで起き、40人以上が死亡した連続自爆テロは、あまり各国メディアで報じられていない。クウェート紙アルライは「レバノンの人々は、世界にとってレバノンの犠牲者はパリと同等でなく、忘れ去られたと感じている」と伝えた。
エジプト紙アルワタンも「アラブ諸国では毎日人々が死傷しているのに、なぜフランスばかりなのか」といったフェイスブック投稿者の違和感を伝えるコメントを掲載。町の喫茶店では「世界は二重基準だ」と不満の声が聞かれたことにも触れ、「強い国は注目され、弱い国は(強い国より)悲惨な事件が起きても目を向けられないものだ」と語る大学教授の見解を紹介した。 フェイスブックでは、プロフィル写真上にフランス国旗を映し出す機能が搭載され、世界中で多くの人がこれを利用している。こうした中、エジプトの著名俳優アデル・イマム氏は「フランスよりレバノンの方が(エジプトに)近い。だから私は連帯を表明する」と述べ、自らの写真にレバノン旗を重ねた。
日刊ゲンダイ
“もうひとりのマララ”と呼ばれるパキスタン人のナビラ・レフマンさん(13)が来日。都内で16日会見し、3年前にその身を襲った空爆の恐怖を語った。ナビラさんがノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさん(18)と比べられるのは、母国のパキスタンで同じようにテロの犠牲になったからだ。しかし、その後の境遇はまったく違う。
女子教育を訴えてタリバンに襲撃されたマララさんは、英国の病院で先端治療を受けて回復。英国にとどまり、学生生活を送っている。一方、ナビラさんは農作業中に米軍の無人偵察機にミサイル攻撃を受けて負傷した。祖母も失ったナビラさん一家に対し、パキスタン政府は「米政府の責任」と突き放し、何の補償も受けられずに故郷を追われた。国内難民としての生活を余儀なくされている。
ナビラさんの招聘に動いた現代イスラム研究センターの宮田律理事長はこう言う。
「加害者が〈誰なのか〉で欧米政府やメディアの対応はここまで違うのかと愕然とします。タリバンの被害者のマララさんは〈自由の象徴〉のごとく祭り上げられているのに、米国の被害に遭ったナビラさんは完全に無視されている。13年にナビラさん一家は渡米し、米議会の聴聞会でスピーチしたのですが、出席した議員はわずか5人。報道はほとんどされず、帯同する予定だったナビラさんの担当弁護士は入国を拒否された。今回の招聘にあたっても、在イスラマバードの日本大使館はビザ発給に非協力的でした」
米国は過激派組織「イスラム国」に対する空爆を続け、その成果ばかりが伝えられるが、その裏で多数の民間人が犠牲になっている現実がある。
毎日新聞
ナビラさんの狙撃は「武装勢力とみられる3人を殺害」(地元紙ネーション)、「『標的は武装組織の拠点』と治安関係者」(AFP通信)と報道された。だが、実際に死亡したのは、モミナさんと4頭の牛だ。
「無人機攻撃はテロリズムを増幅させる。罪のない人が殺害され、憎悪をもたらすことになる」。マララさんはオバマ大統領に訴え、後に米メディアのインタビューにこう語った。「無人機はテロリストを殺害するが、民間人も標的になっている。もし父が殺されたら、子供はテロリストになってしまう」。当時16歳のマララさんが、米軍の最高司令官に無人機攻撃をいさめたことは、メディアで大きく取り上げられた。
パキスタン軍は今年9月、国産無人機による攻撃を初めて実施したと発表したが、それまで同国で無人機による攻撃を行っていたのは米国だけだ。ロンドンの非営利団体「調査報道局(BIJ)」のまとめによると、パキスタンでは04年以降、421回の無人機攻撃があり、最大3989人が殺害された。965人は民間人で、うち207人が子供だったという。4人に1人は「テロリスト」と無関係の市民ということになる。米インターネットメディア「インターセプト」は10月、米軍の機密文書とされる資料を基に、アフガンでは一時期、無人機で殺害した9割が標的と異なっていたと報じた。
米国から帰国したナビラさん一家に、つらい現実が待っていた。14年6月、北ワジリスタン管区でパキスタン軍によるTTPの掃討作戦が始まった。「3日以内に村を出て行くように」。突然、長老に告げられた。地上戦が始まる−−。ナビラさんら村民は衣類や現金などわずかな財産を抱え、約50キロ離れた隣接州の町を目指した。ひどい一日だった。ナビラさんは祖父と並んで山道をひたすら歩いた。「家も畑も捨ててきた。どこに行くかも分からなかった」。友人とはすぐに離ればなれになった。避難所があるバンヌーの町に着いたのは午後9時ごろ。難民キャンプはいっぱいで、行く当てもなく、路上で一夜を明かすしかなかった。郊外にある政府庁舎の敷地に空き地を見つけたのは、数日後のことだ。それから1年半がたった現在も、一家は空き地に建てた粗末な小屋で暮らしている。地元の学校教師だったレフマンさんは失業し、生活は政府や支援団体の配給が頼み。息子たちは2キロ離れた学校に通うが、付近に女子校はなく、ナビラさんら娘はずっと家にいる。
ナビラさんには三つの夢がある。学校に行って勉強すること。いつか弁護士になること。そして、教育を受けられない故郷の子供たちのために、何かをすること−−。だが、避難生活の終わりは見えない。いつ学校に通えるのかも分からない。そして、残りの人生を「幕」の向こうで過ごすことになるかもしれない。
無人機に限ったことではない。空爆は常に一般人の犠牲が伴う。それを承知で行う大国の攻撃。
16日放送の「報道ステーション」(テレビ朝日系)で、古舘伊知郎氏がフランスによる過激派組織ISIL(イスラム国)への空爆を「テロ」と表現した。
フランスは、自国へのテロ計画があるとして、9月27日からシリア領内のISILに空爆を踏み切っている。テロ発生後にも、フランス軍はラッカにあるISILの訓練施設や司令部などを攻撃した。同国のファビウス外相は「ひどい攻撃を受けた。このまま引き下がるわけにはいかない」との声明を出している。
中東の国際関係に精通した同志社大学大学院教授・内藤正典氏は「私たちは『テロ』とは、テロ組織を指して言っていますが、昨年のガザとイスラエルの紛争のとき、ガザの子どもが500人は亡くなった。ご遺族からすればこれがテロでなくて何でしょうか」と疑問を投げかけた。さらに内藤氏は、これまでには黙殺にあった死者が膨大にいるといい、「テロの肯定はできないが、そういう犠牲になる人たちの目線では、有志連合がやっていようが、フランスがやっていようが同じくテロじゃないか」と、誰の手であろうと無実の人が殺される攻撃はテロであるとしていた。
内藤教授はさらに、シリアから膨大な数の難民が出ているのは、イスラム国が怖いことも確かにあるものの、有志連合による空爆を恐れていることの方が大きいとした。その理由としては、「一瞬にして、住む家、家族を吹き飛ばされてしまうわけですから」と述べた。イスラム国から何かの刑罰を受けるまでには時間があるものの、空爆は時間がないともいう。
また、内藤教授は、「軍事力の行使によってこのテロが根絶されるという可能性はまったくない」とも述べた。7000~9000回も行われているという空爆で難民が続々と出て、テロリストがその中に紛れ込んでしまうからだという。難民が虐げられて辛酸をなめれば、最後には敵意を向ける恐れがあるとも指摘した。
テロとは、民族、宗教的グループあるいは秘密工作員によって行われるもので、非戦闘員を対象として、大衆に恐怖を与える意図のもとに行われる。テロリスト殺戮が目的だから、一般人が犠牲になってもテロとは言わないのだろうか?
ネット上では、「そう、逆から見りゃテロなんだな」「有志連合がやってきた事にも目を向けてほしい」と同意する意見が出た一方で、「では、何もしないことが正解というのかね?」といった疑問も噴出している。