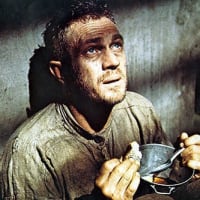アポロ計画は、米ソ冷戦時代に宇宙拡張競争をしていた超大国の重要な宇宙計画であった。暗殺されたケネディ大統領は、「アメリカは必ず有人ロケットで月に行く」と宣言した。宇宙拡張競争に米国は遅れてはならないという、重要ミッションを公式に表現したのである。そして、アポロ計画の元、アポロ11号は、人類を乗せ、月面に着陸したのである。「この1歩は小さな1歩であるが、人類にとっては大きな1歩である」とアームストロング船長に言わせたのである。アポロ計画は、17号までの運用で終了した。NASAは国家予算の削減のためであると理由を説明したが、それが真実だったのか疑問である。
ここに、アポロ計画を断念せざるを得なかった理由を明快に示した映画がある。『アポロ18号』(2011年アメリカ制作)がそれだ。1969年7月20日、アポロ11号が人類初の月面着陸に成功。1970年、NASAは予算削減を理由にアポロ18~19号の計画中止を発表。1972年12月7日、アポロ17号が最後の月面着陸に成功し、アポロ計画は完了した。しかし1974年、ジョン・グレイ指令操縦士のもとへ一本の連絡が入った。「アポロ18号飛ばす。」それを受け、着陸操縦士のベン・アンダーソン、船長のネイト・ウォーカーを招集し12月20日、中止したはずのアポロ18号が秘密裏に月へと向け発射された。
12月25日、着陸線リバティは無事月面着陸に成功する。今回の任務は動体感知カメラと“国防総省PSD5”と表記された装置を月面に設置することだった。比較的簡単にその作業を終えたネイトとアンダーソンは忘れずに月の石も採取し、リバティへと戻った。しかし翌日、採取したはずの月の石が床に散乱しており、不審に思いつつ二日目の船外活動に出かける二人はさらに驚愕の真実と直面する。自分たち以外の足跡を発見し、それをるとソ連の探査機が着陸していたのだ。公式にはアメリカしか降り立ったことのない月面に何故ソ連船が・・・?船内に乗組員はおらず、白骨化した死体まで見つかった。月で一体何があったのか。時同じくして昨日設置した動体感知カメラは異様な物体を写していた。『アポロ18』はネットの片隅にアップされていた“記録映像”である。
『ブレアウィッチ・プロジェクト』、『クローバー・フィールド/HAKAISHA』そして『REC/レック』とP.O.V=主観映像作品は過渡期を迎え、『パラノーマル・アクティビティ』、『ラスト・エクソシズム』、『トロールハンター』など新世代の“記録映像”を産み出してきた。その中でも『アポロ18』は乗組員の手持ちカメラと、任務で月面に設置した定点カメラの映像とで進行していくため『パラノーマル・アクティビティ』の手法に類似していると言える。しかし、それと異なるのは宇宙空間という密室で繰り広げられるシチュエーションだ。酸素なし、光なしの暗闇という閉塞感の中で展開する『アポロ18』はP.O.V映像の効果的な使い方の一例になったと言っても過言ではない。

プロデューサーを務めるのは『ウォンテッド』、『デイ・ウォッチ』のティムール・ベクマンベトフ監督だ。『アポロ18』にも映像に趣向を凝らす彼の拘りが反映されているのか、ざらついた質感の映像はリアルそのものを映し出すかのようで臨場感をぐっと上げることに成功している。
アポロは最初から月には行っていなかったと唱える捏造説をはじめ、アポロ計画に関する陰謀論は多々あり、今日まで熱狂的なほどに議論がなされてきた。折しも1977年には火星に行ったふりをしてとある基地で火星探査の様子をでっちあげる『カプリコン・1』という映画まで公開された始末だ。そういった意味で『アポロ18』はアポロ陰謀論への新たな解釈・答えを成しており、結末を観てさらに想像力が掻き立てられることは間違いない。
『アポロ18』はアメリカ合衆国がおこなった「アポロ計画」における公式には存在しない最後のミッションである。そもそもアポロ計画とは、人間が月まで飛んで着陸する宇宙計画である。いまでこそ宇宙計画といえば約60億kmの旅をしてサンプルリターンした小惑星探査機「はやぶさ」を思い出すが、あれは無人機だった。
有人の宇宙計画では「国際宇宙ステーション」が思いつくが、それは地球からの高度400 km足らずのところ、いわゆる低地球軌道(LEO)を周回している。LEOはもっと高くまであるが、高度500 kmあたりからヴァン・アレン帯という放射線の強い空間に入るので、それより低いところを周回する。いまは引退してしまったスペースシャトルも、ヴァン・アレン帯にはめったに入らなかった。シャトルの高度記録はハッブル宇宙望遠鏡を運んだディスカバリー号(STS-31)の615 kmである。人類はこれより高く、そして、地球から遠くへは飛んでいないのだ、アポロ計画を除いては。
ヴァン・アレン帯が見つかったのは1958年のことである。国際地球観測年(IGY)に便乗し、1957年にロシア(旧ソ連)が世界初の人工衛星スプートニク1号を打上げ、同年のスプートニク2号ではメス犬一頭を乗せた世界初の生物宇宙飛行をした。アメリカは慌てて翌年にエクスプローラー1号を打上げ、それで強放射線のヴァン・アレン帯を発見したのである。
1961年、旧ソ連は人類初の有人宇宙飛行を成功させた。ときのアメリカ大統領J・F・ケネディはそれが悔しくて、1960年代のうちに人間(もちろんアメリカ人)を月面に立たせると宣言した。アポロ計画の始まりである。ケネディは暗殺されたが、その二代後のニクソン大統領が就任してちょうど半年後の1969年7月20日にアポロ11号が月面着陸を果たした。
アポロ計画捏造説は古くから存在する都市伝説である。たとえば、ヴァン・アレン帯を通過するときの放射線に人間は耐えられないという。しかし、月に行くための最低速度、すなわち第2宇宙速度(秒速約11.2 km)だと、ヴァン・アレン帯の通過時間は往復で一万秒もない。地球と月を往復しても10ミリシーベルトくらいの被曝だ。短期と長期の違いはあるが、1マイクロシーベルト毎時の放射線を一年間浴びる被曝量と同程度である。
アポロ12号(1969)はすでに月面着陸していた無人機サーベイヤー3号からカメラなどの機器を持ち帰った。すると、カメラ内から微生物が見つかった。はじめのうちは月の微生物かと思われたが、すぐに地球から運ばれた雑菌だとわかった。しかし、それは2年半も月面の真空と放射線に曝されながら生存したのだ。世界初の生物サンプルリターンである。
アポロ計画では382 kgにも達する月面サンプルを持ち帰った。あまり知られていないが、旧ソ連も「ルナ計画」(1957~1976)において無人の月着陸機でサンプルリターンをした。成功したのはそのうち3回で合計326グラム(kgではない)と少量だが、もしかしたら、失敗例というのは失敗ではなく、わざとリターンしなかった、つまり、ずっと月面に機体を置く意図のミッションだったかもしれない。
アポロ計画は公式には17号(1972)で終了した。同年に旧ソ連が世界初の宇宙ステーション「サリュート1号」をソユーズ11号で打上げたのが、アメリカにはショックだったのである。それで、当初はアポロ20号まで予定していたのに、18号に使うはずだったサターンV型ロケットを宇宙ステーション「スカイラブ1」(1973)の打上げに転用したのだ。そして、1975年、アポロ計画の真のラスト・ミッションが、米ソ共同の「アポロ-ソユーズ・テスト計画」という形で行われたのである。『アポロ18』はこの間の1974年という設定である。
ルナ計画で先に月に到達し、有人宇宙飛行でも先行していた旧ソ連がなぜ月にロシア人を送り込まなかったのか。なぜアメリカはアポロ計画以降ずっと低地球軌道にとどまっているのか。もはやアポロ計画捏造説などという都市伝説にかまうことはない。むしろ、アポロ計画は、いったい何を見たのか、秘められた事実のほうがおもしろいということなのである。