
★湯木美術館 「日本<茶>料理の開拓者 吉兆庵湯木貞一生誕110周年記念展」 サイト
※二期:「数寄者との交流 - 小林逸翁・松永耳庵・松下幸之助」 5月29日(日)まで
この春は初代館長の故・湯木貞一氏の生誕110周年を記念した三部に分割した展覧会。
ワタシが見に行ったのは5月8日だったので、第2期で交友関係がテーマ。
まず、1901年生まれだったことに反応。
同い年には昭和天皇、安宅英一氏(安宅産業の会長)、青山二郎氏(美術評論家)といった面々がいらっしゃる。
ワタシの2人の祖父も同年生まれだけに、ちょっと感心がある。
大正時代末期に青春時代、昭和初期のいい時代を生き、40代前半で太平洋戦争、40代後半からの終戦後を生き抜いた…
という激動の20世紀を生きた世代で、すごいなぁと思う。
時代背景を考えながら鑑賞できたので、面白かった。
のっけから小林逸翁のお手紙。←表装されて掛け軸になっているところがスゴイ。
「お茶事に招かれたので、自動車を手配して行く満々だったけど、ドクターストップが 」
」
という内容で、タイトルも「茶事欠礼の文」。
言い訳以外の何物でもない情けない内容を掛け軸にしているところが微笑ましい。
その前に唐物肩衝茶入「富士山」。
大好きなのに、なかなか会えなくて、前回やっと巡り会えた
こんなにすぐ再会できなんて、ウレシイ
他は立花大亀老師、吉田茂元首相、松下幸之助氏の合筆による色紙が見応えあった。
(「無」を中心に「無心」「無為」「無策」)
高畑誠一・出光佐三合筆の色紙。「吉兆はお茶と料理で天下一」。
いつ、どういう状況で書かれたのかなぁ
御所丸茶碗「由貴」は松永耳庵による追銘だとか。
利休所持と伝わる古銅のソロリ花入はとってもスマート。乾家伝来とのこと。
継ぎだらけの赤楽は長次郎作「再来」、鈴木大拙筆の色紙「無事」もいい感じ。
変わったところではスエーデンの陶器。
北大路魯山人は「やっぱり」という印象。
ひっそりと濱本宗俊業躰より到来と説明書きがある赤楽茶碗「寒牡丹」。
(同い年だということに、これもオドロキ)
昭和ノスタルジイが感じられる茶の湯展。
鑑賞の後は昭和レトロ気分のビルの中で、ベトナム料理



にほんブログ村
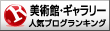 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
応援ヨロシク 致しマス
致しマス
★参考~過去の湯木美術館訪問
2010.9月 『上方豪商の茶』
2010年5月 『釜と水指』
2010年3月 『茶の裂地』
2009年11月 『棗と茶杓』
2009年5月 『千家十職-茶道具と懐石の器』
2008年10月 『茶道具と器にみる四季の花』
2008年3月 『茶碗を愉しむ』
2007年11月 『風流と美』
※二期:「数寄者との交流 - 小林逸翁・松永耳庵・松下幸之助」 5月29日(日)まで
この春は初代館長の故・湯木貞一氏の生誕110周年を記念した三部に分割した展覧会。
ワタシが見に行ったのは5月8日だったので、第2期で交友関係がテーマ。
まず、1901年生まれだったことに反応。
同い年には昭和天皇、安宅英一氏(安宅産業の会長)、青山二郎氏(美術評論家)といった面々がいらっしゃる。
ワタシの2人の祖父も同年生まれだけに、ちょっと感心がある。
大正時代末期に青春時代、昭和初期のいい時代を生き、40代前半で太平洋戦争、40代後半からの終戦後を生き抜いた…
という激動の20世紀を生きた世代で、すごいなぁと思う。
時代背景を考えながら鑑賞できたので、面白かった。
のっけから小林逸翁のお手紙。←表装されて掛け軸になっているところがスゴイ。
「お茶事に招かれたので、自動車を手配して行く満々だったけど、ドクターストップが
 」
」という内容で、タイトルも「茶事欠礼の文」。
言い訳以外の何物でもない情けない内容を掛け軸にしているところが微笑ましい。
その前に唐物肩衝茶入「富士山」。
大好きなのに、なかなか会えなくて、前回やっと巡り会えた

こんなにすぐ再会できなんて、ウレシイ

他は立花大亀老師、吉田茂元首相、松下幸之助氏の合筆による色紙が見応えあった。
(「無」を中心に「無心」「無為」「無策」)
高畑誠一・出光佐三合筆の色紙。「吉兆はお茶と料理で天下一」。
いつ、どういう状況で書かれたのかなぁ

御所丸茶碗「由貴」は松永耳庵による追銘だとか。
利休所持と伝わる古銅のソロリ花入はとってもスマート。乾家伝来とのこと。
継ぎだらけの赤楽は長次郎作「再来」、鈴木大拙筆の色紙「無事」もいい感じ。
変わったところではスエーデンの陶器。
北大路魯山人は「やっぱり」という印象。
ひっそりと濱本宗俊業躰より到来と説明書きがある赤楽茶碗「寒牡丹」。
(同い年だということに、これもオドロキ)
昭和ノスタルジイが感じられる茶の湯展。
鑑賞の後は昭和レトロ気分のビルの中で、ベトナム料理



にほんブログ村
応援ヨロシク
 致しマス
致しマス
★参考~過去の湯木美術館訪問
2010.9月 『上方豪商の茶』
2010年5月 『釜と水指』
2010年3月 『茶の裂地』
2009年11月 『棗と茶杓』
2009年5月 『千家十職-茶道具と懐石の器』
2008年10月 『茶道具と器にみる四季の花』
2008年3月 『茶碗を愉しむ』
2007年11月 『風流と美』


























