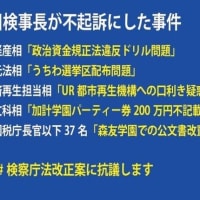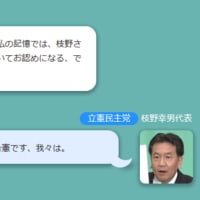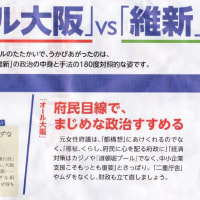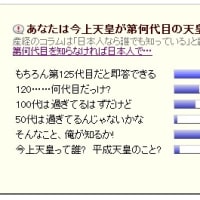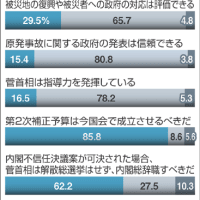(承前)
著者の近衛文麿批判はさらに続く。よほど腹に据えかねるものがあるのだろう。
そして、その舌鋒は海軍にも向かう。
以上、東京裁判の副弁護人を務め、「東京裁判をさばく」はずの本書の文中に見られる、戦前・戦中期の軍や指導者への批判のうち印象的なものをいくつか挙げてみた。
こういった箇所があるからといって、本書全体のトーンがそうした批判で貫かれているわけではもちろんない。主題はあくまで東京裁判批判である。ただその中で、こういった戦前・戦中期の軍や指導者への批判が多々述べられていることに私は驚きを禁じ得なかった。
なお、私は著者によるこれらの批判に、全面的に同意しているのではない。
これらの批判の中には、見方が一方的に過ぎるものもあるだろう。批判された者にはそれなりの言い分があるだろう。
また、事実関係が誤っているものもあるかもしれない。
しかし、そうした点を考慮しても、占領直後の国民の東京裁判に対するアンビバレントな心理の一例として、広く紹介する価値があると私は思った。
(続く)
著者の近衛文麿批判はさらに続く。よほど腹に据えかねるものがあるのだろう。
また公が折角終戦後まで生き永らえていたのなら、堂々と巣鴨の拘置所へ出頭すればよかった。伝記『近衛文麿』によると、公が自殺した晩、後藤隆之助氏をはじめ側近の人々は、いずれも公に法廷に立って堂々と所信を述ぶべきだ、そうして陛下をお守りしてくれと極力説いた。しかし、公は、支那事変の責任を追究してゆけば、結局統帥権の問題になる。したがって陛下の責任も出てくる。だから法廷に立って所信を述べるわけにはゆかない、と考えた。それに法廷に出れば、木戸内府や東條大将などとドロ合戦になるだろう。それも嫌だと言っていたという。しかし、そんなことはみな公が考えた理窟で、公が戦犯者として法廷に立つことを嫌って自殺を遂げたのは、拘置所で窮屈な恥多き生活をすることが死ぬよりも苦しかったからであろう。幼少の時から侍婢にかしずかれ、衣食住なに不自由のない生活を送ってきたこの■袴子〔■は糸へんに丸。がんこし。貴族の子弟〕には、肉体的な苦痛には何ひとつ堪え得なかったのである。公は吉田茂が憲兵に捕えられて投獄されたとき、僕なら絶対に行かないよというので、牛場友彦氏が、どうするのかと訊くと、「なに手はあるさ。まさか立廻りはしないから大丈夫だ。」と笑ったという。公は国内で憲兵に引張られても自殺するつもりであったので、青酸加里はその当時から用意されていたのである。公が統帥権の問題で陛下に累が及ぶと考えていたなら、何故法廷へ出て「責一身にあり」と主張しなかったのか。責一身にありという気持でおれば、木戸や東條と泥仕合をせずともすむではないか。公の遺書の末文には「其時初めて神の法廷に於て正義の判決が下されよう。」とあったというが、公はどうしてその信念を法廷で述べることができなかったのか。公が法廷に立ってくれれば、累を陛下に及ぼすまいと苦慮した東條はじめ幾人かの被告の肩の荷は、どんなに軽かったであろうか。私は証人台に立つ被告の言葉を聞きながら、幾度そう考えたか知れない。公の側近の人々はどう考えているか知らないが、私は公の死は、君を思わず、民を思わず、友を思わない利己的な死であったと思う。あんな時に死ぬくらいなら、なぜ日米交渉のときに死んでくれなかったろう、というのが、公を遠くから見ていた一般国民の声であった。われわれ武士の家に生れ、侍としての庭訓を受けた者の眼から見れば、公の死は土中から引きずり出されてその首を梟せられた信西入道藤原通憲の死に方よりも、もっともっと卑怯な死に方である。男子なすべきことをなさずして死ぬ。一身の安きを貪って自ら毒を仰ぐ。これほど卑怯なことが世にあろうか。死んでしまえばおしまいだ、そんな無責任な気持で、この人は国政をあずかっていたのであろうか。虚脱状態に陥っていた国民は終戦後の公の再出発に不快の念を懐いたが、声を大にして公の責任を問わなかったが、米国戦略爆撃調査団は厳しく公の支那事変における責任を追及した。昭和二十年十一月九日、公は調査団から出頭を命ぜられ、〔中略〕調査団は、公を支那事変から太平洋戦争に導いた最高責任者として、公に対して容赦のない質問を浴びせかけた。質問の重点は、どういう計画で戦争を始めたか、勝算はどの程度にあったかということであったが、公は戦争は統帥部でやることで、内閣総理大臣としてはあずかり知らぬことだと答えた。公は内閣と統帥部の分立はどうにもならなかったことを縷々説明したが、米人にはどうしてもそれが納得できなかった。最後に彼らは吐き出すように「それでは日本の総理大臣は何も知らない傀儡だと思っていいのか。」と質問した。公は「まあそうだ。責任のがれをするわけではないが、そういう制度だった。」と重い声で答えざるを得なかった。この戦略爆撃調査団の訊問は、自分でいい児になっていた公に決定的な打撃を与えた。公はそれから軽井沢へ行ったが、怏々として楽まず、食慾も進まなかった。十二月二日、梨本宮をはじめ平沼騏一郎、広田弘毅など五十九名に逮捕状が出、梨本宮が大きな包を抱えて入所する写真を新聞で見た公の心は重るばかりであった。この調査団によって加えられた精神的な打撃が、公が自殺を決心するに至ったもう一つの原因であったと思う。(下巻 p.167-169)
そして、その舌鋒は海軍にも向かう。
この近衛公の手記を読んで、私が最も不愉快に感ずることは、この時及川海相、岡軍務局長等が、「総理一任」とのみ言って、「戦争はやれぬ」とハッキリ言わなかったことである。「総理一任」は、いかにも合法的である。しかし、陸軍を押えて太平洋戦争を罷めさすことのできるのは、海軍だけであったのであるから、海軍は「総理一任」などと言わずに、「戦争はやれぬ」とハッキリ言うべきであった。太平洋戦争は海戦が主であるのであるから、いかに横車を押す陸軍も、海軍に戦意がないというなら、考え直さずにはいられなかったと思う。それを海軍の面子とか責任ということに囚われて、ハッキリと「戦争はやれぬ」と言わなかった海軍の首脳部は、海軍あるを知って国家あるを知らない連中の集まりであったといってよい。〔中略〕戦争中には、よく「陸軍が暴力犯なら、海軍の方は智能犯だ。」と言われたが、「総理一任」などは智能犯の最たるものである。海軍の方は、陸軍のように無茶なことはやらなかったが、蔭に廻って旨い汁を吸うことは陸軍以上であり、対立意識の強いことも陸軍以上であった。昭和十三年、私は北京から青島に旅行したが、青島の優良住宅はみな海軍の軍人が占め、陸軍の軍人はひどくそれを憤慨していた。私はその町で新聞社の社長をしていた橋川時雄氏の令弟に会ったが、同氏は海軍の軍人が新聞に陸海軍と書くのは怪しからぬ、海陸軍と書けと怒鳴り込んできて困るといっていた。一般に国民は、陸軍だけが無闇に乱暴を働いたと見ているが、海軍も同じ穴のむじなであって、海軍の将校の中には自分たちが乗っている船は、国民の膏血を絞った税金で出来ているのだということを考えた者はひとりもなかったといってよい。私は前に日米交渉の癌となった仏印進駐は、功名心にあせる陸軍の軍人だけがやったことのように書いたが、米国戦略爆撃調査団の報告によると、仏印進駐を背後から推進したのは、海軍の急進分子であったという。(下巻 p.169-171)
以上、東京裁判の副弁護人を務め、「東京裁判をさばく」はずの本書の文中に見られる、戦前・戦中期の軍や指導者への批判のうち印象的なものをいくつか挙げてみた。
こういった箇所があるからといって、本書全体のトーンがそうした批判で貫かれているわけではもちろんない。主題はあくまで東京裁判批判である。ただその中で、こういった戦前・戦中期の軍や指導者への批判が多々述べられていることに私は驚きを禁じ得なかった。
なお、私は著者によるこれらの批判に、全面的に同意しているのではない。
これらの批判の中には、見方が一方的に過ぎるものもあるだろう。批判された者にはそれなりの言い分があるだろう。
また、事実関係が誤っているものもあるかもしれない。
しかし、そうした点を考慮しても、占領直後の国民の東京裁判に対するアンビバレントな心理の一例として、広く紹介する価値があると私は思った。
(続く)