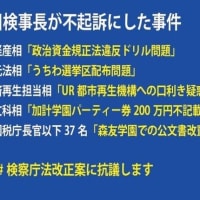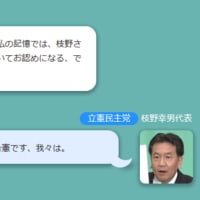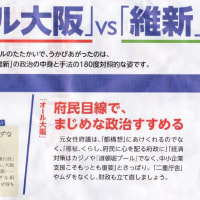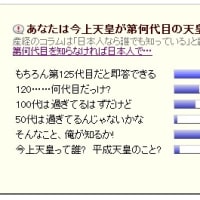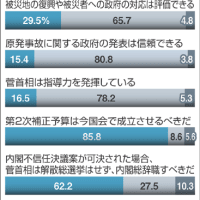(関連記事)
かつて、わが国の刑法には尊属殺人罪が設けられていた。
刑法第200条 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
現在の刑法からはこの条文は削除されている。
削除のきっかけとなったのは、1973年4月4日の最高裁大法廷判決である。この判決が、刑法第200条は憲法第14条に定める法の下の平等に反し違憲無効であるとしたため、以後政府は刑法第200条を死文化し、尊属殺についても刑法第199条の通常の殺人罪を適用するようになった。そして刑法第200条は1995年の刑法改正(口語化)に伴い削除された。
この判決は、最高裁による初の違憲判決として著名なものである。しかし井上薫『市民のための裁判入門』(PHP新書、2008)によると、井上の蛇足判決理論から見て、この判決は最高裁の越権行為による違法の産物であって、何ら判例と見なすべきものではないという。
どういうことだろうか。
「死刑又ハ無期懲役ニ処ス」といっても、情状などにより減軽される余地があるので、実際に判決で言い渡される刑罰は必ずしも死刑か無期懲役に限られていたわけではない。
しかし、減軽しても懲役3年6月が下限だった。執行猶予は懲役3年以下でないと付けられないので、実刑とせざるを得ない。この点で、通常の殺人罪に比べて尊属殺人罪は著しく不平等であるとされたわけだ。
この判決が下される前は、最高裁は刑法第200条は合憲であるとの立場をとっていた。それが一転したのは、本件事案が極めて特殊で、被告人に情状酌量の余地が多々あると判断されたからにほかならない。
井上は、こうした事情を一通り説明した上で、次のように述べる。
《しかしそれなら、本件限りの特殊な判決をすれば足りることになります。つまり、尊属殺人罪を本件のような被告人の情状が極端によいという特殊事情のある事案について適用することは、憲法の定める平等原則に違反すると判断すれば足りたのです。こう判断すれば、本件では、尊属殺人罪の適用はできなくなり、普通殺人罪の適用により懲役刑の執行猶予にできたのです。本件以外の尊属殺人事件に適用した場合とか、一般的な尊属殺人罪の合憲性などに一言も言及することなく、本件での情状に見合った妥当な判決はできたのです。
裁判の本質について改めて考えてみると、裁判は具体的紛争を対象とするものでした。だから、今担当しているその事件について法令をどう適用するかだけを決めれば、判決における判断としては十分だということになります。すると一般論を述べることは、すべて必要がないことになります。裁判における判断は、すべて本件限りの判断である必要があるのです。ここで、前に触れた必要性の原則を適用すれば、判決理由中の一般論はすべてその必要性がなく、蛇足と断定することができます。
日本国憲法が採用した前述の付随的違憲立法審査制度からしても、憲法判断は、裁判権を行使するのに必要な限度が守られるべきで、この点からも、本件最高裁大法廷の判決のした違憲判断は蛇足であるということができます。》
果たしてそうだろうか。
たしかに、井上が言うように、本件に限っては尊属殺人罪ではなく通常の殺人罪を適用すべきであるという判決を下すことも可能だろう。
しかし、それでは刑法第200条自体は有効なままとなり、その後も尊属殺人罪を適用されるケースも有り得ることになる。
刑法第200条自体が違憲であり、今後あらゆるケースで適用すべきでないと最高裁が考えたからこそ、違憲判決が下されたのだろう。
それは、井上が言うように、わが国の違憲立法審査制度から見て不適切な判断なのだろうか?
なるほど、わが国の裁判所の違憲立法審査制度は、ドイツの憲法裁判所などとは異なり、一般的、抽象的に憲法判断をするのではなく、具体的事件に即して判断する、付随的違憲立法審査制度だとされている。
しかし、井上のように、違憲判断の効力は具体的事件ただそれのみに及ぶと解するのは、違憲立法審査制度の意義を失わせるものではないだろうか。
裁判所の違憲立法審査権とは、そもそも三権分立において、司法府が立法府を抑制する役割を果たすものだ。憲法は最高法規であるから、立法府においても憲法に反しない法律を制定することは当然だが、仮に立法府が合憲であると解釈して法律を制定したとしても、司法府がそれは違憲であると判断すれば、その判断が立法府よりも優先するわけである。
その効力が具体的事件ただそれのみに及ぶと解しては、その事件以外の類似のケースにおいては、違憲判断は無意味であり、それにより不利益を被る者は、個別に訴訟で争わなければならないということになってしまう。それでは最高裁の判例など何ら実質的意味を持たないということにならないか。
違憲立法審査権は、憲法第81条の次の条文に定められているのだが、
《最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。》
この条文から、違憲判断の効力は具体的事件ただそれのみに及ぶという解釈を導き出すのも困難であるように思える。
一方井上は、次のようにも述べている。
《はっきりいって、違憲立法審査制度は、所期の機能を発揮していないのです。〔中略〕
このようなことでは、違憲立法審査制度によって人権を守ろうとする憲法体制が、次第に有名無実となってしまうのを、指をくわえてながめているしかありません。
私は、蛇足判決理論〔中略〕を駆使することで、違憲立法審査制度の機能不全という現実の打開策としようとしています。憲法訴訟の環境全体を見回してもこの理論以外に、有効な打開策はないといえましょう。》
違憲判断の一般化を違法だと断じる蛇足判決理論が、どのような打開策と成り得るというのか、理解に苦しむ。
* * * *
余談だが、井上はこの最高裁大法廷判決を「親殺し普通化判決」(p.136)と述べている。
親殺し、つまり尊属殺人罪を違憲とし、通常の殺人罪(井上はこれを「普通殺人罪」と呼ぶ)を適用すべきとした判決であるが故のネーミングなのだろうが、何やらこの判決によって、親殺しが普通に行われるようになったかのような、まがまがしい印象を与える表現ではないか。
また、被告人の情状について、次のように述べている。
《第一審判決は、刑の免除を言い渡しています。刑の免除とは、有罪だが刑は科さないものです。親を殺しながら刑を科さないという以上、よほど被告人情状がよろしかったのでしょう。控訴審判決は〔中略〕懲役三年六月の実刑を科しました。これは、尊属殺人罪の規定を適用して減軽した場合、法律上可能な最も軽い刑です。最高裁は、〔中略〕普通殺人罪を適用して、何と懲役刑の執行猶予を導きました。被告人は、最終的に刑務所に入らなくてもよいということになったのです。以上のとおり、三つの判決とも、何とかして被告人の刑を最も軽くしようとしています。被告人の情状が極端によいのでしょう。
そこで、被告人の実父殺しに至る経緯を見ると、本件の特殊性が明らかになります。〔中略・経緯の説明が続く〕
こうした本件事案の特殊性からして、最高裁の裁判官らは、被告人の情状をよく感じ取り、何とか刑務所に入れないように心を砕いたのでしょう。》
青色で表示した箇所について、先の「親殺し普通化判決」というネーミングとあいまって、冷笑的なイメージを私は受けるのだが、いかがだろうか。少なくとも、この被告人に同情的な表現を、この箇所に限らず私は本書の中から感じ取ることはできなかった。
蛇足判決理論を安易に援用する人々には、井上がこのようなメンタリティの持ち主であることも知っていただきたいものだ。
かつて、わが国の刑法には尊属殺人罪が設けられていた。
刑法第200条 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
現在の刑法からはこの条文は削除されている。
削除のきっかけとなったのは、1973年4月4日の最高裁大法廷判決である。この判決が、刑法第200条は憲法第14条に定める法の下の平等に反し違憲無効であるとしたため、以後政府は刑法第200条を死文化し、尊属殺についても刑法第199条の通常の殺人罪を適用するようになった。そして刑法第200条は1995年の刑法改正(口語化)に伴い削除された。
この判決は、最高裁による初の違憲判決として著名なものである。しかし井上薫『市民のための裁判入門』(PHP新書、2008)によると、井上の蛇足判決理論から見て、この判決は最高裁の越権行為による違法の産物であって、何ら判例と見なすべきものではないという。
どういうことだろうか。
「死刑又ハ無期懲役ニ処ス」といっても、情状などにより減軽される余地があるので、実際に判決で言い渡される刑罰は必ずしも死刑か無期懲役に限られていたわけではない。
しかし、減軽しても懲役3年6月が下限だった。執行猶予は懲役3年以下でないと付けられないので、実刑とせざるを得ない。この点で、通常の殺人罪に比べて尊属殺人罪は著しく不平等であるとされたわけだ。
この判決が下される前は、最高裁は刑法第200条は合憲であるとの立場をとっていた。それが一転したのは、本件事案が極めて特殊で、被告人に情状酌量の余地が多々あると判断されたからにほかならない。
井上は、こうした事情を一通り説明した上で、次のように述べる。
《しかしそれなら、本件限りの特殊な判決をすれば足りることになります。つまり、尊属殺人罪を本件のような被告人の情状が極端によいという特殊事情のある事案について適用することは、憲法の定める平等原則に違反すると判断すれば足りたのです。こう判断すれば、本件では、尊属殺人罪の適用はできなくなり、普通殺人罪の適用により懲役刑の執行猶予にできたのです。本件以外の尊属殺人事件に適用した場合とか、一般的な尊属殺人罪の合憲性などに一言も言及することなく、本件での情状に見合った妥当な判決はできたのです。
裁判の本質について改めて考えてみると、裁判は具体的紛争を対象とするものでした。だから、今担当しているその事件について法令をどう適用するかだけを決めれば、判決における判断としては十分だということになります。すると一般論を述べることは、すべて必要がないことになります。裁判における判断は、すべて本件限りの判断である必要があるのです。ここで、前に触れた必要性の原則を適用すれば、判決理由中の一般論はすべてその必要性がなく、蛇足と断定することができます。
日本国憲法が採用した前述の付随的違憲立法審査制度からしても、憲法判断は、裁判権を行使するのに必要な限度が守られるべきで、この点からも、本件最高裁大法廷の判決のした違憲判断は蛇足であるということができます。》
果たしてそうだろうか。
たしかに、井上が言うように、本件に限っては尊属殺人罪ではなく通常の殺人罪を適用すべきであるという判決を下すことも可能だろう。
しかし、それでは刑法第200条自体は有効なままとなり、その後も尊属殺人罪を適用されるケースも有り得ることになる。
刑法第200条自体が違憲であり、今後あらゆるケースで適用すべきでないと最高裁が考えたからこそ、違憲判決が下されたのだろう。
それは、井上が言うように、わが国の違憲立法審査制度から見て不適切な判断なのだろうか?
なるほど、わが国の裁判所の違憲立法審査制度は、ドイツの憲法裁判所などとは異なり、一般的、抽象的に憲法判断をするのではなく、具体的事件に即して判断する、付随的違憲立法審査制度だとされている。
しかし、井上のように、違憲判断の効力は具体的事件ただそれのみに及ぶと解するのは、違憲立法審査制度の意義を失わせるものではないだろうか。
裁判所の違憲立法審査権とは、そもそも三権分立において、司法府が立法府を抑制する役割を果たすものだ。憲法は最高法規であるから、立法府においても憲法に反しない法律を制定することは当然だが、仮に立法府が合憲であると解釈して法律を制定したとしても、司法府がそれは違憲であると判断すれば、その判断が立法府よりも優先するわけである。
その効力が具体的事件ただそれのみに及ぶと解しては、その事件以外の類似のケースにおいては、違憲判断は無意味であり、それにより不利益を被る者は、個別に訴訟で争わなければならないということになってしまう。それでは最高裁の判例など何ら実質的意味を持たないということにならないか。
違憲立法審査権は、憲法第81条の次の条文に定められているのだが、
《最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。》
この条文から、違憲判断の効力は具体的事件ただそれのみに及ぶという解釈を導き出すのも困難であるように思える。
一方井上は、次のようにも述べている。
《はっきりいって、違憲立法審査制度は、所期の機能を発揮していないのです。〔中略〕
このようなことでは、違憲立法審査制度によって人権を守ろうとする憲法体制が、次第に有名無実となってしまうのを、指をくわえてながめているしかありません。
私は、蛇足判決理論〔中略〕を駆使することで、違憲立法審査制度の機能不全という現実の打開策としようとしています。憲法訴訟の環境全体を見回してもこの理論以外に、有効な打開策はないといえましょう。》
違憲判断の一般化を違法だと断じる蛇足判決理論が、どのような打開策と成り得るというのか、理解に苦しむ。
* * * *
余談だが、井上はこの最高裁大法廷判決を「親殺し普通化判決」(p.136)と述べている。
親殺し、つまり尊属殺人罪を違憲とし、通常の殺人罪(井上はこれを「普通殺人罪」と呼ぶ)を適用すべきとした判決であるが故のネーミングなのだろうが、何やらこの判決によって、親殺しが普通に行われるようになったかのような、まがまがしい印象を与える表現ではないか。
また、被告人の情状について、次のように述べている。
《第一審判決は、刑の免除を言い渡しています。刑の免除とは、有罪だが刑は科さないものです。親を殺しながら刑を科さないという以上、よほど被告人情状がよろしかったのでしょう。控訴審判決は〔中略〕懲役三年六月の実刑を科しました。これは、尊属殺人罪の規定を適用して減軽した場合、法律上可能な最も軽い刑です。最高裁は、〔中略〕普通殺人罪を適用して、何と懲役刑の執行猶予を導きました。被告人は、最終的に刑務所に入らなくてもよいということになったのです。以上のとおり、三つの判決とも、何とかして被告人の刑を最も軽くしようとしています。被告人の情状が極端によいのでしょう。
そこで、被告人の実父殺しに至る経緯を見ると、本件の特殊性が明らかになります。〔中略・経緯の説明が続く〕
こうした本件事案の特殊性からして、最高裁の裁判官らは、被告人の情状をよく感じ取り、何とか刑務所に入れないように心を砕いたのでしょう。》
青色で表示した箇所について、先の「親殺し普通化判決」というネーミングとあいまって、冷笑的なイメージを私は受けるのだが、いかがだろうか。少なくとも、この被告人に同情的な表現を、この箇所に限らず私は本書の中から感じ取ることはできなかった。
蛇足判決理論を安易に援用する人々には、井上がこのようなメンタリティの持ち主であることも知っていただきたいものだ。