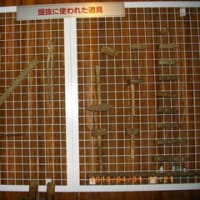前回(昨日)は、礫川全次編『在野学の冒険』(批評社 二〇一六)収録の一篇、芹沢俊介「思想としての在野学」を紹介しました。今回はその後半です。前半(昨日)は芹沢氏が「在野学の先駆」と位置づけた民間学の定義をめぐって、芹沢氏から見た鶴見俊輔の議論を紹介しました。それによれば、民間学とは「親問題」(「自分にとっての問題」)の取り戻しのことで、この「取りもどし」のためには「学びほぐし」が必要なことが語られていました。私はこの「学びほぐし」こそ、<自分化>の前提になるものだと考えていますが、芹沢氏によれば(「自分にとっての問題」の)「取りもどし」はまた「反逆のダイナミズム」を含み、氏の考える「思想としての在野学」に引き継ぎたいと書いていました。「反逆のダイナミズム」を含む「在野学」とはどのようなものなのでしょうか。その核心に迫りたい。
●外在的であって同時に内在的な問題
では、私にとっての最初の「親問題」とはなんであったか。一言でいえば、家族であった。もう少し具体的に記すと、同居する家族の中の老いであった。二十代後半の私の生存の不安の大きな部分はここにあったのである。/なぜ家族の中の老いという問題に私が遭遇したかについて簡単に述べてみたい。それには、時間の針を五十年ばかり過去へと巻き戻さなくてはならない。/批評というジャンルで物を書き始めたのは、一九六〇年代末である。その頃の私は、自分が老いることなど想像もしていなかった。それどころか、目の前の一寸先が光なのか闇なのかもわからなかった。「いま・ここ」にいることだけでせいいっぱいであった。当然と言えば、当然かもしれない。一九四二年生まれの私は、若さの真っ只中にいたのであるから。/したがって、老いの問題は、自分が老いを生きて体験しているわけではないという点では、明らかに私(という自我)にとって外在的な問題にすぎなかった。研究対象としては成立しても、これだけでは批評の主題にはならない。批評において「親問題」になるということは、外在的な問題が同時に内在的な問題でもあるという二重化状態が生まれなければならない。それが「自分の問題を探し当てる」ということの意味だからだ。
私は、若さの真っ只中にいた。その一方で、当時、老いは実生活面における私の最大と言ってもいいくらい気がかりの一つであった。私には、帰る故郷や頼るべき身寄りをもたない祖母(継祖母)がいたからである。徐々に述べるが、目の前に老いたいのちがあり、その寄る辺のないいのちにすがるようにされながら、何一つ応えられずにいる自分の無力さに、恐怖に近い絶望感を覚えていたのである。反面、すがられることのうっとうしさをもあった。自分にのしかかっている対象化不能な問題という意味では、老いは十分に内在的な主題であったのである。/老いは、私という自我にとって、外在的であって同時に内在的な問題でもあるという二重性として登場していたのである。言葉がこうした二重性を蝕知することができるなら、批評は、あるいは思想は、ここに立ち上がるかもしれない。/基本条件は満たせた、これで書いていける、と思ったのだ。私は躊躇なく、老いの問題を主題にしたのだった。(前掲書 八三~四頁)
この文章はまだ先があるのですが、長いのでここまでとせざるを得ません。そこにはもっと具体的に書いてあります。さて、引用から私が受け取れることの一つは、なんらかの外在的な問題に対するとき、それが既に、というか外在的な問題への気づきが同時に自分にとって切実な問題になってしまっていることがある、ということです。俗な言い方をすれば、人はそれぞれの境遇において逃げられない問題を抱えてしまっているわけです。宿命的な問題の存在です。これは自分をふりかえってみた場合いくつもあった気がしますが、年を重ねるにつれていつのまにか一つに収斂していることに心づきます。もしかしたら、これは例外的なケースではなく、人はいくつもあった切実な問題を、結局は一つの道を選んで「自分にとっての問題」としてを考えて行くしかないことを示唆しているように思えます。「考える」ということはそういうことなのだ、という感慨が自分にもやってきたことを想います。(この一つを追究したいと思ったら少し元気になりました)
二つめは、芹沢氏は外在的な問題は対象化されたもの、内在的な問題は対象化不能なものとしてその二重化状態を言葉で蝕知することが批評(知的営為)のはじまりだと述べていますが、この点に関して、です。この指摘は「在野学」の核心に触れているのではないかと考えます。というのは、まず「雑学」を興味・関心の渦中にあること、いってみれば「対象化不能」という内在的問題の範囲にとどまっている段階と見なせば、「独学」を外在的問題と内在的問題という二重性の高度に発展した段階と想定することができます。つまりこの二重性(両義性)が雑学段階と独学段階を架橋する中間的な性格を持っているということなのです。とすれば、私が「方法としての<自分化>」で表現しようとした段階の、その構造を意味していると考えられます。図式化すれば、
方法としての<自分化>の構造 = 外在的問題と内在的問題の二重性
というふうにです。こうみてくると、「自分にとっての問題」を探し出すことは批評への道であり、独学に至る道の一本を開示してくれているということが分かります。
三つめは、雑学から独学へと媒介する「方法としての<自分化>」は、普遍化つまり「のぼる」過程を意味していますが、独学から雑学への具体化つまり「おりる」道も示唆しているのではないか、もっと簡単にいえば、この方法は「のぼる」だけでなく「おりる」ことをも媒介していると思えるのです。たとえば今日視聴した朝ドラ『とと姉ちゃん』の話です。主人公常子の出版社が、電化製品トースターの「商品試験」の結果を雑誌で発表したら、粗悪な製品を作っていた小さな工場を窮地に追い込んでしまいます。常子がこのことに悩む場面がありました。ここをどう解決するか興味をもって視聴しました。「商品試験」という雑誌の企画を、「のぼる」過程としてみれば、高度成長期において量産されてくると粗製濫造が生まれ、電化製品の質が問題になってきます。そして、このような外在的な問題に対して、消費者の安心安全な暮らしのお手伝いをしたいという「常子にとっての問題」(内在的問題)が干与することによって、外在的な「商品試験」という問題は精度の高度化や消費者の支持が広範化する、つまり高次化・普遍化する過程としてとらえ直すことができます。
ところが「商品試験」の高次化・普遍化は、さきに述べたような問題を呼び寄せてしまいます。編集長の花山の中では、市場で勝ち抜くには企業側の努力はあたり前ですから、小さな工場主の訴えなどただ退けるだけです。ところが常子は今後どう対処すべきかで悩むのです。この悩みの解決は、生産者の小さな工場がどうすればいいかにかかっています。これが「おりる」過程です。常子にとっての問題は「安心安全な暮らしのお手伝い」でした。ここには消費者への確かな情報提供ばかりでなく、じつは生産者側への改善の願いが含まれています。常子はかつての恋人・星野が語る息子の火傷のあとのエピソードを聞いて、この願いを思い起こすのです。ここに、「おりる」過程における「常子にとっての問題」の価値があります。そしてその小さな工場に出かけてゆき、訴えていきます。工場主は反論するものの、大手の製造するトースターでも欠陥のない製品はいまだ日本には出現していないことを常子から聴き、小さい工場が生き残る方法は製品を安くするしかないと考えていた自分を反省します。そして欠陥のない製品を作ることを決意するという話でした。工場主をみる常子の視線が、雑誌の反響に喜んでいた頃とずいぶんちがいます。「のぼる」だけではまだ半分なんですね。「おりる」過程があって初めて全体が見えるのです。
私たちはこのような「のぼり・おり」を暮らしの多様な局面で経験しているのではないでしょうか。その鍵が方法としての<自分化>にあるのではないか、こう思うのです。やはり、この感想はもう一回必要なようです。