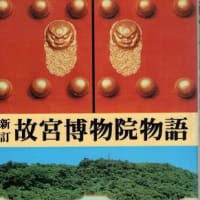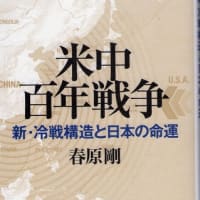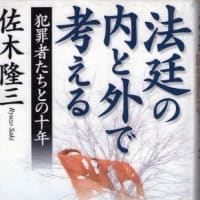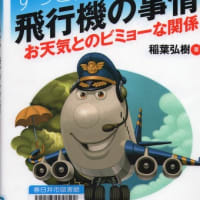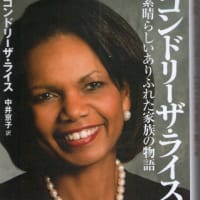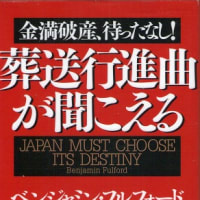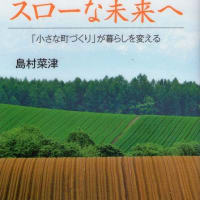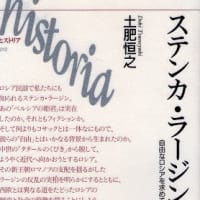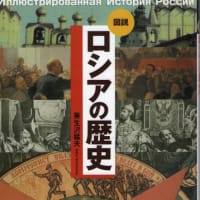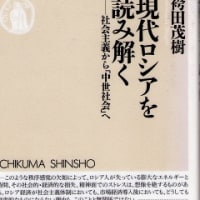例によって図書館から借りてきた本で「みなしご『菊と刀』の嘆き」という本を読んだ。
サブタイトルには「学会の巨頭たちが犯した大過」となっている。
要するにルース・べネジェクト女史の「菊と刀」に対する日本の学者、名を挙げれば柳田國男、和辻哲夫、津田左右吉、南博、川島武宜、有賀喜左衛門という日本の文化人類学の草々たる人物が、この本を評価しなかったことは、彼らがバカだったということを言っている。
確かにそれはそうだと思う。
この本の真意が見抜けなかったという点では、彼らの目は節穴で、彼らの学識経験は一体何であったのかということは言える。
だがしかし、この「菊と刀」の著述の本旨は、日本人をマスとして、人の集団として、大衆という人の群れとして、物事をどういう風に考え、どういう風に対処するか、を掘り下げることが本意であり、そこを究明することが彼女の研究対象であった。
その事から推し量ると、日本の高名な文化人類学者もべネジェクト女史に掛かると、実験材料のモルモットに過ぎなかったということである。
現実には、彼女はこの本の出版の2年後には没しているので、彼らが試されたということはないが、彼らの反応を彼女が見れば鼻でセセラ笑っているかもしれない。
本人達は、自分がモルモットと見做されているなどとは露ほども思っていないに違いないが、こういう日本人の思考がべネジェクト女史の研究対象であったわけだ。
彼女は、「日本人はどういうモノの考え方をするのか」を研究テーマにしていたわけで、その延長線上に、日本の文化人類学者は、こういうモノの見方をする、という一つの典型的な事例でもあったわけだ。
私自身は、この「菊と刀」を随分と若い時に読んで、大きな衝撃を受けた。
この本で俎上に載せられた6人の日本の著名な文化人類学者達は、この本を読んでも、そういう衝撃を感じずに、ある意味で見下げた評価を成しているので、この本でもって反駁を食っているわけだが、私は大きな衝撃を受けた。
私の受けた衝撃は、日本人の恥部をアメリカ人女性に暴かれた、という羞恥心に近いものであった。
そもそもアメリカ軍が対日戦という戦略の為にアメリカ人の女性にこういう研究をさせる、というところから驚天動地の驚きを感じた。
軍からそういう要請を受けたべネジェクト女史が、日本という敵国に一歩も足を踏み入れることもなく、たまたま接見できる日本人捕虜に対する面接から、こういう学術的見識を導き出したという実績に大いに驚いたものである。
そもそも、軍が文化人類学者に敵国の民族性、民俗性を研究させるということ、その研究者は女性でも構わない、という発想そのものが私にとっては驚きの対象であった。
50年前の日本でそういうことが考えられるであろうか。
戦時中の日本で、軍部が大学に対して「朝鮮人や、台湾人の民俗性を研究せよ」ということが有りうるであろうか。
我々の方は、対米戦が始まると、英語は「敵性用語だから使うな、禁止だ」という措置をとったわけで、この発想の相異を、ここで俎上に上げられた日本の学者たちはどういう思いで見ていたのであろう。
あの「菊と刀」という本は、基本的には日本人向けに書かれたものではなく、アメリカの軍部向け、アメリカの対日政策担当者向けに書かれたわけで、ある意味で学術論文ではないかもしれないが、内容的には完全に学術論文である。
学術論文であるから一般大衆向けの記述ではないかもしれないが、あれを読んだ日本人で、衝撃を受けない人は、やはり空きメクラに近い知性の持ち主と言わざるを得ない。
この本で俎上に上げられた人たちは、もともとが文化人類学の専門家であるものだから、そういう人たちが毛唐の女に自分よりも優れた研究を先に発表されたので、その腹いせに酷評をしたということだと思う。
ただ日本で学者というと、どうしても「象牙の塔」にたてこもって、世間とは没交渉のまま、タコつぼに入り込んで「葦の髄から天を覗いている」からこういう陳腐な評価をしがちになるものと思う。
そもそも我々とアメリカ人は、発想の原点のところから物事の捉え方が違っている事を考えなければならない。
それがお互いに戦争ということになれば、当然のこと、相手の国情を探り、軍の配備を探り、情報収集をし、集めた情報を分析して、勝てるという見積もりを得て始めて開戦ということになるわけで、我々の側はそういう手順を踏んだであろうか。
ルース・べネジェクト女史が軍の依頼を受けて日本人の民族性の本質を突きとめようとしたのは、アメリカの戦略を最も効果的に行うにはどういう手法が一番ベターか、ということを探るためであったわけで、いわば戦争に勝つための手法を探る行為であったわけだ。
戦時中、我々の側も「東京ローズ」という魅惑的な女性の声で、アメリカ将兵の戦意を籠絡するPR作戦をしたが、アメリカ人の戦意、敢闘精神がどこから来るものか、という考え方はなかったように思う。
アメリカ人男性は一般的に女性に優しい態度をするものだから、彼らの敢闘精神は軟弱に違いない、と勝手に思い込む愚はあちらこちらに散見出来た。
アメリカ人男性がレディ―・ファーストで、女性をやさしく扱うのを見て、「アメリカの兵隊は軟弱だ」と早合点する愚昧な思考は一体どこからきたのであろう。
戦前、戦中の日本人の思考は、教養や学歴の有る無しに関わらずこの程度の認識であったわけだ。
これと同じように、日本の大学者の愚は、そもそも発想の段階からアメリカ人を見下し、西洋人の知性というものを軽んじていたということだと思う。
こういう人に掛かると、発想の段階から日米の間には大きな格差がある、という認識には至らない。
例えば西部劇。
駅馬車や幌馬車がインデアンに追われていて、そこに騎兵隊のラッパの音がなり渡ると、観客が一緒になって手を叩いて喜ぶなどということは如何にもミ―ハ―的な感情として軽蔑に値するであろうが、こういうシーンにも作る側の無意識の潜在意識が入り込んでいて、文化というモノはそういうもので成り立っているという考察は、こういう大学者には受け入れないと思う。
これと同じことをべネジェクトは言っているわけで、それは日本映画から考察であるが、日本の大学者にはミ―ハ―的な映画から学術的な思考をひねり出すなどという研究態度は、受け入れ難いことであったに違いない。
極めてミ―ハ―的な西部劇やチャンバラ映画から文化を考察するなどということは、日本の大学者からすれば想定外の学究態度であって、許しがたい行為に思えたに違いない。
しかし、極めてミ―ハ―的な西部劇やチャンバラ映画からでも、その地に住む人々の無意識の文化というモノはきちんと洞察できるわけで、そこまで思考が至らなかったという点では、日本の文化人類学の完全なる敗北である。
西部劇を見て、日本の時代劇を見て、馬の鞍を見比べて、そこに文化の相異を感じない人は、明らかに文化的に感性の乏しい鈍感な人と言わなければならない。
西部劇の馬の鞍は如何にも実用一点張りであるが、日本の時代劇で殿様の乗る馬の鞍は、漆細工の如何にも絢爛豪華な出来栄えであることに気が付かない人は、やはりバカに近い人と言わざるを得ない。
映画を作っている人はいちいちそんなことを考えているわけではなく、無意識のうちにそういう場面を映しているが、だからこそそこに民族の潜在的な文化の相異が現れるのである。
「菊と刀」の本質を見落とした日本の文化人類学者は、この無意識の潜在意識が民俗の固有の文化だ、ということに気が付かなかったわけだ。
目に見えるものだけが文化だ、と思い込んで今まで来たけれども、べネジェクト女史は、目に見えないものの中に文化を見出したわけで、その事に気が付かなかった彼らの屈辱感が、この本の評価として現れたに違いない。
今、世の中はグローバル化ということで、人もモノもカネも、国境を越えて自由に行き来できるようになったが、物事の発想の相異というのは、そうそう安易に埋められるものではなさそうだ。
日本に来て、日本で活躍して有名になる人も大勢いるが、当然その逆もあるに違いないが、この方はあまり我々の目に触れない。
無理もない話で、我々の周りで有名になるということは、我々の感性にぴったりと合う要因が無い事には、我々の話題には上らないわけで、この我々の感性にぴったりと適合するという部分に、モノの考え方の根本的な相異があるからである。
その良い例がこの本の登場で、軍が文化人類学者に、占領政策の下敷きにするために敵国の人間の民族性を研究をさせるというアイデアが、我々の側にありえるであろうか。
戦前において、我々は台湾と朝鮮、はたまた満州という国を統治したが、その時に相手国の国情を大学の先生方に委託研究させたであろうか。
こういう発想は、我々は逆立ちしても内側の発想としては湧き出てこないと思う。
この発想の相異という面では、あの戦争の総括も、我々の内側からは出てこないというのと軌を一にしていると考えられる。
この本で述べられているように、日本の著名な学者が、この「菊と刀」を正当に評価しなかったということは、やはり我々日本人の国民性として、自分のタコつぼから出て広い公平な視点でモノを見るという器量に欠けていて、自分が「葦の髄から天を見ている」ことに慣れ切ってしまっているということである。
学者先生もいわば官僚の一員なわけで、戦時中の軍人は階級で自己の位置が保障されていたが、学者も学会の権威という衣で包まれている限り、身分が保障されているようなものなので、毛唐の女に自分でもなし得なかったような実績を誇示されると、非常な恐怖感にさいなまれたのかもしれない。
私に言わしめれば、文化人類学などという学問は、人間の驕り以外の何ものでもないと思う。
人間の驕りというよりも、学者諸氏の驕りだと思う。
地球上の人々は、如何なる民族でも個人一人では生きられないわけで、群れを作って社会という組織を構成して始めて部族、民族を形作っている。
それぞれの民族や部族は、それぞれ自分の置かれた環境に順応して生きているわけで、文化的な先進国でも未開な土人でも、それらの間に人間の価値の相異はないはずであって、ただあるのは生き方の選択のみである。
人々が知識を潤沢に得れば、生き方の選択肢の幅は広くなり多くなるが、それが良い事か悪い事かは、個人の考え方によるわけで、知識を沢山得たものが未開の人たちの生活ぶりを曝け出し炙り出して、それを学問などということは、まさしくたまたま知識を得ることに恵まれた人の傲慢な思考そのものだと思う。
貧乏長屋の向こう三軒両となりの人々が、如何なる生活しているかを逐一報告しているようなもので、こんな事柄が何で学問などと言えるのだ。
そこには自分の研究対象に対する蔑視的な視線は、避けようがなくあるものと思われる。
日本の文化人類学者は、全てが未開な人々の研究をすることで、それを生業としているが、それは明らかに対象物に対して自分が恵まれた位置にいる事を誇示している姿だと思う。
そういう認識からすると、ルース・ベネジェクトが未開人ではない、日本民族を文化人類学的に考察するという意味は、彼らの想定外の研究姿勢なわけで、自分達は無知蒙昧な土人達を研究対象としていたのに、先進国の人間を文化人類学の研究対象にしたという意味でも、彼女の実績を認めたくなかったに違ない。
日本人の中で、恥の概念を掘り下げた日本人研究者はいないわけで、この誰もまだしたことのことに挑戦するというのは、明らかに研究者としては魅力的なことであったに違いない。
我々は今アメリカとは強い絆で結ばれているが、この絆は今後もしっかりと維持しなければいけない。
それは隷属するという意味ではないが、我々は往々にして言葉狩りに嵌り込んで、危機に陥りがちである。
「絆を大事にする」と言うと、直ちに隷属というイメージが湧きたつというのも、言葉狩りの一種であろう。
国と国の関係は、正義とか善悪とか正邪という価値観で機能しているのではなく、あくまでも国益最優先で機能しているので、この部分で甘くて当たり障りなく、きれいな言葉に幻惑されたり、言葉狩りで国益を損なったりすることのないように注意が肝要である。
こういう場合でも、我々の側の本当に優れた教養・知性の持ち主であるべき学識経験者たちは、物事の本質に無頓着であってはならず、「井戸の中の蛙」や「葦の髄から天を覗く」ような思考であってはならない事は言うまでもない。
知識人の責任として、無知蒙昧な大衆をリードしてやろうという意欲は持って当然であるが、真贋を見定める鑑識眼も大いに養わねばならない。
権威に安住するというのでは、昔の関東軍の高級将校、高級参謀とすることなすことが全く同じだということになる。
同じ官僚という点からすると、この基底、深層心理の部分で、学者と旧軍の高級将校とは相通じるものがあるやに見える。
すなわち、身の保身のために、もの事のプリンシプルを投げ捨て、言うべき事を言うべきタイミングで言わないという傾向があるように見受けられる。
サブタイトルには「学会の巨頭たちが犯した大過」となっている。
要するにルース・べネジェクト女史の「菊と刀」に対する日本の学者、名を挙げれば柳田國男、和辻哲夫、津田左右吉、南博、川島武宜、有賀喜左衛門という日本の文化人類学の草々たる人物が、この本を評価しなかったことは、彼らがバカだったということを言っている。
確かにそれはそうだと思う。
この本の真意が見抜けなかったという点では、彼らの目は節穴で、彼らの学識経験は一体何であったのかということは言える。
だがしかし、この「菊と刀」の著述の本旨は、日本人をマスとして、人の集団として、大衆という人の群れとして、物事をどういう風に考え、どういう風に対処するか、を掘り下げることが本意であり、そこを究明することが彼女の研究対象であった。
その事から推し量ると、日本の高名な文化人類学者もべネジェクト女史に掛かると、実験材料のモルモットに過ぎなかったということである。
現実には、彼女はこの本の出版の2年後には没しているので、彼らが試されたということはないが、彼らの反応を彼女が見れば鼻でセセラ笑っているかもしれない。
本人達は、自分がモルモットと見做されているなどとは露ほども思っていないに違いないが、こういう日本人の思考がべネジェクト女史の研究対象であったわけだ。
彼女は、「日本人はどういうモノの考え方をするのか」を研究テーマにしていたわけで、その延長線上に、日本の文化人類学者は、こういうモノの見方をする、という一つの典型的な事例でもあったわけだ。
私自身は、この「菊と刀」を随分と若い時に読んで、大きな衝撃を受けた。
この本で俎上に載せられた6人の日本の著名な文化人類学者達は、この本を読んでも、そういう衝撃を感じずに、ある意味で見下げた評価を成しているので、この本でもって反駁を食っているわけだが、私は大きな衝撃を受けた。
私の受けた衝撃は、日本人の恥部をアメリカ人女性に暴かれた、という羞恥心に近いものであった。
そもそもアメリカ軍が対日戦という戦略の為にアメリカ人の女性にこういう研究をさせる、というところから驚天動地の驚きを感じた。
軍からそういう要請を受けたべネジェクト女史が、日本という敵国に一歩も足を踏み入れることもなく、たまたま接見できる日本人捕虜に対する面接から、こういう学術的見識を導き出したという実績に大いに驚いたものである。
そもそも、軍が文化人類学者に敵国の民族性、民俗性を研究させるということ、その研究者は女性でも構わない、という発想そのものが私にとっては驚きの対象であった。
50年前の日本でそういうことが考えられるであろうか。
戦時中の日本で、軍部が大学に対して「朝鮮人や、台湾人の民俗性を研究せよ」ということが有りうるであろうか。
我々の方は、対米戦が始まると、英語は「敵性用語だから使うな、禁止だ」という措置をとったわけで、この発想の相異を、ここで俎上に上げられた日本の学者たちはどういう思いで見ていたのであろう。
あの「菊と刀」という本は、基本的には日本人向けに書かれたものではなく、アメリカの軍部向け、アメリカの対日政策担当者向けに書かれたわけで、ある意味で学術論文ではないかもしれないが、内容的には完全に学術論文である。
学術論文であるから一般大衆向けの記述ではないかもしれないが、あれを読んだ日本人で、衝撃を受けない人は、やはり空きメクラに近い知性の持ち主と言わざるを得ない。
この本で俎上に上げられた人たちは、もともとが文化人類学の専門家であるものだから、そういう人たちが毛唐の女に自分よりも優れた研究を先に発表されたので、その腹いせに酷評をしたということだと思う。
ただ日本で学者というと、どうしても「象牙の塔」にたてこもって、世間とは没交渉のまま、タコつぼに入り込んで「葦の髄から天を覗いている」からこういう陳腐な評価をしがちになるものと思う。
そもそも我々とアメリカ人は、発想の原点のところから物事の捉え方が違っている事を考えなければならない。
それがお互いに戦争ということになれば、当然のこと、相手の国情を探り、軍の配備を探り、情報収集をし、集めた情報を分析して、勝てるという見積もりを得て始めて開戦ということになるわけで、我々の側はそういう手順を踏んだであろうか。
ルース・べネジェクト女史が軍の依頼を受けて日本人の民族性の本質を突きとめようとしたのは、アメリカの戦略を最も効果的に行うにはどういう手法が一番ベターか、ということを探るためであったわけで、いわば戦争に勝つための手法を探る行為であったわけだ。
戦時中、我々の側も「東京ローズ」という魅惑的な女性の声で、アメリカ将兵の戦意を籠絡するPR作戦をしたが、アメリカ人の戦意、敢闘精神がどこから来るものか、という考え方はなかったように思う。
アメリカ人男性は一般的に女性に優しい態度をするものだから、彼らの敢闘精神は軟弱に違いない、と勝手に思い込む愚はあちらこちらに散見出来た。
アメリカ人男性がレディ―・ファーストで、女性をやさしく扱うのを見て、「アメリカの兵隊は軟弱だ」と早合点する愚昧な思考は一体どこからきたのであろう。
戦前、戦中の日本人の思考は、教養や学歴の有る無しに関わらずこの程度の認識であったわけだ。
これと同じように、日本の大学者の愚は、そもそも発想の段階からアメリカ人を見下し、西洋人の知性というものを軽んじていたということだと思う。
こういう人に掛かると、発想の段階から日米の間には大きな格差がある、という認識には至らない。
例えば西部劇。
駅馬車や幌馬車がインデアンに追われていて、そこに騎兵隊のラッパの音がなり渡ると、観客が一緒になって手を叩いて喜ぶなどということは如何にもミ―ハ―的な感情として軽蔑に値するであろうが、こういうシーンにも作る側の無意識の潜在意識が入り込んでいて、文化というモノはそういうもので成り立っているという考察は、こういう大学者には受け入れないと思う。
これと同じことをべネジェクトは言っているわけで、それは日本映画から考察であるが、日本の大学者にはミ―ハ―的な映画から学術的な思考をひねり出すなどという研究態度は、受け入れ難いことであったに違いない。
極めてミ―ハ―的な西部劇やチャンバラ映画から文化を考察するなどということは、日本の大学者からすれば想定外の学究態度であって、許しがたい行為に思えたに違いない。
しかし、極めてミ―ハ―的な西部劇やチャンバラ映画からでも、その地に住む人々の無意識の文化というモノはきちんと洞察できるわけで、そこまで思考が至らなかったという点では、日本の文化人類学の完全なる敗北である。
西部劇を見て、日本の時代劇を見て、馬の鞍を見比べて、そこに文化の相異を感じない人は、明らかに文化的に感性の乏しい鈍感な人と言わなければならない。
西部劇の馬の鞍は如何にも実用一点張りであるが、日本の時代劇で殿様の乗る馬の鞍は、漆細工の如何にも絢爛豪華な出来栄えであることに気が付かない人は、やはりバカに近い人と言わざるを得ない。
映画を作っている人はいちいちそんなことを考えているわけではなく、無意識のうちにそういう場面を映しているが、だからこそそこに民族の潜在的な文化の相異が現れるのである。
「菊と刀」の本質を見落とした日本の文化人類学者は、この無意識の潜在意識が民俗の固有の文化だ、ということに気が付かなかったわけだ。
目に見えるものだけが文化だ、と思い込んで今まで来たけれども、べネジェクト女史は、目に見えないものの中に文化を見出したわけで、その事に気が付かなかった彼らの屈辱感が、この本の評価として現れたに違いない。
今、世の中はグローバル化ということで、人もモノもカネも、国境を越えて自由に行き来できるようになったが、物事の発想の相異というのは、そうそう安易に埋められるものではなさそうだ。
日本に来て、日本で活躍して有名になる人も大勢いるが、当然その逆もあるに違いないが、この方はあまり我々の目に触れない。
無理もない話で、我々の周りで有名になるということは、我々の感性にぴったりと合う要因が無い事には、我々の話題には上らないわけで、この我々の感性にぴったりと適合するという部分に、モノの考え方の根本的な相異があるからである。
その良い例がこの本の登場で、軍が文化人類学者に、占領政策の下敷きにするために敵国の人間の民族性を研究をさせるというアイデアが、我々の側にありえるであろうか。
戦前において、我々は台湾と朝鮮、はたまた満州という国を統治したが、その時に相手国の国情を大学の先生方に委託研究させたであろうか。
こういう発想は、我々は逆立ちしても内側の発想としては湧き出てこないと思う。
この発想の相異という面では、あの戦争の総括も、我々の内側からは出てこないというのと軌を一にしていると考えられる。
この本で述べられているように、日本の著名な学者が、この「菊と刀」を正当に評価しなかったということは、やはり我々日本人の国民性として、自分のタコつぼから出て広い公平な視点でモノを見るという器量に欠けていて、自分が「葦の髄から天を見ている」ことに慣れ切ってしまっているということである。
学者先生もいわば官僚の一員なわけで、戦時中の軍人は階級で自己の位置が保障されていたが、学者も学会の権威という衣で包まれている限り、身分が保障されているようなものなので、毛唐の女に自分でもなし得なかったような実績を誇示されると、非常な恐怖感にさいなまれたのかもしれない。
私に言わしめれば、文化人類学などという学問は、人間の驕り以外の何ものでもないと思う。
人間の驕りというよりも、学者諸氏の驕りだと思う。
地球上の人々は、如何なる民族でも個人一人では生きられないわけで、群れを作って社会という組織を構成して始めて部族、民族を形作っている。
それぞれの民族や部族は、それぞれ自分の置かれた環境に順応して生きているわけで、文化的な先進国でも未開な土人でも、それらの間に人間の価値の相異はないはずであって、ただあるのは生き方の選択のみである。
人々が知識を潤沢に得れば、生き方の選択肢の幅は広くなり多くなるが、それが良い事か悪い事かは、個人の考え方によるわけで、知識を沢山得たものが未開の人たちの生活ぶりを曝け出し炙り出して、それを学問などということは、まさしくたまたま知識を得ることに恵まれた人の傲慢な思考そのものだと思う。
貧乏長屋の向こう三軒両となりの人々が、如何なる生活しているかを逐一報告しているようなもので、こんな事柄が何で学問などと言えるのだ。
そこには自分の研究対象に対する蔑視的な視線は、避けようがなくあるものと思われる。
日本の文化人類学者は、全てが未開な人々の研究をすることで、それを生業としているが、それは明らかに対象物に対して自分が恵まれた位置にいる事を誇示している姿だと思う。
そういう認識からすると、ルース・ベネジェクトが未開人ではない、日本民族を文化人類学的に考察するという意味は、彼らの想定外の研究姿勢なわけで、自分達は無知蒙昧な土人達を研究対象としていたのに、先進国の人間を文化人類学の研究対象にしたという意味でも、彼女の実績を認めたくなかったに違ない。
日本人の中で、恥の概念を掘り下げた日本人研究者はいないわけで、この誰もまだしたことのことに挑戦するというのは、明らかに研究者としては魅力的なことであったに違いない。
我々は今アメリカとは強い絆で結ばれているが、この絆は今後もしっかりと維持しなければいけない。
それは隷属するという意味ではないが、我々は往々にして言葉狩りに嵌り込んで、危機に陥りがちである。
「絆を大事にする」と言うと、直ちに隷属というイメージが湧きたつというのも、言葉狩りの一種であろう。
国と国の関係は、正義とか善悪とか正邪という価値観で機能しているのではなく、あくまでも国益最優先で機能しているので、この部分で甘くて当たり障りなく、きれいな言葉に幻惑されたり、言葉狩りで国益を損なったりすることのないように注意が肝要である。
こういう場合でも、我々の側の本当に優れた教養・知性の持ち主であるべき学識経験者たちは、物事の本質に無頓着であってはならず、「井戸の中の蛙」や「葦の髄から天を覗く」ような思考であってはならない事は言うまでもない。
知識人の責任として、無知蒙昧な大衆をリードしてやろうという意欲は持って当然であるが、真贋を見定める鑑識眼も大いに養わねばならない。
権威に安住するというのでは、昔の関東軍の高級将校、高級参謀とすることなすことが全く同じだということになる。
同じ官僚という点からすると、この基底、深層心理の部分で、学者と旧軍の高級将校とは相通じるものがあるやに見える。
すなわち、身の保身のために、もの事のプリンシプルを投げ捨て、言うべき事を言うべきタイミングで言わないという傾向があるように見受けられる。