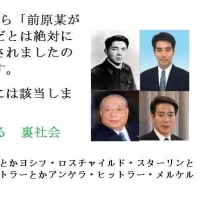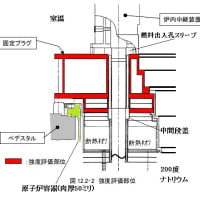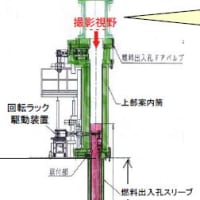My Life After MIT Sloan 様、2010-08-15 19:50:11 | ビジネス・社会論
『水ビジネスの将来を考えるオススメ本』
より転載します
<転載開始>
水ビジネスの将来を考えるオススメ本
古典的かもしれないが、今世紀にグローバルなビッグビジネスになるのは何か、と考えたとき、
世界的に供給に対して需要が圧倒的に足りなくなるものであろうと思う。
つまり1に水、2に食料、3にエネルギーではないかとやはり思うわけである。
中でも、水には個人的に以前から興味があったので、仕事で忙しい中睡眠時間を削って、先々週末から水ビジネスに関する本を何冊か読んでみた。
中でも一番、分かりやすくてとっつきやすく、日本企業が水ビジネスに関わる上で重要な課題がカバーされてるのは次の本だった。
この本を読んでから、他の専門的な書籍を読むと、短時間で格段に理解力が上がる。
対談方式が苦手でなければ、この本はお勧め。
日本人が知らない巨大市場 水ビジネスに挑む ~日本の技術が世界に飛び出す!
吉村 和就,沖 大幹
技術評論社
このアイテムの詳細を見る
~~~画像(元ぺーじをご覧下さい)~~~
簡単に読んで勉強になったところをピックアップしてご紹介しようと思う。
1) バーチャルウォーターという考え方:日本は食糧自給率が低いからこそ国内の水を使わずに済んでいるらしい
水というと、つい飲み水のことばかり考えがちだが、実は食料を作るにも大量の水が使われている。
例えば、牛を育てるには大量の芝や飼料が必要で、それには大量の水が消費される。
その結果、ハンバーガー一個を作るのに、約1000リットルの水が必要なのだそうだ。
こういう水を換算して「バーチャルウォーター」と呼ぶ。
全ての食料を作るためにはこのように水が大量に必要となるわけだ。
つまり食料自給率の低い日本は、結果としてアメリカやオーストラリア、中国から大量の水を輸入してるのと同じことになるそうだ。
同様に、工業製品を作るにも大量の水が必要だが、日本が輸出する自動車や家電製品よりも、
日本が輸入している衣料品や鉄鋼の方がはるかに多くの水を使う。
結果として、日本は作る過程で水を大量に使う食料や衣料品などを輸入しているおかげで、自国の水を使用せずに済んでいるそうだ。
食料自給率問題ってこういう視点からも眺める必要があるのね、と思った。
2) 蛇口から飲める水が全国で出るのは日本とスイスだけ。なのに水道水が安い
蛇口から直接飲める水が出る国は世界で11カ国あるという。
そのうち、全国で飲める水が出るのは、スイスと日本だけだという。
それなのに、日本の水道代の平均利用料金は、先進国の多くの国より安い方であるという。
それって、住んでる国民にとってはすばらしいことであるが、水道事業をビジネスとして考えるならとても良いこととも言い切れない。
特に日本は、今後高齢化で水の使用量が減ると言われている。
人間ってのは、水の使用量が一番多いのは若い女性で、年をとると共に使用水量って下がっていくらしい。
国全体の使用水量が減れば、収入も減る。
ところが、水道とは巨大な固定費ビジネスであり、コスト削減ってのは人の削減以外には難しい。
そうすると品質・スキルを維持しながらの効率化と水道料金の値上げが避けられなくなるだろう。
3) 日本の上下水道のインフラ保有資産は約120兆円
正直、数字の大きさに驚いた。
1700の地方自治体に分かれて運営されている、日本全国の上下水道の保有資産を全部足すと、120兆円だという。
(上水道が40兆円、下水道が80兆円)
金融機関であれば100兆円超の保有資産を持つことはあるが(たとえば郵貯は330兆円と言われた)、
インフラビジネスでこれほどの保有資産の規模は非常に珍しい。
たとえば日本中に発電所を持ち、電力線網を張り巡らせている電力会社は、
東京電力が13兆円、関西電力が6兆円、と言ったところで、全国でも40兆円程度の規模だ。
または日本中に電話網を張り巡らせているNTTの総資産は8兆円程度、ソフトバンクなど他の電話系企業と足し合わせても15兆円に届かないだろう。
JRだって全部足しても20兆円行かない規模だ。
如何に120兆円のインフラ資産が巨大なものかわかる。
仮に、日本の上下水道が全てくっついて民営化、などということになったら、そういう規模のインフラ企業が誕生することになるわけだ。
4) 世界の水ビジネス市場は2025年には100-125兆円。そのうち素材技術はたった1兆円市場しかない。
日本は水ビジネスでは、膜技術などの素材系に強い、とよく言われ、またその規模も1兆円程度まで成長などといわれているが、
そもそも水ビジネス全体で見れば、その市場規模は全体の1%に過ぎない、という驚愕の事実。
120兆円のうち9割は、それこそ世界の水メジャーのヴェオリアやスエズが得意とする運営・管理の市場なのである。
要素技術というのは、一般的には、うまくパッケージにして出したり、高いシェアで市場を独占すれば化けることも多い。
しかしそのまま裸で出しても、運営とマーケティングが巧い会社にアービトラージされてしまうことも多々ある。
具体的には、要素技術だけが優れても、それを活用して市場価値のあるものを作っていける会社は少ないから、その技術の本来の価値より安く買い叩かれてしまう。
で、買った会社は、その要素技術を他の運営管理力やマーケティング力と総合的に組み合わせて魅力的なパッケージとして、高く売りつけるってことだ。
だから、日本企業が世界の水ビジネスで生き残るためには、こういうノウハウをつけていくことが重要になっていく、という話だ。
5) 水ビジネスでも経営力より技術力にこだわり、「ガラパゴス」な日本
日本は「運営ノウハウが無い」などと言われているが、日本では料金回収や盗水に直面するなんてことが無いので、これは当たり前とも言える。
しかしながら、下水処理の浄化槽や膜技術などは世界一のものがたくさんあるという。
管理でも、先進国の都市の漏水率で20%を超えるのはざらだが、日本はたった3.1%という圧倒的な技術力。
それもあるのか、日本の水関係会社の社長さんは「他社にない優れた技術があれば一番になれる」
「人より優れた製品を持てば、受け入れられる」という人が多いんだそうだ。
なんか水ビジネスまで、ガラパゴスなのねぇ、と思った。
これじゃ、日本が現状で台湾や韓国に大負けしてる半導体などの分野と一緒になってしまうじゃない。
さっきも書いたように、要素技術っていうのは、いくら優れたものを持っていても、一部企業にしか刺さらないから、買い叩かれやすい。
運営力や他の技術と組み合わせてパッケージする力やマーケティングのうまい会社にアービトラージされやすいのだ。
だから技術だけで売れるなんて考えちゃダメ。
一方、グローバルな水メジャーは「我々には技術力なんて無いが、そんなものは後からついてくる」
と言う。
それで、実際に途上国などをはじめとする各国の水道運営・管理ビジネスに乗り出し、拡大している。
日本の水道事業の技術力が如何に上でも、結局外に出ていかないから、日本国内にとどまって終わり。
まさにガラパゴスじゃないの。
6) 途上国上下水道を受注しようにも、世界銀行の入札条件に見合わない日本の水道局
じゃあ東京都水道局とか、大きな水道事業者の一部は世界に出て行きゃいいじゃない、という人もいるだろう。
ここに大きな壁があるのであった。
水ビジネスで海外進出と言っても、既に水道事業がある先進国から運営・管理を受注するか、
途上国に新たに上下水道を作って運営・管理を行うの2通りしかない。
当然後者の方が入り込みやすい。
実際、日本は途上国に対して多額のODAを投じている。
ところが、ODAの水ビジネスには日本の水道事業は入り込めない。
なぜなら、ODAで行われる事業は世界銀行の入札基準を満たさないとならないわけだが、
水ビジネスの場合「10万トン以上の浄水場で5年以上の運営・管理を5カ国以上で行った事がある会社」とのことで、
日本の会社は一社も該当しないので、いつまでも入札に参加できないのだそうだ。
まぁ。
漸く最近、三菱商事などが中心となって、フィリピンの水道事業に進出したり、今年5月にもオーストラリアの水ビジネスの買収などが行われている。
東京都水道局などもそれに関わっている形だ。
自治体ベースでもいいので、こういう取り組みをしていかないと、世界の水ビジネスの気運に日本だけ取り残されるのは目に見えているだろう。
7) カーボン(炭素排出権)に次いで、金融業界に注目される水
金融業界は、儲かりそうなところ、アービトラージしやすいおいしいところを見つけて、すぐに金融商品に仕立てて金にしようという人たちの集まりなわけだが、環境ビジネスもそのターゲットの一つである。
つい最近も、CO2削減の手段である排出権をさっさと金融商品に仕立てる仕組みを作ったばかり。
その彼らは、今は水に注目しているのだそうだ。
具体的には、さっきの「バーチャルウォーター」の考え方に近い「ウォーターフットプリント」という考え方を導入。
一つの製品を作るのに消費する水を「ウォーターフットプリント」として、
排出権と同じように、一国が消費してよい「ウォーターフットプリント」の量を制限してしまう。
そうすると、どうしても水を使う必要がある国は、「ウォーターフットプリント」を他国から買い入れないとならなくなるので、それを証券化して取引対象とすれば儲かる、と考えているわけである。
こういう流れは良い悪いは別として、どこかが始めると避けられなくなる動きである。
排出権がそうだった。
日本がより良いものを導入しようとしても、動きが遅ければ、単に損して終わるだけである。
こういう動きも考えると、日本全体の水ビジネスへの意識を挙げていくってのは重要なのがわかる。
日本は水資源には恵まれた国だ。
だから、水ビジネスの必要性なんて殆ど考えないわけだけど、世界の潮流は違う。
そういうわけで、是非皆さんにも興味を持っていただければと思ってご推薦でした。
さらにこの本の後に読むと、知識と理解が深まる本もご紹介。
ウォーター・ビジネス――世界の水資源・水道民営化・水処理技術・ボトルウォーターをめぐる壮絶なる戦い
作品社
写真をクリックするとAmazonへ。
~~~画像(元ぺーじをご覧下さい)~~~
上の本は水ビジネスに関連する広範な話題をカバーしてるが、日本視点が中心だ。
それに対して、この本は、実際に水資源が不足し、内戦になっている地域も含め、世界中の水問題を、
深く掘り下げているので世界的な視点で非常に勉強になる。
上の本を読み終わって興味を持ったら、是非読むのをお勧め。
水ビジネスの現状と展望 水メジャーの戦略・日本としての課題
服部 聡之
丸善
写真をクリックするとAmazonへ
~~~画像(元ぺーじをご覧下さい)~~~
この本は、問題提起というよりは、歴史やケーススタディ、データが豊富で、資料集としてとても使える。
結局、詳細を理解しようとなると、数字の感覚が無いと議論できないわけで、そのあたりを補ってくれる。
←面白かったら、クリックして、応援してください!
<転載終了>
転載元 http://blog.goo.ne.jp/mit_sloan/e/cf39b05c44841099de2c43ced2fb2101
『水ビジネスの将来を考えるオススメ本』
より転載します
<転載開始>
水ビジネスの将来を考えるオススメ本
古典的かもしれないが、今世紀にグローバルなビッグビジネスになるのは何か、と考えたとき、
世界的に供給に対して需要が圧倒的に足りなくなるものであろうと思う。
つまり1に水、2に食料、3にエネルギーではないかとやはり思うわけである。
中でも、水には個人的に以前から興味があったので、仕事で忙しい中睡眠時間を削って、先々週末から水ビジネスに関する本を何冊か読んでみた。
中でも一番、分かりやすくてとっつきやすく、日本企業が水ビジネスに関わる上で重要な課題がカバーされてるのは次の本だった。
この本を読んでから、他の専門的な書籍を読むと、短時間で格段に理解力が上がる。
対談方式が苦手でなければ、この本はお勧め。
日本人が知らない巨大市場 水ビジネスに挑む ~日本の技術が世界に飛び出す!
吉村 和就,沖 大幹
技術評論社
このアイテムの詳細を見る
~~~画像(元ぺーじをご覧下さい)~~~
簡単に読んで勉強になったところをピックアップしてご紹介しようと思う。
1) バーチャルウォーターという考え方:日本は食糧自給率が低いからこそ国内の水を使わずに済んでいるらしい
水というと、つい飲み水のことばかり考えがちだが、実は食料を作るにも大量の水が使われている。
例えば、牛を育てるには大量の芝や飼料が必要で、それには大量の水が消費される。
その結果、ハンバーガー一個を作るのに、約1000リットルの水が必要なのだそうだ。
こういう水を換算して「バーチャルウォーター」と呼ぶ。
全ての食料を作るためにはこのように水が大量に必要となるわけだ。
つまり食料自給率の低い日本は、結果としてアメリカやオーストラリア、中国から大量の水を輸入してるのと同じことになるそうだ。
同様に、工業製品を作るにも大量の水が必要だが、日本が輸出する自動車や家電製品よりも、
日本が輸入している衣料品や鉄鋼の方がはるかに多くの水を使う。
結果として、日本は作る過程で水を大量に使う食料や衣料品などを輸入しているおかげで、自国の水を使用せずに済んでいるそうだ。
食料自給率問題ってこういう視点からも眺める必要があるのね、と思った。
2) 蛇口から飲める水が全国で出るのは日本とスイスだけ。なのに水道水が安い
蛇口から直接飲める水が出る国は世界で11カ国あるという。
そのうち、全国で飲める水が出るのは、スイスと日本だけだという。
それなのに、日本の水道代の平均利用料金は、先進国の多くの国より安い方であるという。
それって、住んでる国民にとってはすばらしいことであるが、水道事業をビジネスとして考えるならとても良いこととも言い切れない。
特に日本は、今後高齢化で水の使用量が減ると言われている。
人間ってのは、水の使用量が一番多いのは若い女性で、年をとると共に使用水量って下がっていくらしい。
国全体の使用水量が減れば、収入も減る。
ところが、水道とは巨大な固定費ビジネスであり、コスト削減ってのは人の削減以外には難しい。
そうすると品質・スキルを維持しながらの効率化と水道料金の値上げが避けられなくなるだろう。
3) 日本の上下水道のインフラ保有資産は約120兆円
正直、数字の大きさに驚いた。
1700の地方自治体に分かれて運営されている、日本全国の上下水道の保有資産を全部足すと、120兆円だという。
(上水道が40兆円、下水道が80兆円)
金融機関であれば100兆円超の保有資産を持つことはあるが(たとえば郵貯は330兆円と言われた)、
インフラビジネスでこれほどの保有資産の規模は非常に珍しい。
たとえば日本中に発電所を持ち、電力線網を張り巡らせている電力会社は、
東京電力が13兆円、関西電力が6兆円、と言ったところで、全国でも40兆円程度の規模だ。
または日本中に電話網を張り巡らせているNTTの総資産は8兆円程度、ソフトバンクなど他の電話系企業と足し合わせても15兆円に届かないだろう。
JRだって全部足しても20兆円行かない規模だ。
如何に120兆円のインフラ資産が巨大なものかわかる。
仮に、日本の上下水道が全てくっついて民営化、などということになったら、そういう規模のインフラ企業が誕生することになるわけだ。
4) 世界の水ビジネス市場は2025年には100-125兆円。そのうち素材技術はたった1兆円市場しかない。
日本は水ビジネスでは、膜技術などの素材系に強い、とよく言われ、またその規模も1兆円程度まで成長などといわれているが、
そもそも水ビジネス全体で見れば、その市場規模は全体の1%に過ぎない、という驚愕の事実。
120兆円のうち9割は、それこそ世界の水メジャーのヴェオリアやスエズが得意とする運営・管理の市場なのである。
要素技術というのは、一般的には、うまくパッケージにして出したり、高いシェアで市場を独占すれば化けることも多い。
しかしそのまま裸で出しても、運営とマーケティングが巧い会社にアービトラージされてしまうことも多々ある。
具体的には、要素技術だけが優れても、それを活用して市場価値のあるものを作っていける会社は少ないから、その技術の本来の価値より安く買い叩かれてしまう。
で、買った会社は、その要素技術を他の運営管理力やマーケティング力と総合的に組み合わせて魅力的なパッケージとして、高く売りつけるってことだ。
だから、日本企業が世界の水ビジネスで生き残るためには、こういうノウハウをつけていくことが重要になっていく、という話だ。
5) 水ビジネスでも経営力より技術力にこだわり、「ガラパゴス」な日本
日本は「運営ノウハウが無い」などと言われているが、日本では料金回収や盗水に直面するなんてことが無いので、これは当たり前とも言える。
しかしながら、下水処理の浄化槽や膜技術などは世界一のものがたくさんあるという。
管理でも、先進国の都市の漏水率で20%を超えるのはざらだが、日本はたった3.1%という圧倒的な技術力。
それもあるのか、日本の水関係会社の社長さんは「他社にない優れた技術があれば一番になれる」
「人より優れた製品を持てば、受け入れられる」という人が多いんだそうだ。
なんか水ビジネスまで、ガラパゴスなのねぇ、と思った。
これじゃ、日本が現状で台湾や韓国に大負けしてる半導体などの分野と一緒になってしまうじゃない。
さっきも書いたように、要素技術っていうのは、いくら優れたものを持っていても、一部企業にしか刺さらないから、買い叩かれやすい。
運営力や他の技術と組み合わせてパッケージする力やマーケティングのうまい会社にアービトラージされやすいのだ。
だから技術だけで売れるなんて考えちゃダメ。
一方、グローバルな水メジャーは「我々には技術力なんて無いが、そんなものは後からついてくる」
と言う。
それで、実際に途上国などをはじめとする各国の水道運営・管理ビジネスに乗り出し、拡大している。
日本の水道事業の技術力が如何に上でも、結局外に出ていかないから、日本国内にとどまって終わり。
まさにガラパゴスじゃないの。
6) 途上国上下水道を受注しようにも、世界銀行の入札条件に見合わない日本の水道局
じゃあ東京都水道局とか、大きな水道事業者の一部は世界に出て行きゃいいじゃない、という人もいるだろう。
ここに大きな壁があるのであった。
水ビジネスで海外進出と言っても、既に水道事業がある先進国から運営・管理を受注するか、
途上国に新たに上下水道を作って運営・管理を行うの2通りしかない。
当然後者の方が入り込みやすい。
実際、日本は途上国に対して多額のODAを投じている。
ところが、ODAの水ビジネスには日本の水道事業は入り込めない。
なぜなら、ODAで行われる事業は世界銀行の入札基準を満たさないとならないわけだが、
水ビジネスの場合「10万トン以上の浄水場で5年以上の運営・管理を5カ国以上で行った事がある会社」とのことで、
日本の会社は一社も該当しないので、いつまでも入札に参加できないのだそうだ。
まぁ。
漸く最近、三菱商事などが中心となって、フィリピンの水道事業に進出したり、今年5月にもオーストラリアの水ビジネスの買収などが行われている。
東京都水道局などもそれに関わっている形だ。
自治体ベースでもいいので、こういう取り組みをしていかないと、世界の水ビジネスの気運に日本だけ取り残されるのは目に見えているだろう。
7) カーボン(炭素排出権)に次いで、金融業界に注目される水
金融業界は、儲かりそうなところ、アービトラージしやすいおいしいところを見つけて、すぐに金融商品に仕立てて金にしようという人たちの集まりなわけだが、環境ビジネスもそのターゲットの一つである。
つい最近も、CO2削減の手段である排出権をさっさと金融商品に仕立てる仕組みを作ったばかり。
その彼らは、今は水に注目しているのだそうだ。
具体的には、さっきの「バーチャルウォーター」の考え方に近い「ウォーターフットプリント」という考え方を導入。
一つの製品を作るのに消費する水を「ウォーターフットプリント」として、
排出権と同じように、一国が消費してよい「ウォーターフットプリント」の量を制限してしまう。
そうすると、どうしても水を使う必要がある国は、「ウォーターフットプリント」を他国から買い入れないとならなくなるので、それを証券化して取引対象とすれば儲かる、と考えているわけである。
こういう流れは良い悪いは別として、どこかが始めると避けられなくなる動きである。
排出権がそうだった。
日本がより良いものを導入しようとしても、動きが遅ければ、単に損して終わるだけである。
こういう動きも考えると、日本全体の水ビジネスへの意識を挙げていくってのは重要なのがわかる。
日本は水資源には恵まれた国だ。
だから、水ビジネスの必要性なんて殆ど考えないわけだけど、世界の潮流は違う。
そういうわけで、是非皆さんにも興味を持っていただければと思ってご推薦でした。
さらにこの本の後に読むと、知識と理解が深まる本もご紹介。
ウォーター・ビジネス――世界の水資源・水道民営化・水処理技術・ボトルウォーターをめぐる壮絶なる戦い
作品社
写真をクリックするとAmazonへ。
~~~画像(元ぺーじをご覧下さい)~~~
上の本は水ビジネスに関連する広範な話題をカバーしてるが、日本視点が中心だ。
それに対して、この本は、実際に水資源が不足し、内戦になっている地域も含め、世界中の水問題を、
深く掘り下げているので世界的な視点で非常に勉強になる。
上の本を読み終わって興味を持ったら、是非読むのをお勧め。
水ビジネスの現状と展望 水メジャーの戦略・日本としての課題
服部 聡之
丸善
写真をクリックするとAmazonへ
~~~画像(元ぺーじをご覧下さい)~~~
この本は、問題提起というよりは、歴史やケーススタディ、データが豊富で、資料集としてとても使える。
結局、詳細を理解しようとなると、数字の感覚が無いと議論できないわけで、そのあたりを補ってくれる。
←面白かったら、クリックして、応援してください!
<転載終了>
転載元 http://blog.goo.ne.jp/mit_sloan/e/cf39b05c44841099de2c43ced2fb2101











![[人工地震] プロジェクト・シール B29ビラ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/37/87/0eb29a7b3a65f5f2d0b4fe1312862291.jpg)