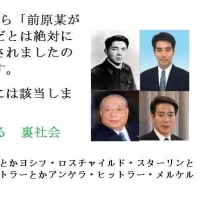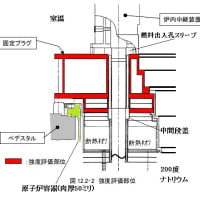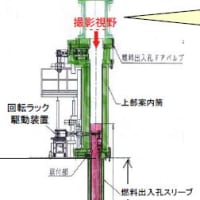甘い妄執
コーヒーや紅茶に砂糖を入れて飲む習慣があるのは、ヨーロッパ人である。日本でもその真似をして、喫茶店やファミレスでは砂糖が添えられて出てくる。
私は紅茶にもコーヒーにも甘みなしで愉しみたいので、カップの脇に角砂糖が添えられていると余計なことをするなあと思い、私が使わなければ捨てるのだから、もったいないことをするものだと思う。
日本の喫茶店で、当たり前のようにコーヒー、紅茶に砂糖をつけるのは、たぶん近代以降の英国文化崇拝によるものではないか。「英国紳士」などという妙な言葉があるくらいだ。エゲレス人は決してジェントルマンではないという話をしてみたい。
ヨーロッパの白人は、コーヒー、紅茶、それにココアなどは甘くするものと思い込んでいるが、例えばコーヒーの原産地であったアラビアでは、甘味をつけるものではない。
昔、西田佐知子が歌ってヒットした「コーヒールンバ」にあるように、コーヒーはアラブの坊さんの飲み物だったのである。修行僧が徹夜で修行する際、眠くならないようにカフェインたっぷりの、苦い味のままのコーヒーを飲んでいたのだ。修行僧はコーヒーの豆と葉っぱを煮だしたものらしい。
それが16世紀にヨーロッパに伝わり、17世紀には欧州全土に広まると、とたんに砂糖を入れて飲むようになった。
紅茶も同じである。中国では、発酵させる茶の系統でも砂糖は入れない。ウーロン茶を考えてもらえばいい。しかしそれを持ち帰ったイギリス人は、英国紅茶などと称して、堂々と砂糖を入れて飲むようになった。
ココアも南米の原産地では、甘くしないで料理のソースにしていたものだった。
ココアを世界で初めてパウダーにして売り出したのは、今日でも品質ナンバーワンのバンホーテンで、1828年のことだった。元はオランダの食品会社であった。1820年代は中南米の国々がスペイン、ポルトガルから独立していった時期でもあった。
ココアがパウダー化されてヨーロッパに持ち込まれると、とたんに砂糖を入れてドド甘くしてしまった。ベートーヴェンは1827年没だから、ココアを知らずに死んだのである。
どうしてこうもヨーロッパの者どもは、甘いものが好きなのかを考察したものは数多あるのだろうが、先般紹介した増田悦佐氏の『クルマ社会・7つの大罪 ~アメリカ文明衰退の真相』が説いている説に説得力があった。
ヨーロッパが今日で言う中東、エジプト、メソポタミア、ギリシアの文明圏から相当に遅れた僻地であったのは、気候が寒冷で農業に適さなかったからであるが、ためにヨーロッパでは肉食が主とされた。
肉食は、野獣鳥もしくは家畜をしてから食べるものだけれど、動物の肉は死後硬直するから、直後を逃すと食べられないほど硬くなってしまう。それからしばらくして死後硬直が緩む、つまりは腐りはじめるまでの間は、食べられないのである。
中世末期までは、人類はこの処理方法がわかっていなかった。死後硬直が緩むまでの間の温度や時間がわかってきてから、安定的に食肉が得られるようになったのである。
だからヨーロッパでは、中世末期までは腐る寸前まで寝かせておいてから食用にしていた。
増田悦佐氏は、「そこまで『熟成』させてしまうと相当臭くなるので、スパイスなどの調味料が必需品だった。そして、肉に調味料としてよく合うのは、じつは甘いものだった」と解説している。
* *
コショウももちろん合うが、醤油とかソースよりも、ヨーロッパ人は甘いもので肉を食べたがる、日本ではカモといえばネギをしょってくることになっているが、ヨーロパではカモには甘酸っぱいオレンジジュースをつけて食べるのが定番になっている。また七面鳥は必ずと言っていいぐらい、クランベリーソースで食べる。
それは単に腐りかけのときにどうしても自然に酸味が出るから、酸味を果物でごまかすというようなことではなく、ヨーロッパ人の味覚にとって、肉と甘味は切っても切れない縁があるからだった。だから、ヨーロッパ人がたとえば中国料理の酢豚を作ると、必ずといっていいほどパイナップルを入れたりするわけだ。
ヨーロッパ人の原罪として、甘いもの欲しさに世界各国を侵略していったわけだが、その一つの結果が世界各国から取り入れてきたソフトドリンクが、軒並み甘くなったことだった。
(中略)
とにかく、そもそも甘いものを欲しがる体質と言うか、国民性というか、民族性があって、その甘いものを確保するために、サトウキビ・プランテーションをカリブ海のあっちこっちの島々で作ったのが、奴隷制を採用せざるをえなくなった理由であったわけだ。
ヨーロッパの近代的な製造業としての大規模工場制度さえもが、カリブ海諸国で奴隷を使った大規模製造業としてのサトウキビの精製から始まったくらいだ。ヨーロッパ人はそれほど甘いものに執着があり、ある意味では甘いものを確保するために世界中に進出したし、カリブ海諸国を征服したし、奴隷貿易も始めたとさえ言えるかもしれない。
サトウキビを煮詰める段階で、まだ精製の度合いが非常に低いものを糖蜜と呼ぶ。その糖蜜からラム酒を造る。このラム酒もまた、海賊映画によく出てくるように、人を騙して海賊船に拉致するときに使ったり、長い航海のあいだに船員や水夫たちが反乱を起こさないようにおとなしくさせておくためにふるまったりした。近代初期の海運には不可欠の商品だった。ラム酒にしろ、サトウキビそのものにしろ、あるいは砂糖にしろ、香料にしろ、嗜好品としての食べ物への執着も、ヨーロッパ人が競争で世界中に植民地帝国を築こうとした原動力となっていた。
(中略)
ヨーロッパ諸国が築いた植民地で奴隷として働かせるために、アフリカから商品として買った黒人を連れて行くというようないわゆる「三角貿易」の網の目を形成するについても、イギリス人の砂糖への執着は大きな要因だった。
* *
増田悦佐氏は、『クルマ社会・7つの大罪』で、面白い統計を見せてくれている。
世界各地で砂糖の消費量が歴然と多いのは、旧大英帝国の国々だというのである。
1位はトリニダード・トバゴで、以下上位には、ニュージーランド、バルバドス、セントクリストファーネビス、カナダ、オーストラリア、マレーシア、そしてイギリス本国というように、英国関連の国の砂糖消費量の多さが目立つ。
大英帝国の植民地だった、カリブ海諸国もいまだに砂糖消費量が多い。みな大英帝国の植民地にされた遺産かもしれない。
それでも「世界は広いと実感させられるのが、あの日本人にとって閉口するほど甘いもの好きのアメリカ人が、アングロサクソンが先住民を追い出して多数派となった旧大英帝国植民地では砂糖消費量がいちばん少ないという事実」と述べている。
増田悦佐氏は、アメリカ人とイギリス人が現代では極端に肥満が多いことを指摘しているのである。そして以下のように説く。
* *
そして、大英帝国の落ちた甘い罠と、アメリカ合衆国が抗しきれなかったぐうたら暮らしへの誘惑という世界経済覇権国二代にわたる妄執を総合した結果が、アメリカ・イギリスで国民病として蔓延する肥満だと言って言いすぎではないだろう。イギリスはすでにこの国民病を克服することなく衰退期に入ったし、アメリカも結局は克服できないうちに没落をはじめる可能性が高い。
クルマだけ、あるいは甘みだけならなんとかしのげたかもしれないが、この2つの妄執の相乗効果は、怠惰な生活になれたアメリカ人にとっては打ち勝つことのできない業病なのだろう。
* *
ヨーロッパ人は、カソリックでもプロテスタントでも、とまれキリスト教徒である。彼らはただ甘いもの欲しさに、世界中に侵略して無辜の民を虐げつづけ、虐殺してきた。増田氏がいうように、恐ろしい妄執というほかない。甘いものがほしいから人殺しをし、平然と敬虔なクリスチャンと言い張ってきた。
日本ではクリスチャンはよく「敬虔な」という褒め言葉で飾られるけれど、恥を知るべきである。
新・心に青雲 様より
2012年03月13日
http://kokoroniseiun.seesaa.net/article/257345630.html











![[人工地震] プロジェクト・シール B29ビラ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/37/87/0eb29a7b3a65f5f2d0b4fe1312862291.jpg)