社会的分配構造に有利に働く付加価値としての知識・言葉を身に付ける場と身体・存在の拠り所となる知識・言葉を身に付ける場の相違。前者は国家管理の社会制度で推進され際限もなく弱者を排除・収奪し尽くし病・障害を造り出し施設に囲い込む。不登校・降りる生き方は後者の先駆けの模索として実るか?
@mirai_list お久しぶりです。二項選択ではなくて、2つとも拒否するか留保して長時間待つことも大切なことでは?更に、視野が窄いからの二項選択になると考えて、他の選択肢を多様に考えることだって有り得ますよ!
@mirai_list ワイン、酒、発酵食品の長く寝かして熟成の視点は多分ウッカリ放置の末に気付いたのでしょうね!失敗からも学べますよ(笑)!発達障害支援の選択肢を少なくする支援は当事者よりも支援者の自己肯定感、管理のし易さに結び付き当事者の意思の無視、人間性の否定です!
では 何か学び・掴み取るもののmathemata マテマタは?その程度の弱点なら数寄魔マターこそ素敵ですね(笑)!RT @emiemi14: 内緒にしてたのに・・"@you999: スキーマの弱点は複数形がスキーマタってこと。スキーマタ療法、っていうととってもマヌケ。"
@hannah_tohu_tho セキュリティシステム、警備保障会社との連携で地域にアピールする様な施設とは大違いですね!一連のツイを読んでいて施設の意味合いと違う本来の意味での心の安らぐ安息のhomeだったのでしょうね!
@mirai_list 『自分自身にとっての当り前』を語ることがmiraiさんには完璧に欠落している印象です。常に懐疑的に自分自身を語る。世間一般の「当り前」は確かに当事者には酷ですが、当事者の当り前を示せない状態は当り前なのでしょうか?それとも、当り前ではないのでしょうか?
地域の連携だけではない。施設間の交流もあった。その地域の各施設が集まってマラソン大会もあった。虚弱児施設だったから、私たちは弱かった。周りの施設からは努力賞、下手をすればバカにされるくらいの力しか出せなかった。そんな中、走るのだけは速いたぶん知的か発達の子どもが一人いた。
その子どもは施設内でもいつもからかわれたりしていたが、愛嬌のある子どもだった。当時中学生だったと思う。マラソン大会の季節になると、きりりとして練習に臨んでいた。大会蒔、施設の期待を一身に背負った。普段「バカ〇〇」とか言われる子どもを施設総出で応援。他の施設の子どもも息を飲んだ。
その子どもは走ることかけては施設のヒーローだった。いつも小学生にからかわれるのに、その小学生が名前を大声で名前を叫び、応援した。正直、走るその子どもの姿はかっこよかったのだ。
施設の頃、正月が好きだった。クリスマスが終わると一時帰宅(里親あり)する子どもが多くいた。私は帰る場所が無かったわけではない。帰りたくなかったのだ。正月は施設で朝寝坊が許され、お雑煮を食べ、お年玉をもらい、みなで初売りに行く。施設にいた方が心安らかだったのだ。
そういえば地域のうどん屋かそば屋の協会が年一回施設に来てくれた。その場で手打ち。おかわり自由でみんなたらふく食べた。近くのハンバーグチェーン店がやはり年一回招待してくれる。こちらは食べ放題じゃないが、子どもは楽しみにしていた。こうしてみるとあの施設は地域の中で受け入れられていた。
その変わりか知らないが、地域の清掃行事には施設総出で赴いたし、地域広報の仕訳・配達などは高校生が担った。これには高校生にバイト代が出た。夜の配達の後、車を出してくれる指導員がコンビニに寄ってくれてポケットマネーをくれた。ジュースやらアイスやらを買うのも楽しみだった。










 YOSH @yosh0316
YOSH @yosh0316 藤風院咲子 @hannah_tohu_tho
藤風院咲子 @hannah_tohu_tho



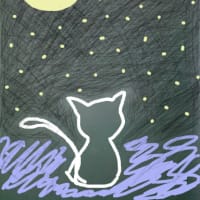
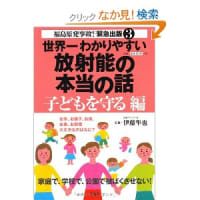
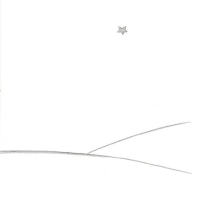
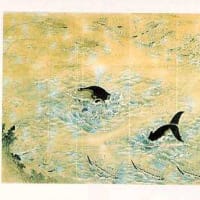

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます