【ネタ切れに付き、過去記事の「編集・加筆」です。】
1997年に成立した「アイヌ文化振興法」の附帯決議では「アイヌの人々の『先住性』は、歴史的事実であり、この事実も含め、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発の推進に努めること。」とされていました。
2019年に成立した「アイヌ新法」の第一条に「この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、・・・」と明記されました。
「13世紀以降のアイヌの先住性」は「紀元前に遡る縄文人の先住性」を否定するものではなく、「13世紀以降に入植した和人よりも先住性が有る」と云う意味では問題はありません。しかし「アイヌ民族は先住民族」と書くと、国際基準では「先住民の居住地に全く別の民族が入り込む」ことを意味し、「日本列島北部周辺、とりわけ北海道には縄文人は存在しなかった」か「アイヌは唯一の直系縄文人」と云う事になります。これは、科学的に証明されている「和人は縄文系」である事を否定する事になります。
憲法第14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
「アイヌ新法」は日本全国の「アイヌ民族」と「アイヌに関係する地方公共団体」が対象なので、「憲法第95条」には違反しませんが、「アイヌ民族は先住民族である」と明記すと、日本人が「先住民」と「非先住民」とに分けられることになります。
区別だけなら「男女の区別」や「親子の区別」などのように問題は有りませんが、「アイヌである事を理由に公金を支出する」事は、「アイヌ以外の人」を(逆)差別する事になり憲法14条の「すべて国民は・・・差別されない。」に違反します。
「アイヌ新法」【基本理念】第4条
・・・何人もアイヌに対して、アイヌであることを理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
この条文からすると、「アイヌに対して、アイヌで無い事を理由に差別する」事は合法となります。これは矛盾しているように見えますが、「アイヌ」の定義が定かでない事に起因します。つまり「アイヌ協会が認定したアイヌA」に対して、Aが「自分は日本人でありアイヌ民族ではない。」と主張した場合、Aを差別する事が可能になり、「アイヌ系日本人」の人権を侵害する事になります。逆に「アイヌ協会が認定しなかったアイヌB」に対して、Bが「自分はアイヌであり、アイヌの権利を保障せよ。」と言っても、「アイヌ新法」の対象になるかどうかは定かではありません。
更に、「アイヌの血を引く 砂澤陣 氏」の場合はさらに複雑です。砂澤氏の父親である「砂澤ビッキ」が考案した「ビッキ文様」について、当時「これはアイヌ文様ではない」として「アイヌから差別を受け」、最近になり北海道新聞が「ビッキ文様」を「アイヌ文様」として記事にした為に「砂澤氏」は道新に対して「ビッキ文様はアイヌ文様ではない」としてクレームを入れたそうです。
「アイヌ民族」と云う「民族」は現在は存在しないと主張する「アイヌ系日本人」の砂澤氏が「アイヌ協会」の不正を批判した為、「アイヌ協会」から除名され、実質的に権利を侵害されています。しかしこれも、「アイヌ新法」では違法にはならないようです。実際に「アイヌ系日本人である砂澤氏」を、アイヌ協会が差別したにも拘らず、何の制裁も加えられていどころか補助金の支給対象になっています。
一定の要件を満たした人を「アイヌ協会」が「アイヌ」と認める事で、その人は「アイヌ」になります。その人が「アイヌの血」を引き継いでいる必要はなく、白人でも黒人でも、外国人でも関係ありません。政府は「アイヌ」の定義を確定していないので、「アイヌの血を引いていて、『アイヌ協会】がアイヌと認定した人」以外では、
①アイヌ協会がアイヌと認定しない、アイヌの血を引く人。
②アイヌの血を引くが、本人はアイヌと思っていない人。
③アイヌの血を引かないが、自身は自分をアイヌと思っている人。
④アイヌの血を引かないが、「アイヌ協会」がアイヌと認定した人。
⑤その他。古来日本に住んでいたウィルタ、ニブフ、等のオホーツク・シベリア民族等とその混交アイヌ。「アイヌ(良い人)」に対する「ウェンペ(悪い人)」等。
などが考えられ、現在の所 ④以外は政府による「アイヌ認定」は不明です。
「アイヌ」は「和人」より数百年ほど遅れて北海道に定住したとは言え、一貫して「日本民族」なので「人種・民族の違い」はなく、「民俗」の違いがあるだけです。「民俗」の違いなら、日本各地に現存し地理的分類や宗教的分類など、切り口を変えれば日本には先住民が無数に存在すると言えます。
日本には「日本民族」以外の「先住民族」の存在が科学的に確認できないので、「アイヌ民族は先住民族である」と書いて日本を分断する事は「憲法違反」であり、「米国のインディアン虐殺」や「オーストラリアのアボリジニ虐殺」と「日本国が同類であると云うウソ」が世界中に拡散される恐れがあります。
「アイヌ」と思われる人々の歴史は現在から700年(~最大限1200年?)ほど遡れますが、北海道の和人の歴史は確実に1300年は遡れます。阿倍比羅夫は蝦夷(えみし)を討って、後方羊蹄(しりべし)に至り、政所を置き郡領を任命して帰ったとの記述が日本書紀にあります。この時に蝦夷(えみし)や粛慎(みしはせ)を平定したと書かれています。勿論、蝦夷や粛慎は「和人ではない」かも知れませんが、確実に縄文人の血を引く「日本人」ですし、この時には「アイヌ」の痕跡は有りません。
現行の「アイヌ新法」が「アイヌ民俗」を保存する為の法律ならば憲法には違反しませんが、「アイヌ民族」と「和人やその他の先住民族」を切り分けるのなら、確実に「憲法違反」と言えます。
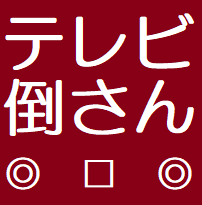
1997年に成立した「アイヌ文化振興法」の附帯決議では「アイヌの人々の『先住性』は、歴史的事実であり、この事実も含め、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発の推進に努めること。」とされていました。
2019年に成立した「アイヌ新法」の第一条に「この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、・・・」と明記されました。
「13世紀以降のアイヌの先住性」は「紀元前に遡る縄文人の先住性」を否定するものではなく、「13世紀以降に入植した和人よりも先住性が有る」と云う意味では問題はありません。しかし「アイヌ民族は先住民族」と書くと、国際基準では「先住民の居住地に全く別の民族が入り込む」ことを意味し、「日本列島北部周辺、とりわけ北海道には縄文人は存在しなかった」か「アイヌは唯一の直系縄文人」と云う事になります。これは、科学的に証明されている「和人は縄文系」である事を否定する事になります。
憲法第14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
「アイヌ新法」は日本全国の「アイヌ民族」と「アイヌに関係する地方公共団体」が対象なので、「憲法第95条」には違反しませんが、「アイヌ民族は先住民族である」と明記すと、日本人が「先住民」と「非先住民」とに分けられることになります。
区別だけなら「男女の区別」や「親子の区別」などのように問題は有りませんが、「アイヌである事を理由に公金を支出する」事は、「アイヌ以外の人」を(逆)差別する事になり憲法14条の「すべて国民は・・・差別されない。」に違反します。
「アイヌ新法」【基本理念】第4条
・・・何人もアイヌに対して、アイヌであることを理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
この条文からすると、「アイヌに対して、アイヌで無い事を理由に差別する」事は合法となります。これは矛盾しているように見えますが、「アイヌ」の定義が定かでない事に起因します。つまり「アイヌ協会が認定したアイヌA」に対して、Aが「自分は日本人でありアイヌ民族ではない。」と主張した場合、Aを差別する事が可能になり、「アイヌ系日本人」の人権を侵害する事になります。逆に「アイヌ協会が認定しなかったアイヌB」に対して、Bが「自分はアイヌであり、アイヌの権利を保障せよ。」と言っても、「アイヌ新法」の対象になるかどうかは定かではありません。
更に、「アイヌの血を引く 砂澤陣 氏」の場合はさらに複雑です。砂澤氏の父親である「砂澤ビッキ」が考案した「ビッキ文様」について、当時「これはアイヌ文様ではない」として「アイヌから差別を受け」、最近になり北海道新聞が「ビッキ文様」を「アイヌ文様」として記事にした為に「砂澤氏」は道新に対して「ビッキ文様はアイヌ文様ではない」としてクレームを入れたそうです。
「アイヌ民族」と云う「民族」は現在は存在しないと主張する「アイヌ系日本人」の砂澤氏が「アイヌ協会」の不正を批判した為、「アイヌ協会」から除名され、実質的に権利を侵害されています。しかしこれも、「アイヌ新法」では違法にはならないようです。実際に「アイヌ系日本人である砂澤氏」を、アイヌ協会が差別したにも拘らず、何の制裁も加えられていどころか補助金の支給対象になっています。
一定の要件を満たした人を「アイヌ協会」が「アイヌ」と認める事で、その人は「アイヌ」になります。その人が「アイヌの血」を引き継いでいる必要はなく、白人でも黒人でも、外国人でも関係ありません。政府は「アイヌ」の定義を確定していないので、「アイヌの血を引いていて、『アイヌ協会】がアイヌと認定した人」以外では、
①アイヌ協会がアイヌと認定しない、アイヌの血を引く人。
②アイヌの血を引くが、本人はアイヌと思っていない人。
③アイヌの血を引かないが、自身は自分をアイヌと思っている人。
④アイヌの血を引かないが、「アイヌ協会」がアイヌと認定した人。
⑤その他。古来日本に住んでいたウィルタ、ニブフ、等のオホーツク・シベリア民族等とその混交アイヌ。「アイヌ(良い人)」に対する「ウェンペ(悪い人)」等。
などが考えられ、現在の所 ④以外は政府による「アイヌ認定」は不明です。
「アイヌ」は「和人」より数百年ほど遅れて北海道に定住したとは言え、一貫して「日本民族」なので「人種・民族の違い」はなく、「民俗」の違いがあるだけです。「民俗」の違いなら、日本各地に現存し地理的分類や宗教的分類など、切り口を変えれば日本には先住民が無数に存在すると言えます。
日本には「日本民族」以外の「先住民族」の存在が科学的に確認できないので、「アイヌ民族は先住民族である」と書いて日本を分断する事は「憲法違反」であり、「米国のインディアン虐殺」や「オーストラリアのアボリジニ虐殺」と「日本国が同類であると云うウソ」が世界中に拡散される恐れがあります。
「アイヌ」と思われる人々の歴史は現在から700年(~最大限1200年?)ほど遡れますが、北海道の和人の歴史は確実に1300年は遡れます。阿倍比羅夫は蝦夷(えみし)を討って、後方羊蹄(しりべし)に至り、政所を置き郡領を任命して帰ったとの記述が日本書紀にあります。この時に蝦夷(えみし)や粛慎(みしはせ)を平定したと書かれています。勿論、蝦夷や粛慎は「和人ではない」かも知れませんが、確実に縄文人の血を引く「日本人」ですし、この時には「アイヌ」の痕跡は有りません。
現行の「アイヌ新法」が「アイヌ民俗」を保存する為の法律ならば憲法には違反しませんが、「アイヌ民族」と「和人やその他の先住民族」を切り分けるのなら、確実に「憲法違反」と言えます。
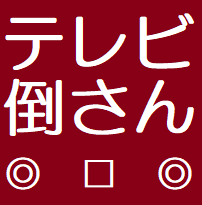










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます