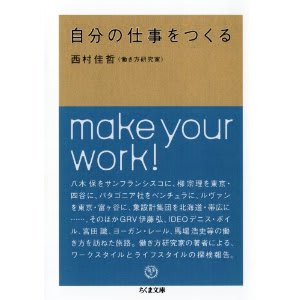右脳の重要性はよくTVなどでも言われているが、まだまだ言い足りない、そうです。
左脳の働きをシャットダウンし、右脳を活性化してかく自画像の授業で、訳者の絵の変わり具合には
びっくりでした。
そもそも、論理的思考が得意な著者、その上での右脳活性化だが、論理的思考があまり得意とはいえない
人でも、右脳を活性化するこのような教室に通うことで、所得につながるような効果があるのだろうか。
それは、私の下の下の代くらいから切実になってくるのことなのかな、と思いました。
もうひとつ、かいてあったことで、印象に残ったのが人々は「物語」を渇望していて、ストーリー
テリングというのは、重要ということ。この本の発行年は2006年だけれど、思えばそのころから、TVのCMでも
物語を意識したものがでてきていた気がします。(某通信関係、車など)
影響の大きい本だったのかしら。