東洋経済新報社に、趣味・教養と分類されるカテゴリーがある。そこには現代をテーマにしたエッセーがあって、たまに読んでいる。今回は小室哲哉氏の零落と詐欺容疑で逮捕された関連からか、つぎのものに注目した。
■山口百恵をめぐる阿久悠の「対決」(高澤秀次氏)
※「小室哲也」氏を「小室哲哉」氏と訂正しました。
スマヌ・・・(泣)。
敗戦後の復興が主な目標だった、と考えられる昭和時代の神話的なイコンは多いが、「山口百恵」と「阿久悠」(故人)という固有名もその例である。昭和から平成、さらに現代へとシフトしてきた日本人の無意識に、なにか参考があれば――これが興味の中心だった。
エッセーの構造は、同時代の阿久悠氏を道具立てて「山口百恵」のアイドル度を素描し、やがて山口百恵から松田聖子・中森明菜を経由するJ-POPと呼ばれた日本歌謡の変遷を考えるというものだ。
POPSはどう変遷したか。著者の考えでは、こうである。
――山口百恵は「私」を語らない無冠の女王であり、そのことによって「私」を超えた存在だった。一方、松田聖子・中森明菜の時代以降のタレントは、「私」の露出度が高い。「私」を全面に押し出した、歌による「私」語りの隆盛を意味した。
POPSをとおして見た文化の変遷として、まあ、ありふれた感想だ。もう少し時代の幅をひろげて、昔は歌声喫茶などで合唱できたものだが、最近の歌はカラオケでも合唱できないなどともいわれる。だが、そうした観かたが阿久悠氏の発言を参照しているとは、新しい知識になった。
――「昭和と平成の間に歌の違いがあるとすれば、昭和の歌には人に伝えたいことがあり、平成の歌は自分だけを語っているということです。それを「私の時代」というのなら、僕はむしろ「私を超えた時代」の昭和という時代を愛します」(インタビュー「歌謡曲の向こうに昭和という時代が見える」、『阿久悠 命の詩』所収)
つづけて著者はいう――JポップからJ文学まで、平成の世にあって、あられもない「私」語りは、紛れもなく時代の主流になりつつある。各自各様に、「自分だけを語っている」のだ。
さらに著者は、こうもいう。
――ここに、ブログという名の“極私的メディア”での、匿名の「私」による語りの氾濫を重ね合わせてみるといい。いかに容易に、「私」を立ち上げることが可能な時代か想像がつくだろう。それは、「私を超えた」ものへの想像力の欠如と、おそらく正比例の関係にあるのだ。
「人に伝えたい」語りと「自分だけを語る」語り?
私が、私がという語りの主語の問題だけじゃないだろう。どう違う?
●『イミテーション・ゴールド』(1977)
作詞/阿木燿子 作曲/宇崎竜童 歌/山口百恵
##########################
シャワーのあとの髪のしずくを 乾いたタオルで拭きとりながら
彼が窓辺で話しかけるわ 流れる雲さえ季節の色だと
私は軽い目まいを感じ マニキュアの指、かざしてみるの
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド ア・ア・ア、焼けた素肌が
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド 若いと思う今年の人よ
声が違う、年が違う、夢が違う ほくろが違う
ごめんね、去年の人とまた比べている
西陽(にしび)の強い部屋の片隅 彼が冷蔵庫バタンと閉じる
パックのままの牛乳かかえ 身軽な動作で運んでくれるわ
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド ア・ア・ア、命そのまま
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド 飲み干したけど今年の人よ
くせが違う、汗が違う、藍が違う きき腕違う
ごめんね、去年の人にまだ縛られてる
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド ア・ア・ア、そのやさしさで
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド まっててほしい今年の人よ
日が当れば、影が違う、色が違う 光が変わる
ごめんね、去年の人を忘れるその日を
##########################
声が違う、年が違う、夢が違う ほくろが違う
くせが違う、汗が違う、藍が違う きき腕違う
日が当れば、影が違う、色が違う 光が変わる
と歌っているが、「私」語りとどう違う? 歌詞を読むかぎりどこも違ってないのだ、たぶん。戯画的な感じがするので、あまり好きじゃない演歌を含めて、昔からどんな歌謡曲もPOPSも自分語りだったのだ。もちろん、文学も小説も。
※『イミテーション・ゴールド』は、倉木麻衣のカバー曲でもある。
1982年10月28日生まれ。キャーーーッかわいい!!


花の赤さを述べる言葉は、それだけですでに「私を超えたもの」だ。もともと言葉はそういうものであり、そうでなければ言葉の表現と伝達機能は失われてしまう。言葉は「私」をこえたところにインストールされている重要なソフトである。日本語の文法や語法、それぞれの単語は、「私」をこえたところに、すでに設定されているのだ。どんなに足掻いても、私たちはその基本的な設定から自由になれない。
にもかかわらず、昔の歌は「私」語りじゃなくて、人に伝えたい「私を超えた」ものを持っていると語る意見が、何故くりかえし現われるのか。その理由のひとつは、山口百恵が「私」を語らない無冠の女王であり、そのことによって「私」を超えた存在だったと著者が表現しているところにある。アイドル本の元祖ともいわれる『蒼い時』を書いて自分をはじめてカミング・アウトした直後に、山口百恵氏は芸能界から引退したという。テレビやラジオなどメディアへの露出度が、現代のヴォーカルにくらべてきわめて少なかったといわれている。
露出度の少なさは、歌手個人の自分史と呼ばれる文脈の少なさに対応している。リスナーは、いわば歌そのものから歌手の「物語」を想像するほかはない。彼女が発するメッセージは、自分史をもった歌手個人の文脈に束縛されないので、リスナーひとりひとりが構成する文脈にダイレクトに問いかけられる。この歌の意味を、あなたはどう受け取るのかと。メッセージにたいする既成の暗号解読機はない。人それぞれが無意識のなかにもっている自分史に、直接問いかけられるほかはない。
ご気楽にメディアに露出し、メディアによって「自分史」を構成される歌手にくらべて、無冠の女王のメッセージは強烈だっただろう。いわばリスナーは、もっとも自分が得意とする方法で、そのメッセージを読むことが許されるからである。
この意味の恣意性・自由度は、その歌について複数のリスナーが語りあえば、なおさら明らかになるだろう。一部を重ねあいながら、彼らは歌の真意について、いろいろと違った意見をもちよって話しあうだろう。別の解釈をとおして、新しい発見に気づいた瞬間、その歌は、人に伝えたい「私を超えた」ものを持っていることが理解できる。いいかえれば「私を超えた」ものとは、私以外のリスナーのことだ。この、孤独であるのに孤独でないかもしれない人間の存在の形を、「私を超えた」ものと著者は呼んでいるのだ。そこにうっすらと見えてくるのは、不思議で超越的な言葉の世界である。
■山口百恵をめぐる阿久悠の「対決」(高澤秀次氏)
※「小室哲也」氏を「小室哲哉」氏と訂正しました。
スマヌ・・・(泣)。
敗戦後の復興が主な目標だった、と考えられる昭和時代の神話的なイコンは多いが、「山口百恵」と「阿久悠」(故人)という固有名もその例である。昭和から平成、さらに現代へとシフトしてきた日本人の無意識に、なにか参考があれば――これが興味の中心だった。
エッセーの構造は、同時代の阿久悠氏を道具立てて「山口百恵」のアイドル度を素描し、やがて山口百恵から松田聖子・中森明菜を経由するJ-POPと呼ばれた日本歌謡の変遷を考えるというものだ。
POPSはどう変遷したか。著者の考えでは、こうである。
――山口百恵は「私」を語らない無冠の女王であり、そのことによって「私」を超えた存在だった。一方、松田聖子・中森明菜の時代以降のタレントは、「私」の露出度が高い。「私」を全面に押し出した、歌による「私」語りの隆盛を意味した。
POPSをとおして見た文化の変遷として、まあ、ありふれた感想だ。もう少し時代の幅をひろげて、昔は歌声喫茶などで合唱できたものだが、最近の歌はカラオケでも合唱できないなどともいわれる。だが、そうした観かたが阿久悠氏の発言を参照しているとは、新しい知識になった。
――「昭和と平成の間に歌の違いがあるとすれば、昭和の歌には人に伝えたいことがあり、平成の歌は自分だけを語っているということです。それを「私の時代」というのなら、僕はむしろ「私を超えた時代」の昭和という時代を愛します」(インタビュー「歌謡曲の向こうに昭和という時代が見える」、『阿久悠 命の詩』所収)
つづけて著者はいう――JポップからJ文学まで、平成の世にあって、あられもない「私」語りは、紛れもなく時代の主流になりつつある。各自各様に、「自分だけを語っている」のだ。
さらに著者は、こうもいう。
――ここに、ブログという名の“極私的メディア”での、匿名の「私」による語りの氾濫を重ね合わせてみるといい。いかに容易に、「私」を立ち上げることが可能な時代か想像がつくだろう。それは、「私を超えた」ものへの想像力の欠如と、おそらく正比例の関係にあるのだ。
「人に伝えたい」語りと「自分だけを語る」語り?
私が、私がという語りの主語の問題だけじゃないだろう。どう違う?
●『イミテーション・ゴールド』(1977)
作詞/阿木燿子 作曲/宇崎竜童 歌/山口百恵
##########################
シャワーのあとの髪のしずくを 乾いたタオルで拭きとりながら
彼が窓辺で話しかけるわ 流れる雲さえ季節の色だと
私は軽い目まいを感じ マニキュアの指、かざしてみるの
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド ア・ア・ア、焼けた素肌が
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド 若いと思う今年の人よ
声が違う、年が違う、夢が違う ほくろが違う
ごめんね、去年の人とまた比べている
西陽(にしび)の強い部屋の片隅 彼が冷蔵庫バタンと閉じる
パックのままの牛乳かかえ 身軽な動作で運んでくれるわ
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド ア・ア・ア、命そのまま
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド 飲み干したけど今年の人よ
くせが違う、汗が違う、藍が違う きき腕違う
ごめんね、去年の人にまだ縛られてる
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド ア・ア・ア、そのやさしさで
ア・ア・ア、イミテイション・ゴールド まっててほしい今年の人よ
日が当れば、影が違う、色が違う 光が変わる
ごめんね、去年の人を忘れるその日を
##########################
声が違う、年が違う、夢が違う ほくろが違う
くせが違う、汗が違う、藍が違う きき腕違う
日が当れば、影が違う、色が違う 光が変わる
と歌っているが、「私」語りとどう違う? 歌詞を読むかぎりどこも違ってないのだ、たぶん。戯画的な感じがするので、あまり好きじゃない演歌を含めて、昔からどんな歌謡曲もPOPSも自分語りだったのだ。もちろん、文学も小説も。
※『イミテーション・ゴールド』は、倉木麻衣のカバー曲でもある。
1982年10月28日生まれ。キャーーーッかわいい!!


花の赤さを述べる言葉は、それだけですでに「私を超えたもの」だ。もともと言葉はそういうものであり、そうでなければ言葉の表現と伝達機能は失われてしまう。言葉は「私」をこえたところにインストールされている重要なソフトである。日本語の文法や語法、それぞれの単語は、「私」をこえたところに、すでに設定されているのだ。どんなに足掻いても、私たちはその基本的な設定から自由になれない。
にもかかわらず、昔の歌は「私」語りじゃなくて、人に伝えたい「私を超えた」ものを持っていると語る意見が、何故くりかえし現われるのか。その理由のひとつは、山口百恵が「私」を語らない無冠の女王であり、そのことによって「私」を超えた存在だったと著者が表現しているところにある。アイドル本の元祖ともいわれる『蒼い時』を書いて自分をはじめてカミング・アウトした直後に、山口百恵氏は芸能界から引退したという。テレビやラジオなどメディアへの露出度が、現代のヴォーカルにくらべてきわめて少なかったといわれている。
露出度の少なさは、歌手個人の自分史と呼ばれる文脈の少なさに対応している。リスナーは、いわば歌そのものから歌手の「物語」を想像するほかはない。彼女が発するメッセージは、自分史をもった歌手個人の文脈に束縛されないので、リスナーひとりひとりが構成する文脈にダイレクトに問いかけられる。この歌の意味を、あなたはどう受け取るのかと。メッセージにたいする既成の暗号解読機はない。人それぞれが無意識のなかにもっている自分史に、直接問いかけられるほかはない。
ご気楽にメディアに露出し、メディアによって「自分史」を構成される歌手にくらべて、無冠の女王のメッセージは強烈だっただろう。いわばリスナーは、もっとも自分が得意とする方法で、そのメッセージを読むことが許されるからである。
この意味の恣意性・自由度は、その歌について複数のリスナーが語りあえば、なおさら明らかになるだろう。一部を重ねあいながら、彼らは歌の真意について、いろいろと違った意見をもちよって話しあうだろう。別の解釈をとおして、新しい発見に気づいた瞬間、その歌は、人に伝えたい「私を超えた」ものを持っていることが理解できる。いいかえれば「私を超えた」ものとは、私以外のリスナーのことだ。この、孤独であるのに孤独でないかもしれない人間の存在の形を、「私を超えた」ものと著者は呼んでいるのだ。そこにうっすらと見えてくるのは、不思議で超越的な言葉の世界である。












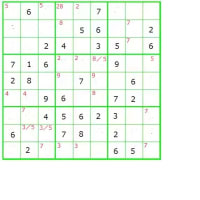
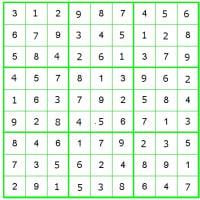
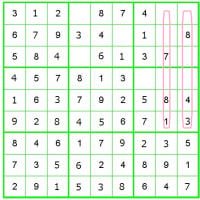
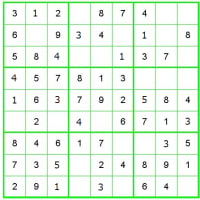
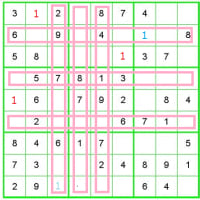
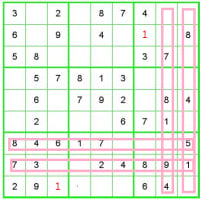
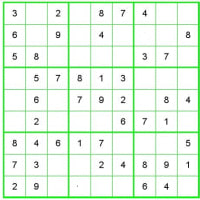

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます