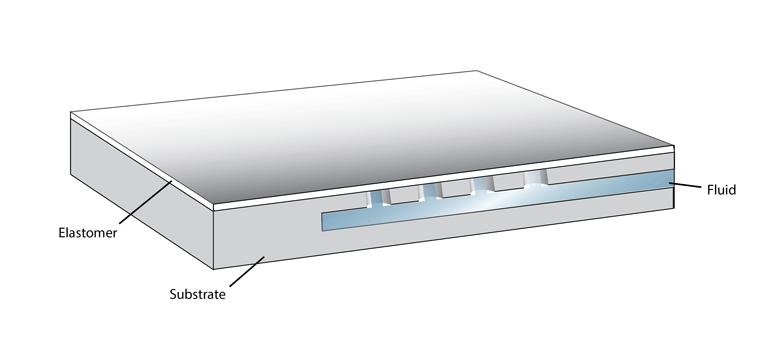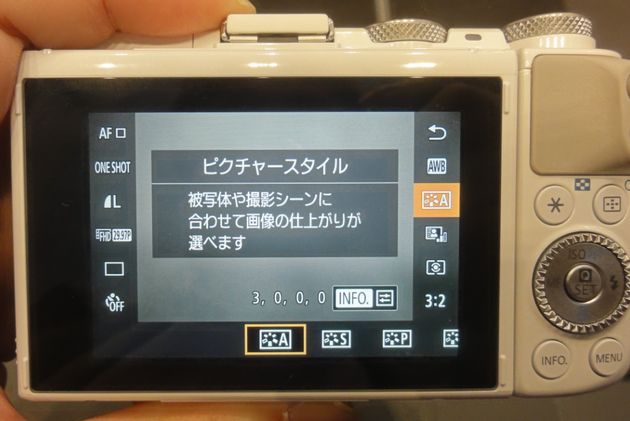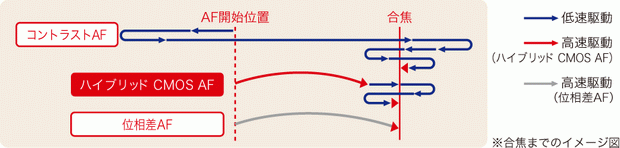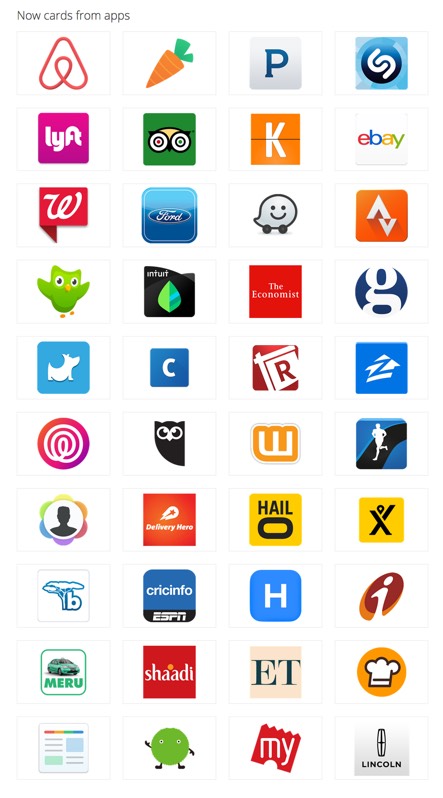<header class="entry-header">
空撮ドローンParrot Bebop Droneは7万円台で4月上旬発売。Oculus対応コントローラ付き14万円
</header> 
Parrot は魚眼180度カメラ搭載のクアッドコプター Bebop Drone を国内で4月上旬に発売します。予約開始は明日3月13日。
Bebop Drone は定番クアッドコプター AR. Drone シリーズで知られる Parrot のコンシューマー向け新製品。高度な自律制御による安定性やスマホを使った簡単な操作に加えて、デジタルジンバルと3軸ブレ補正機能を備えた魚眼180度 1400万画素や、リアルタイムに歪み補正や動画ブレ補正を施すプロセッサの内蔵など空撮能力が向上しました。
(訂正: 当初「電動ジンバルを備え」としていましたが、正確にはカメラを安定させる3軸ブレ補正と、180度映像から切り出して視点を変更する「デジタルジンバル」を備えます。お詫びして訂正いたします。)
また GPS / GLONASS 内蔵により、プログラムしたフライトプランどおりに飛行/撮影させる機能、WiFi信号をロストした際や、ホームに戻るボタンを押すと離陸地点に戻る自動帰還機能も搭載します。

さらにオプションのコントローラSkyController も Bebop の特徴のひとつ。通常は250mの通信距離を最大2kmまで延長できること、HDMI出力ポートを使い Oculus Rift などヘッドマウントディスプレイを使った主観フライトにも対応する点が特徴です。
主な仕様は、本体サイズが23 x 32 x 3.6cm、重さはバッテリー搭載で390g。屋内用の外殻(ハル)を装着すると410g。大きさからすると意外なほど軽く、落ちた時のダメージも少なくなっています。
バッテリー駆動時間は11分。標準で二個付属するため、交換すれば計22分。
撮影機能は6エレメント F2.2の180度魚眼レンズ、1400万画素センサ、3軸ブレ補正。動画は1920 x 1080p 30fps の H.264。静止画は4096 x 3072まで。JPGのほかRAW, DNG も残せます。内蔵ストレージは8GB。

価格は Bebop Drone 単体が 税別7万900円、SkyController 付属パッケージは13万900円。AR. Drone からの機能向上を思えば単体ではむしろお買い得価格ながら、コントローラが付属すると価格が倍近くに跳ね上がります。
SkyController が本体に近い価格である理由は、コントローラ機能に加えてレンジ最大2kmのアンテナを備えたWiFiアクセスポイントでもあること、Androidを内 蔵することで、スマホやタブレットを使わずコントローラだけでも飛ばせるAndroid端末でもあることなど。
写真のタブレットは付属せず、iPad や iPhone など一般的なスマートフォンやタブレットを固定します。またHDMIポートに Oculus Rift などを接続した主観フライトには SkyController が必要です。主観フライト向けのヘッドマウントディスプレイはHDMI入力を備えた製品なら原則的に対応。
ジャイロセンサ出力を内蔵したHMDであれば、ユーザーの頭の動きで Bebop Drone のカメラの向きも操作できます。