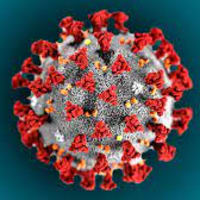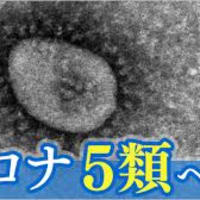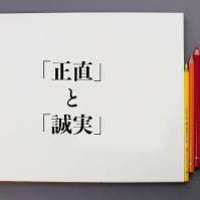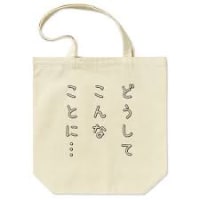武漢コロナウイルス感染症:WARS (https://blog.goo.ne.jp/tributary/e/84da922cdd25a87b24d80a3e0c6df67b)の流行が医療崩壊を招くと言われている。医療崩壊とは、元々は「過度な医療安全への要求から医療の提供が困難となった状態」を意味していた。完全に安全な医療はあり得ないところ、それを強く要求する風潮となると、期待に反する医療行為が補償や捜査の対象となり、医療者が犯罪者扱いされる事態となる。その結果、医療職の疲弊や離脱から医療の提供が困難となる。この意味での医療崩壊は、社会の理解が進み医療訴訟も増加から減少に転じるなど、危機は遠のいている。
近年いわれる医療崩壊とは、理由は問わずに「医療の提供が困難な状態」の意味である。例えば、医師不足でへき地の医療が困難、特定の診療科の医師(産科医など)の不足、救急隊が受け入れ病院を見つけられない(たらい回し)などである。医療側の人材や資材・設備の不足または患者数の増加による、相対的な医療需要の過大が原因である。WARSの流行が招く医療崩壊も、事情は同じである。
感染症に応じる医療施設が限られたところに患者が急増すると、病院がWARS患者で溢れ人材や防護資材や治療機器が不足し、医療の提供が困難になる。この対応策として、治療方法はすぐには開発できないので、受診抑制の呼びかけ、PCR検査の抑制的運用、医療施設間での役割分担、防護資材の優先的配布、ホテル隔離の許容などが実施され、行動自粛を促す緊急事態宣言までが発出された。これらの成果があって、幸い今は(5月上旬)顕著な問題は起こっていない。
しかし、WARS患者に対応する中、その裏側で起こっている医療崩壊もある。WARSの診療を行う病院の多くは、地域の中核病院である。すなわち、脳梗塞、心筋梗塞、がん、その他の領域で、高度な急性期の医療を提供している病院である。そのような病院は、一般的に人員や設備が充実しており、WARS流行のような突発的な医療需要の増大にも対応できる。しかし、WARSに対応する分、他の医療行為は抑制せざるを得ない。その結果、治療すべき他の疾患への医療の提供が困難となる。
更に、もう一つの医療崩壊が進んでいる。医療機関の経営悪化である。中核病院は、高度な急性期医療を提供するために多くの人員や設備を抱えている。その高い固定費を賄うのは、診療報酬、特に急性期医療に対する医療への高額な報酬である。しかし、その高くあるべき報酬額は政府の方針で低く抑えられ続け、多くの病院は赤字経営というのが常態であった。そこにWARS患者の急増である。WARS患者に対する診療報酬は、解釈変更等で多少の増額はあるも、ならせば他の急性期医療に遠く及ばない。一方で人員の増員や危険手当の支給、緊急の医療機器の購入などで出費は増える。しかも、他の(診療報酬が高い)患者は断らざるを得ない。収支は極端に悪化する。
外出・外食の自粛で観光業や交通業、飲食業などが打撃を受けている。病院も同じである。その上にWARS患者を診療すればするほど赤字を抱えることになる。風評被害を受けても、自らの感染の危険を感じても、医療機関の職員はWARSに対峙する気概や使命感を有している。応援の声もあげられ、寄付や応援物資も届いている。
しかし、経営指標は無慈悲である。公立病院では、赤字は税金から補填されるだろう。しかしそうでない病院には、戦の後には巨額の赤字だけが残される。勝利しても賠償金はない。待っているのは経営破綻と医療崩壊である。解決は患者数に応じた補助金が分かりやすい。患者数2万人なら、一人500万円でも総額1000億円で済む。アベノマスク4枚分になろうか・・。
WARSに伴う医療崩壊には、流行が去れば消える医療崩壊と流行後に到来する医療崩壊がある。長期的には、後者の方が遥かに深刻である。