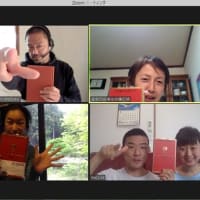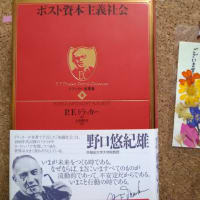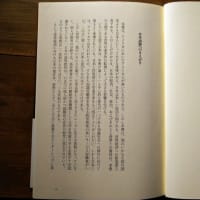今日の尼崎は、最低気温ー3℃。
全国的にも、過去最強クラスの寒波が来ているそうです。
寒さ真っ盛りのこの時期、ときどき耳にする「寒麹(かんこうじ)」を仕込みました。
秋田では、以前から作られているそうです。
よく見かける塩麹との違いは、
・塩麹=麹+塩+水⇒1週間ほどで完成
・寒麹=麹+米+塩⇒1年ほどかけて完成
寒麹はお米のでんぷん質をゆっくり分解する分、濃厚な旨みがあって、甘じょっぱい感じになるそうです。
未体験ですが(^^ゞ
今の時期に仕込んでおくと、これから季節が進んでゆっくり気温が上がるにつれて発酵が進むのだと思います。
お味噌と同じ感じですね^^
つくり方も、大豆の代わりに米を使うだけで、味噌仕込みとほぼ同じ。
甘じょっぱい感じになるのも納得できます。
そう言えば、ご飯に麹を混ぜて置いたもので酒まんじゅうを作ったりしますね。
麹との関わりは、元々は何気ない身近なものなのかも知れません。
『千年の一滴 だし しょうゆ』という美しいドキュメンタリー映画で、「枯れ木に花を咲かせましょう」と唱えながら、茹でた大豆に麹菌を蒔くシーンがありました。
花咲か爺さんのお話は、麹の扱いをモチーフにしてたのかな。
寒麹の作り方は、ネットなどで様々に紹介されています。
私が作ったのは、いつも食べてる3分搗きご飯に、麹と塩を合わせたもの。
一般的な作り方と違うかも知れませんが、この後どうなるのか観察してみたいと思います。
【割合】
・米 :300g⇒固めに炊く
・米麹:300g
・粗塩:150g
【手順】
1.麹と塩を混ぜる(お味噌でも、麹の塩切りしますね^^)。
2.ご飯と混ぜ合わせて、焼酎で拭いた容器で保存。
フタの代わりに、ボウルを被せました。なんだかユーモラス(笑)
3.1週間ほどの間は、1日に1度かき混ぜる。
4.その後は、半年~1年ほど寝かせて、発酵・熟成させる。
(発酵期間中は、小さめの樽に移して、紙をかけて紐で縛ってフタにするつもりです。ホコリをよけつつ、中の微生物が呼吸できるように)
・
・
・
無数にいる微生物の働きで、時間とともに美味しくなるんですね。
池上彰さんが書かれた本の一節を、ふと思い出しました。
『仏教って何ですか?』
「インドや東南アジアに行くと、高温多湿な環境の中で、生命があっという間に死に、しかし、あっという間に生まれてくる強力な生命力を感じます。
人が何度も転生し、別の生物に生まれ変わる輪廻という発想が出てくるのも実に自然に思えます。
至るところに神々がいるという発想も、豊かな自然の中から生まれてきたのでしょう」
この一文に触れて、ああ、自分はアジアの人間なんだなあ~と思いました。
日本にも「八百万(やおよろず)の神」という言葉がありますしね。
身の回りの至るところに、たくさんの微生物がいて、あるときは困ったカビにもなりますが、うまくお付き合いできれば素敵なものをもたらしてくれる。
まるで、私たち自身が、生命の海の中に住んでるみたいです。
旺盛に生まれてくる生命の巡りの中に、自分も存在してると思うと、とても安らぎます。
なんて。
お話が、ずいぶん麹からずれましたね(笑)
周りを取り囲むたくさんの生命に支えられて、元気に過ごせていることに感謝しつつ、美味しい調味料の完成を待ちたいと思います^^
「美味しい調味料」で思い出しました。
先日、神戸南京町で購入した台湾の調味料「腐乳(フールウ)」。
塩気と旨みが強くて、なんだかイカの塩辛みたいです。
お粥のおかずにぴったり。
隠し味にも、威力を発揮しそうで、お気に入りです^^
ラベルを見ると、自分でも作ってみたくなりました!(^^)!
これもまた、近い機会に^^