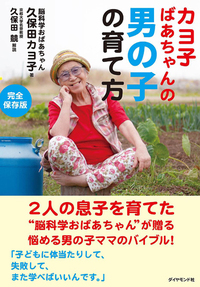男の子の“やる気
親がほんのちょっと変わるだけで、男の子はぐんぐん伸びる!
やる気、チャレンジ精神、コミュニケーション力、将来の力になる基礎的学力、そして、やさしさとたくましさ……。一般に女の子より成長が遅いとみられがちな男の子ですが、その「成長の特性」を知ることで、自分の力でぐんぐん成長しながら、よいところを開花させ、自立できる子に育ちます。
男子教育のエキスパートである著者が、男の子の育て方に不安を感じている親(とくに母親)の悩みに寄り添いながら、無理なく楽しみながら実践できる毎日の「ちょっとした子育て習慣」、また「家庭学習」や「生活習慣」の身につけさせ方など、“具体的なヒント"でアドバイス!
『男の子の“やる気”を引き出す魔法のスイッチ』
3 Introduction 親がハッピーなら子どももハッピー
なんてすばらしい仕事なのでしょう。
子どもが生まれたとき、あなたはそんな仕事を神様から任されたのです。
さて、もう一つの目的は、親(教育者)の側にあると私は考えています。
つまり、二つ目は、親(教育者)が子育て(教育)という仕事を通して成長し幸せになること。
私たちは人間として幸せになるためにこの世に生まれてきました。
そして、子どもを育てるというすばらしい仕事を通して、人間的に成長し、より幸せな人生を歩んでいくことのできる機会をあたえられているのです。
この二つの目的は、表裏一体のようなところがあります。
子育てを通して親が成長すれば、子どももより成長するからです。
たとえば、この本を読んで何かのヒントに取り組む人は、きっと自分の親としての成長を感じるようになるはずです。
そしてそれは、きっと子どもにもよい影響をあたえます。
またふつう、子どもが喜んでいれば、親もうれしいものですね。
同じように、親が笑顔であれば、子どもも笑顔でハッピーになります。
4
逆に親が不機嫌であれば、子どもは不安定で満たされない心の状態になります。
﹁子は親の鏡﹂とはよく言ったもので、子どもの内面は親に似てくるのです。
親がちょっと変わるだけで子どもはみるみる変わる
子育てはすばらしい仕事ですが、やはり疲れますよね。
とくに男の子をもつお母さんは、子育てに疲れている人が多いようです。
﹁男の子って、言うことを聞かない、もう、たいへん﹂という声をよく耳にします。
私が知っているあるお母さんは、怒らない子育てがよいとわかっているものの、ついつい現実のわが子にイライラして叱りつけ、毎日ストレスがたまり気味でした。
子どものかわいい寝顔を見ながら﹁明日から、いいお母さんになるからね﹂と決心しつつも、翌日になるとまたガミガミ言ってしまう。
日々その繰り返しで、そんな自分が嫌になり、すごく悩んでいたそうです。
けれど、そのお母さんもあるときから、子育てに対する考え方をちょっとポジティブに変えただけで、次第に子育てが楽しくなってきたのです。
ちょっと意識を変え、考え方を変えるだけで、子育てはラクになり、楽しくなります。
そして、お母さんがそんなふうにちょっと変われば、男の子は変わってきます。
プレッシャーなしに親の言うことが聞けるようになり、自主性が育っていきます。
5 Introduction 親がハッピーなら子どももハッピー
男の子には男の子にあった子育てが効果的
私は私立小中一貫の男子校で教えていた
23
年間、どうすれば男の子を伸ばすことができるか、仲間とともに、日々、悩みながら、いろいろなことを実践してきました。
そうして、先輩・同僚の教師や親御さんたち、子どもたちから、じつに多くのことを教えていただきました。
それを一言でまとめると、男の子を伸ばすには男の子にふさわしいやり方があるということです。
もちろん個人差はありますが、一般に男の子と女の子は興味・関心、成長のスピード、能力の得意分野、行動や学習態度、脳のはたらきなど、あらゆる違いがあります。
ですから、しつけ、生活習慣、学習習慣など、目標とすることは同じであっても、男の子と女の子では、まず同じようにはいきません。
その子にあったやり方であることはもちろんのこと、男の子にあったやり方でアプローチしたほうがより効果的なのです。
この本では、私がこれまで多くの方から教えていただいた、また、実際に実践して大きな成果が得られた男の子の育て方の基礎となる考え方や、やる気を引き出す魔法のようなスイッチをハッピーヒントとして、つぎのように5章に分けて紹介していきます。
6
第1章 親の意識がほんの少し変わるだけで男の子はぐんぐん伸びる
第2章 男の子のやる気やチャレンジ精神を伸ばす
第3章 男の子のコミュニケーション力を伸ばす
第4章 将来の力になる基礎的学力を伸ばす
第5章 男の子のたくましさとやさしさを伸ばす
家庭でできるたいせつなことは、親が勉強そのものを教えるというより、将来、子どもが自分自身で人生を切り拓き、幸せになるためのしつけや生活習慣づくりです。
やろうと思えば、いますぐにでもできることばかりです。
でも、早く早くと急ぐ必要はありません。
また、すべてを実践する必要もありません。
お子さんにとってこれはいいなと思うものを一つずつ、親子で楽しみながら取り組んでいただければと思います。
急がずに、少しずつ、笑顔で、スイッチオン!
子育てを楽しみ、親子ともども幸せな毎日を送っていただければと願っています。
Introduction ︱︱親がハッピーなら子どももハッピー
2 男の子がわかれば子育てはラクになる
12
現実の男の子ってこんなもの
!?
16
男の子って、めんどくさがりやだけど、好奇心旺盛
!?
20
しつけはニコニコ「太陽ママ」が基本
24
結果を急がず長い目で
28
前向きな心、肯定的な心、感謝の心で
32
COLUMN ① ……男の子と女の子のさまざまな違い
36
C O N T E N T S
親の意識がほんの少し変わるだけで
男の子はぐんぐん伸びる
第1章
親の言葉が前向きだと男の子は前向きになれる
38
親に肯定されると子どもはやる気満々に!
42
夢があるからがんばれる
46
具体的な目標があると具体的な行動ができる
50
子どもがぐんぐん伸びる「上手なほめ方」5原則
54
勉強を「おもしろい」「楽しい」と思わせると、やる気が育つ
58
勉強がゲームやクイズだと男の子は燃える 62
動き出せば、やる気がでてくる
66
COLUMN ② ……男の子をやる気にする言葉かけ
70
話を聞かない男の子もちょっとしたコツで聞くようになる
72
親の言葉かけ次第で男の子は伸びる
76
男の子のやる気やチャレンジ精神を伸ばす
男の子のコミュニケーション力を伸ばす
第3章第2章
家庭学習の習慣をつけるリビングでの勉強 98
リビングに辞典や地図帳を置いておくと子どもは賢くなる
102
「読み聞かせ」が聞く力、読む力、集中力などをぐんと伸ばす
106
読書をすると学力的にも人間的にも成長していく
110
子どもはむずかしい漢字でも本当は好き
114
国語辞典はひらがなが読めれば今日から使える
118
子どもは俳句も好き
122
親子日記、手紙で文章力がぐんぐん伸びる
126
COLUMN ④ ……男の子が楽しめて大人も感動する絵本
130
親は男の子の会話力を伸ばす最高の先生
80
親以外の人にも伝わらなければ、子どもの願いはかなわない
84
親の伝え方が子どものコミュニケーション力を左右する
88
クイズの出し合いが会話と思考のトレーニングになる
92
COLUMN ③ ……男の子の「コミュニケーション力」をみるチェックポイント
96
将来の力になる基礎的学力を伸ばす
第4章
おわりに︱︱男の子はお母さんが大好き
166
お手伝いをさせるとしっかりした子になる
132
自然の中で遊ぶとたくましくなる
136
ガマンをすることで忍耐力や克己心が育つ
140
子どもどうしのケンカは成長のきっかけになる
144
「英雄的瞬間」を戦うと心が強くなる 148
運動や遊びを通していっそうたくましくなる
152
男の子はしっかりした男性と接してたくましく成長する
156
親の愛によって子どもの生きる力は育つ
160
COLUMN ⑤ ……男の子の子育てmini
Q&A
165
男の子のたくましさとやさしさを伸ばす
第5章
12
男の子って宇宙人?
男の子って不思議な存在ですね。とくに、母親にとってはそうでしょう。
わが子でありながら、自分とは違うところがいくつもあります。
たとえば、遊んで服が汚れても気にしない。その汚れた服をずっと着ていても気にしない。
脱いだらそこらにほうりっぱなし。雨が降っても傘をささない。水たまりの中に平気で入っていく。危ないのに高いところに登りたがる︙︙。
女性であるお母さんにとっては、ちょっと受け入れがたいことですよね。
「ちょっと、何やってるの?」「どうしてこんなことばかりするの!?」と言いたくもなります。
「もう、ちゃんとしなさい!」と叱られると、男の子は、そのときは親の言うとおりにするかもしれません。
男の子がわかれば
子育てはラクになる
13 第1章 親の意識がほんの少し変わるだけで男の子はぐんぐん伸びる
でも、ほとんどの場合、またしばらくすると同じことをするでしょう。
わかっていてもそうしてしまうのです。それが男の子です。
「なんでやらないの?」
「なんでちゃんとできないの?」
これまで何度言われてきたことでしょう。
でも、男の子に「なんで」と聞いてもあまり意味がありません。
別に深い考えがあるわけではなく、本人もうまく説明できないでしょう。
ふざけているわけでもなく、ましてや親を困らせようとしているのでもなく、言ってみればやる気になれないからです。
女の子なら、「ちゃんとしないと恥ずかしいから」とか「やらないと怒られるから」と意識します。でも、男の子はそこまで気がまわりません。
それに、怒られるとわかっていても、やりたくないものはやらないですませたいというのが平均的な男の子です。
そこが、女性であるお母さんには理解しづらいところでしょう。
「お母さんの言うとおりにしなきゃな」と思っても、お母さんとは意識が違います。言ってみれば、ちょっと「めんどくさい」のです。
男の子は、「めんどくさい」のが苦手です。
14
お母さんにとって楽しみなこと、たとえば、買い物、洋服選び、おしゃべりなどは、平均的な男の子にとっては「めんどくさい」のです。
そんな男の子ですから、お母さんにとっては不思議な生き物。そして、なんともかわいいけれど、悩みの種にもなりうるのです。
教育熱心なお母さんなら、そういう男の子の不可解な言動に、ある時期は悩まされるものです。悩むほどでなくても、「ああ」「もう!」「何やってるの!」
と、毎日同じ言葉を何度も繰り返すことになります。
そんなため息まじりの言葉が、女の子を育てるときよりも、何倍も多いはずです。
それでも、男の子はたいてい聞きません。わかっているけれど、やらない。
お母さんにとって当たり前だと思っていることが、男の子にとっては当たり前ではないのですね。
そのギャップがお母さんをイライラさせ、ストレスを生み出してしまうのですね。
「ぜんぜん言うことを聞かない」「子育てがうまくいかない」と悩む人のほとんどは、男の子のお母さんです。
15 第1章 親の意識がほんの少し変わるだけで男の子はぐんぐん伸びる
男の子の子育ては楽しい!
でも、お母さん、だいじょうぶです!
息子さんがダメなのでも、お母さんの育て方が間違っているわけでもありません。
これまでの経験でおわかりのように、わが息子でありながら、お母さんにとっては「なんでそんなことするの?」というようなことばかりするのが男の子というものなのです。
そんな男の子を育てていくのは、「たいへん」なことでしょうか?
いえいえ、もちろんたいへんなことはあるでしょうが、けっこう楽しいこともたくさんあり
ますよ。
親の意識がほんの少し変わるだけで、男の子の子育ては変わってきます。
まずは、「そうか、男の子ってこんなものか」と理解するだけで、子育てがラクになります。
男の子の子育ては悩んであたりまえ。
62
「うちの子、ゲームばかりしている」
「何かに熱中していると、話しかけても聞こえていない」
こういった声は、男の子をもつ親に多くあります。
男の子は、一つのことに集中できる傾向があり、興味を抱いたことに没頭してしまう脳をもっています。勉強は気分がのるとやるのですが、のらなければ、まず手もつけません。
宿題よりも遊ぶほうが当然楽しいので、たいていあと回し、というのが平均的な男の子です。
このような男の子をやる気にさせるには、どうすればよいのでしょうか。
好きなことで﹁やる気﹂を引き出す
勉強がゲームやクイズだと男の子は燃える
63 第2章 男の子のやる気やチャレンジ精神を伸ばす
男の子の場合、勉強はやらなければならないことであるのはもちろんですが、むしろ勉強はおもしろいものだと思わせることです。
どんな勉強でも、興味をもたせることがたいせつなのです。
たとえば、車の好きな子なら、算数の文章題には、車の数を計算させる問題をつくって解かせたり、つくらせたりすると、興味をもって取り組めます。
サッカーの好きな子なら、ワールドカップに出てくる国を話題にします。
サッカーの強いスペイン、ドイツ、イタリア、ブラジルなどは、地図の上ではどこにあって、どんな国かを調べると、しぜんと地理の勉強ができます。
昆虫の好きな子なら、いっしょに昆虫採集をしたり、昆虫のことを調べさせたりするのです。
すると理科が好きになり、図鑑を読むことで、読書習慣もつきます。
興味をもち、「おもしろい!」と感じるようになれば、男の子はのめり込みます。
そして、どんどん自分から、遊び感覚で、勉強をしていくようになります。
男の子の勉強には遊び要素を取り入れる
また、勉強をゲーム化すると男の子は燃えます。
女の子はグループで協力し、教え合いながら学習するのが好きで得意です。
64
しかし、男の子は協力よりも競争によって意欲が高まります。
「さて、どの班が一番かな?」
「誰が早いかな?」
そんなふうに意識させるだけで、男の子の集中度は全然ちがいます。
男の子は、ふつうに練習やおさらいの勉強をするよりも、ゲーム化したほうが
10
倍盛り上が
ります。
たとえば、漢字のしりとりゲーム。
このゲームのルールはカンタン。つぎのような説明でじゅうぶんです。
「漢字を使って熟語のしりとりをしていくゲームです。最初、中井という漢字をノートに書いて、つぎは井が頭につく熟語を見つけて、どんどん書いていきましょう。
たとえば、中井→井戸→戸口→口紅……というようにね。
さて、5分でいくつできるかな。国語辞典を使ってもいいですよ。
では、えんぴつを持って。ようい、はじめ!」
こんなカンタンなゲームに、男の子たちはむちゃくちゃ真剣に取り組むのです。
一番たくさん書けた子は、それはもう大得意。
他の子はくやしがって、「先生、もう1回やりましょう!」と言い出すほどです。
2回目以降は、自分との競争もできるのがよいところです。
65 第2章 男の子のやる気やチャレンジ精神を伸ばす
「1回目の自分よりも、たくさん書けた人?」と聞くと、多くの子の手があがります。
1回目より進歩したことがわかれば、それなりに達成感を感じることができます。
あまり書けなかった子はくやしがって、その後、ふだんの漢字の練習を真面目に取り組むようになります。
また、クイズも大好きです。
「では、クイズを出します。山のつく県名は、いくつあるでしょう?」
問題を出すと、地図帳をめくりながら必死で探し出します。
こんなふうに勉強にゲームや遊びを取り入れると、燃えてくるのが男の子です。
ゲーム感覚で勉強に夢中にさせる。
88
子どもが単語ばかりで伝達しようとする背景には、親のマネをしている場合があります。
ですから、親も省略せずに伝えるということを意識するとよいです。
ところが、やや感情的になっているときは、誰でも投げつけるような厳しい言葉の言い方になりがちです。それでは子どもは受けとめられません。
言い方を少し変えるだけでよい
以前、レストランで食事をしているときに、となりの親子の会話が聞こえてきたのですが、若いお母さんが4歳くらいの男の子に矢継ぎ早にこう言っていました。
「ほら、お箸! ひじ! ちゃんとしなさい」
親の伝え方が子どものコミュニケーション力を左右する
89 第3章 男の子のコミュニケーション力を伸ばす
その子は、そう言われて、お箸を動かしたり、ひじを見たりするのですが、すぐには改まりません。
その子を見て、私はこの年齢なら仕方ないなと思ったのですが、当のお母さんは、「もう、ちゃんとしないと、今度から連れてこないからね」
そう言って、かなりご立腹なようすなのです。
子どもは、いまにも泣き出しそうでした。
それを見ていたお父さんが、割って入り、穏やかな声でこう言いました。
「○○ちゃん、お箸をこういうふうに持ちなさい」
すると、その子はお父さんのマネをして箸を持ちかえました。
「じゃあ、今度はひじをつかないで食べなさい」
すると、その子はひじをテーブルから上げました。
「よし、それでいいよ」
お父さんはにっこり。
子どもはお母さんの顔を見て、「これでいいの?」という表情でした。
お母さんは、「○○ちゃんは、パパの言いつけはよく聞くわね。ママの言うこともちゃんと
聞いてね」と言っていました。
私は、このお母さん、ちょっと勘違いをしているなあと思ったものです。
90
読者の皆さんは、もうおわかりでしょう。
この子がお母さんの言うことを聞けなかったのは、お母さんの言葉の使い方にあります。
お父さんは、言葉を省略せずに伝えていました。
しかも、穏やかに、動作も交えて。
ですから、子どもは受け入れることができたのです。
さらに、お父さんは「よし、それでいいよ」と笑顔で認めてあげていました。
このようなことをお母さんもしていたら、同じように子どもは反応していたと思うのです。
子どもがキャッチできる言葉にする
ある親は怒っているとき、「どうしてそんなことするの?」「ちゃんとしなきゃダメでしょ」
「どこ行くの?」とやや感情的になって叱りつけます。
しかし、子どもは、どうやら怒られているのはわかるけれど、どう行動すればよいのか、よくわかりません。
子どもに指示をする場合は、具体的にどうすればよいのか、子ども自身がわかるように言ったほうがよいのです。
91 第3章 男の子のコミュニケーション力を伸ばす
例 「どうしてそんなことするの
!?
」↓「生き物をいじめたらダメよ」
「ちゃんとしなきゃダメでしょ!」↓「椅子にすわっておこうね」
「どこ行くの
!?
」↓「戻っておいで」
穏やかに具体的に言えば、子どもは受け入れやすいのです。
教師が授業をするときもそうですが、あいまいな言葉では、子どもはどうしてよいかわからず、あるいは思い思いに解釈して、混乱します。
しかし、的確な指示があたえられれば、たいていはその通り動くものなのです。
子どもをしつけるとき、言葉を省略せずに具体的に伝えることを意識しましょう。
そういう言い方を親がしていると、子どもも人に自分のメッセージを伝えるとき、相手がわかるように配慮して言葉を選ぶ能力を身につけていくようになります。
子どもへの指示は省略せずに具体的に伝える。
114
漢字に強くなれば、内容豊かな言葉をたくさん覚え、味わうことができます。
そうすれば読む力もついて、読書が楽しくなり、国語力はぐんぐんついていきます。
漢字はむずかしいから、子どもは嫌がるかというと、そうでもありません。
子どもは漢字が好きです。
男の子は、何度も同じ漢字を練習するのはめんどくさがっても、新しい漢字を勉強することには意欲的です。
とくに、読むのは好きです。
漢字指導において第一人者である教育学博士の石井勲先生は、長年の研究の結果、つぎのようなことを主張されています。
子どもはむずかしい漢字でも本当は好き
115 第4章 将来の力になる基礎的学力を伸ばす
①低学年の子どもほど、ひらがなより漢字のほうが読むのはやさしい。
②漢字の読み書きを同時に学習するより、まず読めるようにしたほうがよい。
これには、私も賛成です。
ところが、現在の学校の国語教育では、まずひらがなから、そしてだいたい画数の少ない漢字から読みと書きを順に習わせることになっています。
また、その学年で教える配当数(1年生なら80字)も決められています。
しかし、実際に教えてみると、小学1年生でも、小学6年生の配当漢字を難なく読めるようになるのです。
いやむしろ、幼い子どもたちは漢字を絵や図のようにイメージでき、興味をもってどんどん覚えていくことができます。
小学1年生はすぐに漢字を読めるようになる
私は小学1年生の担任のとき、入学式の日から子どもたちに漢字を教えました。
「学校」「一年生」の読み方を尋ねると、すでに読める子どもが多かったものです。
「四月八日」「月曜日」などは、教えてあげればすぐに読めるようになります。
昔話を語りながら、登場してくる「熊」「お団子」「川」などの漢字のカードを見せていく
116
と、話が終わったときは全部読めるようになっています。
日常的にも、子どもたちへの連絡として、黒板にわざと漢字を使って書きました。
おはようございます。
朝の会に先生が来るまで、
教室の机の中を整理して、
読書をしましょう。
すると、みんな、これを読んで、読書をしながら待っていてくれます。
「教室」「机」「整理」「読書」も2年生以上で習う漢字ですが、子どもたちは日常的によく耳にしますし、目にします。
そういう漢字は、その配当学年まで待たずに、ふつうに使っていれば、子どもたちもしぜんに読めるようになります。
親子で漢字学習を楽しむ
家庭でも、子どもに漢字を教えることができます。
117 第4章 将来の力になる基礎的学力を伸ばす__















 岡田知也氏
岡田知也氏



 久保田カヨ子(くぼた・かよこ)
久保田カヨ子(くぼた・かよこ) 久保田カヨ子(くぼた・かよこ)
久保田カヨ子(くぼた・かよこ)