こんばんは、たこーすけです。
「らき☆すた」第3話を視聴しましたので、その感想を書きたいと思います。
原作は未読です。
以下、「らき☆すた」第3話までの内容、ネタバレを含みます。未見の方は御注意下さい。
Last modified: 2007-04-29 23:40
目次
[世界史未履修問題]
[何のパロディなのか]
[もう一人のレギュラー陣]
[世界史未履修問題] (目次へ)
「らき☆すた」第3話には、たくさんのパロディネタがありました。
ぼくは、恥ずかしながらあまり知識がないもので、その場で即座にはわからないものも結構ありました。
「ウェディングピーチ」も知りませんでしたし、
「ドラクエ」もIIIまで、いやIIかな?までしかやったことがないですし、
「クロマティ高校」は知っていましたが、「ぱにぽに」は読んだこと観たことがないのです。
あと「あたしンち」も読んだこと観たことがない…
といって、元ネタがわからなかったから面白くなかったかというとそんなことはなく、知らないなりにも、楽しく観ることが出来たと思います。
こういった元ネタが即座にわかる人は、教養があるなあとぼくは思います。
アニメや漫画やゲームの知識を「教養」と呼ぶのか?と思われる方もいらっしゃると思いますが、ぼくはそれらは「教養」であると思います。
あるいは、昔やっていたTV番組や昭和歌謡とかを覚えていて、その知識をしっかりと使うことができるのも、「教養」だとぼくは思います。
もう少し固めにいって、
前回も触れた「空飛ぶモンティ・パイソン」を再び持ち出せば。
例えば、こういうスケッチがあります。
「The Spanish Inquisition(スペイン宗教裁判)」
(会話のやりとりがあった後…)
俺をスペインの宗教裁判みたいに責めないでくれ!
(その台詞を合図として、扉から真っ赤な服に身を包んだ異端審問官が登場)
まさかの時にスペイン宗教裁判!
我々の武器は「驚愕」…
「驚愕」と「恐怖」。
あ。つまり二つ。
「驚愕」と「恐怖」、そして「冷酷」。
や。つまり三つ。
「驚愕」と「恐怖」と「冷酷」、そして「法王への服従」!
いや、つまり四つ。ちょっと待って。
つまり、我々の武器は「恐怖」と「きょ…」、やり直し!
(退場する異端審問官)
…
このように、テンポよく数がどんどん増えていくところがとても面白いスケッチです。
この回ではこの後も、「スペイン宗教裁判」という単語が出る度に、彼らは「まさかの時にスペイン宗教裁判!」と言って飛び出してきます。
そして、「言葉の勘違い」からくる間抜けな拷問などをしたりします。
下敷きは15、16世紀の「スペイン異端審問」です。
これは、本来キリスト教の中で異端の信仰を持つ者を裁くはずの「異端審問」を政治利用し、ユダヤ教徒やイスラム教徒を迫害したという点において、キリスト教史に暗い影を落としているもののようです。
裕福なユダヤ人の財産を没収する狙いがあったともされています。
Wikipediaの絵にあるように、審問官はこのように真っ赤な服に身を包んでいたのでしょう。
また、告発者は秘密とされ、しばしば無実の人が恨みから、あるいは報奨金目当てに訴えられることも多かったようで、その「理不尽さ」もこのスケッチでは描かれているように思います。
「スペインの宗教裁判みたいに…」という台詞が出てくるだけで、彼らが飛び出してくるのも、その恐怖政治的な有様を表していると思えます。
そして、このスケッチ中の審問官の一人は、なぜか頭に飛行機のゴーグルをつけているのですが、これは、第一次世界大戦でのイギリスの撃墜王・ビグルス(架空の人物?)を表していて、審問官長に「ビグルス!」と呼ばれると客席から笑いが起きます(「客席」ではなく「ドリフの大爆笑」のような、笑いのSEだと思いますが)。
このような元ネタは「教養」であるといってよいでしょう(全てGoogle先生やWikipediaのおかげです)。
そして、これと同じように、アニメや漫画やゲームに関することも、ぼくは「教養」なのだと思うのです。
そもそも「教養」とはなんでしょうか。
「教養がある人」とはどんな人でしょう。
ぼくは、「広範な知識を、適切に使用することが出来る人」だと思っています。
「適切に使用することが出来る」をもっと具体的に言えば、「会話などのコミュニケーションに、『笑い』を持たせるように使うことが出来る」となります。
この「笑い」を「エスプリ」や「ウイット」や「ユーモア」といった単語に置き換えてもよいでしょう。
「あの人は教養がある」と言ったとき、皆さんはどのようなイメージを持つでしょうか。
幅広い知識を持っている人なんだろうなと思うのではないでしょうか。
そして、そのような「幅広い知識」とは、実生活でそんなに役に立たないものであるとも思うのではないでしょうか。
各人の実生活、つまり仕事や専門領域において必要とされる「知識」は、「教養」とは呼びそうにないですよね。
その人の「専門、本流」から外れている知識。これが「幅広い知識」であることでしょう。
つまり、一見、無駄なこと。
「効率の良い」生活を営もうとするのであれば、無駄なこと。
でも、そんな無駄なことが、人と人との関わり合いを、とても豊かにするのではないでしょうか。
「教養」とは、そういうものなのではないでしょうか。
ネタを繰り出し、そしてそれを受け取ることが出来る。
「らき☆すた」を作る京アニも、そしてそれを観て楽しんでいる視聴者の皆さんも、教養があるなあとぼくは思わずにはいられないのです。
昨年(2006年)に発覚した「世界史未履修問題」。
詳細はWikipediaにお任せしますが、
受験の追い込みの時期に、試験科目でない教科の補習を突然に受けなければならなくなった受験生の方々は本当に気の毒であると思いますし、かといって、その教科をカリキュラム通りに履修していた受験生の方々にとっては、本当に不公平極まりないことだと思います。
これは、授業時間数が減少しているのに、教科はむしろ増加したことがその原因なのだと思いますが、ではどうしたらよいのかといっても、ぼくにはわからないところです。
昨年度の受験生の方々は、昨年あるいは卒業前に補習して、最終的には履修したのだと思いますが、昨年度以前の卒業生の方々は未履修のままになってしまっているのでしょう。
ぼくは、「世界史未履修問題」は、「世界史を学ぶ機会が失われた」という点にその問題があるのだと思っています。
このブログをご覧になって下さっている方は、ぼくと同世代くらいの「おっさん」wwが多いと思いますが、もしかしたら高校生くらいの方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方に、ぼくはお伝えしたいです。
しばしば、
勉強はなんのためにするのか、とか、
受験勉強で得た知識なんて将来の役に立つのか、とか耳にします。
テストや受験が終わったら、すぐに忘れてしまうような…
そんなものは役に立つのか、と。
それに対し、「役に立つ」ではなく「役に立たせる」ようにするのだ、ということをよく耳にします。
その通りだとぼくは思います。
そして、どのように「役に立たせる」のかというと、ぼくは、「『笑い』を繰り出したり理解するために使うのである」と答えたいです。
元ネタを常識として共有していないと、「笑い」は成り立たないのです。
高校生、受験生の皆さんは、いま、「元ネタ」を毎日毎日仕込んでいるのです。
世界史や日本史、古典や漢文などに、「元ネタ」は顕著だと思いますが、物理や数学や化学とかだって、その例にもれません。
皆さんはいま、「元ネタ」を「勉強」しているのです。
そしてその詳細は、すぐに忘れてしまってもいいのだと思います。
「みWikiさん」のように、淀みなく出てこなくてもいいのです。
授業や受験で、ある意味、強制的に習ったことは、その詳細を忘れてしまっても構わないと思います。
大事なのは、大まかな概略を覚えていることと、どの辺りを読めばその詳細がわかるのか知っていること、なのだと思います(最も大事なのは、内容の「理解」をしていることであるのは論を俟ちません。そして「暗記していること」と「理解していること」はもちろん違います。「理解」とは、各人の中で自身の「経験」に結び付け照らし合わせた後の「一般化」であると思います。したがって、内容の「詳細の暗記」を必要としません)。
もちろん、スラスラと出てくれば一番よいのですが、でも、「教科書や辞書や参考書や文献のこのページの辺りを見れば詳細はわかる」というのでも、最低限、「元ネタ」を受け取ることは出来ると思います。
そしてそういうことは、一度、授業や受験で強制的に習っていると、そして内容を「理解」していると、なかなか忘れたりしないものです。
「世界史未履修問題」は何が問題であったか。
ぼくは、彼らから「元ネタ」を理解する機会が奪われてしまったことだと思います。
なんのために勉強するのか。
ぼくは、「笑い」を理解し、また繰り出すために勉強をするのだと思います。
それが、「教養」なのではないでしょうか。
そして「教養」とは、実生活には何ら役に立たない、無駄なものであるとぼくは思います。
しかし、「無駄なもの」であるからこそ、ぼくたちの精神を豊かにしてくれるのではないでしょうか。
ぼくは、アニメや漫画やゲームも「教養」であると思うのです。
[何のパロディなのか] (目次へ)
さて、前述の通り「らき☆すた」第3話にはパロディネタがたくさんあったわけですが。
一口に「パロディ」といっても、その様式は多様であるように思います。
先に挙げた例は、なんというか、「引用によるパロディ」といった感じのものだと思います。
こなた達が会話において、例として引用しているような様式です。
パロディにはこういうものもあると思います。
先ほどの「空飛ぶモンティ・パイソン」の「The Spanish Inquisition(スペイン宗教裁判)」もそうなのですが、「ひょうきん族」の「ひょうきんベストテン」や「とんねるず」による「仮面ノリダー」のようなパロディです。
これらは、元ネタを引用しているというよりは、元ネタの形式を模倣している様式といえましょう。
「パスティーシュ」といった方がわかりやすいかもしれません。
「らき☆すた」にはこのようなパロディもあると思います。
OPの「美水かがみ劇場」は「世界名作劇場」でしょうし、また台詞は「怪物くん」のOPの模倣でもあります。
そして、次回予告は「サザエさん」の形式を模倣しています。
でも、それ以外にもあると思います。
それは、どこか。
教室でのこなたとかがみの会話、コナンとか金田一が出てくるところ。
二卵性双生児の話の後の電車の中。
あるいは第2話でも。
勉強会でのかがみの、
「宿題写すのはいいけどね。自分でしっかりやらないと、休み明けのテスト、ひっどい結果になっちゃうわよ?」
というところ。これは第1話の後の次回予告でも使われたカットです。
これらのシーンでぼくは、ある作品を思い出していました。
それは、なにか。
それは「涼宮ハルヒの憂鬱」です。
「漫画とかドラマの探偵って、みょーに殺人事件ばっか遭遇するよね。コナンとか金田一とかさ」
「そうしないと、お話が成り立たないでしょう?」
ぼくはここで、「孤島症候群(前編)」でのデッキ上の古泉くんとキョンの会話を思い出しました。
電車の中。
こなたが制服の中まで扇いでいるその前で、目のやり場に困っている「メガネをかけたサラリーマン」。
ぼくはここで、「ハルヒ」のCMを思い出しました。
ハルヒに扮した平野綾さんが、都電の中で、「宇宙人、未来人、超能力者がいたら私のところにきなさい…」と呟いているバージョンです。
その平野綾さんの目の前に座って困惑している「メガネをかけたサラリーマン」。
このサラリーマンを扮しているのは、「ハルヒ」のシリーズ演出であり「らき☆すた」の監督である山本寛さん。
このCMと、今回の「らき☆すた」の電車の中のシーンは、その構図が全く同じであると思います。
そして、勉強会でのかがみ(第1話後の次回予告でも使われたカット)の指をこちらに向けたカットは、あまりにも、あの特徴的な「ハルヒのポーズ」に似ているといったら言い過ぎでしょうか?
他にも「ハルヒ」を連想させるものはありました。
七夕だってそうですし。
ポニーテールだってそうでしょう。
OPのダンスおよびチアだって、「ハルヒ」のOPやEDを連想させます。
ちょっと強引かもしれませんが、図書室の電気を消してしまったみゆきさんに、こなたが「いわゆる一つの萌え要素。みゆきさん、グッジョブ!」と言うところだって、ハルヒがみくるに言っているようにさえ聞こえてきます。
それにそもそも、「本編」を劇中劇と位置づけるのなら、それは「朝比奈ミクルの冒険」の形式に他ならないわけです。
そのように。
「らき☆すた」は、「涼宮ハルヒの憂鬱」のパロディになっているといえるのではないでしょうか。
では、その狙い、意図するところはというと…
ちょっとまだ、ぼくには考えが及びません。
しかし、パロディ化することは、元作品を客観視することであり、さらに言えば、突き放して相対化することでもあるのだとすれば。
「らき☆すた」で「ハルヒ」のパロディ、パスティーシュをすることは、「妄想界の住人は生きている。」のだんちさんが仰っている、
>「夢を見せながら夢から醒ます」方法論を手に入れること。
> 同時に、平野綾さんが演じる女の子は虚構の人物だよ、ということを改めて印象付けること。
(「妄想界の住人は生きている。」の『「らき☆すた」第3話を見た。』の後半より)
のためではないかと思えます。
あるいは、少なくとも、その論を補強する根拠の一つになるのではないかと思います。
[もう一人のレギュラー陣] (目次へ)
さて、「どうなの?レギュラー陣」のレギュラー陣は、こなた、かがみ、つかさ、みゆきさんなわけですが。
「本編」だけでなく、「らき☆すた」全体で見れば、あきらさんと白石みのるくんも毎回登場する「レギュラー陣」なわけです。
皆さんは、もう一人、毎回登場している人物にお気づきでしょうか?
第1話の「らっきー☆ちゃんねる」でおハカギを出した人物。
第2話の「こなたとつかさの画面2分割」中のテレビドラマに出ていた人物。
そして、
第3話の「電車の中」にいた人物。
そう、山本寛監督です。
第1話の「らっきー☆ちゃんねる」でおハカギを出したのは、「大阪府のベリ工大好きっ子さん」です。
これは、どう考えても、「Berryz工房」好きな山本寛監督であるとしか思えません。
「ハレ晴レユカイ」の振り付けの元ネタが、「Berryz工房」の振り付けであることは、皆さんもご存知のことでしょう。
第2話のテレビドラマ中の、「メガネをかけた」人物の台詞は、
「10年一緒にやってきた会社の先輩に、まだ名前を覚えてもらえてません…『ゆたか』です…」
です。
「山本 寛」は「やまもと ゆたか」と読みます。
ぼくも最初は「ひろし」かなとか思っていました。
第3話の電車の中は、前述の通りです。
このように、毎回、山本寛監督は、ヒッチコック監督のようにどこかに姿を見せています。
今後も、毎回、画面上のどこかに登場してくるのではないでしょうか。
もう一人のレギュラー陣。
それは、山本寛監督。
今晩からスタートする第4話でも、きっと姿を見せることと思います。
「らき☆すた」。
そんな楽しみ方も、いかがでしょう。
(出てこなかったら、ごめんなさい!)
それでは!
(TOPへ)











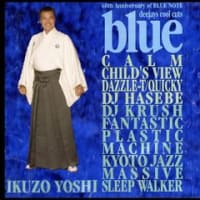
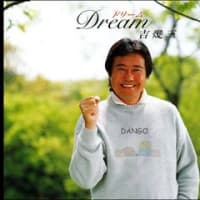

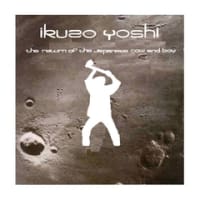
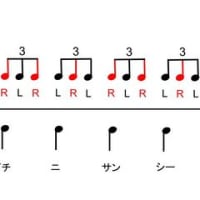
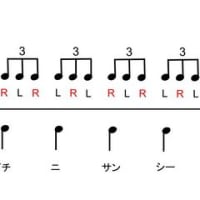
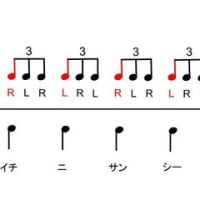
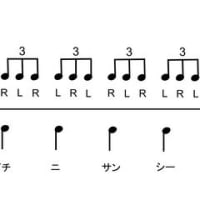
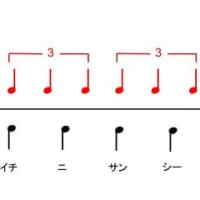
ようやく、3話の感想が書き終わりました。
ブログへのコメント・トラックバック、有り難うございました。返事が遅れて、申し訳ありません。
『らき☆すた』の監督、交替なんですね。
色んなサイトを見ていると、『ネタじゃないの?』という意見もあり、まだ4話を見ていない身では何も言えませんが、僕もネタだったらなぁ、と思います。
もし本当にネタだったら、京アニは凄すぎます。
兎に角、4話をしっかりと観たいと思います。
コメントをありがとうございます!たこーすけです。
拝見しました!
ぼくも、最近、「レギュラー陣」は「実在の人物(声優さん)」を指しているのではないかとも思うようになってきています。
トラックバックまた送っちゃいました。
yukitaさんも、どしどし送ってプリーズ!
というか、弾いちゃっていますか?もしかして。
監督交代が「ネタ」かどうかは、とても悩ましいところです。
「週間らっきー☆ちゃんねる」第3回での「あきら様の喫煙描写削除」さえなければ、ぼくも「ネタ」だと思えるのですけれども…
それさえなければ、あとは、「第4話」をどう受け止めるかなのだと思います。
監督交代は「ネタ」か否か。
yukitaさんをはじめ、これから第4話を視聴する皆さんがどう受け取るか、とても興味深いです。
楽しみにしております。
それでは。
たくさんありました。
また遊びに来させて下さい^^