(その2)からの続きです。
[4分の3拍子]
さて、その渚ですが。
岡崎さん、伊吹先生をご存じだったんですか?
前に、店に誰もいなかった時、早苗さんのパンをあげたんだ。
渚ちゃんのボーイフレンドだったんですか。
違いますっ!
…即答。
あっ、いえ!わたしが岡崎さんを嫌いという意味ではなく!
その…岡崎さんにはもっと素敵な人が…
もうおつきあいしてる方がいらっしゃるんですか?
いやいや。そんな相手は、いませんけど。
…そうなんですか?
チャンスですね、渚ちゃん。
はっ!…は…はっ…は、い、いまのは聞かなかったことにして下さい!
渚ちゃん、可愛いですよね。
可愛すぎます、渚!
もうまじでやばいくらい可愛いです。
そ、そうだ!先生こそ、御婚約おめでとうございます!
のところの口の形とかも、ちょーいい感じ。
このシーンのBGMは、第1回、古河家食卓(「ぐー」のとこ)でのBGMと同じもの。
第1回感想では、この曲のことを、ぼくは「パットメセニー風8分の6拍子」と書きましたが、これは8分の12拍子と書くべきだったかも…と思ったら、あれ?そう書いてる。
書きなおしたのかな…たしか最初は8分の6拍子と書いたような気がするのですが。
というか、この曲。
8分の5拍子と8分の7拍子からなる変拍子なのかしらん。
Aメロ(イントロ?)、つまり、
第5回、公子さんの家の前でのシーンで言うと、
「先生!こんにちは、古河です」から
「その…岡崎さんにはもっと素敵な人が…」までの部分、
第1回、古河家食卓のシーンで言うと、
「当り前だ。娘の友だちを粗末に扱うもんかよ」「ぐー」から
「大宇宙銀河。いい名前だろ?」までの部分、
ここのメロディーを聴くと、
|6/8 + 6/8|5/8 + 7/8|
なのかな、と思ったりもします。
でも、ここのベースやトライアングルを聴くと、むしろ、
8分の7拍子+8分の5拍子かな、とも思ったり。
というか、みなさんは「8分のなんとか」ではなく、「4分の4拍子」、すなわち「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」なんじゃないのと仰るかもしれません。
じつは実際はぼくにも、そのように「4分の4拍子」に聴こえています。
こんな感じですね。

これの、3連符(「タタト」と書いたやつ)のアクセントが、変なとこ面白いところにくるメロディーでありトライアングルのリズムである、と考えた方が自然かもしれません。
では、この「4分の4拍子」をなぜ「8分の6拍子」とか書いたかといいますと、これは、便宜上の理由からです。
3連符を書くときには、上のように、音符の上に「3」と書かなくてはなりません。
ですので、この曲の楽譜を書くとしたら、曲の始めから終りまでずっと3連符が続きますので、延々と何個も何個も「3」をつけていかなくてはいけなくなります。
それは、かなり大変です。
そこで、もっと楽に書くために、3連符の1音(「タ」とか「ト」とか)を8分音符1個と考えてしまうのです。
さきほどの例の中には、「タ」とか「ト」が全部で12個あります。
したがって変換後は、次の図のように、8分音符が全部で12個、つまり8分の12拍子となるわけです。(ただし、8分の6拍子が2小節あるとして書きました)

こう書くと、いちいち「3」をつける必要がなくなります。
とても書きやすい、というわけです。
元々は3連符ひとかたまり(タタト)が、4分音符1個分(イチとか二とか)でした。
ですので、8分音符に変換後は、8分音符3個で「イチ」とか「二」になります。
つまり、符点4分音符1個が「イチ」とか「二」になるわけです。
本来は、やはり、小節数を変えたくはないので、これは「8分の12拍子」が1小節と書くべきところなのだろうなと思います。
しかし、ぼくやぼくの周りの連中は、この曲のような感じのリズム、じつはこの曲は後述するように「4分の3拍子」を感じることができるのですが、そのようなリズムのものを、昔からなぜか「ハチロク」と呼んできていますので、ここでは「8分の6拍子」が2小節、とさせて下さい。
実際、この曲は、4分の4拍子(8分の12拍子)のアクセントが面白いところにあるだけでなく、明らかに途中に「8分の5拍子」や「8分の7拍子」の小節を含んでいます。
Aメロ(イントロ)からBメロに移るとき、
また、BメロからAメロに戻るとき、
これらのときに、「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」とリズムをとっていると、ズレてしまうことにお気づきでしょうか。
第5回、公子さんの家の前で言えば、
「もうおつきあいしてる方がいらっしゃるんですか?」から「いやいや。そんな相手はいませんけど」に至る箇所(AメロからBメロへ)、
第1回、古河家食卓で言えば、
「俺の名前は岡崎朋也だ!」「うるせえ野郎だなあ」
のところ(AメロからBメロへ)、
これらのところを、「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」とリズムをとっていると、ズレてしまいませんか?
これは、ここが、
…|6/8 + 6/8|6/8 + 5/8|Bメロ開始|…
と、最後だけ8分の5拍子になる変拍子だからです。
BメロからAメロへ移るところも変拍子です。
第1回、古河家食卓での、
朋也のおかわりから渚の微笑み、「サンキュー。ここまでくれば道がわかる」に至る箇所(BメロからAメロへ)は、
…|6/8 + 6/8|6/8 + 7/8|6/8 + 6/8|6/8 + 6/8|Aメロ開始|… (← 2007-11-16 01:50 訂正しました。)
のようになっています。
ここで面白いのは、AメロからBメロへ移る際に8分音符1個分少なくなってズレてしまったのが、BメロからAメロに移るときに8分音符1個増える結果、元に戻るというところです。
ちょっとわかりづらいかもしれませんが、トライアングルのリズムパターンに注目してみて下さい。
AメロとBメロではリズムパターンが異なっているように聴こえると思います。
しかし、じつは、このトライアングルのリズムパターンは曲中ずっと、同じなのです。(← 2007-11-16 01:50 訂正しました。「ほぼ同じ」でなく、「完全に」同じです。)
AメロとBメロのトライアングルのリズム譜を書くと、次のようになります。

Aメロで一番最初にあった4分音符は、Bメロにおいては、8分音符ひとつ分ズレています(赤矢印)。
のみなず、そのあとに続く音符も、すべて等しく8分音符ひとつ分、綺麗にスライドしていることがわかると思います。
AメロからBメロへ移る際、前述のようにAメロ最後の小節は、8分の5拍子になります。
そのため、上図Aメロの一番最後の4分音符は8分音符になります。
余ったもう半分の8分音符は、はじき出されてBメロの一番最初にやってきます。
したがって、Bメロでのリズムパターンは、Aメロのそれとちょうど8分音符ひとつ分だけスライドしたものになるわけです。
BメロからAメロへ移る際は、その逆のことがおこります。
Bメロラストは途中の小節で、8分の7拍子を含みます。
ですので、先ほどとは逆に、上図Bメロの最後の小節に、一番最初の8分音符が吸収されます。
それにしたがい、つづく音符もすべて8分音符ひとつ分スライドします。
結果として、Aメロのリズムパターンに戻るというわけです。
このようにして、「リズムパターン」はずっと一定なのに、「拍子」がズレるために、あたかも違うパターンであるかのように聴こえるのです。
てりぃさんは、第3回レビューにおいて次のようにお書きになりました。
(てりぃさんの「Old Dancer's BLOG」、『CLANNAD 第3回「涙のあとにもう一度」』より)
>>オレもそうだからな…同じ場所にいる。
>再スタートを切るにあたり、二人の関係を朋也が明示した言葉です。
>この先、どんどん深化していくはずの、この「同じ」という言葉…。
>原作未プレイの方は、心の中に深く刻み込んでおいて損は無いですよ。
>保証します。
一見、違うように見えて、じつはずっと一定の「同じ」リズムを刻んでいたもの。
あるいは、状況や環境(拍子)が変わっても、ずっと「同じ」であり続けるもの。
このBGM「田舎小径」(さかなやさん、ありがとうございます!きっと教えて頂けるだろうと、秘かに期待しちゃっていましたw)。
この曲のトライアングルは、そのような、じつは「同じ」であるものを表している、というのは穿ちすぎでしょうか。
さて、この「田舎小径」は、第5回中もう1シーンで使われます。
なあ、いい加減に元気出せよ。
風子は元気です。
そうは見えないから言ってるんだ。
仕方ないです。
三井さんとは入学式の日に、ちょっと話しただけで、
名前を覚えていてもらえただけでもよかったです。
風子は1度も授業に出ていないし…
ただ美術室で木のかけらを拾って、
空いている教室でヒトデを彫っているだけですから。
…風子も、1度だけでも授業に出てみたかったです。
よし!杏と春原に電話だ!
授業風景のシーンです。
「田舎小径」の別バージョン。
中南米の民族音楽風、「アンデス山脈」辺り?
そんな感じのアレンジです。
この授業シーンで、何故この曲が使われているのでしょうか。
この曲は、前述のように、その大半が8分の6拍子からなります。
8…
6…
この数字が意味するものは…
渚、朋也、風子、春原…
そう!これは「渚、朋也、風子、春原、杏、椋、智代、ことみ」の「8人」中「6人」が一堂に会するということ!だから「8分の6」の曲だったということなんだよ!!
Ω ΩΩ<な、なんだってー!
…有紀寧は?という声は聞かなかったことにして進めますw
この「8分の6拍子」の曲は、前述のように、自然に聴けば「イチ、二、サン、シー、…」と「4分の4拍子」を感じるわけですが、じつは、「イチ、二、サン、イチ、二、サン、…」と「4分の3拍子」として捉えることもできます。
これは次のように説明できます。
上の方でこの「8分の6拍子」の譜面を書く際、8分音符3つでひとつの単位(イチとか二とか)にしました。
これは、元の「4分の4拍子」で3連符(タタト)ひとかたまりが、ひとつの単位になっていたことからきます。
さてここで、「8分の6拍子」を、8分音符ふたつずつに区切ってみましょう。
つまり、下図のように、「赤色8分音符+黒色8分音符」という具合にです。

この「赤色8分音符+黒色8分音符」を「ひとつの単位」として捉えなおすと、「8分音符1個+8分音符1個」で「4分音符1個」が単位となります(下図)。

そうすると、これは、1小節中に4分音符が3つ。
つまり「4分の3拍子」に他なりません(下図)。

早苗さんによる「授業」は、因数分解をやっていたことから数学のようです。
数学においては、8分の6は、
6/8=3/4
と「約分」することができます。
音楽の「拍子」は、一般に、勝手に「約分」してはいけないとされます。
しかし、上のようにして「8分の6拍子」を「4分の3拍子」と捉えること、つまり見かけ上「約分」することができます。
実際、このシーンでの「田舎小径」は、「4分の3拍子」に感じたくなる箇所が、いくつかでてきます。
最も決定的なところは、
磯貝風子です!好きなものはヒトデです!
はい。よく出来ました。
の直後から。
風子ちゃん。
早苗さんの呼びかけと同時に、この曲は「4分の3拍子」になります。
風子ちゃん、ここにいる人たちはみんな、
風子ちゃんのクラスメートで、お友だちなんですよ。
そして風子の「満面の笑み」を通って、
仲良くしましょうね、みなさん。
はーい。
それでは授業を始めましょう。委員長。
え…?
まで。
杏の「号令よ、号令」の直前まで、です。
この「4分の3拍子」のリズムは、元々の「4分の4拍子」で考えると、「2拍3連」になります(下図の赤色)。

「2拍3連」は、ポリリズム(このように「4拍子」と「3拍子」が同居するようなリズム)の基本中の基本といえるものです。
はーい。授業を始めますよー。
早苗さんではないですが、今日はひとつ、皆さんにこの「2拍3連」を体感・習得していただきたく思います。
まずは、4分の4拍子で次のように「3連符」を、両手で叩いてみて下さい。
机の上を叩いてもいいですし、膝の上とかでもよいでしょう。
図中、「R」が「右手」で、「L」が「左手」の意味です。
両手で「交互」に。
ゆっくりから始めて、だんだんと、速くでもできるように、といってもこの「田舎小径」のテンポほどでなくて、もう少しゆっくりでいいです。(そんなの無理!できない!という方は、譜面が出なくなるまで下に進んでみて下さい)

4分音符(イチ、二、サン、シー)と重なるところを強く叩く(アクセントをつける)と、やりやすいと思います(下図赤色)。

アクセントが右・左交互にやってくるので、難しいかもしれません。がんばって!
ゆっくりからでよいですので。
と同時に、この4分音符(イチ、二、サン、シー)のところを、足でリズムをとれたら、ちょーイイ感じです(そこまで出来なくても問題ありません)。
さて、これができるようになったら、次に「右手」のみに注目してみて下さい。下図のように。

この「右手」すべてにアクセントをつけられますでしょうか(下図赤色)。
しかし、右・左交互にやってくるより、むしろ簡単かもしれません。

この赤色アクセントの右手が、「2拍3連」に他なりません。
4分音符(イチ、二、サン、シー)のところを、足でリズムをとりながら、2つの譜例を交互に叩けたら、もう立派に「ポリリズム」を習得できているといっても過言ではないかもしれません。いえ!(ry
(改めて譜例1、2。これを交互に)


ちょっと、リズムを叩くのとかできないかも…ちょっと苦手…という方は、次を読むというか唱えるというかしてみて下さい。
できるだけテンポを崩さず。
タタトタタト タタトタタト タンタンタン タンタンタン
この後半の「タンタンタン」が「2拍3連」です。
(たぶん上手くいく…はず…)
さて、この「2拍3連」を介して、4分の4拍子(8分の6拍子)は、4分の3拍子へとリズムチェンジすることができます。
前述のように、この授業風景シーンの「田舎小径」で、4分の3拍子が決定的なのは、風子の自己紹介後、早苗さんの「風子ちゃん」の呼びかけからですが、そこに至る前から、「2拍3連」が随所に顔を出し、「4分の3拍子」を誘っています。
緊張する風子が教室に入れないでいるとき、
ふぅちゃん!来て下さい。もうすぐ授業が始まりますよ!
こっち、こっち!
早く来いよ!
みんなの誘い。
このバックのギターのカッティングに「2拍3連」が含まれます。
自己紹介中。
先生。春原くんはアホです。
以降、朋也の自己紹介が終わるまで。
ここにも「2拍3連」が含まれます。
委員長。
お。いいんじゃないか?
風子、やる気あるか?
から、風子が頷くまでにも。
そして、
異議なーし!
がんばって下さいね。委員長。
から、ピアノトリオ風に曲は変わりますが、ここも「2拍3連」で誘ってきます。
そして、風子の自己紹介を経て、早苗さんの、
はい。よく出来ました。
風子ちゃん。
の呼びかけで、「4分の3拍子」へと変化します。
3/4を、=6/8=9/12=12/16=…とすることは、物差しの目盛を細かくして、物事を細かく細かく見ていこうとすることと同義です。
逆に、「約分」していくことは、物事を「大きく」捉えようとすることといえます。
8分の6拍子から4分の3拍子へ。
この「約分」は、風子を中心に、彼らが「ひとつ」になっていくことを表していると言えるのではないでしょうか。
随所に表れる「2拍3連」の誘い、それは、みんなからの風子への呼びかけでもあります。
8分の6拍子から4分の3拍子へ、そして、
号令よ、号令。
は、はい!
起立!礼!着席!
そして、ひとつに。
実際、この曲はこの場面から、「のばしの音」2分音符、全音符がでてきます。
全音符とは、(4分音符とかの黒い玉に対して)、白い玉1個。
これは、まさしく、
仲良しだんご
手をつなぎ大きな丸い輪になるよ
に他なりません。
このシーンにとてもマッチした曲であると言えるのではないでしょうか。
しかし、4分の3。
この数字についても、考えてみましょう。
4…
3…
朋也、渚、風子、…
風子は、曲が「4分の3拍子」になっているとき、「満面の笑み」を見せますが、「トリップ」することはありませんでした。
それは何故でしょうか。
「クラスメート」の渚はいるものの、足りないからです。
「お姉ちゃん」が。
4分の3拍子。
1人足りないのは、公子さん。
お前さ、こんなことするよりお姉ちゃんに会いたいって思わないのか?
それは会いたいですけど…
でも、お姉ちゃんに風子の声は届くでしょうか。
どういう意味だ?
会えないから…声が届かないから、風子はこうしてるんだと思います。
他に何もできないから…
この曲は、ラスト、のばしの音が出てくるところで、「4分の3拍子」から「4分の4拍子」に戻ると捉えることができます。
風子の声は、公子さんに届くのでしょうか。
はたして、4分の3拍子は、4分の4拍子になることができるのでしょうか。
(了)
長期間、長文におつきあい下さり、誠にありがとうございました!
大変お疲れ様でした!
お読み下さり、本当にありがとうございます。
おっかしいなー。もっと「さらっ」と書くはずだったのに…
この調子では、「らき☆すた」の二の舞に…
次回から、メモっぽいので済ませることが増えるかもしれません。
よろしくお願いいたします。
もう寝る。ばいにー!
[4分の3拍子]
さて、その渚ですが。
岡崎さん、伊吹先生をご存じだったんですか?
前に、店に誰もいなかった時、早苗さんのパンをあげたんだ。
渚ちゃんのボーイフレンドだったんですか。
違いますっ!
…即答。
あっ、いえ!わたしが岡崎さんを嫌いという意味ではなく!
その…岡崎さんにはもっと素敵な人が…
もうおつきあいしてる方がいらっしゃるんですか?
いやいや。そんな相手は、いませんけど。
…そうなんですか?
チャンスですね、渚ちゃん。
はっ!…は…はっ…は、い、いまのは聞かなかったことにして下さい!
渚ちゃん、可愛いですよね。
可愛すぎます、渚!
もうまじでやばいくらい可愛いです。
そ、そうだ!先生こそ、御婚約おめでとうございます!
のところの口の形とかも、ちょーいい感じ。
このシーンのBGMは、第1回、古河家食卓(「ぐー」のとこ)でのBGMと同じもの。
第1回感想では、この曲のことを、ぼくは「パットメセニー風8分の6拍子」と書きましたが、これは8分の12拍子と書くべきだったかも…と思ったら、あれ?そう書いてる。
書きなおしたのかな…たしか最初は8分の6拍子と書いたような気がするのですが。
というか、この曲。
8分の5拍子と8分の7拍子からなる変拍子なのかしらん。
Aメロ(イントロ?)、つまり、
第5回、公子さんの家の前でのシーンで言うと、
「先生!こんにちは、古河です」から
「その…岡崎さんにはもっと素敵な人が…」までの部分、
第1回、古河家食卓のシーンで言うと、
「当り前だ。娘の友だちを粗末に扱うもんかよ」「ぐー」から
「大宇宙銀河。いい名前だろ?」までの部分、
ここのメロディーを聴くと、
|6/8 + 6/8|5/8 + 7/8|
なのかな、と思ったりもします。
でも、ここのベースやトライアングルを聴くと、むしろ、
8分の7拍子+8分の5拍子かな、とも思ったり。
というか、みなさんは「8分のなんとか」ではなく、「4分の4拍子」、すなわち「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」なんじゃないのと仰るかもしれません。
じつは実際はぼくにも、そのように「4分の4拍子」に聴こえています。
こんな感じですね。

これの、3連符(「タタト」と書いたやつ)のアクセントが、変なとこ面白いところにくるメロディーでありトライアングルのリズムである、と考えた方が自然かもしれません。
では、この「4分の4拍子」をなぜ「8分の6拍子」とか書いたかといいますと、これは、便宜上の理由からです。
3連符を書くときには、上のように、音符の上に「3」と書かなくてはなりません。
ですので、この曲の楽譜を書くとしたら、曲の始めから終りまでずっと3連符が続きますので、延々と何個も何個も「3」をつけていかなくてはいけなくなります。
それは、かなり大変です。
そこで、もっと楽に書くために、3連符の1音(「タ」とか「ト」とか)を8分音符1個と考えてしまうのです。
さきほどの例の中には、「タ」とか「ト」が全部で12個あります。
したがって変換後は、次の図のように、8分音符が全部で12個、つまり8分の12拍子となるわけです。(ただし、8分の6拍子が2小節あるとして書きました)

こう書くと、いちいち「3」をつける必要がなくなります。
とても書きやすい、というわけです。
元々は3連符ひとかたまり(タタト)が、4分音符1個分(イチとか二とか)でした。
ですので、8分音符に変換後は、8分音符3個で「イチ」とか「二」になります。
つまり、符点4分音符1個が「イチ」とか「二」になるわけです。
本来は、やはり、小節数を変えたくはないので、これは「8分の12拍子」が1小節と書くべきところなのだろうなと思います。
しかし、ぼくやぼくの周りの連中は、この曲のような感じのリズム、じつはこの曲は後述するように「4分の3拍子」を感じることができるのですが、そのようなリズムのものを、昔からなぜか「ハチロク」と呼んできていますので、ここでは「8分の6拍子」が2小節、とさせて下さい。
実際、この曲は、4分の4拍子(8分の12拍子)のアクセントが面白いところにあるだけでなく、明らかに途中に「8分の5拍子」や「8分の7拍子」の小節を含んでいます。
Aメロ(イントロ)からBメロに移るとき、
また、BメロからAメロに戻るとき、
これらのときに、「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」とリズムをとっていると、ズレてしまうことにお気づきでしょうか。
第5回、公子さんの家の前で言えば、
「もうおつきあいしてる方がいらっしゃるんですか?」から「いやいや。そんな相手はいませんけど」に至る箇所(AメロからBメロへ)、
第1回、古河家食卓で言えば、
「俺の名前は岡崎朋也だ!」「うるせえ野郎だなあ」
のところ(AメロからBメロへ)、
これらのところを、「イチ、ニ、サン、シー、イチ、ニ、サン、シー、…」とリズムをとっていると、ズレてしまいませんか?
これは、ここが、
…|6/8 + 6/8|6/8 + 5/8|Bメロ開始|…
と、最後だけ8分の5拍子になる変拍子だからです。
BメロからAメロへ移るところも変拍子です。
第1回、古河家食卓での、
朋也のおかわりから渚の微笑み、「サンキュー。ここまでくれば道がわかる」に至る箇所(BメロからAメロへ)は、
…|6/8 + 6/8|6/8 + 7/8|6/8 + 6/8|6/8 + 6/8|Aメロ開始|… (← 2007-11-16 01:50 訂正しました。)
のようになっています。
ここで面白いのは、AメロからBメロへ移る際に8分音符1個分少なくなってズレてしまったのが、BメロからAメロに移るときに8分音符1個増える結果、元に戻るというところです。
ちょっとわかりづらいかもしれませんが、トライアングルのリズムパターンに注目してみて下さい。
AメロとBメロではリズムパターンが異なっているように聴こえると思います。
しかし、じつは、このトライアングルのリズムパターンは曲中ずっと、同じなのです。(← 2007-11-16 01:50 訂正しました。「ほぼ同じ」でなく、「完全に」同じです。)
AメロとBメロのトライアングルのリズム譜を書くと、次のようになります。

Aメロで一番最初にあった4分音符は、Bメロにおいては、8分音符ひとつ分ズレています(赤矢印)。
のみなず、そのあとに続く音符も、すべて等しく8分音符ひとつ分、綺麗にスライドしていることがわかると思います。
AメロからBメロへ移る際、前述のようにAメロ最後の小節は、8分の5拍子になります。
そのため、上図Aメロの一番最後の4分音符は8分音符になります。
余ったもう半分の8分音符は、はじき出されてBメロの一番最初にやってきます。
したがって、Bメロでのリズムパターンは、Aメロのそれとちょうど8分音符ひとつ分だけスライドしたものになるわけです。
BメロからAメロへ移る際は、その逆のことがおこります。
Bメロラストは途中の小節で、8分の7拍子を含みます。
ですので、先ほどとは逆に、上図Bメロの最後の小節に、一番最初の8分音符が吸収されます。
それにしたがい、つづく音符もすべて8分音符ひとつ分スライドします。
結果として、Aメロのリズムパターンに戻るというわけです。
このようにして、「リズムパターン」はずっと一定なのに、「拍子」がズレるために、あたかも違うパターンであるかのように聴こえるのです。
てりぃさんは、第3回レビューにおいて次のようにお書きになりました。
(てりぃさんの「Old Dancer's BLOG」、『CLANNAD 第3回「涙のあとにもう一度」』より)
>>オレもそうだからな…同じ場所にいる。
>再スタートを切るにあたり、二人の関係を朋也が明示した言葉です。
>この先、どんどん深化していくはずの、この「同じ」という言葉…。
>原作未プレイの方は、心の中に深く刻み込んでおいて損は無いですよ。
>保証します。
一見、違うように見えて、じつはずっと一定の「同じ」リズムを刻んでいたもの。
あるいは、状況や環境(拍子)が変わっても、ずっと「同じ」であり続けるもの。
このBGM「田舎小径」(さかなやさん、ありがとうございます!きっと教えて頂けるだろうと、秘かに期待しちゃっていましたw)。
この曲のトライアングルは、そのような、じつは「同じ」であるものを表している、というのは穿ちすぎでしょうか。
さて、この「田舎小径」は、第5回中もう1シーンで使われます。
なあ、いい加減に元気出せよ。
風子は元気です。
そうは見えないから言ってるんだ。
仕方ないです。
三井さんとは入学式の日に、ちょっと話しただけで、
名前を覚えていてもらえただけでもよかったです。
風子は1度も授業に出ていないし…
ただ美術室で木のかけらを拾って、
空いている教室でヒトデを彫っているだけですから。
…風子も、1度だけでも授業に出てみたかったです。
よし!杏と春原に電話だ!
授業風景のシーンです。
「田舎小径」の別バージョン。
中南米の民族音楽風、「アンデス山脈」辺り?
そんな感じのアレンジです。
この授業シーンで、何故この曲が使われているのでしょうか。
この曲は、前述のように、その大半が8分の6拍子からなります。
8…
6…
この数字が意味するものは…
渚、朋也、風子、春原…
そう!これは「渚、朋也、風子、春原、杏、椋、智代、ことみ」の「8人」中「6人」が一堂に会するということ!だから「8分の6」の曲だったということなんだよ!!
Ω ΩΩ<な、なんだってー!
…有紀寧は?という声は聞かなかったことにして進めますw
この「8分の6拍子」の曲は、前述のように、自然に聴けば「イチ、二、サン、シー、…」と「4分の4拍子」を感じるわけですが、じつは、「イチ、二、サン、イチ、二、サン、…」と「4分の3拍子」として捉えることもできます。
これは次のように説明できます。
上の方でこの「8分の6拍子」の譜面を書く際、8分音符3つでひとつの単位(イチとか二とか)にしました。
これは、元の「4分の4拍子」で3連符(タタト)ひとかたまりが、ひとつの単位になっていたことからきます。
さてここで、「8分の6拍子」を、8分音符ふたつずつに区切ってみましょう。
つまり、下図のように、「赤色8分音符+黒色8分音符」という具合にです。

この「赤色8分音符+黒色8分音符」を「ひとつの単位」として捉えなおすと、「8分音符1個+8分音符1個」で「4分音符1個」が単位となります(下図)。

そうすると、これは、1小節中に4分音符が3つ。
つまり「4分の3拍子」に他なりません(下図)。

早苗さんによる「授業」は、因数分解をやっていたことから数学のようです。
数学においては、8分の6は、
6/8=3/4
と「約分」することができます。
音楽の「拍子」は、一般に、勝手に「約分」してはいけないとされます。
しかし、上のようにして「8分の6拍子」を「4分の3拍子」と捉えること、つまり見かけ上「約分」することができます。
実際、このシーンでの「田舎小径」は、「4分の3拍子」に感じたくなる箇所が、いくつかでてきます。
最も決定的なところは、
磯貝風子です!好きなものはヒトデです!
はい。よく出来ました。
の直後から。
風子ちゃん。
早苗さんの呼びかけと同時に、この曲は「4分の3拍子」になります。
風子ちゃん、ここにいる人たちはみんな、
風子ちゃんのクラスメートで、お友だちなんですよ。
そして風子の「満面の笑み」を通って、
仲良くしましょうね、みなさん。
はーい。
それでは授業を始めましょう。委員長。
え…?
まで。
杏の「号令よ、号令」の直前まで、です。
この「4分の3拍子」のリズムは、元々の「4分の4拍子」で考えると、「2拍3連」になります(下図の赤色)。

「2拍3連」は、ポリリズム(このように「4拍子」と「3拍子」が同居するようなリズム)の基本中の基本といえるものです。
はーい。授業を始めますよー。
早苗さんではないですが、今日はひとつ、皆さんにこの「2拍3連」を体感・習得していただきたく思います。
まずは、4分の4拍子で次のように「3連符」を、両手で叩いてみて下さい。
机の上を叩いてもいいですし、膝の上とかでもよいでしょう。
図中、「R」が「右手」で、「L」が「左手」の意味です。
両手で「交互」に。
ゆっくりから始めて、だんだんと、速くでもできるように、といってもこの「田舎小径」のテンポほどでなくて、もう少しゆっくりでいいです。(そんなの無理!できない!という方は、譜面が出なくなるまで下に進んでみて下さい)

4分音符(イチ、二、サン、シー)と重なるところを強く叩く(アクセントをつける)と、やりやすいと思います(下図赤色)。

アクセントが右・左交互にやってくるので、難しいかもしれません。がんばって!
ゆっくりからでよいですので。
と同時に、この4分音符(イチ、二、サン、シー)のところを、足でリズムをとれたら、ちょーイイ感じです(そこまで出来なくても問題ありません)。
さて、これができるようになったら、次に「右手」のみに注目してみて下さい。下図のように。

この「右手」すべてにアクセントをつけられますでしょうか(下図赤色)。
しかし、右・左交互にやってくるより、むしろ簡単かもしれません。

この赤色アクセントの右手が、「2拍3連」に他なりません。
4分音符(イチ、二、サン、シー)のところを、足でリズムをとりながら、2つの譜例を交互に叩けたら、もう立派に「ポリリズム」を習得できているといっても過言ではないかもしれません。いえ!(ry
(改めて譜例1、2。これを交互に)


ちょっと、リズムを叩くのとかできないかも…ちょっと苦手…という方は、次を読むというか唱えるというかしてみて下さい。
できるだけテンポを崩さず。
タタトタタト タタトタタト タンタンタン タンタンタン
この後半の「タンタンタン」が「2拍3連」です。
(たぶん上手くいく…はず…)
さて、この「2拍3連」を介して、4分の4拍子(8分の6拍子)は、4分の3拍子へとリズムチェンジすることができます。
前述のように、この授業風景シーンの「田舎小径」で、4分の3拍子が決定的なのは、風子の自己紹介後、早苗さんの「風子ちゃん」の呼びかけからですが、そこに至る前から、「2拍3連」が随所に顔を出し、「4分の3拍子」を誘っています。
緊張する風子が教室に入れないでいるとき、
ふぅちゃん!来て下さい。もうすぐ授業が始まりますよ!
こっち、こっち!
早く来いよ!
みんなの誘い。
このバックのギターのカッティングに「2拍3連」が含まれます。
自己紹介中。
先生。春原くんはアホです。
以降、朋也の自己紹介が終わるまで。
ここにも「2拍3連」が含まれます。
委員長。
お。いいんじゃないか?
風子、やる気あるか?
から、風子が頷くまでにも。
そして、
異議なーし!
がんばって下さいね。委員長。
から、ピアノトリオ風に曲は変わりますが、ここも「2拍3連」で誘ってきます。
そして、風子の自己紹介を経て、早苗さんの、
はい。よく出来ました。
風子ちゃん。
の呼びかけで、「4分の3拍子」へと変化します。
3/4を、=6/8=9/12=12/16=…とすることは、物差しの目盛を細かくして、物事を細かく細かく見ていこうとすることと同義です。
逆に、「約分」していくことは、物事を「大きく」捉えようとすることといえます。
8分の6拍子から4分の3拍子へ。
この「約分」は、風子を中心に、彼らが「ひとつ」になっていくことを表していると言えるのではないでしょうか。
随所に表れる「2拍3連」の誘い、それは、みんなからの風子への呼びかけでもあります。
8分の6拍子から4分の3拍子へ、そして、
号令よ、号令。
は、はい!
起立!礼!着席!
そして、ひとつに。
実際、この曲はこの場面から、「のばしの音」2分音符、全音符がでてきます。
全音符とは、(4分音符とかの黒い玉に対して)、白い玉1個。
これは、まさしく、
仲良しだんご
手をつなぎ大きな丸い輪になるよ
に他なりません。
このシーンにとてもマッチした曲であると言えるのではないでしょうか。
しかし、4分の3。
この数字についても、考えてみましょう。
4…
3…
朋也、渚、風子、…
風子は、曲が「4分の3拍子」になっているとき、「満面の笑み」を見せますが、「トリップ」することはありませんでした。
それは何故でしょうか。
「クラスメート」の渚はいるものの、足りないからです。
「お姉ちゃん」が。
4分の3拍子。
1人足りないのは、公子さん。
お前さ、こんなことするよりお姉ちゃんに会いたいって思わないのか?
それは会いたいですけど…
でも、お姉ちゃんに風子の声は届くでしょうか。
どういう意味だ?
会えないから…声が届かないから、風子はこうしてるんだと思います。
他に何もできないから…
この曲は、ラスト、のばしの音が出てくるところで、「4分の3拍子」から「4分の4拍子」に戻ると捉えることができます。
風子の声は、公子さんに届くのでしょうか。
はたして、4分の3拍子は、4分の4拍子になることができるのでしょうか。
(了)
長期間、長文におつきあい下さり、誠にありがとうございました!
大変お疲れ様でした!
お読み下さり、本当にありがとうございます。
おっかしいなー。もっと「さらっ」と書くはずだったのに…
この調子では、「らき☆すた」の二の舞に…
次回から、メモっぽいので済ませることが増えるかもしれません。
よろしくお願いいたします。
もう寝る。ばいにー!











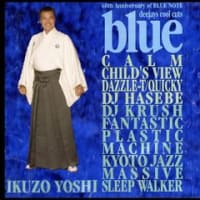
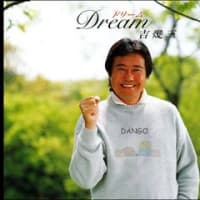

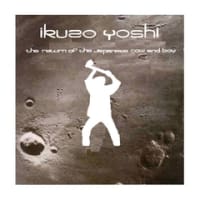
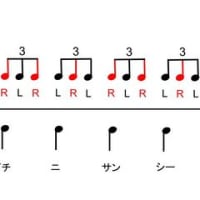
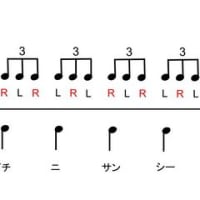
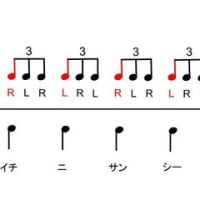
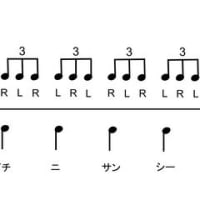
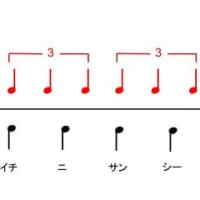
>このシーンのBGM
この曲は「田舎小路」ですね
作曲者さんのコメントを引用してみます
「CLANNADのために書いたいちばん最初の曲です。鳴らしているのはシンセですが、構成楽器は全てアコースティックなので、生演奏でアドリブ回しとかすると、面白いかもしれませんね。」
こんばんは、たこーすけです。
作曲者さんコメントの引用を、どうもありがとうございます!
たしかに「生演奏でアドリブ回し」とか、とても楽しそうです。
実際、アレンジバージョンの方では、途中ジャズのピアノトリオ風にもなりますし。
いやしかし、この曲が一番最初に書かれた曲であるのは、意外でした。
トリッキーなところがありますし。
もっと素直な曲が一番最初かなと思っていました。
てか、そもそも、なんで「田舎」なのかと。
いまのこの舞台は「町・街」なわけですよね?
もっと「田舎」っぽい舞台へ、今後移るのかな?
それとも、この街が「田舎」であった頃へ、とか。
うーん。
どうあれ、この曲が「一番最初」というのは、「田舎」という風景が結構大事だということなのではないかなーと思った次第なのでした。
それでは、またですー。