
今年のお盆は伯父の初盆もあり、お盆に休みをいただいて私の本家、私の母親の本家そして妻の実家と3つのお盆参りをしてきました。
本家は社長宅でもあるので、妻を連れて初めて行きました。昨年の伯父の葬儀は葬祭場で行われた為に、妻は本家に行く事はありませんでしたが、私自身の本家でもあるので当然妻も挨拶に行かせる必要があると思い、今回は初盆でもあるので2人で行ってきました。
本家には仏間もあり、私の祖父母と昨年無くなった伯父の写真が飾られています。その中に真っ先に飾られている軍服姿の青年の古い写真があります。この方は祖父の弟さんで、戦争に出征されて戦死された方です。本家の隣にある檀家であるお寺にはこの方の祈念碑が寺の門の前に大きく立っていて、戦時中の上官の方が書いた、この方の戦歴や戦死した時の様子などが書かれています。まだいわゆる日中戦争が始まったばかりの時に戦死されたので、この時は地元では英雄扱いだったようです。
また祖父は叙勲されていますので、昭和天皇とご一緒されている写真なども飾られていまして、我が本家の歴史を感じる場所でもあります。妻も初めて来てお参りしましたので、そう言った祖父母などの経歴なども説明したりしました。また伯母や社長と一緒にそうした昔話などにも花が咲きました。
可笑しかったのは、昨年の伯父の葬式の時にはうちの身内がたくさん集まり、お父様が一人っ子で身内の少ない妻は、我が一族の人々を紹介しても「こちらは父の3番目の弟の次男で・・・」なんて説明されてもわからないので、「写真入りの家系図を書いて!」と悲鳴をあげていましたが、そのエピソードを話すと伯母や社長は爆笑されていました。私もいとこまでは分かりますが、その子供までなると名前と顔が一致しないなんて事もあります。
という事でそうした私のルーツとも言うべき場所を妻に案内するのはなかなか楽しかったです。
翌日は私の母の実家にお盆参り。こちらは同じ久留米市内にあるので、昨年も妻と一緒に行きましたので、だいたい妻も誰が誰というのは理解出来ているようでした。その後夕方に一旦帰ってから妻の実家に行きました。
妻の実家は本家ではあるんですが、お父様が一人という事もあり、またお母様も兄弟が少ないので、お盆に集まるのは私たちと義弟の家族とお母様の弟である叔父さんの家族くらいです。今年は叔父さんの息子(妻の従弟)が結婚した事もあって、叔父夫婦は前日に挨拶に来てましたので、この日は私達夫婦と仕事で来れない義弟を除き義弟の奥さんと2人の甥っ子と昨年生まれたばかりの姪っ子のみのお盆という事になりました。
夜の19時半くらいなって、ぼちぼちご先祖様を送ろうという事になり、ご先祖が眠っているお寺を参ってから、筑後川の「灯籠流し」に行くことになりました。
ところで、先日から妻と「灯籠流しなのか?精霊流しなのか?」という論争になっておりました。昨年は私は初めて参加したんですが、昨年の記事には「灯籠流し」と書いていました。これは会場には「灯籠流し」とあったというのとネットで調べても「筑後川の灯籠流し」となっていたからです。ところが妻やご両親は「精霊流し」という呼び方をしています。
先日、お盆の事を打ち合わせるのに、昨年同様私は「”灯籠流し”は今年もいくんやろ?」と言ったときに妻が「灯籠?精霊流しやろ?灯籠は流さんやろう」と言われたので、その時はあっそうだっけ?と思っておりましたが、腑に落ちないので調べたらやはり「筑後川の灯籠流し」となっておりました。それに流してるのは灯籠でしょ?という事で後日それを指摘すると今度は妻が怪訝な顔しながらも「そうだっけ?」と言っておりましたが、腑に落ちない様子。妻は腑に落ちない事があると徹底して調べる方なので、すぐにお母様に聞いたようで、「やっぱ”精霊流し”って言ってたよ」と返されました。「でも流してるのは灯籠でしょ?」というと「あれって灯籠だっけ?」と曖昧な返事。妻は長くやっていたはずなのに良く理解していないようです。
という事でこの日は妻と一緒に会場に向かい真相を確かめる事に(って大袈裟な事でも無いですが)。
昨年は義弟の奥さんの運転で車で向かいましたが、会場の水天宮の入り口が凄く混むし、今年は甥っ子姪っ子も参加しているので、大所帯の為に車で行かずに歩こうという事になりました。妻の実家から水天宮の参道の手前にあるお寺にお参りしてから、水天宮の会場まで向かいますが、子供もいるのでゆっくり歩いて30分ちょっとかかります。でもまあ子供達も居てわいわい歩いて行くとなかなか楽しいものがあります。甥っ子の一番上のお兄ちゃんはお供え物である、野菜などを笹に詰めたものを持ち、下の弟はロウソクと線香を持たされましていました。恐らくご先祖様もこの行列に加わり賑やかなお子供達と一緒に楽しげに帰路を歩いていたのでしょうか。
昨年と同様、まずはお寺にお参りしてご先祖様にご挨拶。そして水天宮の会場へと向かいました。途中で美味しそうな餃子屋さんがあり、お父様が食べたいという事で帰りまでに焼いてもらうように注文。さすが久留米です。お盆にもB級グルメ大活躍です。
会場に着くとやはり「灯籠流し」と書いてありました。お供え物は入り口のところでボランティアの方が引き取っていました。昔はこの野菜や果物の入ったお供え物を流していたようですが、ゴミになるという事で今は流さずに会場でボランティアが引き取ってから処分してもらうとの事。その代わり「灯籠」を500円で購入してこれを筑後川に流すという事です。という事でやはり流すのは”灯籠”です。
ちなみにこの”お供え物”は来年からは引き取ってもらえないという事で各家庭で処分して欲しいと告知されていました。お供え物を”ゴミ”と称するのは罰当たりな気がしますが、実際には自治体ごとのルールに従って処分されます。ボランティアの方が集めて処分を代行してもらっていたようですが、コストもかかるという事で来年からは各家庭でという事でしょう。
”灯籠”はボランティアの方が、その場で組み立てられていて、それを購入して自分の名前と送る人の名前(または○○家先祖代々)を記入して中のロウソクに火を灯し筑後川に流します。中には「灯籠船」と言って派手な船の形の灯籠を自分たちで持ち込んで流す人もいました。
先祖を送る灯籠が筑後川を流れる幻想的な風景ですが、会場は人で賑わい露店なども出ていてかなり賑やかな雰囲気です。甥っ子達は灯籠流しよりも、露店のかき氷の方が気になるようで、会場に着く前からかき氷をねだっておりました。私もねだられました。ということで無事ご先祖様を送って水天宮の会場を後にしました。
ところで”精霊流し”というのは、さだまさし氏の歌で有名になりましたが、長崎で行われているのを”精霊流し”と呼ぶようですが、”灯籠流し”も昔は”精霊流し”と言っていたようで、お供え物を流して先祖を送るのを”精霊流し”と言っていたようです。それが精霊流しでの筑後川にゴミが溢れるのを防ぐために今のような灯籠を流すようになって”灯籠流し”と呼ぶようになったようです。意味からすればご先祖様の霊を送るという事で”精霊流し”の方が合っているようです。昔から知っているお母様が”精霊流し”と言っているのは正しいと言えます。
ちなみに長崎の精霊流しはかなり派手なものらしくて、さだまさし氏の歌のイメージで行った人がびっくりするそうです(爆竹とかなりまくりで相当騒がしいらしいです)。
さて、帰りには注文していた餃子を途中で買ってから、またゆっくりと妻の実家へと向かいました。帰りも子供達は元気・・・と思ったら少し疲れたようで、ずっと抱っこされていた一番したの姪っ子以外はちょっと最後は無口になってきました。それでも肩車してあげたらまた元気に喜んでました。
自宅に着く頃には出発から1時間半くらい経っていて、この日は暑かった事もあって汗びっしょり!帰るとすぐに冷えたビールを出してもらい、グッと飲み干しました。「いやあこの一杯の為に生きている!」なんて言うとご先祖様に失礼でしょうか・・・
この日は深夜1時過ぎまで上機嫌のお父様のお酒に付き合いながらお盆は過ぎていきました。
本家は社長宅でもあるので、妻を連れて初めて行きました。昨年の伯父の葬儀は葬祭場で行われた為に、妻は本家に行く事はありませんでしたが、私自身の本家でもあるので当然妻も挨拶に行かせる必要があると思い、今回は初盆でもあるので2人で行ってきました。
本家には仏間もあり、私の祖父母と昨年無くなった伯父の写真が飾られています。その中に真っ先に飾られている軍服姿の青年の古い写真があります。この方は祖父の弟さんで、戦争に出征されて戦死された方です。本家の隣にある檀家であるお寺にはこの方の祈念碑が寺の門の前に大きく立っていて、戦時中の上官の方が書いた、この方の戦歴や戦死した時の様子などが書かれています。まだいわゆる日中戦争が始まったばかりの時に戦死されたので、この時は地元では英雄扱いだったようです。
また祖父は叙勲されていますので、昭和天皇とご一緒されている写真なども飾られていまして、我が本家の歴史を感じる場所でもあります。妻も初めて来てお参りしましたので、そう言った祖父母などの経歴なども説明したりしました。また伯母や社長と一緒にそうした昔話などにも花が咲きました。
可笑しかったのは、昨年の伯父の葬式の時にはうちの身内がたくさん集まり、お父様が一人っ子で身内の少ない妻は、我が一族の人々を紹介しても「こちらは父の3番目の弟の次男で・・・」なんて説明されてもわからないので、「写真入りの家系図を書いて!」と悲鳴をあげていましたが、そのエピソードを話すと伯母や社長は爆笑されていました。私もいとこまでは分かりますが、その子供までなると名前と顔が一致しないなんて事もあります。
という事でそうした私のルーツとも言うべき場所を妻に案内するのはなかなか楽しかったです。
翌日は私の母の実家にお盆参り。こちらは同じ久留米市内にあるので、昨年も妻と一緒に行きましたので、だいたい妻も誰が誰というのは理解出来ているようでした。その後夕方に一旦帰ってから妻の実家に行きました。
妻の実家は本家ではあるんですが、お父様が一人という事もあり、またお母様も兄弟が少ないので、お盆に集まるのは私たちと義弟の家族とお母様の弟である叔父さんの家族くらいです。今年は叔父さんの息子(妻の従弟)が結婚した事もあって、叔父夫婦は前日に挨拶に来てましたので、この日は私達夫婦と仕事で来れない義弟を除き義弟の奥さんと2人の甥っ子と昨年生まれたばかりの姪っ子のみのお盆という事になりました。
夜の19時半くらいなって、ぼちぼちご先祖様を送ろうという事になり、ご先祖が眠っているお寺を参ってから、筑後川の「灯籠流し」に行くことになりました。
ところで、先日から妻と「灯籠流しなのか?精霊流しなのか?」という論争になっておりました。昨年は私は初めて参加したんですが、昨年の記事には「灯籠流し」と書いていました。これは会場には「灯籠流し」とあったというのとネットで調べても「筑後川の灯籠流し」となっていたからです。ところが妻やご両親は「精霊流し」という呼び方をしています。
先日、お盆の事を打ち合わせるのに、昨年同様私は「”灯籠流し”は今年もいくんやろ?」と言ったときに妻が「灯籠?精霊流しやろ?灯籠は流さんやろう」と言われたので、その時はあっそうだっけ?と思っておりましたが、腑に落ちないので調べたらやはり「筑後川の灯籠流し」となっておりました。それに流してるのは灯籠でしょ?という事で後日それを指摘すると今度は妻が怪訝な顔しながらも「そうだっけ?」と言っておりましたが、腑に落ちない様子。妻は腑に落ちない事があると徹底して調べる方なので、すぐにお母様に聞いたようで、「やっぱ”精霊流し”って言ってたよ」と返されました。「でも流してるのは灯籠でしょ?」というと「あれって灯籠だっけ?」と曖昧な返事。妻は長くやっていたはずなのに良く理解していないようです。
という事でこの日は妻と一緒に会場に向かい真相を確かめる事に(って大袈裟な事でも無いですが)。
昨年は義弟の奥さんの運転で車で向かいましたが、会場の水天宮の入り口が凄く混むし、今年は甥っ子姪っ子も参加しているので、大所帯の為に車で行かずに歩こうという事になりました。妻の実家から水天宮の参道の手前にあるお寺にお参りしてから、水天宮の会場まで向かいますが、子供もいるのでゆっくり歩いて30分ちょっとかかります。でもまあ子供達も居てわいわい歩いて行くとなかなか楽しいものがあります。甥っ子の一番上のお兄ちゃんはお供え物である、野菜などを笹に詰めたものを持ち、下の弟はロウソクと線香を持たされましていました。恐らくご先祖様もこの行列に加わり賑やかなお子供達と一緒に楽しげに帰路を歩いていたのでしょうか。
昨年と同様、まずはお寺にお参りしてご先祖様にご挨拶。そして水天宮の会場へと向かいました。途中で美味しそうな餃子屋さんがあり、お父様が食べたいという事で帰りまでに焼いてもらうように注文。さすが久留米です。お盆にもB級グルメ大活躍です。
会場に着くとやはり「灯籠流し」と書いてありました。お供え物は入り口のところでボランティアの方が引き取っていました。昔はこの野菜や果物の入ったお供え物を流していたようですが、ゴミになるという事で今は流さずに会場でボランティアが引き取ってから処分してもらうとの事。その代わり「灯籠」を500円で購入してこれを筑後川に流すという事です。という事でやはり流すのは”灯籠”です。
ちなみにこの”お供え物”は来年からは引き取ってもらえないという事で各家庭で処分して欲しいと告知されていました。お供え物を”ゴミ”と称するのは罰当たりな気がしますが、実際には自治体ごとのルールに従って処分されます。ボランティアの方が集めて処分を代行してもらっていたようですが、コストもかかるという事で来年からは各家庭でという事でしょう。
”灯籠”はボランティアの方が、その場で組み立てられていて、それを購入して自分の名前と送る人の名前(または○○家先祖代々)を記入して中のロウソクに火を灯し筑後川に流します。中には「灯籠船」と言って派手な船の形の灯籠を自分たちで持ち込んで流す人もいました。
先祖を送る灯籠が筑後川を流れる幻想的な風景ですが、会場は人で賑わい露店なども出ていてかなり賑やかな雰囲気です。甥っ子達は灯籠流しよりも、露店のかき氷の方が気になるようで、会場に着く前からかき氷をねだっておりました。私もねだられました。ということで無事ご先祖様を送って水天宮の会場を後にしました。
ところで”精霊流し”というのは、さだまさし氏の歌で有名になりましたが、長崎で行われているのを”精霊流し”と呼ぶようですが、”灯籠流し”も昔は”精霊流し”と言っていたようで、お供え物を流して先祖を送るのを”精霊流し”と言っていたようです。それが精霊流しでの筑後川にゴミが溢れるのを防ぐために今のような灯籠を流すようになって”灯籠流し”と呼ぶようになったようです。意味からすればご先祖様の霊を送るという事で”精霊流し”の方が合っているようです。昔から知っているお母様が”精霊流し”と言っているのは正しいと言えます。
ちなみに長崎の精霊流しはかなり派手なものらしくて、さだまさし氏の歌のイメージで行った人がびっくりするそうです(爆竹とかなりまくりで相当騒がしいらしいです)。
さて、帰りには注文していた餃子を途中で買ってから、またゆっくりと妻の実家へと向かいました。帰りも子供達は元気・・・と思ったら少し疲れたようで、ずっと抱っこされていた一番したの姪っ子以外はちょっと最後は無口になってきました。それでも肩車してあげたらまた元気に喜んでました。
自宅に着く頃には出発から1時間半くらい経っていて、この日は暑かった事もあって汗びっしょり!帰るとすぐに冷えたビールを出してもらい、グッと飲み干しました。「いやあこの一杯の為に生きている!」なんて言うとご先祖様に失礼でしょうか・・・
この日は深夜1時過ぎまで上機嫌のお父様のお酒に付き合いながらお盆は過ぎていきました。















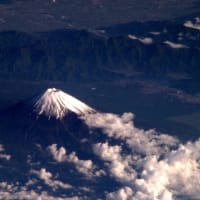


3ヶ所へのお盆参り、ご苦労さでした!
子供の時は親に連れられて、お参りしたものですが、今となっては、僕ら世代が、先祖供養し、それを守っていき、継承していく歳になりました。
「供養のこころ」で、お互い、しっかりと守っていきたいですね!!
記事に書いたとおりお父様の話し相手で遅くまで付き合いましたので、遅い時間のお電話になってしまいました。
今度はぜひとも参加したいと思います(チッセも来るかな?)
昔から親が私には必ずお盆に本家に行くように言われていました。他のいとこ達があまり来なくなってからも、私は良く一緒に行かされていました。
昔は意味がわからず付いてきていたんですが、そうやってご先祖様を大事にするという心を自然と育ててもらった気がします。こうやって次の世代に受け継いで行くんですね。
今自分があるのはご先祖様皆様のおかげです。一人でも欠けていたら自分は存在しなかったと思うと本当に大事にしないといけないなと思います。
という事でお互いにご先祖様を大事にして繁栄していきましょう!