おはようございます。ゴールデンウィークが始まりましたね。念願の能登半島に行けるのが楽しみでならないただけーまです。
今回も2月に鑑賞した作品ですが、カンヌでグランプリを受賞したネメシュ・ラースロー監督の『サウルの息子』の感想を更新します。

<Story>
1944年10月、アウシュヴィッツ=ビルケナウ収容所。サウルは、ハンガリー系のユダヤ人で、ゾンダーコマンドとして働いている。ゾンダーコマンドとは、ナチスが選抜した、同胞であるユダヤ人の死体処理に従事する特殊部隊のことである。彼らはそこで生き延びるためには、人間としての感情を押し殺すしか術が無い。
ある日、サウルは、ガス室で生き残った息子とおぼしき少年を発見する。少年はサウルの目の前ですぐさま殺されてしまうのだが、サウルはなんとかラビ(ユダヤ教の聖職者)を捜し出し、ユダヤ教の教義にのっとって*手厚く埋葬してやろうと、収容所内を奔走する。そんな中、ゾンダーコマンド達の間には収容所脱走計画が秘密裏に進んでいた・・・。 *ユダヤ教では火葬は死者が復活できないとして禁じられている。(オフィシャルサイトより)

整列するゾンダーコマンドたち
後日更新しようと思っていますが、カンヌでパルムドールを受賞した『ディーパンの闘い』よりもこちらの作品の方が私は好きでした。というのも、作品のテーマさておきこちらの方がより映画的な手法が用いられていると感じたからです。
映画にしろ絵画にしろ小説にしろ漫画にしろアニメにしろ、その表現手法でしか為し得ない描写というものが私は好きなので、やはりより映画的な作品が好きなのかもしれません。(玄人さんからすればディーパンの方がより映画的だと言う方も多い気がしますが!)
ピンボケという手法
映画とは比較的鑑賞者の五感に干渉することの多い表現です。視覚と聴覚には完全に干渉していきますし、最近では触覚や嗅覚にもコミットし始めている。また、臨場感という観点ではそれ以上の感覚を鑑賞者に与えてしまいます。要は鑑賞者の想像力の介する余地が比較的少ないのです。
しかし、本作はあえてピンボケを多用することで、鑑賞者にサウルの視点ではなく心象を強要する強烈な作品となっているのです。聴覚を意識させるヤキモフスキ監督の『イマジン』に近いものを感じますね。

ピンボケするカメラワーク
サウルの視点は常にピンボケしているわけではなく、仲間と会話するシーンや息子の遺体と対面するシーンでは綺麗にピントが合います。ユダヤ人の死体を処理するゾンダーコマンド、嘗ての仲間の遺体を処理する非人間的な行為に身を費やしている時のみ、サウルは感覚をオフにしているのです。こうした心象をピンボケという映画ならではの手法で表現した点が個人的にはかなり好きでした。「最期まで<人間>であるために」というキャッチからも、ピンボケという手法が非人間性に身を落とさないように努めるサウルの視点であることがわかりますね。
息子の遺体の位置づけ
ユダヤ教の様式に異常に固執(自身の命や仲間の危険を顧みない)し、息子の遺体を土葬するために奔走するサウルは、やはり未来での息子の復活、大袈裟に換言すると未来への希望を望んでいるようにも考えられます。
しかし、息子の遺体は逃走中に川の水に流されていってしまいます。(ユダヤ教はどうだかわかりませんが、仏教概念では水葬は無常観念と結びつくようです)息子の遺体はサウルが人間的であろうとすることのよすがでもあったわけですから、遺体の消失は同時にサウルの人間性の喪失のようにも映り、あたかも息子の遺体とともに未来への希望までも流されていってしまったように感じられます。
そして、最も印象的で不可解だったのがラストシーン。サウルを含めたユダヤ人一行が逃亡中に休憩していた小屋で、サウルが見ず知らずの子供と視線を交わすシーンです。
子供と対峙した瞬間、サウルは作品中で初めて人間らしい笑顔を見せるのですが、その後のカメラワークはサウルからは離れ、見ず知らずの子供を追うようにして草木の中へと消えていってしまいます。
ある種サウルは息子の遺体に囚われるが故に、実のところ非人間的であったのではないでしょうか。執念という非人間的な感情に捉われていたサウルは、息子の遺体を失うことで逆説的に人間性を取り戻したように感じられます。
つまり、サウルにとって息子の埋葬は未来への希望ではなく、過去に縛られるという絶望にしか過ぎなかったのに対し、対峙した生きている子供こそが、真の意味で未来の希望なのだという作品の主張であったようにも考えられます。
今回も2月に鑑賞した作品ですが、カンヌでグランプリを受賞したネメシュ・ラースロー監督の『サウルの息子』の感想を更新します。

<Story>
1944年10月、アウシュヴィッツ=ビルケナウ収容所。サウルは、ハンガリー系のユダヤ人で、ゾンダーコマンドとして働いている。ゾンダーコマンドとは、ナチスが選抜した、同胞であるユダヤ人の死体処理に従事する特殊部隊のことである。彼らはそこで生き延びるためには、人間としての感情を押し殺すしか術が無い。
ある日、サウルは、ガス室で生き残った息子とおぼしき少年を発見する。少年はサウルの目の前ですぐさま殺されてしまうのだが、サウルはなんとかラビ(ユダヤ教の聖職者)を捜し出し、ユダヤ教の教義にのっとって*手厚く埋葬してやろうと、収容所内を奔走する。そんな中、ゾンダーコマンド達の間には収容所脱走計画が秘密裏に進んでいた・・・。 *ユダヤ教では火葬は死者が復活できないとして禁じられている。(オフィシャルサイトより)

整列するゾンダーコマンドたち
後日更新しようと思っていますが、カンヌでパルムドールを受賞した『ディーパンの闘い』よりもこちらの作品の方が私は好きでした。というのも、作品のテーマさておきこちらの方がより映画的な手法が用いられていると感じたからです。
映画にしろ絵画にしろ小説にしろ漫画にしろアニメにしろ、その表現手法でしか為し得ない描写というものが私は好きなので、やはりより映画的な作品が好きなのかもしれません。(玄人さんからすればディーパンの方がより映画的だと言う方も多い気がしますが!)
ピンボケという手法
映画とは比較的鑑賞者の五感に干渉することの多い表現です。視覚と聴覚には完全に干渉していきますし、最近では触覚や嗅覚にもコミットし始めている。また、臨場感という観点ではそれ以上の感覚を鑑賞者に与えてしまいます。要は鑑賞者の想像力の介する余地が比較的少ないのです。
しかし、本作はあえてピンボケを多用することで、鑑賞者にサウルの視点ではなく心象を強要する強烈な作品となっているのです。聴覚を意識させるヤキモフスキ監督の『イマジン』に近いものを感じますね。

ピンボケするカメラワーク
サウルの視点は常にピンボケしているわけではなく、仲間と会話するシーンや息子の遺体と対面するシーンでは綺麗にピントが合います。ユダヤ人の死体を処理するゾンダーコマンド、嘗ての仲間の遺体を処理する非人間的な行為に身を費やしている時のみ、サウルは感覚をオフにしているのです。こうした心象をピンボケという映画ならではの手法で表現した点が個人的にはかなり好きでした。「最期まで<人間>であるために」というキャッチからも、ピンボケという手法が非人間性に身を落とさないように努めるサウルの視点であることがわかりますね。
息子の遺体の位置づけ
ユダヤ教の様式に異常に固執(自身の命や仲間の危険を顧みない)し、息子の遺体を土葬するために奔走するサウルは、やはり未来での息子の復活、大袈裟に換言すると未来への希望を望んでいるようにも考えられます。
しかし、息子の遺体は逃走中に川の水に流されていってしまいます。(ユダヤ教はどうだかわかりませんが、仏教概念では水葬は無常観念と結びつくようです)息子の遺体はサウルが人間的であろうとすることのよすがでもあったわけですから、遺体の消失は同時にサウルの人間性の喪失のようにも映り、あたかも息子の遺体とともに未来への希望までも流されていってしまったように感じられます。
そして、最も印象的で不可解だったのがラストシーン。サウルを含めたユダヤ人一行が逃亡中に休憩していた小屋で、サウルが見ず知らずの子供と視線を交わすシーンです。
子供と対峙した瞬間、サウルは作品中で初めて人間らしい笑顔を見せるのですが、その後のカメラワークはサウルからは離れ、見ず知らずの子供を追うようにして草木の中へと消えていってしまいます。
ある種サウルは息子の遺体に囚われるが故に、実のところ非人間的であったのではないでしょうか。執念という非人間的な感情に捉われていたサウルは、息子の遺体を失うことで逆説的に人間性を取り戻したように感じられます。
つまり、サウルにとって息子の埋葬は未来への希望ではなく、過去に縛られるという絶望にしか過ぎなかったのに対し、対峙した生きている子供こそが、真の意味で未来の希望なのだという作品の主張であったようにも考えられます。










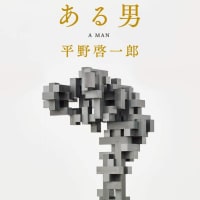









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます