
おひさしぶりなのです。
もう名古屋生活も残り半年を迎え、何やら新天地での仕事が楽しみでもあったり、名古屋での知人としばらく会えなくなるのが寂しくもあり、非常に複雑な思いに駆られているただけーまです。
あまり名古屋では美術展に行かないわたくしですが、今回は行こう行こうと思って行けてなかったヤゲオ財団所蔵の現代美術作品展が巡回に来ていたので(なんと名古屋に!!!)思わず行ってしまいました。
なんか現代アートのアラカルト的な展示だったので、美術史的なコメントは全くできませんので、適当にざっくばらんな感想をば……(あと今回は現代アートばっかりだったので図像もほとんど載せられませんの。本当は全部だめなんだろうけど……)
この展示会は「ミューズ」「ポップ・アート」「サンユウ(常玉)」「中国の近現代美術」「崇高」「威厳」「リアリティ」「記憶」「実存的状況」「新しい美」というテーマで分けられて展示されており、なんだか結構無理やりな分類だなあとか思いながら観覧してましたが、展示されていた作品群は【超】一級品ばかり。作品目録を見ながらその作品の素晴らしさを思わず回想してしまいます。
1.抽象表現主義の先
ポロックやニューマン、デ・クーニングなど、アメリカで隆盛した抽象表現主義の絵画は人間の根源的な部分(例えばポロックの原始性であったり、ニューマンの生命力、デ・クーニングのセックス性であったり)が、それはもう誰も真似の出来ないエネルギッシュで偶然性に満ちた手法で描かれており、個人的にはかなり好きなジャンルの絵画なのですが、今回の展示ではそれらの作風を凌駕する作品に出会えました。
その作風に圧倒されたのが、原題ドイツ美術の最高峰ゲルハルト・リヒターです。現代アーティストランキング世界1位!というテラ・フォーマーズを思わせるような評判(わかる人だけわかってください)に相応しい、圧倒的な作品・絵画手法でした(絵画作品で涙が出たのは久しぶりでした)
マルセル・デュシャンやウォーホルらの登場によって「芸術は終焉した」というのはダントーの言葉ですが、技法的な意味で彼の作品は芸術の終焉の更に先へ到達しているような印象さえ覚えます(美学的な意味での芸術は既に限界を迎えてしまったのかもしれませんが……)
彼の作風を私なりに表現するとしたら「絵画を超えた絵画」といったところでしょうか。彼の絵画は絵画でありながら、従来の絵画とは一線を画す作品のように映ります。人が表現不可能な美的領域を表現することに成功しているように思えてならないのです。
例えば今回展示されていた《川》という作品や《横たわる裸体》という作品は、抽象的でありながら具体的な絵が見えてしまう、そういう不思議な絵画でした。そして美術愛好家の多くはこの感覚を「印象主義」らの手法で知っています。瞬間瞬間の「印象」をぼんやりと筆色分割という技法で表現しようとしたのが印象派であるとすれば、彼はその瞬間の「具体的な光景」をアブストラクト・ペインティングの手法で捉えたと言えるのかもしません。
そして私が彼の作品に鳥肌が立ったのが、彼が意図して制作した絵画が、人間の表現出来ない範囲の美的瞬間をかなり的確に表現しているという点です。例えば《川》は一見したところ全体が緑色の抽象画のように見えますが、その実夜の街のネオンが川に反射して光っているという具体的なイメージがはっきりとわかってしまいます。川の水面の反射は光の屈折や反射、水の濁り具合、外光の強さなど様々な要素が複雑に絡み合った、その瞬間にしかあり得ない光景(印象)であり、言わば「奇蹟的な偶然の積み重ね」とも言うべき光景だと私は思っています(例えばオイルが反射して虹色になる瞬間とか……)
それ故に人間が表現することは不可能に近い光景であり、印象派の多くがこの「川の水面」という題材を正直曖昧にしてきたように思われるのです(特にシスレーやコロ―、ピサロなど)辛うじて「お、これは……」というのはモネの《睡蓮》や《太鼓橋》と思われますが、それでもやはり「印象」の域に留まっているような気がしています。
彼の作品はその「印象」の領域から抜け出し、その「奇蹟的な偶然の積み重ね」を緻密に計算して描写出来ているように感じるのです。写真の模写等でも表現できないその瞬間の偶然のリアルをまるで随意的に表現したかのような彼の絵画は、それまで不随意的に偶然を用いていた抽象表現主義画家とは一線を画するように思えるのです。
そして、それを端的に示しているのが彼の「フォト・ペインティング」という手法。これは写真を絵画に落とし込み、全体をぼかす手法なのですが、これこそ人間の描写限界を超えているような気がするのです。
「ぼかす」というひと手間を加えるだけで、どうしてこうもノスタルジックで泣きたくなる気持ちになるのでしょうか。写真だけであれば、過去の「記録」としては十分なものです。彼はここに「フォト・ペインティング」というひと手間を加えることで、「記録」を「記憶」へ変容させることに成功しているように思います。そして、この「記憶への変容」を可能にしているのが、彼の天才的なところだと個人的には思っているのです。
単に写真の図をぼかせば「記憶」的な表現になるわけではありません。そこには「記憶」へ変容するに相応しいぼかし方があると私は思っています。どれくらいの割合で、どれくらいの長さで、どれくらいの振れ幅で……といったような、具体的な「どれくらい」という基準が彼の中に存在していて、それが人類共通の「記憶性」という要素に通じている、という事実。まさしく圧巻の描写力(とここでは言ってしまいましょう)ではないでしょうか。
また、彼がこの手法を適用した題材というのもまた興味深いものです。彼はドイツで第二次世界大戦を経験した後、東ドイツという共産主義国家に身を置くことになります。彼の哲学には明らかにその頃の経験が反映されています。例えば彼はこの「フォト・ペインティング」という手法の題材として社会主義の代名詞でもある毛沢東の肖像や戦争で殺害された叔母のマリアンネの肖像画を選んでいます。
特に作品《叔母マリアンネ》は叔母の死に対する深い悲しみが否応なしに伝わってきます。これほど、悲哀という感情が喚起される作品も珍しい。
ここまでリヒターだけの話でしたが、この展示の前半に目を奪われたのが、ザオ・ウーキー(中国名は趙無極……厨二病みたいなカッコよさ)という作家です。ザオ・ウーキーは割と目にしていた作家でしたが、改めて、というかリヒターと並べて初めて感じる感覚がありました。
リヒターもザオ・ウーキーも共にぱっと見抽象画なのですが、リヒターの絵画に具体的な対象が見え隠れする一方、ザオ・ウーキーの作品は完全な抽象画に映ります。しかし、こちらも何となく既視感があります。今回の展示に関して言えば、彼の抽象画は非常に宇宙的です。青系をベースとした下地に様々な色が複雑に絡み合い、宇宙の創世を思い起こさせるような作品群ばかりでした。
今迄自分の中でザオ・ウーキーはあまり面白くない作家というイメージが強かったのですが、今回の展示のおかげでザオ・ウーキーの新しい見方、というか本当の良さのようなものがわかったので、これからは要チェックかもしれません!!!(おせえよタコという突っ込みは無視します)
2.アメリカンアートはもう古い?
そして、少し印象的だったことが、アートシーンの変遷です。今回の展示会では冒頭で既にウォーホルやリキテンスタインらのアメリカンポップアートの作品が展示されており、美術史上ではモダンに分類される彼らの作品が既に旧モダンとなっているのだなあと何やら感慨深く思ってしまいました(展示内容自身も、中国現代アーティストやドイツの作家が多くなっていました)
それでも、アメリカンポップアートはやっぱり良いですね~。
今回ではジョン・チェンバレンの作品が印象的でした。ジャンク・アートの作品を間近で鑑賞したのが初めてだったからかもしれないですが……。ガラクタを寄せ集めたアッサンブラージュという手法は、映画のモンタージュを思わせます。このくだらないガラクタの欠片が作品になる感覚は、日常性を捉えた映像が映画を形づくっているのと似たような感覚に陥りますね。
そしてこれらが車の廃材(だったかな?)というところも実に当時の退廃的な消費社会を示しているように感じられ、正に当時のザ・アメリカ的な作品のようでした。
3.写真芸術
そして今回は写真作品も数多くあり、写真は別にな~と思っていた認識がかなり改めさせられました。特に日本トップアーティストの1人である杉本博司の作品と、以前国立新美術館で大々的な個展がやられていたアンドレア・グルスキーの作品はまさに見事の一言。
いずれも単純な写真ではなくひと手間加えた作品となっているのですが、写真芸術の奥深さを改めて感じました。
杉本の海シリーズは長時間露光した海の写真(ダレン・アーモンドの満月の連作を思い出しますね)をモノクロにプリントしたものですが、その海の静謐さと言ったら、もう鳥肌立ちっぱなしでした。最初は白と黒が二色塗られているだけの作品のように見えるのですが、実は白い部分が空、黒い部分が海となっており、その比率は均等に五分五分。抽象的な「静かな海」というイメージを見事に捉えた作品です。
何分見ても飽きない静かな美しさ。「陶酔」するという表現がぴったりですが、この作品を観ていると本当に海の音が聞こえてくるような、奇妙なリアルさがあります(単純に考えると手間を加えない写真方がリアルな気がしますが、彼の作品は実際の写真や、あるいは実際の海よりもよりリアルなのかもしれません)
実際の海と私たちの中にある海というイメージはやはり異なっており、実際の海ではなく私たちの中にある海を捉えているような気がしてならず、それ故に単純な海の写真よりも動きや音が自身の中で響いてくる写真よりも動的な作品になっているのかもしれません。
ここに「動いているものを止める写真」から「止まっている写真を動くように見せる」という彼の根本的な姿勢が現れているような気がします
また、彼の《最後の晩餐》という作品はダ・ヴィンチの同名作品を写真で表現したものなのですが、その被写体は総て実際の役者ではなく、蝋人形を用いている点からも、彼の姿勢の拘りが窺えます。
私たちは実際のイエスやユダの姿を知りません、それ故に実際の人を配置した作品だった場合、私たちは「演技している人」であると認識してしまいます。しかし、そこをあえて蝋人形を対象とすることで、1枚ぼんやりとしたスモークがかかり、彼らのイメージは抽象化→心象風景としてのイエス・ユダにリンクすることになり、実際の人間よりもよりリアルなイエス・ユダ像が私たちの中で形成されることになるのです。
現実よりもリアルという彼の作品は本当に素晴らしいものでした(同じ場所に展示されているロスコ(奇しくも心象風景作家)の作品が見劣りしてしまうくらい!!!)
そして、彼と実は真逆なのではないかというくらい奇妙な写真作品だったのが、アンドレア・グルスキーの作品でした(彼の個展に馳せ参じなかったことを後悔したのは言うまでもありません)
杉本と何が違うかと言うと、彼が現実よりもリアルな作品だったとすれば、グルスキーの作品は写真でありながら非現実的な作品だったということができます。
《メー・デーⅣ》は夥しい量の人が作品(縦2m×横5m!!!)にびっしりと映り込んでおり、それぞれが別々の方向・行動をしていながら、かなり均整に並んでおり、別個の人間でありながらそれが均整を保ったまま1つの大きな作品を形成しているという、なんというか「スイミー」みたいな作品でした。
個々人に目を写すとそれはもう完全にリアルな姿の写真に過ぎないのですが、全体を見た時に露呈する圧倒的非現実感(メーデーという雑然としたものと均整な並びという整然としたものが織りなす不協和音のようなもの)が実にチグハグで奇妙な感覚を引き起こします。
《V&R》も同様、奇妙な均整性がこの作品に非現実感をもたらしています。これはパリコレのようなファッションショーの長い廊下を横から捉えた作品なのですが、ウォーキングするモデルの並びが均整、かつ動きも完璧に合っている(足の出し方向や姿勢)ことが非常に奇妙なリズムを生んでいます。そして、最新ファッションの極彩色がよりこの作品の非現実性を際立てているように感じました。
あとトーマス・シュトゥルートの《アルテ・ピナコテーク、自画像》という写真作品も実にコンセプチュアルで個人的には好きでした。自画像をみる自身を後ろから撮影するという手法で、鑑賞者がこの作品を見て自分の肖像に想いを巡らせることを意図したメタ的な自画像写真で、その狙いが新しく面白かったです。
あー、案の定書きすぎました。これら以外にもマーク・タンジーの《サント・ヴィクトワール山》やピーター・ドイグの《カヌー・湖》、ボール・チアン(江賢二)の四季、サンユウ(常玉)の《六頭の馬》などなど、本当に良い作品ばかりで大満足の展示でした。本当はポストカード買いたかったんですけど、名古屋市美術館に置いておらず大変残念でしたよもう~。。。
次は潮留でやってるキリコの個展に行きたいですね~。あと、ブリジストンでやってるデ・クーニングの個展も!会期中に東京に行く機会があるんかいなという不安はさておき、都合がつけば是非足を運びたいものです。
hona-☆
もう名古屋生活も残り半年を迎え、何やら新天地での仕事が楽しみでもあったり、名古屋での知人としばらく会えなくなるのが寂しくもあり、非常に複雑な思いに駆られているただけーまです。
あまり名古屋では美術展に行かないわたくしですが、今回は行こう行こうと思って行けてなかったヤゲオ財団所蔵の現代美術作品展が巡回に来ていたので(なんと名古屋に!!!)思わず行ってしまいました。
なんか現代アートのアラカルト的な展示だったので、美術史的なコメントは全くできませんので、適当にざっくばらんな感想をば……(あと今回は現代アートばっかりだったので図像もほとんど載せられませんの。本当は全部だめなんだろうけど……)
この展示会は「ミューズ」「ポップ・アート」「サンユウ(常玉)」「中国の近現代美術」「崇高」「威厳」「リアリティ」「記憶」「実存的状況」「新しい美」というテーマで分けられて展示されており、なんだか結構無理やりな分類だなあとか思いながら観覧してましたが、展示されていた作品群は【超】一級品ばかり。作品目録を見ながらその作品の素晴らしさを思わず回想してしまいます。
1.抽象表現主義の先
ポロックやニューマン、デ・クーニングなど、アメリカで隆盛した抽象表現主義の絵画は人間の根源的な部分(例えばポロックの原始性であったり、ニューマンの生命力、デ・クーニングのセックス性であったり)が、それはもう誰も真似の出来ないエネルギッシュで偶然性に満ちた手法で描かれており、個人的にはかなり好きなジャンルの絵画なのですが、今回の展示ではそれらの作風を凌駕する作品に出会えました。
その作風に圧倒されたのが、原題ドイツ美術の最高峰ゲルハルト・リヒターです。現代アーティストランキング世界1位!というテラ・フォーマーズを思わせるような評判(わかる人だけわかってください)に相応しい、圧倒的な作品・絵画手法でした(絵画作品で涙が出たのは久しぶりでした)
マルセル・デュシャンやウォーホルらの登場によって「芸術は終焉した」というのはダントーの言葉ですが、技法的な意味で彼の作品は芸術の終焉の更に先へ到達しているような印象さえ覚えます(美学的な意味での芸術は既に限界を迎えてしまったのかもしれませんが……)
彼の作風を私なりに表現するとしたら「絵画を超えた絵画」といったところでしょうか。彼の絵画は絵画でありながら、従来の絵画とは一線を画す作品のように映ります。人が表現不可能な美的領域を表現することに成功しているように思えてならないのです。
例えば今回展示されていた《川》という作品や《横たわる裸体》という作品は、抽象的でありながら具体的な絵が見えてしまう、そういう不思議な絵画でした。そして美術愛好家の多くはこの感覚を「印象主義」らの手法で知っています。瞬間瞬間の「印象」をぼんやりと筆色分割という技法で表現しようとしたのが印象派であるとすれば、彼はその瞬間の「具体的な光景」をアブストラクト・ペインティングの手法で捉えたと言えるのかもしません。
そして私が彼の作品に鳥肌が立ったのが、彼が意図して制作した絵画が、人間の表現出来ない範囲の美的瞬間をかなり的確に表現しているという点です。例えば《川》は一見したところ全体が緑色の抽象画のように見えますが、その実夜の街のネオンが川に反射して光っているという具体的なイメージがはっきりとわかってしまいます。川の水面の反射は光の屈折や反射、水の濁り具合、外光の強さなど様々な要素が複雑に絡み合った、その瞬間にしかあり得ない光景(印象)であり、言わば「奇蹟的な偶然の積み重ね」とも言うべき光景だと私は思っています(例えばオイルが反射して虹色になる瞬間とか……)
それ故に人間が表現することは不可能に近い光景であり、印象派の多くがこの「川の水面」という題材を正直曖昧にしてきたように思われるのです(特にシスレーやコロ―、ピサロなど)辛うじて「お、これは……」というのはモネの《睡蓮》や《太鼓橋》と思われますが、それでもやはり「印象」の域に留まっているような気がしています。
彼の作品はその「印象」の領域から抜け出し、その「奇蹟的な偶然の積み重ね」を緻密に計算して描写出来ているように感じるのです。写真の模写等でも表現できないその瞬間の偶然のリアルをまるで随意的に表現したかのような彼の絵画は、それまで不随意的に偶然を用いていた抽象表現主義画家とは一線を画するように思えるのです。
そして、それを端的に示しているのが彼の「フォト・ペインティング」という手法。これは写真を絵画に落とし込み、全体をぼかす手法なのですが、これこそ人間の描写限界を超えているような気がするのです。
「ぼかす」というひと手間を加えるだけで、どうしてこうもノスタルジックで泣きたくなる気持ちになるのでしょうか。写真だけであれば、過去の「記録」としては十分なものです。彼はここに「フォト・ペインティング」というひと手間を加えることで、「記録」を「記憶」へ変容させることに成功しているように思います。そして、この「記憶への変容」を可能にしているのが、彼の天才的なところだと個人的には思っているのです。
単に写真の図をぼかせば「記憶」的な表現になるわけではありません。そこには「記憶」へ変容するに相応しいぼかし方があると私は思っています。どれくらいの割合で、どれくらいの長さで、どれくらいの振れ幅で……といったような、具体的な「どれくらい」という基準が彼の中に存在していて、それが人類共通の「記憶性」という要素に通じている、という事実。まさしく圧巻の描写力(とここでは言ってしまいましょう)ではないでしょうか。
また、彼がこの手法を適用した題材というのもまた興味深いものです。彼はドイツで第二次世界大戦を経験した後、東ドイツという共産主義国家に身を置くことになります。彼の哲学には明らかにその頃の経験が反映されています。例えば彼はこの「フォト・ペインティング」という手法の題材として社会主義の代名詞でもある毛沢東の肖像や戦争で殺害された叔母のマリアンネの肖像画を選んでいます。
特に作品《叔母マリアンネ》は叔母の死に対する深い悲しみが否応なしに伝わってきます。これほど、悲哀という感情が喚起される作品も珍しい。
ここまでリヒターだけの話でしたが、この展示の前半に目を奪われたのが、ザオ・ウーキー(中国名は趙無極……厨二病みたいなカッコよさ)という作家です。ザオ・ウーキーは割と目にしていた作家でしたが、改めて、というかリヒターと並べて初めて感じる感覚がありました。
リヒターもザオ・ウーキーも共にぱっと見抽象画なのですが、リヒターの絵画に具体的な対象が見え隠れする一方、ザオ・ウーキーの作品は完全な抽象画に映ります。しかし、こちらも何となく既視感があります。今回の展示に関して言えば、彼の抽象画は非常に宇宙的です。青系をベースとした下地に様々な色が複雑に絡み合い、宇宙の創世を思い起こさせるような作品群ばかりでした。
今迄自分の中でザオ・ウーキーはあまり面白くない作家というイメージが強かったのですが、今回の展示のおかげでザオ・ウーキーの新しい見方、というか本当の良さのようなものがわかったので、これからは要チェックかもしれません!!!(おせえよタコという突っ込みは無視します)
2.アメリカンアートはもう古い?
そして、少し印象的だったことが、アートシーンの変遷です。今回の展示会では冒頭で既にウォーホルやリキテンスタインらのアメリカンポップアートの作品が展示されており、美術史上ではモダンに分類される彼らの作品が既に旧モダンとなっているのだなあと何やら感慨深く思ってしまいました(展示内容自身も、中国現代アーティストやドイツの作家が多くなっていました)
それでも、アメリカンポップアートはやっぱり良いですね~。
今回ではジョン・チェンバレンの作品が印象的でした。ジャンク・アートの作品を間近で鑑賞したのが初めてだったからかもしれないですが……。ガラクタを寄せ集めたアッサンブラージュという手法は、映画のモンタージュを思わせます。このくだらないガラクタの欠片が作品になる感覚は、日常性を捉えた映像が映画を形づくっているのと似たような感覚に陥りますね。
そしてこれらが車の廃材(だったかな?)というところも実に当時の退廃的な消費社会を示しているように感じられ、正に当時のザ・アメリカ的な作品のようでした。
3.写真芸術
そして今回は写真作品も数多くあり、写真は別にな~と思っていた認識がかなり改めさせられました。特に日本トップアーティストの1人である杉本博司の作品と、以前国立新美術館で大々的な個展がやられていたアンドレア・グルスキーの作品はまさに見事の一言。
いずれも単純な写真ではなくひと手間加えた作品となっているのですが、写真芸術の奥深さを改めて感じました。
杉本の海シリーズは長時間露光した海の写真(ダレン・アーモンドの満月の連作を思い出しますね)をモノクロにプリントしたものですが、その海の静謐さと言ったら、もう鳥肌立ちっぱなしでした。最初は白と黒が二色塗られているだけの作品のように見えるのですが、実は白い部分が空、黒い部分が海となっており、その比率は均等に五分五分。抽象的な「静かな海」というイメージを見事に捉えた作品です。
何分見ても飽きない静かな美しさ。「陶酔」するという表現がぴったりですが、この作品を観ていると本当に海の音が聞こえてくるような、奇妙なリアルさがあります(単純に考えると手間を加えない写真方がリアルな気がしますが、彼の作品は実際の写真や、あるいは実際の海よりもよりリアルなのかもしれません)
実際の海と私たちの中にある海というイメージはやはり異なっており、実際の海ではなく私たちの中にある海を捉えているような気がしてならず、それ故に単純な海の写真よりも動きや音が自身の中で響いてくる写真よりも動的な作品になっているのかもしれません。
ここに「動いているものを止める写真」から「止まっている写真を動くように見せる」という彼の根本的な姿勢が現れているような気がします
また、彼の《最後の晩餐》という作品はダ・ヴィンチの同名作品を写真で表現したものなのですが、その被写体は総て実際の役者ではなく、蝋人形を用いている点からも、彼の姿勢の拘りが窺えます。
私たちは実際のイエスやユダの姿を知りません、それ故に実際の人を配置した作品だった場合、私たちは「演技している人」であると認識してしまいます。しかし、そこをあえて蝋人形を対象とすることで、1枚ぼんやりとしたスモークがかかり、彼らのイメージは抽象化→心象風景としてのイエス・ユダにリンクすることになり、実際の人間よりもよりリアルなイエス・ユダ像が私たちの中で形成されることになるのです。
現実よりもリアルという彼の作品は本当に素晴らしいものでした(同じ場所に展示されているロスコ(奇しくも心象風景作家)の作品が見劣りしてしまうくらい!!!)
そして、彼と実は真逆なのではないかというくらい奇妙な写真作品だったのが、アンドレア・グルスキーの作品でした(彼の個展に馳せ参じなかったことを後悔したのは言うまでもありません)
杉本と何が違うかと言うと、彼が現実よりもリアルな作品だったとすれば、グルスキーの作品は写真でありながら非現実的な作品だったということができます。
《メー・デーⅣ》は夥しい量の人が作品(縦2m×横5m!!!)にびっしりと映り込んでおり、それぞれが別々の方向・行動をしていながら、かなり均整に並んでおり、別個の人間でありながらそれが均整を保ったまま1つの大きな作品を形成しているという、なんというか「スイミー」みたいな作品でした。
個々人に目を写すとそれはもう完全にリアルな姿の写真に過ぎないのですが、全体を見た時に露呈する圧倒的非現実感(メーデーという雑然としたものと均整な並びという整然としたものが織りなす不協和音のようなもの)が実にチグハグで奇妙な感覚を引き起こします。
《V&R》も同様、奇妙な均整性がこの作品に非現実感をもたらしています。これはパリコレのようなファッションショーの長い廊下を横から捉えた作品なのですが、ウォーキングするモデルの並びが均整、かつ動きも完璧に合っている(足の出し方向や姿勢)ことが非常に奇妙なリズムを生んでいます。そして、最新ファッションの極彩色がよりこの作品の非現実性を際立てているように感じました。
あとトーマス・シュトゥルートの《アルテ・ピナコテーク、自画像》という写真作品も実にコンセプチュアルで個人的には好きでした。自画像をみる自身を後ろから撮影するという手法で、鑑賞者がこの作品を見て自分の肖像に想いを巡らせることを意図したメタ的な自画像写真で、その狙いが新しく面白かったです。
あー、案の定書きすぎました。これら以外にもマーク・タンジーの《サント・ヴィクトワール山》やピーター・ドイグの《カヌー・湖》、ボール・チアン(江賢二)の四季、サンユウ(常玉)の《六頭の馬》などなど、本当に良い作品ばかりで大満足の展示でした。本当はポストカード買いたかったんですけど、名古屋市美術館に置いておらず大変残念でしたよもう~。。。
次は潮留でやってるキリコの個展に行きたいですね~。あと、ブリジストンでやってるデ・クーニングの個展も!会期中に東京に行く機会があるんかいなという不安はさておき、都合がつけば是非足を運びたいものです。
hona-☆










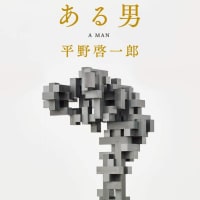









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます