公約通り、大江の各短編の所感を書いていきます。全部書けるかはわかりませんが、とりあえず書けそうなものから。
【死者の奢り】
大学生である僕と女学生が、死体処理室に保管されていた遺体を新しい水槽に移し替える仕事に従事していく中で、死と生と身体の在り方に関する問いが繰り広げられていく非常に哲学的な小説です。
特に女性アルバイトが妊娠していたことが発覚するシーンでは、新しい生命を宿した妊婦が死体を扱うという死生学的な命題が提示されているようです。アルバイトの目的が出産費用を確保するためというのも、なかなかアイロニカルな構造です。
何十年も保管されてきた遺体はそのものが歴史を帯びており、処理室は時が止まっているかのように「死者の世界」が繰り広げられているのですが、そこでの死体の表現が非常に巧みでした。濃褐色のアルコール溶液に浸された死体は飴色に染まり、身体は身体とは思えない物質的な≪物≫として描写されています。「硬く内側へ引き締まる感じ」や「吸収性の濃密さ」など、人体ではなくゴム人形のような描写もさることながら、身体的な特徴も排除されることで男女の性別も曖昧となった遺体たち。主人公は対峙する中で遺体を≪物≫であると強く認識しようとします。そうした中で出てくる「物と意識との曖昧な中間状態をゆっくりと推移している」というフレーズには、主人公が遺体を物体として捉えることに対する躊躇いも見て取れます。(主人公はすぐに火葬される死体の方がより人間的だと考えている)
しかし、こうした物体的な身体は突然現れる助教授(暴力的な生や合理性を暗示するアイコンなのかもしれない)の「古い遺体は全て火葬することに決まっている」「この遺体は医学的にもう使えない」という一連の言葉によって、あっけなく火葬されることになります。物体的身体は本当の意味で死体となり(生者-物体的身体-死者というバランスの崩壊)、遺体の物体性と歴史に訪れる突然の終幕。仕事に誇りを持っていた管理人も、権力者である助教授にあっさりと言い負かされてしまいます。
淡々と進められる焼却の準備とずかずかと乗り込んでくる助教授の一行。死者たちの空間はあっという間に(強い)生者の空間に様変わりし、それまで天窓から差し込む灯りで「微妙なエネルギーに満ちた弾力感」を与えられていた死者たちは電灯の光で「ぶよぶよし、腫れぼった」い印象になってしまいます。死者は死者(或いはそれに準ずる存在)の空間でのみ物体的な弾力感を見せますが、それが暴力的な合理性とともに整理されていく。それは死体を大事に扱おうとする管理人の姿勢とも対比されています。
こうした生者と合理性の波で死者の世界が閉じていく感覚、よそよそしくなっていく様、それは死者の世界に半歩踏み入れていた<僕>という存在の回帰でもあるようです。
【死者の奢り】
大学生である僕と女学生が、死体処理室に保管されていた遺体を新しい水槽に移し替える仕事に従事していく中で、死と生と身体の在り方に関する問いが繰り広げられていく非常に哲学的な小説です。
特に女性アルバイトが妊娠していたことが発覚するシーンでは、新しい生命を宿した妊婦が死体を扱うという死生学的な命題が提示されているようです。アルバイトの目的が出産費用を確保するためというのも、なかなかアイロニカルな構造です。
何十年も保管されてきた遺体はそのものが歴史を帯びており、処理室は時が止まっているかのように「死者の世界」が繰り広げられているのですが、そこでの死体の表現が非常に巧みでした。濃褐色のアルコール溶液に浸された死体は飴色に染まり、身体は身体とは思えない物質的な≪物≫として描写されています。「硬く内側へ引き締まる感じ」や「吸収性の濃密さ」など、人体ではなくゴム人形のような描写もさることながら、身体的な特徴も排除されることで男女の性別も曖昧となった遺体たち。主人公は対峙する中で遺体を≪物≫であると強く認識しようとします。そうした中で出てくる「物と意識との曖昧な中間状態をゆっくりと推移している」というフレーズには、主人公が遺体を物体として捉えることに対する躊躇いも見て取れます。(主人公はすぐに火葬される死体の方がより人間的だと考えている)
しかし、こうした物体的な身体は突然現れる助教授(暴力的な生や合理性を暗示するアイコンなのかもしれない)の「古い遺体は全て火葬することに決まっている」「この遺体は医学的にもう使えない」という一連の言葉によって、あっけなく火葬されることになります。物体的身体は本当の意味で死体となり(生者-物体的身体-死者というバランスの崩壊)、遺体の物体性と歴史に訪れる突然の終幕。仕事に誇りを持っていた管理人も、権力者である助教授にあっさりと言い負かされてしまいます。
淡々と進められる焼却の準備とずかずかと乗り込んでくる助教授の一行。死者たちの空間はあっという間に(強い)生者の空間に様変わりし、それまで天窓から差し込む灯りで「微妙なエネルギーに満ちた弾力感」を与えられていた死者たちは電灯の光で「ぶよぶよし、腫れぼった」い印象になってしまいます。死者は死者(或いはそれに準ずる存在)の空間でのみ物体的な弾力感を見せますが、それが暴力的な合理性とともに整理されていく。それは死体を大事に扱おうとする管理人の姿勢とも対比されています。
こうした生者と合理性の波で死者の世界が閉じていく感覚、よそよそしくなっていく様、それは死者の世界に半歩踏み入れていた<僕>という存在の回帰でもあるようです。










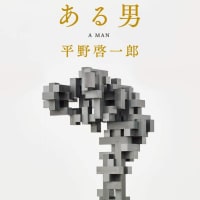









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます