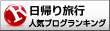新しい環境、新しい人間関係にもようやく慣れてきた春の半ば。
ふと、体が緑を欲しがっていませんか?
それは単なる野菜不足ではありません。
心に栄養を与えるため、いざ、新緑の京都へ。
庭園鑑賞の豆知識
庭園を楽しむのに、理屈は要りません。
ぼんやりと眺めたり、池に沿って歩いてみたり、せせらぎに耳を傾けたり。
でも、一見自然のままに見えるような庭園でも、それを作った人々の時代背景や想いが込められていたりします。
その意図をくみ取りながら鑑賞したとき、また新たな発見があるかもしれません。
有名であっても、そうでなくても、自分にとって心地よく感じられたら、そこがあなたにとっての「名庭」。
今回は、新緑の瑞々しさを感じられるような池泉庭園と静かな新緑コースをご紹介します。

日本庭園の特徴…「自然風景式」
千年もの遙か昔から、日本人は自然に対して畏れの念を抱き、信仰の対象でもありました。
現在の私達が大木や巨石、泉や花等の自然の営みに対して敬虔な気持ちになるのは、古から受け継がれている日本人としてのDNAのなせる業なのかもしれません。
石を環状に並べたり、立てた遺跡や、山の中で露出している岩等を信仰の対象としていたものが、大陸からの文化、宗教、哲学の影響を受けて、自然に対しての敬いと人間の理想郷を抽象的に表現した、日本独自の空間芸術としての庭園が形成されていきました。
日本庭園の歴史と京都の庭園
上古~飛鳥・奈良時代の日本庭園…信仰の対象から自然風景式へ 庭園という概念があったかどうかは定かではありませんが、石を環状に並べた「環状列石」や、山の岩等を神として崇拝する「磐座」等がありました。
また、池を遥かな海に例え、その中に中島を作り、神を奉ったりもしていました。
それから流れや滝、を構えて石を据えるようになり、自然風景式の日本庭園が誕生しています。

鞍馬寺奥の院
平安時代の日本庭園…仏教の伝来により浄土式、貴族好みの寝殿造庭園へ
以前から伝来していた中国道教の蓬莱思想に加え、仏教の須弥山思想が入って盛んにその宗教観や哲学観が庭園に表現され、その頃に流行しいていた浄土式庭園の形態が現れています。

京都では、三方を山で囲まれた盆地であり、多くの清流に恵まれ、程良い起伏の林休や池・湿地も多く、チャートやホルンフェルス、花崗岩等の豊富な種類の岩石が産出するという自然的条件に恵まれ、平安京が置かれた事で千年もの間、日本の政治や文化の中心地であった事から、庭園文化が発展していきました。

東本願寺渉成園、勧修寺、積翠園
(平安初期)

皇族や貴族が、嵯峨野周辺に山荘を営み、遊猟していました。
その頃の貴族住宅・寝殿造りの庭園を「寝殿造庭園」と呼びます。

大覚寺の大沢池と名名古曾滝は、嵯峨天皇の離宮嵯峨院の遺構発掘調査により、高陽院(かやのいん)や堀河院等の庭園の一部が移築保存

「作庭記」(重文)は、自然をモチーフにした寝殿造庭園の作庭理念や技法を記した現存最古の作庭書です。
(平安中~末期)
浄土思想のもと、阿弥陀仏を中心とし、西方浄土の極楽に見たてた美しい池庭「浄土庭園」が作られ、全国に普及しました。
海岸風景や河川を模した洲浜、荒磯や遣水、泉を取り込んだ泉殿等が見られます。

平等院庭園、法金剛院庭園
中世の日本庭園…心象風景を表現。
禅と茶の湯の影響で枯山水や露地が誕生 浄土式の池泉舟遊式から回遊式へ、自然風景から心象風景の表現になっていきます。
広い池庭に蓬莱島や鶴島、亀島などを配し、三尊石組の手法が登場します。

ふと、体が緑を欲しがっていませんか?
それは単なる野菜不足ではありません。
心に栄養を与えるため、いざ、新緑の京都へ。
庭園鑑賞の豆知識
庭園を楽しむのに、理屈は要りません。
ぼんやりと眺めたり、池に沿って歩いてみたり、せせらぎに耳を傾けたり。
でも、一見自然のままに見えるような庭園でも、それを作った人々の時代背景や想いが込められていたりします。
その意図をくみ取りながら鑑賞したとき、また新たな発見があるかもしれません。
有名であっても、そうでなくても、自分にとって心地よく感じられたら、そこがあなたにとっての「名庭」。
今回は、新緑の瑞々しさを感じられるような池泉庭園と静かな新緑コースをご紹介します。

日本庭園の特徴…「自然風景式」
千年もの遙か昔から、日本人は自然に対して畏れの念を抱き、信仰の対象でもありました。
現在の私達が大木や巨石、泉や花等の自然の営みに対して敬虔な気持ちになるのは、古から受け継がれている日本人としてのDNAのなせる業なのかもしれません。
石を環状に並べたり、立てた遺跡や、山の中で露出している岩等を信仰の対象としていたものが、大陸からの文化、宗教、哲学の影響を受けて、自然に対しての敬いと人間の理想郷を抽象的に表現した、日本独自の空間芸術としての庭園が形成されていきました。
日本庭園の歴史と京都の庭園
上古~飛鳥・奈良時代の日本庭園…信仰の対象から自然風景式へ 庭園という概念があったかどうかは定かではありませんが、石を環状に並べた「環状列石」や、山の岩等を神として崇拝する「磐座」等がありました。
また、池を遥かな海に例え、その中に中島を作り、神を奉ったりもしていました。
それから流れや滝、を構えて石を据えるようになり、自然風景式の日本庭園が誕生しています。

鞍馬寺奥の院
平安時代の日本庭園…仏教の伝来により浄土式、貴族好みの寝殿造庭園へ
以前から伝来していた中国道教の蓬莱思想に加え、仏教の須弥山思想が入って盛んにその宗教観や哲学観が庭園に表現され、その頃に流行しいていた浄土式庭園の形態が現れています。

京都では、三方を山で囲まれた盆地であり、多くの清流に恵まれ、程良い起伏の林休や池・湿地も多く、チャートやホルンフェルス、花崗岩等の豊富な種類の岩石が産出するという自然的条件に恵まれ、平安京が置かれた事で千年もの間、日本の政治や文化の中心地であった事から、庭園文化が発展していきました。

東本願寺渉成園、勧修寺、積翠園
(平安初期)

皇族や貴族が、嵯峨野周辺に山荘を営み、遊猟していました。
その頃の貴族住宅・寝殿造りの庭園を「寝殿造庭園」と呼びます。

大覚寺の大沢池と名名古曾滝は、嵯峨天皇の離宮嵯峨院の遺構発掘調査により、高陽院(かやのいん)や堀河院等の庭園の一部が移築保存

「作庭記」(重文)は、自然をモチーフにした寝殿造庭園の作庭理念や技法を記した現存最古の作庭書です。
(平安中~末期)
浄土思想のもと、阿弥陀仏を中心とし、西方浄土の極楽に見たてた美しい池庭「浄土庭園」が作られ、全国に普及しました。
海岸風景や河川を模した洲浜、荒磯や遣水、泉を取り込んだ泉殿等が見られます。

平等院庭園、法金剛院庭園
中世の日本庭園…心象風景を表現。
禅と茶の湯の影響で枯山水や露地が誕生 浄土式の池泉舟遊式から回遊式へ、自然風景から心象風景の表現になっていきます。
広い池庭に蓬莱島や鶴島、亀島などを配し、三尊石組の手法が登場します。



西芳寺の枯滝石組・夜泊石,鹿苑寺の蓬莱島(鎌倉時代)

この頃、水を用いない代わりに砂で大海を、石や刈り込みの木で大山を表現する「枯山水」が登場します。

大徳寺大仙院書院庭園(室町時代)
また、茶の湯と共に露地(茶庭)は「市中の山居」と呼ばれるものが現れて精神文化を深く追求し、近世以降の町家の坪庭へと展開していきます。
中世~近世の日本庭園…武士好みの「書院庭園」、饗宴の空間としての「回遊式庭園」
武家の居館の庭は「書院庭園」と呼ばれ、主従対面の儀式で使用される座観の庭という様式を持っており、寺院方丈にも展開していきます。
園(安土・桃山時代)、南禅寺金地院(江戸初期)
一方で公家が王朝時代の風流を受け継ぎ、池庭に茶室を建て、連歌等を楽しむ「回遊式庭園」を営み、後に大名の饗宴の空間としても発展します。

桂離宮(安土・桃山時代)
近代の日本庭園…数寄者の交流の場として。
里山の風景をモチーフに
江戸中期からの自然風景主義的な庭園は、集大成の時代を迎えます。
東京遷都により、一時活気を失った京都は琵琶湖疎水を完成させ、その水を利用した別荘庭園群が岡崎と南禅寺の界隈にでき、数寄者の交流の場として新たな庭園文化を築きます。
現在作られている庭園はこのような形式のものがよく見られます。

対流山荘庭園(明治時代)
京都各地の庭園は、そのまま保存されているものや、新たな時代の要素が加わっているものもあるため、作庭年代や作者、様式を特定しにくいものもあります。
今私達が眺めている庭園も、時代が変わるごとに進化をし続けていくのかもしれませんね。

松尾大社松風苑(昭和)

※写真は全て過去のものです。