もう何度も行ったことがある場所なのだけれども、雰囲気が一変していて驚いた。
池の見た目が変っているわけではないが、観光客が99%中国人で、日本語がほとんど聞かれなかった。日本人にもそれなりに人気のあるスポットだけれども、こんなに大量の中国人が来るって事は、澄んだ泉に中国国民の感性に訴える何かがあるってことなんだろうか。中国版百度で検索すると中国語のページが出てくるのが面白い。
海外でも、現地の人にはそれほどでもないけれど、日本人の感性に訴えるような観光地ってのがあるんだろうなと思った。
しかし、これほど中国人密度の高い環境下にあって、中池の前にある池本荘のお土産販売ゾーンは、店員さんは全員ぺらぺら中国語を喋っていたけれども、商品説明のポップが全くといっていいほど中国語対応されていないのが不思議だった。土産物屋がここだけなので競争が発生せず、日本語でも何とかなると思ってるのだろうか。
お店の中でボヤッとしていると、日本人の店員さんに中国語で声をかけられた。日本人は中国人とほとんど見分けがつかないってことが、あらためてよく分かった。
池の周りで、写真を撮っている中国人の家族に場所を譲ると、"Thank you"といわれた。どこまで行っても、英語が世界の共通語なんだなと、あらためて強く感じた一瞬だった。
何かしら追い立てられているような気がして、たまには何も考えずに走りたくなって、久しぶりに走ってみた。
久里浜に住んでいると、房総半島以外はどこに行くにも億劫になってしまう。久しぶりに走った道志みちは、もう一年半ぶりくらいになってしまった。
横々~保土ヶ谷BP~R413と走り、三ヶ木を左折して青山の交差点から道志へ。久里浜から一時間半強程度だったかな。梶野の交差点近くのコンビニで一休み。コンビニの駐車場で露店で売っている野菜が相変わらず、すごい量ですごく安い。プラムを買ってその場で洗い、走りながら食べることにする。他にも、桃やピーマン、生姜、キュウリ、ジャガイモなどいろいろあれこれと買い込む。バイクだと積載量を気にしてなかなか買えないところ、四輪だと気にせずに買えるのがよい。
道志みちは、変っていないようで、ずいぶんと変っていた。東京圏から一時間前後とは思えないほどの山の深さは相変わらず。でも、時折町並みを抜けていた細い道がどんどんバイパス化されて、人々の生活圏とレジャーで訪れる人のドライブ圏が分離されている。特に、青根の集落のバイパスを通り過ぎたときには感慨深いものがあった。
道志みちは、特に走るのが好きな車やバイクが多い。深夜にハイスピードで転がす車が生活圏を突っ切るのは危なくて仕方ないことだろう。でも、何年か前の夏の夜に道志を走っていたとき、たまたま出くわした青根の集落のお祭りの御輿は、この付近にこんなに人がいたのか、と驚くくらい沢山の人が集まっていて、熱気があって、とても楽しそうだった。そんな一コマにふとめぐり合えるのが、ふらりと走るツーリングの醍醐味のひとつでもある。
地元の生活圏とレジャー圏を分離するということは、観光資源を一つ手放し、その代わりに地元の生活圏の安全と平穏を保つことになると思う。気楽な部外者である一ツアラーに何を言う資格も無いけれど、変わってゆく道に、ただ感慨を覚えた。
道の駅道志は、駐車場スペースも軽食スペースも増床されていて、相変わらずの賑わいを感じさせた。駐車場のバイクの数も、湧き水の美味しさも、ワサビDEクレソンの味もあまり変らず、穏やかに時間が過ぎる。今回はクレソンのパウンドケーキも食べてみたけれど、とても美味しかった。
津久井のあたりではよく晴れていたのが、山梨に入ってからは曇りがちになり、山伏峠方面は厚い雲に覆われている。少々迷ったがそのまま山中湖まで走ってみた。山伏トンネルの出口は濃霧に覆われ、視界は数十メートル。テニスコートを両脇にきれいに聳える富士山の眺めは別の日のお楽しみにとっておこう。
山中湖周遊道路を走り、忍野八海を見てから河口湖へ。河口湖温泉街で宝刀を食べるともう7時半をまわってしまった。暗い湖面にライトアップされた河口湖大橋が浮かんでいた。
中央道を一路東京へ。途中、左手に圏央道への分岐が見え、ついに中央道と繋がったのかと、ここでもしばし感慨にふける。いったい何年の間、「つながります!圏央道!」の看板に向かって「いつできるんだ!」とヘルメットの中で突っ込みを入れていたのか、もう思い出せないくらいだ。いつの日か、東名高速につながり、いつの日か横々道路まで繋がるのだろう。その頃、僕はいったいどこでなにをしているのだろうか。
久しぶりのドライブは、思い出ばかりがよみがえってくる、感慨の多いものだった。
悪くは無いけれど、素晴らしいって訳でもない。
今度は、新鮮な感動を感じられるような道にしよう。
数年前から、右手の親指に妙なできものができていた。
素人判断でずっとイボだと思い込んでいて、市販のスピール膏を貼ったりヨクイニン粉末を服用したりしていたのだけれども、一向に小さくなる気配もなかった。逆に大きくなる気配もなかったので、そのままにしておいた。
とはいえ気になる事もあって、久里浜駅前の久里浜駅前皮フ科に行って診てもらったこともあったのだけれども、やっぱりイボだといわれて通り一遍の処置をしてもらい、地道に通院するしかないといわれて気が萎えていた。
 そんな共生関係にあったヤツだけれども、この二月ごろから急に活発に成長を始め、今まで皮膚が盛り上がっていたようなモノだったのが、皮膚から突き出たモノへと変貌を遂げ始めた。これは様子がおかしいと思い、三月末に横須賀中央にある峯村皮膚科クリニックという別の皮膚科に行ってみた。
そんな共生関係にあったヤツだけれども、この二月ごろから急に活発に成長を始め、今まで皮膚が盛り上がっていたようなモノだったのが、皮膚から突き出たモノへと変貌を遂げ始めた。これは様子がおかしいと思い、三月末に横須賀中央にある峯村皮膚科クリニックという別の皮膚科に行ってみた。
看護婦さんが見て十秒後に首をかしげ、医者の先生を呼んだところ、お医者さんは一目でイボじゃないと断定し、切るのが一番速いと言われた。うーん、医者によってこんなにも判断が違うものか。医者と一口に言ってもいろいろいるんだなぁ。
利き手の親指って事もあって、大きな病院で切ってもらいなさいといわれ、横須賀共済病院に紹介状を書いてもらう。四月上旬、えらく混雑している病院で二時間待って診察を受け、良性腫瘍といわれる。先生の施術のスケジュールの関係で手術は一ヶ月後。まぁ、四月中は週末もいろいろあったし、親指が使えなくなるのは不便だから僕としてもちょうどよかった。
しかしGW中にヤツは自らの運命を悟ったのか、成長の速度を速め、ぐんぐんと長くなってきた。GW前後で比べると三ミリくらいは延びたんじゃないだろうか。
しかしヤツの運命が変ることも無く、GWが明けた先日の11日に、大げさに入院。昼前に病院に入り、数時間待ってから30分ほどで切り取る。執刀してくれた先生はずいぶんなベテランらしく、手際もよく手術中の会話も安心させてくれるもので、とてもよかった。看護婦さんや他の先生にも人望がある人のようだった。
六時間ほど経って、消灯時間になると麻酔が切れ始める。ガマンできなくなるほど痛かったら飲みなさいと渡されていた痛み止めがあったけれども、ガマンできる範囲内だが寝付けない程度の痛みの場合はどうすればいいのだろうか。まぁどうせ明日も休みだし少々寝不足でもかまわないと思ってガマンし続けていたら、二時ごろに寝付いていた。
翌日も強烈にヒマ。朝ごはんを食べ、ついに読了してしまった「ものづくり経営学」を適宜ひっくり返しながら時間を持て余していると、やっと簡単な診察があり、消毒の仕方などを教えてもらって退院。
振り返ってみると、最初に久里浜駅前皮フ科で診てもらったときにイボ扱いされたのが残念。このお医者さんはアトピーの治療などでは有名なところらしく、良いお医者さんだと思っていたのだけれども、いかんせん混雑が激しすぎるのできちんと診る余裕も無かったのだろうか。二番目の峯村皮膚科クリニックは一回診てもらっただけだけれども、わかりやすく説明してくれたのでいい印象を受けた。横須賀共済病院で担当してくれた先生は説明もしっかりしてくれて、とてもいい先生だったと思う。まぁ、この程度なら入院する必要も無かったのではなかろうかと思ったけれども、しかしそれも素人考えかもしれないし、まぁそれは仕方ないことなのかな。
それよりも、入院は初めてだったので、その経験のほうが心に残った。同室の様子を伺ってみると、やはり年配の人が多い。点滴をうち、頻繁に医師が検査に訪れる人を目の当たりにすると、自らの体が思うままにならないというのがどんなに辛いことなのか、いままで頭でわかっていたつもりのことがより強く感じられる。別のおじいさんは、看護婦さんが車椅子で移動しましょうと何度言っても、いや、自分で歩くといって聞かない。可能な限り自分の体で歩くんだという思いが声の調子から伝わってきて、心を打たれた。
たった一日だったけれども、いろいろと考えさせられる時間だった。
昨日に引き続き、晴れていたので歩いてみた。
今日は10年ぶりくらいにヤビツ峠から大山へ登る。昨日登った大楠山よりはちゃんとした山なので、それなりに食べ物も飲み物も必要。朝6時前に起きておにぎりや野菜炒めなどを適当に作り、お弁当にする。連れは梅干のおにぎりは三角で、昆布のおにぎりは俵で作って中身がわかるようにするというが、僕は全部同じ形にして、三回連続で梅干になってしまったりするような危険性をはらんだギャンブル性のあるお弁当が好きだ。
8時前に出発。下道で葉山~鎌倉~江ノ島と進む。連休も中日ということで思ったよりも渋滞もなく、暑すぎず寒すぎない快適な陽気の中、Z3をオープンにして快適に海岸沿いの国道134を西に進む。西湘二宮でR134を離れ、県道71号を北上して秦野中井I.C.を過ぎ、R246の名古木交差点で県道70号に入り、ヤビツ峠を目指す。名古木と書いてナカヌキと読む珍しい交差点は忘れられない。以前相模大野に住んでいたときにはよく来た道だ。もう3年以上前になるものか。早いもんだ。
ヤビツ峠までの登り坂も所々のコーナーに見覚えがあって、ほとんど変わっていない。でもバイクで走っていたときは十分に広い道だと思っていたけれど、車で走るとずいぶん狭く感じるので奇妙な違和感がある。ヤビツ峠に着いたのは10時過ぎ。久里浜から二時間少々で着くとは、思っていたよりも速かった。

連休で天気が良いこともあり、登山者が大量に着ていてヤビツ峠の駐車場は満杯。少しやり過ごしたコーナーの空き地に車を停め、歩き始めが10時20分ごろだったろうか。鶯の鳴き声が響く道をのんびり歩き始める。
10年前に比べると整備されて階段が増えていたり、ちょっとガレているだけで鎖が張ってあったりと雰囲気が少し変ったなと思いつつ歩く。20分くらい毎に休んで水を飲み、秦野方面や丹沢方面の見晴らしを楽しむ。ヤビツからの道はそれほど人がおらず、5分に一度すれ違う程度だったけれども、70分ほど歩いて大山下社からの登山道と合流すると、一気に登山者が増えて人の中を歩く感じになった。最後にちょっと急な階段を登ると頂上に到着する。11時40分についたので、80分ほど歩いたことになる。コースタイムは一時間程度だけれども、のんびり歩いていたからこんなもんかな。
頂上からの眺めは昨日と同様に靄がかかっていたので、相模湾の海岸線がかろうじて判別できるか、といった程度だったけれども、伊豆、箱根、厚木、横浜、川崎方面まで一望できる眺めはやっぱり素晴らしい。風も強くなく、暖かい陽気で快適だった。
GWで天気が良いだけあって、頂上はまさに人でごった返していて、座れそうなところにはたいてい人が座っていた。阿夫利神社の近くのちょっとした隙間をなんとか見つけて、お弁当を食べる。適度におなかが減っていて、おにぎりも野菜炒めも美味しかった。周りにはいろんな人がいて、見ていると面白い。若い二人連れ、中年の二人連れ、小学生くらいの子どもを連れた夫婦、孫を連れたおじいさん、高校生くらいの女性の三人組、バイク乗りの格好をした男二人連れ、犬と一緒の夫婦などいろんなパタンがある。僕たちのような二人連れもずいぶん多かった。

一時間ほど頂上でゆっくりしてから下山。同じ道を通ってヤビツ峠に降り、少し奥に行った護摩屋敷の清水で水を飲む。この水を飲んだのも4,5年ぶりくらいのはずだ。懐かしいなぁ。以前は志を集める募金箱がおいてあったのだけれども今回は無かった。水場のメンテナンスをする必要がなくなったわけでもないだろうに、やっぱり心無い人が持って行ったりするからなんだろうか。残念だ。
帰り道、県道70号沿いにある大山豆腐のお店「五右衛門」に立ち寄り、湯葉と納豆と、豆乳チーズケーキを買う。
今日もよく歩いたので帰りは温泉に立ち寄る。七沢温泉にでも行こうと思っていたけれども、途中で気が変ったので鶴巻温泉へ。立ち寄り湯の弘法の里湯は駐車場が一杯だったので、大和旅館というところで外湯にはいり、往路と同じ下道を走る。帰路はR134が少し流れが悪かったけれども、渋滞というほどのものでもなく、快適なドライブだった。
昨日は寿司だったので、今日は焼き鳥。久里浜駅のおんどり家で焼き鳥とビールを楽しむ。今日もよく歩いた。
翌朝、「五右衛門」で買った納豆と湯葉で朝食。翌朝の朝食にしたのだけれども、湯葉は上品な甘みがあってとても美味しく、納豆は大粒の豆をかみ締めると豆の味がしっかりして食べ応えがあった。思わずスーパーで買った三パック68円のおかめ納豆と食べ比べてしまったけれども、味も食感も雲泥の差だった。いままで納豆の優劣なんて気にしたことも無かったけれども、こうやってよいものを知ってしまうとこれから選んでしまいそうだ。また少し食費が上がっちゃうなぁ・・・・・・・。豆乳チーズケーキはフワットして甘く、いくらでも食べ続けられそうな素直な美味しさだった。
GW後半は、西伊豆の民宿に泊まって海の幸を堪能しようと思っていた。
でも、直前になってしまってから宿泊できるわけもなく、20件程電話をかけてみてもどこも埋まっていたので、仕方なく三浦半島に居続けることにした。
ただ漫然と居続けるのも芸がない。天気が良かったので、四日は三浦半島の最高峰である大楠山に登ってみた。
書店で斜め読みした本に載っていたハイキングコースがよさそうだったので、少し遠くではあるけれども、京急安針塚駅から出発。快晴に恵まれて暑いほどの陽気の中、家並みの間を少し歩くと塚山公園への登り道が始まる。思ったよりもきつい坂道を10分ほどかけてのんびり登る。133メートルの標高があって、観音崎から横須賀中央、金沢八景、横浜みなとみらい地区が一望できる、眺望がよいところだった。ここにはウィリアム・アダムスの墓である安針塚もある。
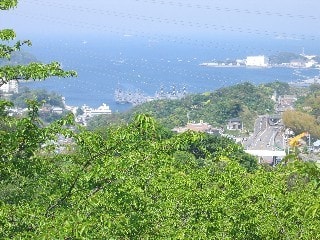
既に疲労感を顔に出していた連れが少し休むのを待って、南西方向に降り、横須賀I.C.の下をくぐり、大繁盛していた鳥ぎんを左手に見ながら南下する。名前は聞いたことがあったけれども、初めて見た店だ。美味しいという話を聞いたことがあるのでいつか行ってみたい。
葉山と衣笠を結ぶ県道27号線に出て、少し西にあるくと大楠山登山口という信号があり、そこから再度南下する。民家の間の細い道を縫い、阿部倉温泉の付近を歩くと横横道路のすぐ脇に出る。道路標識には、右に曲がると大楠山、直進するとしょうぶ園、戻ると塚山公園とある。そういえば先日衣笠のしょうぶ園に行ったとき、大楠山方面と書かれた道路標識があったことを思い出した。案外近くまで来ているもんだなと妙に感心して大楠山方面へ進む。
横横道路をくぐると、舗装道が途切れて山道になる。やっと大楠山登山が始まった気になる。軽装のハイカーと次々にすれ違いながらのんびり登り続けるが、階段の整備率が高く、坂も急なので思ったよりもしんどい道だった。途中で横須賀市に関するクイズ板がいくつかあったりするのはよいけれども、少し迷うようなポイントでも標識がないところがあったりして、もう少ししっかり整備したほうがよいと思った。

20分ほどかけて大楠山山頂へ。西側に視界が開けて三崎から相模湾を一望できる素晴らしい眺め。あいにく靄がものすごくて江ノ島がぼんやり見える程度だったけれども、秋や冬に来たならば素晴らしい富士山を眺められることだろう。更に、大楠山は標高241メートルとは言え三浦半島では一番高い山なので、見晴台に登ると三浦半島全域が見渡せる360度の眺望が楽しめる。北側を向くと湘南国際村から大楠山へ続く葉山国際カントリークラブの全域がすぐ手元に広がり、その向こうにはうっすらと横浜のランドマークタワーが見える。南を見れば目の前に先日登った武山とYRPエリアが見え、僕の職場でもある巨大な黒い建物が異様な存在感を示している。
しばらく眺望を楽しんでから東側へ下山。一時間ほど荒れた舗装道を歩いて芦名口へ到着した。下山中、山肌のあちこちに野生の藤が上品な紫色の花を咲かせていた。先日しょうぶ園で見た一面の藤も素晴らしかったけれども、こうやってそこかしこに見える花も美しく、心を和ませてくれる。
三浦半島の東岸にある安針塚駅から半島を横切って西岸にある芦名口まで、大体3時間ほどかけて歩いた。10分ほどバスを待って逗子駅へ行き、JRで久里浜駅へ戻る。
僕は久しぶりにちょっとした坂道を歩いたし、連れも山道を歩くのは子どもの時以来だというのでかなり足に来た様子。久里浜駅前の銭湯でゆっくり足をほぐしてから、ひさご寿司で伊豆の民宿に泊まれなかった分まで刺身と天婦羅と寿司を食べまくり、満足して帰宅。一泊一万円の民宿に二人で泊まったと思えば安いもんだ。
今年のGWは予定を立てる間もなくやってきた。
GW初日はメーデーの手伝い。いろいろ思うこともあったけれども、わざわざブログに残すほどのものでもない。
二日目は本を読み、髪を切った。先日職場を去った後輩の机から発掘したDEBUGGING THE DEVELOPMENT PROCESSを読み、ソフトウェア開発と研究との違いがあるとは言え、ずいぶんと考えるところが多く、ためになった。現在の自分の行動パタンや自分の職場の習慣と比べてやや暗い気持ちにもなったりしたが、いい本を読めたのでよかったと思っておこう。
三日目の今日は、昼頃に外に出て花を見る。横須賀市しょうぶ園の藤が見ごろらしいので車で行ってみた。衣笠駅からす越のところにあるところで、思っていたよりもずっと大きな規模で、内容も良かったと思う。しょうぶ園という名前のとおり、メインの売りは14000株の菖蒲なんだけど、菖蒲はまだ見頃には一月ほど早く、青々としているだけ。園内に入って最初に見たのは石楠花だった。赤や白、ピンクの大きな石楠花が沢山咲いていて、ぽかぽかした陽気も加わり穏やかな気持ちになる。石楠花といえば、数年前のGWに九州に行く途中、紀伊半島を横切って大阪の南港に行く途中立ち寄った、室生寺の石楠花が見事だったのを思い出す。この1,2年でロングツーリングにはすっかりご無沙汰になってしまったけれども、身近なエリアにもいろんな見所があるんだな、とあらためて感じた。

石楠花エリアを過ぎると、ふじ苑がある。一面に藤が広がる様は壮観だった。藤といえば藤棚ばかりが思い浮かぶけれども、藤棚でなくても普通の木のように植えているのは初めて見たと思う。藤色という言葉で思い浮かべるような気品のある紫から、赤みがかかったもの、白っぽいもの、青が強いもの、紫が濃いもの、薄いもの、花が八重になってみるものなどいろんな種類があって、見ていて飽きない。ちょうど見頃だったこともあり、一面の藤に囲まれると甘い香りに包まれて、藤の花の香りというものも初めて実感した。少し離れたところから見ると、斜面一面に藤色の雲がかかっているように見えた。こんな近くにこんなに素晴らしい場所があるのに、全然知らなかったのが今までもったいない。6月になって菖蒲の季節になったらまた来て見よう。
しょうぶ園を出てからまだ時間があったので、相模湾のほうに少し走り、武山に登る。武山は5月3日からつつじ祭りがあるらしいので、躑躅がきれいなんだろう。あまり道路標識もないところ、狭い道を強引に車で登ってゆく。一応舗装されているから車でも走れるのだけれども、なんとなくいやな予感がしたので道端に停め、歩いて登り始める。道の途中には躑躅が並木になって植えられているところもあり、日陰ではほとんど咲いていないけれども日当たりのよいところでは五分咲き程度には咲いていた。

20分ほど歩いて山頂へ。見晴台からは、南に剣崎と三崎を、西に相模湾を、東には久里浜、観音崎、横須賀中央とその向こうに房総半島が浮かび、北には横浜のみなとみらいエリアのランドマークタワーが望める。すぐ目の前にはYRPエリアが広がり、僕の職場もよく見える。今日は晴れすぎて靄が出ていたけれども、秋から冬にかけては相模湾の向こうに富士山がきれいに見えることだろう。
見晴台で少し休んで柏餅を食べ、のんびり下りる。更に佐島で魚屋を冷やかし、三崎生鮮ジャンボ市場で中トロの細切れとかつおの刺身を買って帰宅。贅沢な夕食を楽しむ。
明日と明後日が過ぎればまたお休みだ。今度はどこへ行こうかな。
穏やかに晴れた午後、溜まった日経新聞を読んでいたら、「長寿の食卓」のコラムに鯖の料理が載っていた。
タキタキという名前で、和歌山の印南町というところの郷土料理らしい。そういえば最近鯖を食べていないなと思って、作ってみることにした。

適当に鯖の切り身を買うつもりだったのだけれども、スーパーに行くと丸の鯖が一尾だけ残っていた。三枚におろす必要があるのでしばらく躊躇したけれども、何事もやってみようと思い、勇気を出して300円で買ってみた。
帰って鯖を冷蔵庫に入れてから、とりあえず包丁を研ぐ。グレステンはとても使いやすくて気に入っているのだけれども、手入れをしないといけないほど切れ味が必要な料理ってめったにしないから、数年は研いでいない様な気がする。よく見ると細かく刃が欠けていたりして、やっぱり手入れは必要だなーと思う。
包丁を研いでから適当に切ってみようかと思ったけれど、とりあえず調べてみた。google様にたずねると一秒くらいで辻料理学校のページでいろんな魚のおろし方を紹介していることをを教えてくれた。魚によって少しづつ違うみたいで、鯖も独立したページを与えられていた。料理の本も買わずに基本的な技法を調べられるなんて便利な世の中だなぁ。これじゃ料理の本は売れなくなっちゃうだろうなぁ。

手順どおり、頭を落とし、内臓を出し、腹側から中骨まで刃を入れ、背側からも刃を入れ、尾の方から中骨に沿って切り離して二枚におろし、逆側も同様に処理して三枚におろす。とりあえず身を崩さずに分離できたので、初めてにしては、よくできたと思っておこう。
調理は簡単至極。生姜と一緒にフライパンで焼き色をつけ、フライパンの底が隠れる程度に酒を入れ、醤油と砂糖を適宜入れてから野菜をのせる。玉葱と葱をのせて少し待ってから白菜とピーマンを入れてみた。野菜は、日経の記事には白菜と葱と書いてあったけれども、あまっていたので他のものも入れてみた。最終的にすき焼きとチャンチャン焼きを足して二で割ったような感じに出来上がった。

酒が結構入っているので柔らかくしっかりした味に仕上がったけれど、いささかパンチのない、ボケ~っとした味だった。白菜を結構入れたので、味がぼけたんだろうか。もう少し醤油を入れても良かったのかもしれない。もともと砂糖を入れるのが好きじゃないところに、少し砂糖を入れすぎと思えるくらい入れてしまったのも問題か。
味噌煮に飽きたら、またやってみよう。

















